| 矢野 |
おふたりがネット上で展開してきた「連画」が、10年になるそうですね。最初に「れんが」と聞いたとき、当然のことながら「連歌」を想像しました。「連歌」というのは、発句に感ずるところがあって、それに沿って句をつないでいく。順ぐりに句をつくる過程を楽しみつつ、共通の関心事が浮かびあがってくる構造をもっているんでしょうが、安斎さんと中村さんがやってこられた「連画」も、同じ精神をもっているのでしょうか。
|
| 安斎 |
僕らが「連画」をはじめたのは1991年の12月、富山で開催されたCG(コンピュータ・グラフィックス)のセミナーがきっかけです。
当時は3次元のCGやフルカラーのCGペイントが、事務用パソコンを拡張すれば個人の手にも届きはじめたころで、僕たちもよくCGセミナーに駆り出されていたんですね。その会場で、何かの手違いで、僕の前のモニターに、たまたま中村さんの作品が現れた。2Dのペイントソフトで描いた作品でしたが、僕は何気なくそれに加筆をはじめたんですよ。長年、油絵を描いてきた人の作品だとわかっていましたから、どこかに「触れてはならない」という気持ちがありましたが、同時に、「これはデジタルデータで、オリジナルは別にあるんだ」という意識もあった。そこで、「まあ、やってみよう」と手を加えていったら、だんだん自分ふうの中村作品ができあがってきたんです。
そのとき、背筋が寒くなるような不思議な感覚に襲われました。これは何か秘密があるな、と思った。本来、「作者」と「作品」には不可分な関係があるとされてきましたよね。ところが僕は、そこにズブズブと手を入れ、割って入った。これは、その密かな喜びと恐れだったのかもしれない、と。もっとおおげさに言えば、有史以来アナログ絵画を描き続けてきた人類として、僕ははじめて他人といっしょに描き、絵を通して他人にアクセスするチャンスを得たのではないか。これは何かしなきゃいけないと思ったんですね。
そこで「連歌」から発想して「連画」という言葉が浮かび、彼女に「連画をやりましょう。種をください。うまく発芽したら、お返しします」とメールを出しました。
|
| 中村 |
 会場でその一部始終を横で見ていたけれども、私は正直、それほどインパクトを感じなかった(笑)。 会場でその一部始終を横で見ていたけれども、私は正直、それほどインパクトを感じなかった(笑)。
でも、安斎さんの「種をください」とのメールを受け取って、新しい遊びの匂いを感じ取ったのはたしかです。当時、ネットワーク会社のコンテンツ企画の部署にいた私には、「4800bpsという速度を生かすコンテンツを考えよ」という課題がありました。セミナーへは、純粋にCGアーティストとして参加したものの、この申し出には、職業的な下心がちょっとあったかな(笑)。新しいサービスのヒントになるかも、とね。
それともうひとつ、私には、連画への伏線となるような体験がありました。画学生だったころに、友だちと1枚のキャンバスを共有して絵を描くという実験をしたことがあります。私は直感的に大づかみにとらえることが得意だけれど、彼女は、全体のバランスを保ちつつ着々と描きすすめることができる。お互いのいいところを積み重ねたらどんなにいい作品が生まれるかという期待を込めた試みでした。ただふたりとも我が強いから、共同作業をするのは避けて、午前中は私、午後は彼女が描くという取り決めをしました。自分の時間は全画面を独占し、バトンタッチしていくという方法ですね。
はじめに私が描いて、あたりがついたところで彼女の番。翌日、私はとっておきのカドミウムイエローオレンジを絞り出し、ピッと橙色の線を描きました。彼女はこれをどう描きすすめるだろう、とワクワクしながら次の朝、イーゼルに向かったら、あの橙色の線がないんです。私の鮮やかなカドミウムイエローオレンジはどこに行ったんだろ?と探したら、イーゼルの前の新聞紙の上になすりつけてあった(笑)。
仕方ないからもう1回描き直しましたよ。ところが次の日に行ったら、そこから絵がすすんでいない。もう1日待っても、次の日になっても、絵はいっこうに変わらない。
そんなふうに、アナログの世界で試みた「連画」が、それ以上はすすまなかったことを思い出しながら、私は、安斎さんとのセッションをスタートさせたんです。
|
| 安斎 |
そのはじめての連画が、3往復6作品の「気軽な日曜日」です。
|
| 矢野 |
自分の作品に手を入れられることに抵抗はなかったですか。
|
| 中村 |
私はずっと油絵と彫刻を勉強してきて、たまたまネットワーク会社に入ったので、デジタルの特性のいいところしか見えていなかったこともありますね。そのせいか、デジタルのコピーとオリジナルが寸分違わないところが素晴らしいと感じたわけ。 安斎さんが貸してくれた「スーパータブロー」というソフトを使うと、油絵の具や水彩、木炭やガッシュなど、現実には、同時に使いにくい多様な表現、道具をデジタル上では瞬時に試すことができる。これは、すごくうれしかった。
|
| 矢野 |
「スーパータブロー」は安斎さんが開発したツールですね。
|
| 安斎 |
 そうです。僕は84年ごろからCGをはじめましたが、当時のパソコンで絵を描くのは困難だったので、少しずつツールを自分で開発し、87年にそれをペイントシステムとしてまとめたんです。それが「スーパータブロー」で、かなり売れました。 そうです。僕は84年ごろからCGをはじめましたが、当時のパソコンで絵を描くのは困難だったので、少しずつツールを自分で開発し、87年にそれをペイントシステムとしてまとめたんです。それが「スーパータブロー」で、かなり売れました。
|
| 矢野 |
安斎さんは、もともとアートの人? それともプログラムの人?
|
| 安斎 |
自分でもよくわからない(笑)。アートではずっと銅版画をやっていました。同時に、パソコンを使って音楽が自動的に発生するプログラムをつくろうと、いろいろやっていた。あるとき、「セルオートマトン」という考え方に出会い、それをいじっているうちに、まるで銅版画の腐食過程のような、ものすごく美しいテクスチャーが現れたんです。これはすごいことだ、何とかツールにしたいと思った。そして気がついてみたら、音楽のことを忘れて、絵のことばかり考えていたんです(笑)。
|
| 矢野 |
90年ごろ、おふたりが出会ったときは、「デジタル」ということにそれぞれが強くひかれ、未知の可能性を感じていたときだったんですね。
|
| 安斎 |
ふたりとも絵には興味がありましたが、さらに、どうやって絵を描こうかというシステムやプランに関心があったんですね。
|
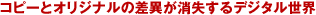 |
| 矢野 |
中村さんは学生時代の共作実験で、橙色の線をピッと引いたあとに友人にそれを消されてむっときたわけですが、デジタルの場合は橙色の線を入れた絵も残るし、それを消した絵も残る。だからデジタルの「連画」なら、消したり加えたりしても問題ない。むしろ「手を入れる」という過程そのものが時系列で見えるところが醍醐味なんでしょうね。
|
| 安斎 |
CGの場合、なにがオリジナルかわからないし、最初のものが必ずしもオリジナルではなかったりしますよね。そのように、根無し草のような状態からはじまるところに、連画のおもしろさの秘密があるのではないかと思います。
オリジナル1点物の絵画にオーラがあって、連画のようなコピーにはないということではなく、どこにでもオーラはあり得る。コピーのコピーであってもゾクゾクすることはありますから。つまり、オリジナルか複製かというところで、オーラの有無が決まるのではないというのが最初の直感です。
|
| 中村 |
そうなんですね。連画をはじめるとき、デジタル技術を使ってコピーをいくつもつくることが、オリジナルをけがしたり、画家の創意や人格を踏みにじることではないと直感的にわかったんです。私の場合、学生時代の純粋絵画領域の勉強が長かったから、かえってわかったのじゃないかと思う。すぐに「連画」で遊べたんです。
|
| 矢野 |
芸術作品の価値は個人の頭脳や感情から生まれて来たところにあり、なおかつその作品は1つしかない。それが複製されるようになり、模造品も含めて多くの人が芸術作品を見られるようになって、作品がもっていた独特の輝き、オーラが消えていったとふつうには考えられているわけだけれど……。
|
| 安斎 |
もともと絵はどれにもオーラがあるものだし、複製であっても変わらないんじゃないかと思いますね。最近、そのことには深く考えさせられました。これまで人類は抗争の歴史のなかで、象徴的な建造物、寺院や仏像などの破壊を繰り返してきましたよね。貴重な遺産が失われることには、我々は大変がっかりするし、取り返しがつかないことと感じます。ところが改めて考えてみると、偶像などに恐ろしさを感じるのは、じつはピュアな気持ちではないかと思うのです。恐れを感じなくなっている僕らのほうが、よほどどうかしているんじゃないか、とも思える。
例えば1000年前、写真も複製技術もない時代には、すべての偶像は怖いものだったと思うのです。絵画に描かれた偶像なら、せめて周囲を額で囲って、その霊性を閉じ込めようとした。そうでもしないと、ドキドキしてしょうがない、そういうものだったのではないか。偶像=イメージへの感動や畏怖の念は、時代を経るにしたがって消費されてしまい、いまや我々は偶像=イメージにオーラなど感じなくなっている。もし、1000年前の感覚をずっとピュアに持ち続けていたら、偶像=イメージを恐れる気持ちは、当然あったはずだと思うんですね。オーラのありかというのは、時とともに移るんだと思うんです。
|
| 中村 |
いままでのアートの世界では、まず本物vs.贋物という意味のオリジナルとコピーをイメージする人もいますが、創造の現場では、コピーとは「コラージュ」(切りとって組み合わせる)や「アッサンブラージュ」(他の画材を加える)という手法を指してきました。でも、連画では、相手から電子メールが届くと、そこに現れる他人の作品に、じかにズブッと手を入れる感じ。安斎さんの絵のどこかの部分を切り取ってコラージュしたり、なにかを加えてアッサンブラージュしたりするわけではなくて、安斎さんのオリジナルに丸ごと手を入れていくわけです。そういう作業をしていると、まさに、いま私が触っているものがオリジナルであるという気持ちになる。デジタルの世界では、コピーという考え方自体が変だと感じるんですね。
|
| 安斎 |
自分がオリジナルだと感じた瞬間に、それはオリジナルなのだという感覚ですね。
|
| 矢野 |
例えばここでおふたりの写真を撮って、あとから背景の壁を消して、替わりにカーテンを加えようとする。それをデジタル写真でやると、本物と偽物の区別は原理上つかない。そういう意味で、中村さんも安斎さんも、「すべてオリジナル」とおっしゃるわけですか。
|
| 安斎 |
いえ、すべてがオリジナルであると同時に、すべてがコピーであるとも言えるんです。アナログ写真の時代だって、巧妙な修正によって、本物であると思い込まされていたかもしれない。事実、本当は会っていない人同士が会っている写真も、歴史上いっぱいあるわけですから。そう考えれば、あるときその写真が「本物らしく振舞う」というだけの話で、絶対的な価値としての「本物」というのはないと思う。つまり、オリジナルかコピーかというのは相対的な価値でしかないと思うのです。
|
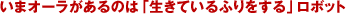 |
| 矢野 |
安斎さんがこれこそオリジナルだと認めるものは何ですか?
|
| 安斎 |
僕が最初にオリジナルのオーラを感じたのは、小学校を卒業するときにもらった名前のゴム印(笑)。ゴム印を押すと、活字体で自分の名前が現れて、それにすごくオーラを感じた(笑)。活字というのは当時の僕にとって特殊なものだったんです。高校時代は『ユリイカ』という雑誌に投稿していて、たまに誌面に自分の名前が載ったんですね。この活字は光り輝いて見えた。ところが、20歳ぐらいになって、自宅に届く雑誌の宛名が漢字プリンタの明朝体で印刷されているのを見たとき、僕の明朝に対するオーラがすべて崩れてしまったわけ(笑)。
つまり、オーラって消費されてしまうものなんですね。最初は感激したけれど、次の瞬間にはもう当たり前になってしまう。おそらくいまの時代、オーラのありかとして求められているのは、ロボットだと思います。育て系のゲームもそうですが、「生きているフリをしているもの」がものすごく注目されている。二足歩行する「ASIMO」を見ると何かワクワクし、「AIBO」が動いているのを見ると、本物の犬を見るよりドキドキするでしょう。みんながそういう「生きてるっぽいもの」を求めているんだけど、しかし、それはいまどこにもないオーラを見つけようとしているにすぎなくて、これまでのオーラと同様、いずれは消費されてしまうのだと思います。
クローン人間について描いた映画『シックス・デイ』はおもしろかったですよ。白紙の人間に自分の遺伝子を注入すると、外形も感情も記憶もDNAも、パーフェクトなコピーができる近未来、それを行っている巨大バイオテクノロジー企業の悪徳経営者が登場するんです。彼が銃で撃たれ、瀕死のときに自分のコピーをつくるわけ。ところが不完全な状態のコピーができてしまい、古い自分とコピーが鉢合わせする。コピーである新しい自分は、古い自分なんてもういらない。一方、古い自分は新しい自分に見捨てられ、見殺しにされる恐怖感を覚える。"2人"が出会った瞬間がすごくおもしろかった。
|
| 矢野 |
普通は新しいものができたら、古いほうは死ななくちゃいけないですからね。
|
| 安斎 |
この映画は、自分のオリジナルな人生がわからなくなることの意味を描きたかったのではないか。じつは連画でも、相手に絵が渡り、手が入りはじめたとたん、オリジナルもコピーもなくなり、作品が根っこから変容していく。そのプロセスを見ていると、「わけがわからない」という感覚に陥っていきますからね。
こうしたことは、これから現実に起こりうる話だと思うんです。これからの時代は、複製としての生命におけるオーラの消失が問題になるはずです。そうすると、自分自身のオリジナリティとかオーラとかというものは、「自分がその中にいる」と実感できるとき以外には見つからないような気がします。
|
| 矢野 |
身体性をもったオリジナル感しか信用できない時代がきている、ということでしょうね。
|