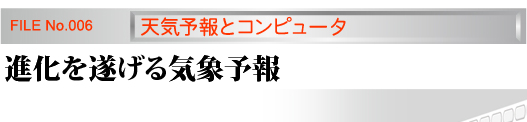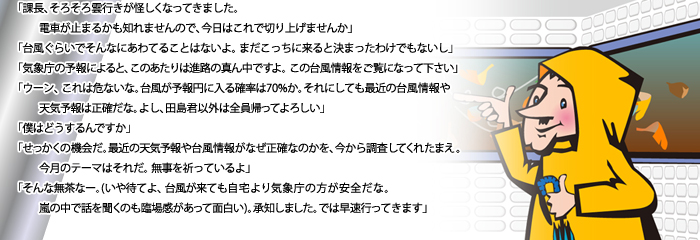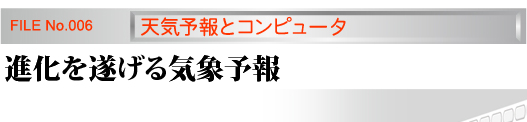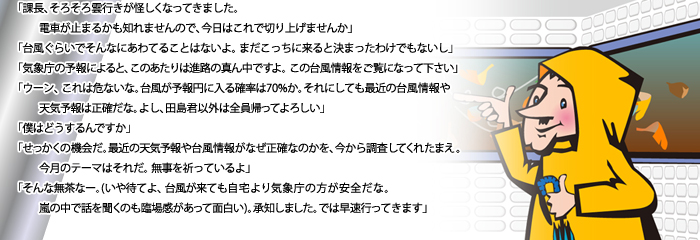|
台風の季節もそろそろ終盤を迎えたが、この時期に私達が大変お世話になるのが台風情報だ。普段は天気予報をあまり見なくとも、台風情報だけは気になるという人は多い。
台風が発生した時点から刻々と更新されるこの台風情報については、私達にとっては当然の情報サービスという感覚が強く、予報スタイルの変化に気付くことは少ない。しかし「よく見れば、台風の進路予測はもちろんのこと、表示法その他も実は大きな進化を遂げているのです」というのが気象庁天気相談所長・日野修氏の指摘だ。台風の進路を正確に予測することは永遠の課題だろうが、コンピュータの飛躍的な能力向上が支えとなって、進路予報をはじめとする台風の予測精度は毎年確実に高まっている。
現在私達が目にする台風情報は、予想進路を円で表示している。台風の予想進路が円になったのは1982(昭和57)年6月からだが、それ以前の台風情報では台風の進路が扇型の線で表示されていた。30代半ば以上の人なら覚えているこの扇型の予想進路は、台風の進行方向の範囲はわかっても、進行速度の誤差については表示されないという欠点があった。そこで、進行方向と将来の台風位置を明確にするために、円表示が採用されることになった。
円予報が採用されてから4年間は、予報円の中心が×として表示されていたが、1986(昭和61)年に中心点が取り払われるとともに、予報円以外に更に広い範囲の暴風警戒域も円で表示されるようになった。
現在の台風情報の予報円には中心点が表示されていない。予報円に中心点をあえて表示しない理由は、ややもすると中心に目が行きがちな私達の性向を配慮したものだ。つまり、予報円の中心部は台風が通過する確率が高いとは言え、周辺部が中心部より安全であるという保証はない。予報円の中心にあるほど危険が増すということではなく、周辺部で記録的な暴風雨が発生することも珍しくないということだ。
台風情報では予想進路に加えて、日本列島周辺の衛星画像も常に紹介されている。衛星からの可視画像による雨雲の様子は素人目にもわかりやすいが、予報するプロの立場としても気象衛星のおかげで台風発生の見落としが皆無になったとされている。
予報円を採用して後、台風情報は「予報できる時間を長くし、予報円を小さく(つまり予想地域を絞り込む)しながら、予報円の中に台風が入る確率を高める」方向で進化を遂げてきた。台風が予報円に入る確率については、1997年(平成9年)7月に60%から70%に引き上げられている。予報可能な時間についても、当初の24時間から48時間へと進み、現在は72時間となっていることは周知の通りだ。 |