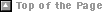−− |
生物多様性という言葉、最近は特によく耳にするようになりましたが、なかなか意味がとらえにくいものですね。 |
岩槻 |
言葉というのは、概念であり、そのコンセプトを示すものですが、では生物多様性とは何を示すものなのか。昨年6月に実施した内閣府の調査「環境問題に関する世論調査」でも、生物多様性という言葉を聞いた憶えのある人が30%、言葉の意味を知っていると答えた人が12.8%という結果が出ています。 |
−− |
そんなに少ないんですか。 |
岩槻 |
ですが、先にも言ったように言葉は概念です。例えば今度のCOP10では、環境省は「SATOYAMAイニシアティブ」を提案・発信しようとしています。「里山」という言葉は、最近、多くの人に知られるようになった言葉です。昨年亡くなった四手井綱英先生が、今日、語られるような意味での「里山」という使い方をして、そこから認識されるようになってきたというのが定説になっています。しかし、里山という言葉自体は、考証した人によると、既に江戸時代に使われた例があるんだそうです。更に最近では、里山という、日本に極めて特徴的な景観が、既に万葉集の時代には確立されていたという論文も書かれています。それ程に伝統があるものなんです。 |
−− |
つまり生物多様性という言葉も、概念を伝えなくてはいけない危機に陥りつつあるから、言葉として語られるようになったわけですか。 |
岩槻 |
そもそも、生物というのは30数億年前に出現した時にはたった一つの型でしかなかったのです。今、明らかにされているのは150万種程度ですが、実際現在では億を超えるだろうと推測される程の生物種が存在しています。つまり生物多様性は、生物にとっての普遍的な原理とも言えるわけです。ですが今、いろいろな要因で生物の絶滅が言われているのは皆さん、ご承知の通りです。 |
−− |
私達がモノを食べる時、その材料となる種をつくったもの、更にその種を生かしているもの…と、結局すべての生き物から恩恵を受けているということになるのですね。 |
岩槻 |
COP10に当たって、国内外で「命のつながり」という言葉が使われています。我々は「命」というと、自分自身の「個体の命」を考えてしまいがちですが、個体の命とはそもそも何なのか。 |
−− |
あらゆるものがつながっているというのは、そういうことなんですね。 |
岩槻 |
|
−− |
あえて伺いたいのですが、ではそういう生命系の中にあって、ある種が絶滅するというのは、どういう意味があるのでしょうか。 |
岩槻 |
一種の絶滅危惧種が生じるということは、実は、その生態系にとって非常に危機的な状況で、その一種の絶滅をきっかけに、たくさんの絶滅危惧種が生じる前兆であると言えます。日本のトキの絶滅については、大きく報じられていましたから皆さんご存じと思います。その時、ダニの研究者である青木淳一さんは「トキが絶滅すると言うと、皆さん残念だと言ってくれるけれども、もしトキが絶滅したら、トキに付くダニも絶滅するということは誰も残念がってくれない」と、アイロニカルにおっしゃっていました。 |
−− |
(笑)。つい笑ってしまいますが、でもそのダニを食糧としている生物も絶滅するということですね。 |
岩槻 |
そういうことです。種は、それだけで生きているわけでなくて、その一種は、ある生態系を構成する要素として生きているんです。だから、ただ1種が絶滅するということが問題なのではなくて、その生物が絶滅するような状態に、生態系が陥っているという事実が問題なのです。生物は、もともと絶滅などしないよう上手に進化してきてきました。ですから、それがたとえ1種でも絶滅するということは、非常に重要なサインとして見なければいけない。ある閾値を超えてからでは、もう手遅れなのです。 |
−− |
私達はつい「可哀想」「寂しい」という感覚でとらえがちですが、その生物がいなくなることは、その系を維持してきた要素が欠けていくということなんですね。 |
岩槻 |
そもそも外来種というのは、外から新しい生態系に入ってきた生物を指します。例えば九州にあったものが関東に入って来れば、それも外来種とも言えます。 |
−− |
え?! 「月見草」という名前からもすっかり日本に古来あるものと思っていましたが、それは意外です。 |
岩槻 |
日本を代表する小説家が、これまた日本を象徴する風景である富士に、メキシコからの外来種である月見草がよく似合うなどと言っているのは皮肉な話ですけれども、それが典型であるように、日本の田園風景に見られる植物のほとんどは外来種なのです。だからといって、「クローバーは外来種だから全部抜いてしまおう」などと言う人は誰もいません。そうやって日本の景観になじむように落ちついてしまった外来種もたくさんあるわけで、だから外来種イコール敵、というわけではないのです。外来種が生活できるように、生態系を変換してしまったのは、誰あろう人間であって、むしろそういう所に外来種が入ってくる方が、自然な状態と言えると思います。 |
−− |
「外来種は何もかもダメ」と一くくりにできるような単純なものでもないということですね。 |
岩槻 |
ええ。そこからも分かるように、生物多様性ということを、言葉で学んでもしようがない。明治以前の日本人が、生物多様性とどう付き合い、どんな良いことと悪いことがあり、自分たちは今、生物多様性とどう付き合っているのかを、自分の頭で考える。僕は科学者ですから、今のように安全で豊かな生活が送れるようになったことは決して悪いと思いませんし、ますますそうなった方が良いと思っています。でも良い面だけでなく、そのために失う物の大きさを知ることも、また極めて大切なんだと思います。 |
−− |
絶滅危惧種とは、センチメンタルな事ではなしに、科学的な面から、生物多様性がいかに歪んでいるかという事象をとらえるためのモデルだったわけですね。 |
岩槻 |
やはり絶滅危惧種が人の心を揺さぶる力は大きいと思うのですが、一方で、私自身は長年に渡って生物多様性について考えてきて、開き直っているわけではないのですが「生物多様性」という言葉を知ってもらうことが、そんなに大切なのかなと思うようになりまして(笑)。 |
−− |
世間一般に広めようと、これまで活動されてきたのに、ですか。 |
岩槻 |
ええ。むしろ、日本人というのは、生物多様性とのつながりという事に関しては、世界に冠たる国民だと思うからです。弥生時代に始まった農耕牧畜では、森林を伐開して――つまり自然に対して人の手を加え、農地を作りました。「自然」というのは人手が加わらない様を指します。ですから本来、里地、里山は自然なものではないわけです。今風に言えば、明らかにそこで自然破壊を始めたことになります。しかし誰も、弥生時代の先祖を自然破壊の創始者だとは言いません。もちろん私も、そんなことはまったく考えていません。里地、里山とは、ある言い方をすれば、人が自然を改変して都合の良い状態に作り上げてきたものではありますが、日本人が自然と上手になじみ合いながら、生物多様性と付き合ってきた一つの証だと言えるのではないでしょうか。 |
−− |
里地、里山の風景は、私たちにとっては自然そのものですし、ほっとする風景でもあります。 |
岩槻 |
里地、里山というのは、いわゆる人が自然と見事に共生している場所ですし、これを見ても日本人にとっては、自然と共生するということが体になじんだ概念と言えると思います。 |
−− |
そうですね。 |
岩槻 |
あるいは、生物学の学術用語として「symbiosis=共生」という言葉があり、「symbiosis」と訳した文章に出会うことがあります。「symbiosis」には、相互に得をする「相利共生」と、サメとコバンザメのように片方が得をするけれど、もう一方には損も得もないという「片利共生」があり、更に日本語で言う「寄生」も含まれます。ですから、生物学者が「symbiosis」という言葉を見ると「まあ、確かに人は自然に寄生しているから…」という見方になってしまう(笑)。 |
−− |
今、自然に対して何か貢献をしているかと言われれば、していないと言わざるを得ませんからね(笑)。 |
岩槻 |
|
−− |
確かに自然全体を、資源として今後も活用しようというのは、日本人には違和感が残るかもしれません。 |
岩槻 |
日本では、森林を伐開して、単一作物である穀物を作り、生産性を高める事で資源を安定供給しました。また、日本列島で水田が作れる場所は、国土の20%程度しかありませんから、そこで生産される資源によって支えられる人口は限られています。その時に、人が住まう人里の後背地である里山から薪炭材といったエネルギーを得たり、ウサギや猪といった小動物や木の実の狩猟採取によって、補助的な資源を獲得してきたわけです。更に里山の奥は、急峻な奥山として残す。こうして奥山は野生の動植物が住まう場所、人里は人が住まう場所、里山はその間のバッファーゾーンという、日本列島特有のゾーニングができあがったわけです。その後、1960年代にエネルギー革命の影響を受けて、里山が放棄され、荒れてきた。ところが、荒れた里山は、どうせ放っておいても自然に戻るだろうと放置されてしまったんですね。 |
−− |
4,300頭ですか!? |
岩槻 |
ええ。少ない年でも1,000頭ほど捕獲されていて、多い年でも3,000頭弱ほどです。日本の熊の総数は約1万5,000頭と推定されていますが、2006年は山の木の実が不作の年とあって、熊が人里まで出てきてしまったんですね。 |
−− |
4分の1以上を占める数ですね。 |
岩槻 |
確かに荒れた里山は、放っておけば自然に戻ります。けれども、安定した自然に戻るためには、400、500年かかる。その間、荒れた状態と付き合い続けるのか…荒れた状態というのは、この熊の数に現れていると思います。日本列島は明治維新まで、中大型の動物が、ただの一種も絶滅していないのです。これは地球上で見ても希有な事です。それ程上手に、日本人は自然と共生しながら生きているということの象徴と言えるでしょう。 |
岩槻邦男(いわつき・くにお)
1934年兵庫県丹波市(旧氷上郡柏原町)生まれ。京都大学理学部植物学科卒業、同大学院博士課程修了。京都大学教授、東京大学教授(および同附属植物園長)、立教大学教授、放送大学教授などを経て、兵庫県立人と自然の博物館館長。専門は植物学、特に植物分類学で、主にシダ植物を対象として研究。ユネスコ国内委員(自然科学小委員会委員長)、国立科学博物館評議員ら、WWF-ジャパン常任理事らNGO・NPOの活動にも参画。日本学士院エジンバラ公賞受賞(1994)、文化功労者顕彰(2007)。植物園で社会教育に関与して以来、生涯教育に強い関心をもっている。著書に『生命系−生物多様性の新しい考え』『多様性の生物学』(ともに岩波書店)、『文明が育てた植物たち』(東京大学出版会)など多数。
●取材後記
「ある種がいなくなるというのは、歓迎すべきことではない」と感じていたもの、多様性については「パンダがいなくなるとなれば、それは可哀想だな」程度の理解でもあった。でもそれだけじゃない。そのパンダが食べている笹が増えすぎて、別の植物が隅に追いやられ、その植物を主な食糧にしていた動物が、やはり食べ物がなくなって…と、すべて繋がっているのだということが、今更ながら理解した取材だった。
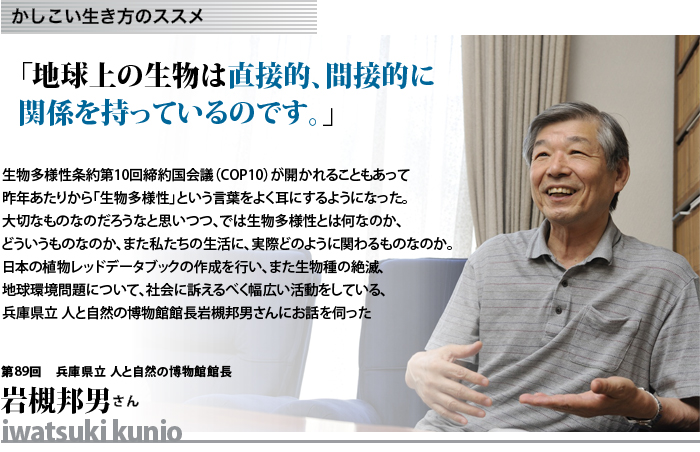
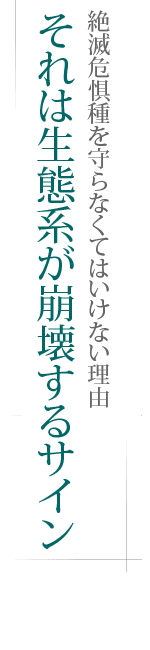
 しばしばアナロジカルに言うのですが、60兆の細胞があって「私」という個体が出来ているとしても、しかし、私の頬の筋肉細胞と足の裏の皮膚細胞が、共同して何かをしよう!ということはないですよね? けれども、そういう一つずつのものがなかったら「私」は存在しません。地球上にいる生物だって、同じことなのです。「私」と、地球の反対側の土の中に住む名もないような菌とは、全く関係ないと思うかもしれませんが、地球上に生きている生物は、相互に直接的、間接的に関係を持っているのです。先にお話したように、元を正せばたった一つの型が、30数億年かけて今に至っているわけです。つまり地球上に生きているすべての生物は生命系という一つの「生」を生きていて、我々人間は、その中の一つの細胞みたいなものに過ぎない。生物多様性とは、何か複雑なものがあるのではなくて、そういう一つの「仕組み」「系」であって、私達はその一つの要素なのです。
しばしばアナロジカルに言うのですが、60兆の細胞があって「私」という個体が出来ているとしても、しかし、私の頬の筋肉細胞と足の裏の皮膚細胞が、共同して何かをしよう!ということはないですよね? けれども、そういう一つずつのものがなかったら「私」は存在しません。地球上にいる生物だって、同じことなのです。「私」と、地球の反対側の土の中に住む名もないような菌とは、全く関係ないと思うかもしれませんが、地球上に生きている生物は、相互に直接的、間接的に関係を持っているのです。先にお話したように、元を正せばたった一つの型が、30数億年かけて今に至っているわけです。つまり地球上に生きているすべての生物は生命系という一つの「生」を生きていて、我々人間は、その中の一つの細胞みたいなものに過ぎない。生物多様性とは、何か複雑なものがあるのではなくて、そういう一つの「仕組み」「系」であって、私達はその一つの要素なのです。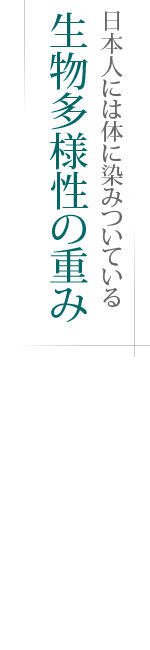
 ええ。元来、日本人は、里地、里山を作り、自然と共生してきました。だから日本列島というのは、世界中のどこよりも、緑の豊かさを維持しているのです。
ええ。元来、日本人は、里地、里山を作り、自然と共生してきました。だから日本列島というのは、世界中のどこよりも、緑の豊かさを維持しているのです。