「情報の行き交うところに擬態あり、です。」
動物が、目的のために何かに姿を変えて自分の身を隠したり、
相手を欺いたりする「擬態」。眼鏡やひげ、服装を変えるくらいしか
「変装」の技を持たない人間にとっては、動物の擬態には眼を見張るものがある。
中でも、ランに化けるハナカマキリ、ハチのふりをするハナアブや、
木に同化してしまったようなシャチホコガなど、見ればいちいち、驚かされる。
しかし、複雑なその仕組みの機構については、ほとんど分かっていない。
そこで今回は、遺伝子という切り口から擬態について取り組む
藤原晴彦さんにお話を伺った。
―― |
私達にとっては、どれもびっくりするような擬態ですが、目的や方法によっていくつかに分類されていますね。 |
藤原 |
|
―― |
同じ昆虫の種どころか、植物のふりをしたりするのですから、驚きます。 |
藤原 |
そうなんです。しかも、その擬態のやり方にもそれぞれ戦略があります。例えばシロオビアゲハというのは、ドクチョウのベニモンアゲハに擬態します。両者の羽の模様はよく似ています。ところが、擬態するのは、ある特定の遺伝子を持ったシロオビアゲハのメスの一部だけなのです。オスや他のメスは全く違う模様をしています。 |
―― |
そうすると、擬態できる遺伝子を持ったほうが長生きするのですか。 |
藤原 |
そう思いたくなりますが、必ずしもそうではないのです。ベニモンアゲハを天敵である鳥などが食べた時、死には至らないけれど、きっととてもまずかったり、気分が悪くなったりして「このチョウ、食べるべからず」ということを鳥が学習するんです。それに擬態したシロオビアゲハは、本当は食べたらおいしいはずですが、ドクチョウに似ているから、食べられない。だったら、皆ドクチョウの模様にしたほうが絶対、得じゃないかと思うのですが、そうではないのです。実際にオスは全て、ベニモンの模様とは全く異なる白い帯状の模様で、擬態することはありません。メスも擬態するのは一部です。恐らく、シロオビアゲハが擬態するには、普段使わない遺伝子を使うためにエネルギーが必要だとか、モテなくなるかもしれないとかいったコストが発生するため、メスの一部しか擬態しないのではないか、と言われています。 |
―― |
モテなくなるんですか。 |
藤原 |
オスは、もともと自分と似たような模様のメスを好むという説があって、そうすると、メスは擬態すると、捕食はされなくなるけれど、結婚できなくなるかもしれません。 |
―― |
けっこう、覚悟が必要ですね(笑)。 |
藤原 |
この擬態では、ベニモンアゲハというモデルがいて、それに似せるシロオビアゲハがいて、それらを捕食する鳥などがいて、という三者関係がなければ成立しません。ベニモンアゲハのいない地域ではシロオビアゲハの擬態は起きないのです。 |
―― |
毒のないチョウに擬態するだけでは、「仮装」でしかありませんね。 |
藤原 |
しかも、ドクチョウの数がわずかで、擬態する方の数が圧倒的に多かったら、捕食者にとってはまずい方よりおいしい方に当たる確率が高いので、この擬態もまた成功しないでしょう。 |
―― |
それらは食べられないようにするためのパターンですが、食べるために擬態するというパターンもありますね。 |
藤原 |
ペッカム型です。ハナカマキリは、ランの花に寄ってくるミツバチなどをだまして食べてしまおうというものです。面白いのはハナカマキリは、幼虫のころは赤と黒の模様が入っていて、あの臭い匂いを出すカメムシに擬態しています。成虫になれば他の生物をだまして補食するハナカマキリは、小さい頃は、食べられないように擬態しているというんです。 |
―― |
擬態を遺伝子のレベルで考えようという藤原さんの研究では、今、特に色と模様に焦点を当てておられますね。 |
藤原 |
ハナカマキリは、4本の脚とお尻が5枚の花弁みたいな形を作ります。これは、研究対象としては発生学という分野になるでしょう。でもこのカマキリはランの花があるところに行ってこそ、擬態に意味があるとすれば、それは行動学の分野の対象になり、そしてお尻を持ち上げたり脚を拡げたりしてランの花に似せるというのは、神経生理学の分野の対象になるでしょう。こんな風に擬態というのは、研究者からすると、分野が大きくまたがっているので、どこから手をつけたらいいのか、よく分からないのです。 |
―― |
確かに、あの擬態の仕組みを見つけるのは、簡単ではなさそうです。 |
藤原 |
ハナカマキリのような擬態を司る遺伝子を探すのは、人間が学習する遺伝子を特定しようというようなものですから、まずは手をつけやすいところから、ということもありますが、ムラサキシャチホコのように、驚くような「絵」を描いている擬態の例がたくさんあるのです。その原理を知りたいということもありますし、もうひとつ、虫の中で一番多く使われているのは隠蔽型の擬態でして、昆虫を採集する趣味の人やプロの人達に聞くと、一番見つけにくいのは、茶色の幹にとまっている茶色の蛾とか、マンションの白壁にとまっている白い蛾とか、体色を背景に合わせてしまう擬態だと言います。ハナカマキリは派手ですが例外的です。昆虫は小さいから食べられてしまう。だからほとんどの虫にとっては、食べられないようにすることが擬態の重要な目的であって、そのために、茶色にしたり緑にしたりして色を変え、模様を上手につけて擬態することが多いのです。それならやはりごくふつうに見られる擬態の機構を知りたいと考えたわけです。 |
―― |
その遺伝子は、まだ分かっていないのですか。 |
藤原 |
今、研究しているところです。ただ、擬態の中で、羽に目玉の模様を描いて、捕食者を怖がらせるとか、逆にそこを襲わせて自分の急所、つまり頭部への攻撃を逸らせるという擬態も多いのですが、その目玉の模様を描く時、昆虫の脚を作る遺伝子が関係しているのではないか、ということが分かってきました。 |
―― |
脚? 例えば、手とか、指とか、脚と同じような器官なら、まだ分かりますが… |
藤原 |
そうですね。ショウジョウバエの脚や羽を形成する「ディスタルレス」という遺伝子があるのですが、この遺伝子が、ジャノメチョウなど目玉模様の中心部分に発現していることを欧米の研究者が突き止めたのです。不思議な話だと思うのですが、脚の形成と目玉模様には、ひとつだけ共通点があります。 |
―― |
それほどに、目玉模様が重要であるということも言えますね。 |
藤原 |
脚を作るほうが重要そうな気がしますけれどね(笑)。こんな風に、「遺伝子を使い回す」ことを専門用語で「コ・オプション(co-option)」と言います。模様というのは一見、画用紙にお絵かきをしているようなイメージですが、実は形を作るということと、平面上に模様を描くというのはそんなに違いはないと考えれば、我々の形を作る遺伝子も、体の表面にお絵かきすることも、同じ遺伝子が使われているケースが結構あるのではないかということが、分かってきたのではないでしょうか。 |
―― |
見ていてちょっと気持ちのよいものではないのですが(苦笑)。 |
藤原 |
|
―― |
乳がん? |
藤原 |
「昆虫の体節の模様と、乳がんってどんな関係があるんだ」と思いますね。でもウィングレスというのは、文字通り、昆虫の羽を作ることに関わる遺伝子として見つかったのですが、その後、研究が進んで、虫でもヒトでも、発生や形を作る時に非常に重要な役割を果たす遺伝子だということが分かってきました。それが、カイコのスポット状の模様作りにも関わっているということなのです。 |
―― |
「単にカイコでのスポット模様」ということではないかもしれませんね。 |
藤原 |
アゲハの幼虫のスポット模様にもこの遺伝子が関わっていることが研究室の仕事で分かってきており、けっこう重要な重役クラスの遺伝子が、擬態における模様作りに関わっている可能性が見えてきましたね。 |
―― |
色についてはいかがですか。 |
藤原 |
色を発現させる遺伝子というのも結構分かってきているのです。要約すると、アゲハなどの幼虫の体の、どんな模様にはどんな遺伝子が発現しているかをざーっとカタログ化していくのです。そうすると、同じような色のところの同じような遺伝子が発現しているので、これは緑の遺伝子じゃないか、赤じゃないか、など推測ができるのです。 |
―― |
見事な昆虫の模様は、こうして遺伝子を駆使して描かれているのですね。 |
藤原 |
ある遺伝子は緑の模様のところで発現していたので、緑の遺伝子かと思ったのです。ところが、よく見ると模様の中に青い領域があって、そこで発現している青色の遺伝子だったのです。緑の領域では、黄色の遺伝子も発現していました。ですから緑に見えるのは、実は青色と黄色を足して緑にしていると分かったのです。 |
―― |
まったくもって、絵の具のようですね。 |
藤原 |
例えばアゲハ幼虫の体表にも薄い黄緑と、濃い緑の部分があります。どうやって絵の具を塗り分けているのか、遺伝子発現を見ていくと、前者は青と黄色、後者は青と黄色と黒を足しているんです。昆虫のいる場所はさまざまな葉っぱの緑色でいっぱい。一口に緑といってもその幅は無限にあります。その緑色を表現するために、塗り方も細かい調整をしているのです。遺伝子の驚くべき働きです。 |
―― |
昆虫たちは、こんな風にしたら、この擬態になるな、と認識しているというか、分かっているのでしょうか。 |
藤原 |
それは多分、答えとしてはノー。昆虫は自分がどういう姿をしているか、全く知らないでしょう。知っているのは捕食者であって、捕食者が誤解するかどうかが問題なのです。これは多分、長期間の自然淘汰によって生じたんだと思います。100匹食べられてしまう模様と、99匹食べられる模様とがあったら、後者のほうが1匹残るという微細なことが、何百年と積み重ねられるうちに、圧倒的に数が違ってきてしまうというセレクションが起き、最終的に擬態が成立するということは考えられます。「目玉のような模様を作ってみたら食べられなくなりました、擬態が成立しました」という単純なストーリーは、あったとしてもごく少数かもしれません。 |
―― |
カメレオンのように周りの環境によって体色や模様を変えてしまうようなものや、ヒラメやある種のカエルのように自分の住む場所によって模様が変わってしまうものもいます。 |
藤原 |
|
―― |
昆虫の擬態を見てきましたが、あらゆる生物において、擬態が存在しますね。 |
藤原 |
私達の目に見えない分子のレベルでも擬態はあります。人間の免疫システムは、生体を守る時、細菌やウイルスに特有の分子を認識して、それを攻撃するという方法をとります。例えば毎年3億人が罹患し、100万人以上の人が命を落とすマラリアは、免疫システムが「マラリア」と認識するための分子の形を四六時中変化させて監視網をかいくぐったりしています。また、マラリア原虫は、免疫システムが「敵ではない、自己である」と認識する分子を体の表面にもっていて、攻撃をくぐりぬけているのかもしれません。これは、まさしく分子が擬態しているといっていいでしょう。 |
―― |
あらゆるところにだまし、だまされ、の世界があるということですね。 |
藤原 |
擬態を情報戦略と考えれば、分かりやすいと思います。擬態でやりとりされるのは、匂いだろうが、視覚だろうが、全て情報です。そこに「錯覚」を持ち込むというのが擬態ということではないでしょうか。昆虫の世界では、色や形を操作することによって捕食者をだましているわけです。一方、分子にしても、他の分子と情報をやりとりして、反応が起きます。従って、その情報が誤って受け取られると異なる反応が起きるわけです。このように、情報のやりとりがあり、さらに既存の情報ネットワークが存在するところには、必ず擬態という戦略が存在し得るのです。 |
藤原晴彦(ふじわら・はるひこ)
1957年兵庫県生まれ。東京大学大学院理学系研究科生物科学課程修了。
厚生省国立予防衛生研究所(現感染症研究所)研究員、ワシントン大学動物学部客員研究員、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻助教授などを経て、現在、東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻教授。著書に『よくわかる生化学―分子生物学的アプローチ』(サイエンス社)、『似せてだます擬態の不思議な世界』(化学同人)。
●取材後記
擬態というのは、その驚くような姿だけで、充分にインパクトがあるので、見ているのがとても楽しい。でも角度を変えてみると、昆虫の世界の熾烈な情報戦略が見てとれる。擬態を遺伝子という切り口からと同時に、情報のやりとりという側面から見ると、こんな「神業」の謎が解けるかもしれない。

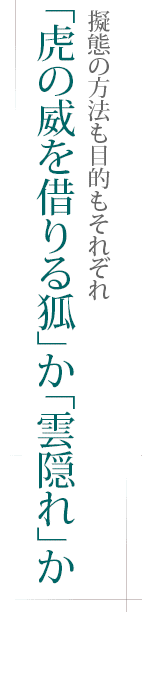
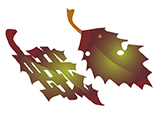 擬態には、大きく分けて標識型擬態と、隠蔽型擬態の二つがあります。前者は、毒のある他の生物などに似せて目立つために真似る擬態、後者は、葉や枝、木などの他の物に似せて隠れるために真似る擬態です。
擬態には、大きく分けて標識型擬態と、隠蔽型擬態の二つがあります。前者は、毒のある他の生物などに似せて目立つために真似る擬態、後者は、葉や枝、木などの他の物に似せて隠れるために真似る擬態です。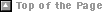

 これは、実際に毒のあるなしにかかわらず「毒がありますよ」という警告的な模様と思われますが、この場合のひとつ一つの模様も目玉模様と考えられます。カイコにもこういう模様を持つ突然変異体がいて、これは1種類の遺伝子が変わったことで生じてくるということが以前から知られていました。これが最近になって「ウィングレス」という遺伝子が原因だということが分かったのです。
これは、実際に毒のあるなしにかかわらず「毒がありますよ」という警告的な模様と思われますが、この場合のひとつ一つの模様も目玉模様と考えられます。カイコにもこういう模様を持つ突然変異体がいて、これは1種類の遺伝子が変わったことで生じてくるということが以前から知られていました。これが最近になって「ウィングレス」という遺伝子が原因だということが分かったのです。 こういった脊椎動物の擬態は、昆虫のそれとは違って、多くの場合、視覚的な情報を基にして、神経系を通じて自分の体色や模様を変更させたりしているので、手法はかなり違うのです。植物は移動できないとか、脊椎動物は骨が内側にあるけれど昆虫の骨は外側にある、といった生物のグループには超えられない枠があります。その枠を超えるのは非常に難しい。この枠を超えてしまっているのではないかと思わせるところが擬態の面白さです。例えば、植物と昆虫は全く異なるグループで発生の仕組みも全く異なるのに、なぜ昆虫は葉に似せられるのかという点が擬態を不思議と感じさせるのです。そのやり方について、答えはまだ見つかっていませんが、本来僕らが持っている固定観念を超えた何かがあるのでしょう。
こういった脊椎動物の擬態は、昆虫のそれとは違って、多くの場合、視覚的な情報を基にして、神経系を通じて自分の体色や模様を変更させたりしているので、手法はかなり違うのです。植物は移動できないとか、脊椎動物は骨が内側にあるけれど昆虫の骨は外側にある、といった生物のグループには超えられない枠があります。その枠を超えるのは非常に難しい。この枠を超えてしまっているのではないかと思わせるところが擬態の面白さです。例えば、植物と昆虫は全く異なるグループで発生の仕組みも全く異なるのに、なぜ昆虫は葉に似せられるのかという点が擬態を不思議と感じさせるのです。そのやり方について、答えはまだ見つかっていませんが、本来僕らが持っている固定観念を超えた何かがあるのでしょう。