 |
|
|


 |
 |
 |
(上)大型ディスプレーに映し出された対局の模様。会場から「よーし、もらった」「あーっ、ダメだ」との喚声が湧く。
(第13回世界コンピュータ将棋選手権にて)
(下) 同選手権の決勝戦を解説する矢内理絵子女流3段。
|
|
| |
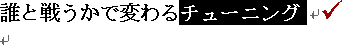 |
| |
将棋ソフトはコンピュータ同士で対戦することで、飛躍的に強くなってきた。ここで面白いのが、対人間で強いソフトが対コンピュータとなると、そうでもないということ。
「いろいろなパターンを作って、コンピュータ同士を対戦させる。その中で生き残ったパターンを採用すると総合的に強くなり、安定する。淘汰された強いものを次のバージョンにしていくと、生物の進化と同じような現象が見られるわけです。ところが、これを対人間用に調整してしまうと、コンピュータ将棋選手権のような場では勝てないことが多い。例えば、これは終盤で顕著に出てくるのですが、三手スキのもう少し先の詰めにかかってくるようなところで、人間だと際どい手を指されると相手を信用して受けにまわったりします。心理的なものが働くのですが、コンピュータの場合は全くそういったことがない。ですから、対人間用にチューニングすると、際どい手ができるようになる代わりに、対コンピュータではあまり強くなかったりするのです」。
|
| |
同じ3段に認定されても、人間から見た強さとコンピュータから見た強さは違う。「3、4年前、国際将棋フォーラムでコンピュータ将棋をテーマにした討論会があり、その時パネラーで参加されていた羽生さんに、コンピュータと人間の感じ方の違いについて聞いてみました。すると『何が違うのかはわからないけれど、同じ段位でもどこか違う』とおっしゃった」。この摩訶不思議な違いが何であるかを明確に定義することが、人工知能を考える上で重要な課題だという。
「人工知能と人間の知能は、何が同じで何が違うのか。もっと突き詰めると、知の創造はどこまでいけるのかということになる。今のところ、ある特定の、例えば将棋のようにエキスパートと呼ばれる人がいる分野では、ほとんど限界はないのではないかという気がしています。むしろ曖昧な分野、たとえば常識とか、そういったところに限界があるのではないか。チェスのように高度な知的活動を必要とするところでコンピュータが世界チャンピオンを超えたという現実がある一方、小さな子供でもわかる常識のような部分をコンピュータになかなか理解させられない」。 |
| |
 |
|
 |
|
|


|