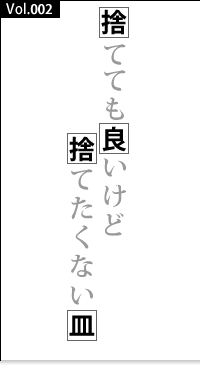|
紙皿を一度使えばもったいなくても捨てなきゃしょうがない。スチロールのトレーは捨てたくても捨てられない。どうせ使い捨てなら、捨てても良いけど、捨てたくない皿が良い。
竹は生命力が強く成長の早い植物である。特に、太く肉の厚い孟宗竹は筍が頭を出してから3〜5年で20メートルを超えるほどに伸びきる。その後放置すれば立ち枯れて倒壊し、地下茎はさらに森の奥へと伸びてゆく。管理されていない竹林は森を荒らし、環境に悪影響を与える。竹は活用すべき材料なのである。
その竹で作った皿がある。孟宗竹を蕪剥き(かぶらむき)にして厚さ0.5mmほどの薄いシートを作る。これを、繊維の方向がたて横互い違いになるように2〜3枚重ね合わせ、プレス、接着して様々な形の皿に成形にしたもので、これは中国製。
竹ならではの抗菌性能があり、熱に強いから電子レンジに耐え、軽く洗えば何回か使える。天然素材なのでそのまま捨てても問題ない。独特のテクスチャーが美しいトレーとして、食卓以外での使い道もいろいろ考えられる。
一方、杉の間伐材を利用して同じように積層した木の皿がある。こちらは高知県安芸郡馬路村(うまじむら)産。節だらけの自然な木目がなんとも素朴で、杉の香りも清清しい。こんな皿には是非、大ぶりの握り飯を盛って出したい。
かつて、日本の森が生み出す余剰の資源で炭や薪などの燃料の他、割り箸や楊枝、竹ひごや竹串など様々な消耗品や工芸品が作られた。放って置けば枯れ朽ちてしまうだけの間伐材や枝打ちした枝から生まれた道具は、いっとき、生活の役に立ち彩りを添えた後は廃棄されることで土へと戻り、やがて再び森の木として再生した。
こういう自然のリズムを取り戻すことができるなら、ささやかな使い捨ても悪くない。間伐材の皿が作られるということは、森が生きている証拠で、日本中の杉林がこういう健全な森ばかりなら花粉症の問題も起きないだろう。
竹と杉どちらも自然の余りで作った皿だけに、サラッと捨てられるから気持ち良い。
|