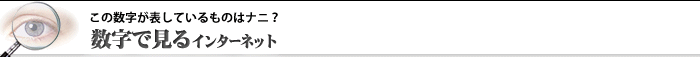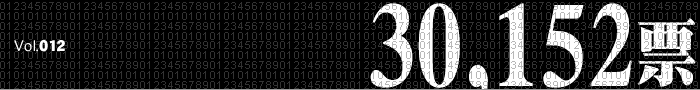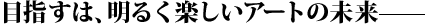
「日本アートアカデミー賞」という絵画の公募展をご存じだろうか?
NPO法人 日本アートアカデミー協会が主催するこの美術コンクールは、今年で2回目という新しい賞ながら、そのスケールの大きさと画期的な取り組みで注目を集めている。
まず、グランプリ賞金は、こうした公募展としては破格の1000万円! 審査委員の顔ぶれも豪華で、審査委員長を務める作家で評論家の室伏哲郎氏を筆頭に美術評論家や美大教授ら11名、さらに特別審査員として、北野
武氏、黒柳徹子氏、中村勘九郎氏というビックネームが並ぶ。
しかし、何より特徴的なのは、審査方法だろう。1次審査では審査委員がノミネート作品を絞り込むが、その後の2次審査は全国を巡回する展示会での会場投票とインターネット投票とで行われる。つまり、出品だけでなく、審査にも誰もが自由に参加できるのだ。
今回の数字は、2002〜03年1月にかけて実施された「第1回 日本アートアカデミー賞」でのインターネット投票数。2次審査の総投票数は3万9533票なので、投票の8割近くがインターネットからということになる。となれば気になるのが投票の公平性だが、この賞ではセキュリティシステムの関係上、1台のパソコンからは1票しか投じることができない。そのため、投票操作を繰り返して大量票を投じるといった不正が起きる心配はないわけだ。また、ノミネート作品の掲載・展示には作者名は添付せず、絵柄と作品データだけを公表するといった配慮もされており、出品者がホームページなどを利用して不特定多数の人に自作への投票を促したとしても、影響を受けにくいようになっている。
インターネット投票と全国を移動しながら開催する巡回展。考えてみると、一般参加型という新しい審査のスタイルは、主催者にとってはかなり手間のかかるものである。それでも日本アートアカデミー協会がこの審査方法にこだわり続けるのは、そこに既成の価値観を覆す可能性があるから。つまり、“絵画=評論家やキュレーターといった専門家の視点でのみ優劣が判定されるもの”という閉鎖的な日本美術界の常識を、この賞が回を重ね、多くの人の支持を得ていくことで、変えていきたいと願っているのだ。
美術界がオープンになれば、これまで専門家の方ばかり向いてきたアーティストも受け手である鑑賞者の視線に敏感になるだろうし、面白い作品が増えれば新たに絵画に興味を持つ人も増えてくる。さらには、今は特別なモノというイメージが強い絵画が、音楽や映画と同じように、日常生活の中にごく普通に取り入れられるようになるかもしれない。こんなふうに絵画を取り巻く環境を変えることも決して不可能ではないのだ。
ユニークな取り組みの中に秘められた大きなミッション――。日本アートアカデミー賞に参加することは、日本の絵画やアートの未来の一端を担うことでもある。
「第2回 日本アートアカデミー賞」の2次審査は7月18日から。これまで絵画に興味のなかった人も、これを機会にぜひアクセスしてみてほしい。 |
 |
第1回 日本アートアカデミー賞
グランプリ受賞作品
「MOVIN'」柏本龍太氏
「第1回 日本アートアカデミー賞」の受賞作品は、日本アートアカデミー協会のホームページにある「ネットギャラリー」で見ることができる。
| ■第2回
日本アートアカデミー賞スケジュール |
| 2004年 |
 |
1月10日 |
 |
出品申込書類受付開始 |
| 4月6日 |
 |
出品手続き締め切り
(応募出展総数1577点) |
| 5月13日 |
 |
1次審査開始 |
| 5月21日 |
 |
1次審査終了、ノミネート50作品決定
|
| 5月21日〜6月4日 |
| |
 |
審査巡回展スケジュール発表 |
| 7月18日〜 |
 |
2次審査
(巡回展、インターネット投票開催) |
 |
| 2005年 |
| |
1月10日 |
|
授賞式典 |
|
|
|