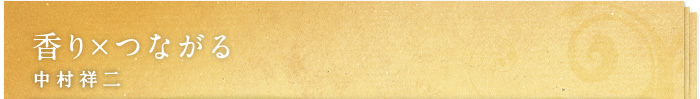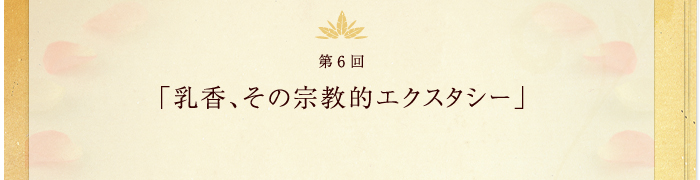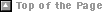香たどん(香を焚くための炭)に火を付け香炉に置き、火が回ったところで乳香をのせて薫じる。淡黄緑色を帯びた半透明、乳白色の小指の先ほどの乳香からは、澄んだ甘さと松ヤニに似た香りの青紫の混じった白い煙が広がる。目を閉じると、古代エジプトの神官達が神に捧げたこの薫煙には、"立ちくらみ"に似た軽いめまいをおぼえる。初めは好きでなかったその香りが、繰り返し焚いている内に次第に惹かれる香りに変わり、それが恍惚感につながるようになってきた。「この香りは私に何をしようとしているのだろう」と思ったものだ。

乳香が樹皮からしみ出しているところ。乳香の名前はこの性状に由来している。代表的芳香樹脂で、北東アフリカのソマリアやアラビア半島南部のオマーンなどで産出される。写真はドローム社提供。
乳香とは北東アフリカのソマリアやアラビア半島南部のオマーンで産出される芳香樹脂で、古代エジプトの第5〜6王朝時代(紀元前26世紀〜22世紀ころ)には、すでに用いられていた。古代エジプト人は、芳しい香煙が天上に昇っていく様子を「神の臨幸」とか「神の顕示」の兆候として眺めていたようだ。
それから2500年のち、イエスがユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき「(星に導かれて東方からやって来た占星術の学者たちが)家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬(もつやく)を贈り物として献げた」。聖書に記されるこの話の中で「乳香」は神を寓意している。
更に2000年たって、私は、パリのノートルダム寺院とサクレクール寺院、スペイン、トレドのサンタ・マリア・ラ・ブランカ教会、ウィーンの王立礼拝堂、そして東京ではニコライ堂の名前で知られる東京復活大聖堂で薫煙を嗅いだ。
ミサが行われている寺院では司祭の祈りが歌うような旋律で流れている。オルガンの音色と、高い天井と、美しいステンドグラスから差しこむほの暗い光が、ミサの荘重な雰囲気を醸し出している。王立礼拝堂ではウィーン少年合唱団の、天使の歌声が天上から降ってくる。この雰囲気にひたると、異教徒の私でも何か逆らい難い力につき動かされ、自然と敬虔な気持ちになってしまう。
乳香は宗教上の儀式や祭祀に用いられ、祭壇で焚かれた香(かぐわ)しい煙は、崇拝する神と人間とを仲立ちするもので、天上の神を喜ばせ、また人々の願いを神に届けるものだった。そして人体を清め、災厄をもたらすあらゆる悪鬼悪霊を追い払い、祖先の魂を慰める方法として、古い時代から広く世界各地で用いられてきた。祭壇の前で祈る人々には宗教的な瞑想と陶酔感、心地よさと生きる喜びを与えてきた。
私は壮大な歴史に秘められた乳香の香りに接するとき、心のときめきと同時に大きな悦びの不思議な感覚に包まれ、神とつながりを感じるのである。
1935年東京生まれ。58年東京大学農学部農芸化学科卒業後、株式会社資生堂に入社。資生堂リサーチセンター香料研究部部長、チーフパフューマーを経て、95〜99年まで常勤顧問。40年にわたり、香水、化粧品の香料創作及び花香に関する研究、香りの生理的、心理的効果の研究を行う。現在は、国際香りと文化の会会長として香り文化の普及に尽力。フランス調香師協会会員。著書に『調香師の手帖』(朝日文庫)、『香りを楽しむ本』(講談社)、『香りの世界をのぞいてみよう』(ポプラ社)など。