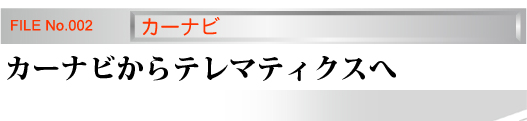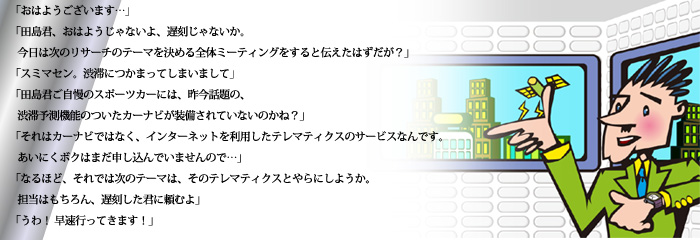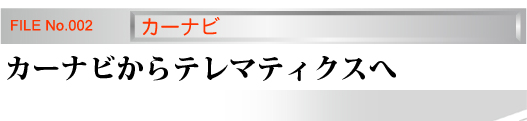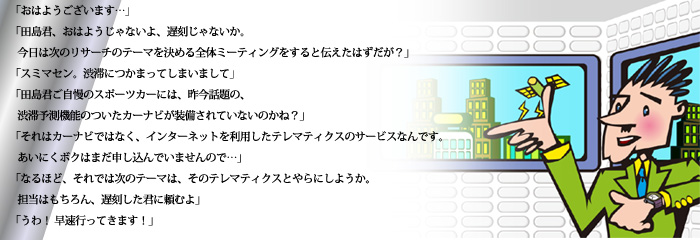地球を回る人工衛星からの情報によって自分の位置を判断するGPSは、カーナビによって私達の生活に身近なものとなっている。そしてカーナビが普及してきたことで、そこに新しいサービスも生まれている。最近では、カーナビにインター ネット接続機能を付加することでさまざまなサービスを実現する「テレマティクス」が自動車メーカーによって実用化、トヨタ自動車の「G-BOOK」や日産自動車の「カーウイングス」、本田技研工業の「インターナビ」などが知られている。移動体通信と車との関係は更に強まり、「走る・曲がる・止まる」という基本の3機能に、「つなぐ」機能を付加したことで、車文化そのものにも大きな影響を与えているようだ。 ネット接続機能を付加することでさまざまなサービスを実現する「テレマティクス」が自動車メーカーによって実用化、トヨタ自動車の「G-BOOK」や日産自動車の「カーウイングス」、本田技研工業の「インターナビ」などが知られている。移動体通信と車との関係は更に強まり、「走る・曲がる・止まる」という基本の3機能に、「つなぐ」機能を付加したことで、車文化そのものにも大きな影響を与えているようだ。
カーナビとテレマティクス。すでに幅広い普及を見せながら、今ひとつ見えにくい両者の関係について、メーカーの話を参考に現状を整理してみよう。
まず原点となるGPS(Global Positioning System=全地球測位システム)は、1960年代に米海軍によって開発が始まった。地球を回る人工衛星に原子時計を搭載、4個以上の衛星からの信号を同時にキャッチすることにより現在位置を測定する衛星測位システムだ。
GPSは、地上約2万キロメートルを周回する24個のGPS衛星と、GPS衛星の追跡と管制を行う管制局、測位を行う受信機で構成され、地球を回るGPS衛星は6軌道面に4個ずつ配置されている。位置の特定には4個以上のGPS衛星からの距離を同時に知ることが必要だ。GPS衛星からの距離は、GPS衛星から発信された電波が受信機に到達するまでに要した時間から求める。軍事におけるGPSの威力は圧倒的で、1991(平成3)年の湾岸戦争
でその効果が世界中に知れ渡ったことは記憶に新しい。
さてGPSによるカーナビは、日本では1990(平成2)年、マツダが三菱電機の協力を得てロータリーエンジン車「ユーノス・コスモ」に初めて搭載した。更にその2ヶ月後、パイオニアが市販型のカーナビを発売した。当時は民需で使えるGPS精度は100メートルと限られていたため、これらGPSカーナビの精度も実用性という意味では充分ではなく、話題性先行の時代だった。
現在パイオニアとカーナビのトップシェアを分け合う松下電器産業が1号機を発売したのは93(平成5)年のことだ。このカーナビはGPSではなく、速度センサーで移動距離を算出、またジャイロセンサーで進行方向の変化を検出して現在地を割り出す自律航法を採用した。つまりパイオニアはGPS、松下電器産業は自律航法を採用したということで、同じカーナビと言っても、技術的には異なる商品として登場したことになる。 |