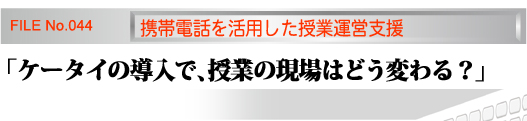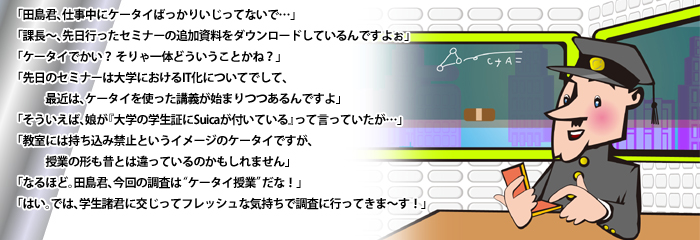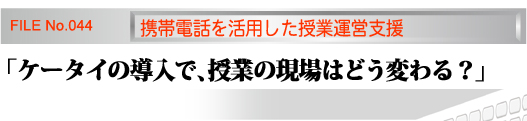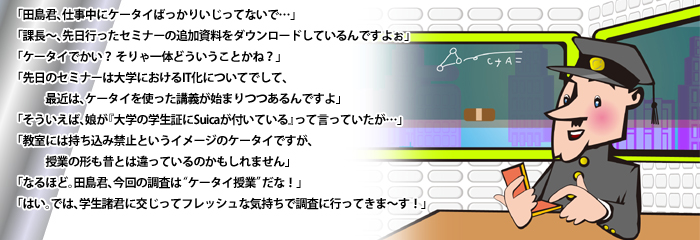|
寺尾先生の授業風景。アンケート結果は随時学生にフィードバックする。
|
次に紹介するのは、実際の授業でよく使われている「アンケート」機能。先生は事前にパソコンでアンケート内容を作成しておき、授業の流れの中で質問する。学生がケータイから返答すると、そのデータはリアルタイムに集計され、先生のパソコンに%数字や棒グラフで表示される。従来のアンケート用紙では不可能だったリアルタイム集計は、授業にどんな効果をもたらすのだろう。
「私たち教員が学生の理解度や意識をその場で把握できるのはもちろんですが、それだけではありません。アンケートの場合は、プロジェクターを使って結果を学生にフィードバックすることが多いですね。そこから、ちょっとした思考実験ができるんです」
寺尾先生の専門分野は、認知心理学と統計学。先生が「統計入門」の授業で行った、ユニークな試みを紹介しよう。
先生はまず、ある主婦が投稿した新聞記事を学生に見せた。話題は定額給付金について。投稿の主旨は「新聞の世論調査では63%の人が給付金を要らないと言っているけれど、本音とは思えない。身近な人と話すと、皆欲しいと言っている。世論調査は実態を反映していない」というもの。先生は学生に「投書した人の考え(世論調査がおかしい。本音ではない)に、どれくらい同意できますか?」という質問を投げかけた。ここで寺尾先生が問題にしているのは、サンプリングデータにおける無作為抽出の重要性。ただし、そのことは学生に伏せたまま質問している。
この時点でのアンケート結果は「非常に同意できる」が21%、「同意できる」が40%、「やや同意できる」が26%、「あまり同意できない」が11%、「同意できない」が2%、「まったく同意できない」が0%。学生の意見は主婦に同意する方に偏っていた。
|
ケータイでアンケートに答える学生。普通の授業では考えられない光景だ。
|
アンケートの結果を公表しないまま、寺尾先生は「青山学院大学の学生の意識調査をしたい時、自分の友人だけを選んだのでは無作為抽出にならない」という例え話をし、学生に考えるヒントを与えた。その後、1回目と同じ質問を学生にしたところ、結果は意外なほどの変化を見せた。「非常に同意できる」が17%、「同意できる」が28%、「やや同意できる」が21%とそれぞれ減り、「あまり同意できない」が23%、「同意できない」が11%、「まったく同意できない」が0%と、主婦の意見に反対する声が一挙に増えたのだ。
「学生がそう答えた理由も興味深いものでした。『無作為抽出といっても、必ずしも無作為になっていないかもしれない』『そういう考えを持った人が、たまたま自分の周りに多かっただけ』など、意見はさまざま。学生も自分たちの変化に驚いていましたね。実はこのアンケートで私が学生に伝えたかったのは『統計学の意味は、多様な見方ができることにある』ということなんです。言われたことをうのみにするのではなく、違った可能性を考えてみる。ケータイを使ったリアルタイムのアンケートだからこそできた調査と言えるでしょう」
|
アンケート画面。設問と回答の選択肢は、あらかじめパソコンから設定しておく。
|
他にも寺尾先生は、アンケートを通じて学生たちの異なる認識を引き出し、その認識に対する解説を加えながらアンケートを繰り返していく、テキストマイニングの手法を授業に採り入れている。「例えば、ある言葉に対する認識が、最初と最後ではかなり違ってしまう。ケータイを使ったアンケートでは、ひとつの物事について深く考察させることができるんです」
こうしたアンケートに対し、挙手や口頭で答えさせるのは難しい。学生は周りを気にするので正直な意見が出にくいし、結果を集めるのも手間がかかる。学生の素の意見をリアルタイムに抽出できる点で、「C-Learning」のアンケート機能は先生に高く評価されているのだ。
ちなみに小テストもアンケートとほぼ同じ手法で行われるが、正解がある点に違いがある。短文なら自由記述させることも可能だ。今の学生はケータイの文字入力に慣れているので、操作面での問題は皆無だという。テストが終わったら、学生は正解だけでなく、自分の得点や解答までに要した時間、順位などをパソコンから閲覧することができる。先生が合格点を設定しておけば、合否の判定もそこで確認できる仕組みだ。
ところで、ケータイを使ったアンケートに課題はないのだろうか。ケータイを操作している間は、授業がストップしてしまうはずだが。「その時間は短いのであまり気になりません。それより気になるのは、アンケートの集計に時間をかけ過ぎると、早く送信した学生が私語を始めてしまうこと。ですから、全員の回答を待つことなく授業を再開することにしています」と寺尾先生は苦笑する。
|
先生のパソコンに表示されるアンケートの回答傾向。回答率がグラフ化されるので分かりやすい。 |
では、授業に参加している学生はどう感じているのだろう? 数人に聞いてみたところ、「ケータイの使用に違和感は全くない」「言いたいことを言える点がいい」という声が多かった。一方で、「興味が湧くかどうかは授業の内容次第」という声も。必修科目での利用が多いこともあるが、学生は意外にクールに受け止めているようだ。
寺尾先生も、ケータイ授業に過剰な期待はしていない。「ほんの数%でも授業に興味を持ってくれる学生がいれば、導入した意義は充分にある」と考えている。 |