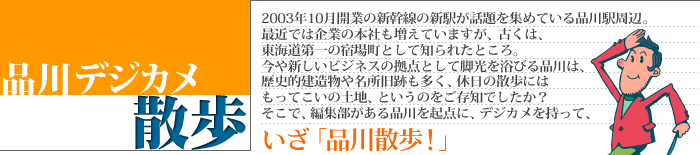もう少し進むと、利田神社がある。 もう少し進むと、利田神社がある。
十一代将軍家斉の時代、寛政10年5月1日、嵐のために品川沖に迷い込んだ鯨を漁師達がとらえたとのこと。長さ9間1尺とあるから、大体18メートルくらい。当時の騒ぎを伝えるかわら版が展示されている。昨今のタマちゃんのようなもの? |
|
 |
 |
 |
| 利田神社の鯨塚。この当時は品川にも鯨が来ていたという |
 |
|
| 旧東海道をはさんで向こう側に渡ると善福寺。 |
 |
|
 |
伊豆の長八の鏝絵(こてえ)があるところ。鏝絵とは、土壁の上塗りの材料として使われる漆喰を鏝やヘラを使って盛り上げ、花鳥風月や人物を半立体的に浮き上がらせる技法のこと。江戸時代末期から明治時代に盛んだったものだ。伊豆の長八は、この鏝絵に日本画の狩野派の技法を取り入れたもので、芸術として高く評価されている。
ただ、残念なことに保存状態があまり良くない。 |
|
| この旧東海道の品川宿は、地域の人が積極的にまちづくりをおこなっているところで、まちの有志が運営する新宿お休み処も、そのあらわれ。ここではお茶のサービスや、旧東海道のまち歩きマップが置かれ観光客をもてなしている。 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
当時大流行だったという鏝絵がある善福寺(写真上段)
宿の歴史を物語る写真が飾られているお休み処(写真下段) |
 |
|
 |
| そしてとにかく子どもがたくさん。みんな楽しそうだ。東京でこんなにたくさんの子どもを一度に見たのは、ちょっと久しぶりだ。 |
|
| この日は、荏原神社の南の天王祭。境内にもたくさんの屋台が出ていて、ケーブルテレビの取材カメラも来ていたが、観光客はさほど多くないようだ。町会ごとに、揃いの着物を誂えているらしい。まちの緊密なおつきあいぶりが伝わってくる。路地では軒先にいすとテーブルを出して近所の人といっぱいやる光景があったり、道を行き交う人がしょっちゅう「こんちわ」「ああ」、どうも、どうも」などとことばを交わしていたり…。
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 屋台も多く、はっぴを着ている子どもがたくさんいる |
 |
|
 |
今日の締めくくりは品川寺。品川寺と書いて「ほんせんじ」と読む。大同年間(806〜810年)に開創された品川で最も古いお寺。 |
|
|
| まずは座高2メートル75センチの青銅の地蔵菩薩座像が目に入る。というか、地蔵というよりは大仏のようだ。
地蔵菩薩座像は、江戸に出入りする六つの街道の入口に置かれた「江戸六地蔵」のひとつ。他にも、開祖である弘法大師空海上人が授けたという水上観音、大田道灌が置いた聖観音や、京都三条の鋳物師、大西五郎左衛門の手による大梵鐘がある。
この梵鐘は幕府の衰退とともに海外に流出して行方が分からなくなっていたが、ジュネーブのアリアナ美術館にあることがわかり、昭和5(1930)年に贈還されたもの。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 品川寺の門前にある地蔵。旅人の安全を見守っていた |
 |
|
|
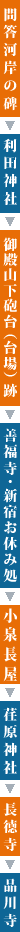
|
 |
 |
 最初に出くわしたのが、問答河岸の碑。沢庵和尚と将軍家光の禅問答が繰り広げられた場所とのことだ。写真を撮っていたところ、案内板を見てメモを取っていた初老の男性が、親切に解説して下さった。 最初に出くわしたのが、問答河岸の碑。沢庵和尚と将軍家光の禅問答が繰り広げられた場所とのことだ。写真を撮っていたところ、案内板を見てメモを取っていた初老の男性が、親切に解説して下さった。
こんな「袖摺り合う他生の縁」があるのも街歩きの醍醐味だ。
左手に入ると品川浦の舟だまりがある。もっと暑くなったら浴衣で屋形船クルーズなどというのも風情があっていいかも。そのときには冷えたビールが欠かせない。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
沢庵和尚と家光が禅問答を繰り広げたという問答河岸 |
|
 |
 |
 次に向かった御殿山下砲台(台場)跡は、台場小学校の中にある。ペリーの来航に驚いた幕府が海岸に砲台を作った。ここに残ったのは唯一陸続きのもの。上に載っかっているのは別の台場にあった「品川灯台」。 次に向かった御殿山下砲台(台場)跡は、台場小学校の中にある。ペリーの来航に驚いた幕府が海岸に砲台を作った。ここに残ったのは唯一陸続きのもの。上に載っかっているのは別の台場にあった「品川灯台」。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
台場小学校にある台場跡。ペリーの来航を迎え撃とうとした政府だったが、品川に6つの砲台を作ったくらいでは到底太刀打ちできなかったようだ |
|
 |
 |
 少し進んで右手に入ると、東海七福神の布袋さまのいる養願寺にあたる。このあたり小泉長屋は、昔の風情が今も色濃く残っていて、今も井戸が使われている。 少し進んで右手に入ると、東海七福神の布袋さまのいる養願寺にあたる。このあたり小泉長屋は、昔の風情が今も色濃く残っていて、今も井戸が使われている。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
この小泉長屋一帯では今も現役という井戸 |
|
 |
 |
 長徳寺は、木造の閻魔様が祀られているという珍しいお寺。5枚の地獄絵図とともに一見の価値あり。本堂の隣にある建物に展示されており、住職に見せて欲しいとお願いしたところ、快く開けてくださり、帰り際に地獄絵図を解説した冊子を下さった。 長徳寺は、木造の閻魔様が祀られているという珍しいお寺。5枚の地獄絵図とともに一見の価値あり。本堂の隣にある建物に展示されており、住職に見せて欲しいとお願いしたところ、快く開けてくださり、帰り際に地獄絵図を解説した冊子を下さった。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
長徳寺の地獄絵。他に木造の閻魔大王坐像があり、こちらも見物 |
|
|
|
|