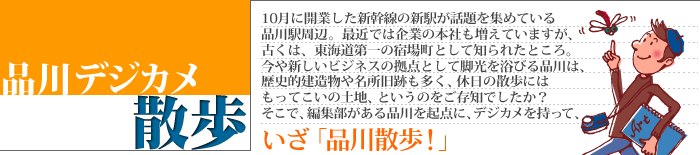|
|
|
 |
日本語のローマ字記述ヘボン式で有名なJ.C.ヘボン氏、新訳聖書の日本語訳を初めて行ったS.R.ブラウン博士、明治新政府の顧問を務めたF.フルベッキ博士の3人がそれぞれに開いた塾が前身となっている。第一期生には島崎藤村がいて、著書『桜の実の熟する時』は、明治学院を舞台に描かれたものだ。
|
 |
 |
|
 |
 |
| 緑に美しく映える明治学院大学
|
|
|
|
|
|
 |
荏原製作所を設立した畠山一清氏のコレクションを保存、展示公開しているのがこちら。ポンプの開発で財をなした一清氏は、即翁と号して能楽や茶の湯なども嗜んだとかで、茶道具のコレクションは見事。館内ではお抹茶とお茶菓子をいただくこともできる。
コレクションもさることながら、一見に値するのはこちらの庭。鬱蒼と緑が茂り、茶室でのひとときと相まって、清々しい気持ちになれる所だ。
|
 |
 |
|
 |
 |
| 都会のオアシスのような空間。畠山記念館
|
|
|
|
|
|
 |
この辺りは、桜田通りをはさんでこちら側が島津山、向こう側が池田山と呼ばれ、それぞれ島津家と池田家の屋敷があったそうだ。
桜田通りに面した地域をはじめ、マンションの建設ラッシュもあるが、昭和10年代から30年代の建築もいまだに多く残っていて、雰囲気のある地域だ。
清泉女子大学の本館が、旧島津侯爵邸だった所。建築は日本の西洋建築の師とも言える英国人建築家ジョサイア・コンドルで1915(大正4)年に竣工した。
区の「しながわ百景」に指定されているが、見学には申し込みが必要。
|
今回、改めて感じたのが品川の路地の面白さ。歴史的な建築があり、人々の暮らしがあり、本当に飽きない。
今回は桜田通りに沿って歩いたが、あるいは八芳園あたりに足を延ばしてみるのもいいかもしれない。 |
 |
 |
|
 |
 |
| 清泉女子大学のある界隈には、島津家の邸宅があった。屋根の上から犬が道路を覗いている
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
| 国道1号は東京・日本橋を起点にして、江戸時代の東海道とほぼ重なる道路で、大阪日本橋までの全長約750kmの国道。起点の日本橋が中央通り、交差点で右折して永代通りに入り、大手町交差点で日比谷通りに入り、桜田門で分かれて桜田通りに入る。ちなみに警視庁を「桜田門」と呼ぶのは門の向かいにあるため。この桜田通りを入って、霞ヶ関、虎ノ門、三田、五反田を抜け、ようやく今日の起点、明治学院大学に到着。
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
まっすぐに伸びる国道1号沿い。休日は車の数も少ない
|
|
|
|
 |
 |
キャンパス内にはいくつかの建学当初の建築が残っている。チャペルは、1916(大正5)年の建築。日本で多くの西洋建築を手がけたヴォーリズの設計だ。ちなみにこのヴォーリズは、かつて「メンソレータム」を発売していた近江兄弟社の設立者でもある。このチャペルは今ももちろん現役で、日曜日のミサや結婚式が行われたりしている。
インブリー館は、1889(明治22)年に建設。当時の宣教師の住まいで国の重要文化財に指定されている。
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
インブリー館。天井の造作など西洋木造建築の特徴が見える
|
|
|
|
 |
 |
畠山記念館を出て商店街にあるお茶屋さん。「こちらは古くからご商売をされているんですか?」と伺うと「いえいえ、まだ60年程度ですよ」とのこと。この界隈、60年ではまだ短いらしい。
近隣の方がお茶を買いに来られるのはもちろんのこと、おなじみは三田の辺りまでいるとのことだ。写真家が撮影をしたいと言って訪れることもあるそうで、今回もモデルをお願いしてしまった。
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
|
商店街のお茶屋さん。時間が止まったようなひとときだった
|
|