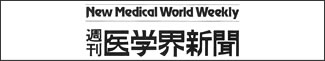
飛行機の中で「急病人が出ました。お医者様はいませんか?」と流れるアナウンス。ドラマならここで医師がさっそうと名乗り出るところだが、日本人の医師で実際にそうした対応ができる人は非常に少ないと言う。
原因は医師養成制度。医師になるには、大学の医学部 → 国家試験・合格(医師免許取得) → 2年間の臨床研修(研修医)という過程を経るが、この研修は努力規定で内容も統一されていない。毎年7割以上の研修医を受け入れる大学病院では、内科や産婦人科、耳鼻科など一つの診療科だけを学ぶ「ストレート研修」が多く、結果、自分の専門以外の部位は全く診ることができない専門医が増えてしまったのだ。
この弊害を克服するため、国は来年度から臨床研修を法的に義務付け、その内容も内科や外科、救急、小児科など7分野においては1カ月以上の研修を必須とした。と同時に、それぞれの研修先をコンピュータの「マッチング」で決定する新システムの導入にも踏み切った。
マッチングとは、医学生は研修したいと考えるいくつかの病院で面接や試験を行ったあと「行きたい病院」の順位リストを、同じく病院側も「採用したい医学生」の順位リストを提出。集まったデータをコンピュータが一定ルールの下に組み合わせる、というもの。
第1回目となるマッチングは11月に実施され、8109人の参加者のうち7756人(95.6%)の研修先が決定。内訳も大学病院が58.8%、その他の「臨床研修病院」が41.2%となり、大学病院への一極集中も改善された形だ。一方、希望した病院とマッチングできなかった353人は、今後募集枠に空きのある病院と個別交渉を行うことになる。
必要性を指摘されながら、なかなか実現しなかった医学界のシステム改善。やっとその一歩を踏み出した今、一人でも良医が増え、少しでも医療が良くなることを願わずにはいられない。
|
|

今や文書作りはパソコンが中心、作ったデータはそのまま電子メールで人に送ることもできる。それなのに、いつまでたっても私達の周りで紙が減る気配がない。いや、むしろインターネットで収集した情報を“念のため”印刷しておいたりする分、紙の消費量は増えているのかもしれない――。
これは結局、電子ディスプレイが、紙の手軽さ、読みやすさにまだまだ追い付いていないためなのだろう。しかし、「電子ペーパー」が実現すれば、今度こそ本当のペーパーレス時代がやってくる!
電子ペーパーとは、紙のように薄く、軽く、読みやすく、丸めたり、折り曲げたりできる電子ディスプレイ。イメージとしては、クリアファイルの中に紙が1枚入っていて、そこにさまざまな情報が映し出される様子を想像してもらえばいいだろうか。1990年代後半から次世代のディスプレイとして世界各国のさまざまな企業で研究開発が続けられてきたが、それがいよいよ実用間近だと言う。しかも、その第1号は日本製となる可能性が大きいのだ。
凸版印刷がアメリカのイー・インク社と共同開発したモノクロ表示の電子ペーパーディスプレイがそれ。メーカー名は発表されていないが、携帯端末機に採用され、2003年度中の発売予定となっている。しかし、これは曲がらないタイプの“第1世代電子ペーパー”で、フレキシブルに曲げられる第2世代が実用化されるのは2005年ごろ。
今後、技術開発が順調に進めば、将来的には新聞や雑誌に電子ペーパーが採用される可能性は高い。何しろ、1枚の電子ペーパーを持ち歩けば何十ページもの情報をいつでも気軽に読めて、またダウンロードすればいつでも最新号に更新できるようになるのだから。
約2000年前に中国で発明され、以後、さまざまな情報を記録・伝達してきた紙。その長い歴史を電子ペーパーが変えることになるかどうか。その答えが出るのはあと数年先のようだ。
|