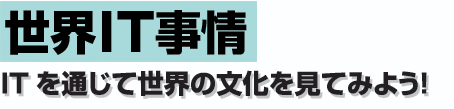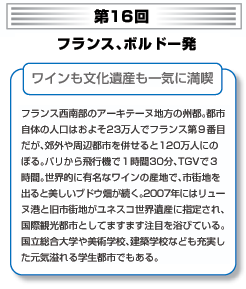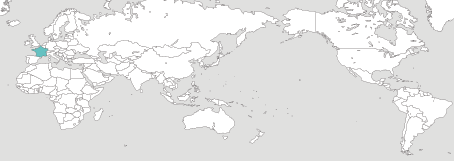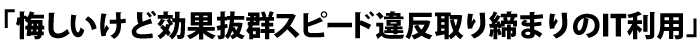 フランス西南部に位置するボルドーは言わずと知れたワインの産地。広々と続く美しいブドウ畑は、四季を通じてその表情を変える。そしてワインだけでなく、牡蠣も名産で、海あり、砂丘あり、歴史的遺産あり、国立自然公園のピレネー山脈までも車で3時間程度と、見所は盛りだくさん。この地方の魅力をじっくり味わうにはやはり車を使っての観光がお勧めなのだが、麗しき大自然の中を真っ直ぐに伸びる国道で、自動車のCMさながら気分良く加速をしていたらとんでもない憂き目にあう。
IT化にイマイチ乗り遅れているような印象を与えるこの国。往々にして古いものが大好きで、アメリカものが嫌い、そして「コンピュータ」をそのまま「コンピュータ」と呼ばずに「オーディナター」とふにゃりとフランス語化してしまうものだから、端から見たら「フランスのIT化って進んでいるの?」と疑問を投げかけたくなる。しかし、意外なところでしっかりとハイテクを駆使しているのがさすがフランス。その一例が「ネズミ捕り」、つまりスピード違反取り締まりである。 もちろん「ネズミ捕り」は25年以上も前から存在した。おまわりさんが暑くも寒くもない日に国道沿いの並木の後ろなどに隠れてスピードを計るアレである。その姿形からフランスでは「バーベキュー」と呼ばれた初期のMESTA206型から現在に至るまで、レーダーの進歩は目覚ましい。しかし最初のレーダーは、技術が発達したとはいえ、機械の後ろにはそれを操作する人間が必要であった。やがて無人で24時間計測可能な「自動レーダー」が登場する。だが2003年以前に設置された「ご先祖様タイプ」のそれも自動的に撮影はしても、ネガフィルムを使っているので、そのフィルムを定期的に取り出してプリントしてから違反車両のナンバーを割り出すという代物。やはり人間の手が必要であった。
フレンチドライバーが本格的にその走行速度に注意せざるを得なくなったのは2003年10月以降、最新のレーダー技術に加えて通信と、こちらも先端の情報処理能力を駆使した「自動レーダー」の設置が始まってからだ。写真は2枚撮られる。車全体とドライバーが写る構図で1枚、ナンバープレートのみで1枚。即、ADSL回線を使ってブルターニュ地方のレンヌにある「CACIR(Centre
Automatise de Constatation des Infractions Routiere)」=「交通違反検証自動化センター」に送られる。そこで、ナンバープレート写真は自動読み取り機にかけられ、警視庁の保管するナンバー登録データから車両の持ち主を自動割り出し、罰金支払いの催促状が発送されるというシステムだ。ナンバープレート写真は自動読み取りの後、調査員が確認をすることになっており、さすがに100%無人化には至っていない。
現在その「自動レーダー」の設置数は増え続け、フランス全土でおよそ1300ポイント、加えて600の「移動式自動レーダー」が覆面パトカーから狙いを定めている。2008年2月には「今から5年の間に2000ポイントの自動レーダーを増やす」と警視庁発表があった。バカンスで人の動きが一番多かった7月19日と20日は、両日で10万台以上の車が「自動レーダー」に「フラッシュ」されている。市街地など制限速度が時速50km以下の所で20km以内のスピード違反ならさっさと払えば90ユーロ(1ユーロ=162円換算で14580円)、郊外や高速道路など制限速度が時速50km以上の所で20km以内のスピード違反なら45ユーロ(同7290円)の罰金だ。最近のガソリン高騰(フランスではディーゼルが230円に迫る勢い!)の上に、こんなものを食らっていてはかなり痛い「車回り」の出費となる。更に悔しいことには、普通郵便や小包などは「国内船便でもあるのか?」と思う程、遅れたり届かなかったりするフランス郵便事情だが、この罰金催促状は呆れる程優秀で違反の2日後にはきちんと到着している。 そんな訳で、制限速度には要注意なフランスドライブだが、さすがオープンなラテン系、政府のサイトにもちゃんとレーダー設置場所が公開されている。(http://www.securiteroutiere.gouv.fr/) しかも、実はIT大好きとしか思えないフランス政府、ネットでの迅速罰金支払いもちゃっかり受け付けているのだ。 (https://www.amendes.gouv.fr/)
|