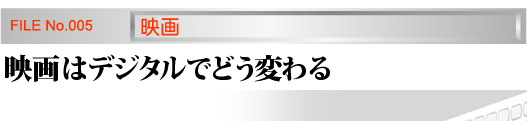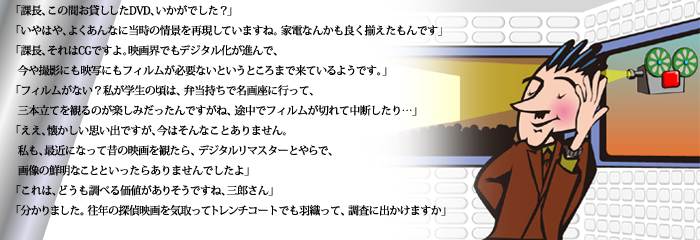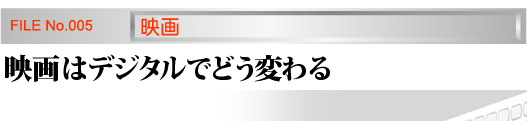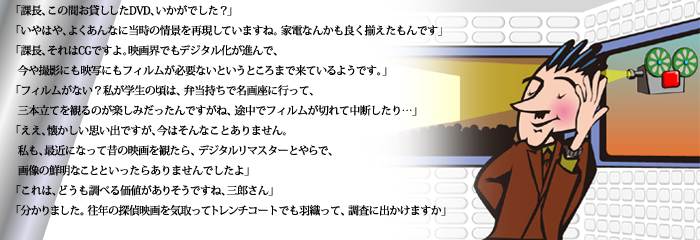| デジタル技術の進化によって、企画、制作、配給、興行、商品化のすべてを巻き込んだ形で変革の真っ只中にあるのが映画だ。映画がデジタル化に取り組み始めてすでに30年が経過しながらも、映画館で実際に上映するという段階では現在もなおフィルムが主役である。映画をデジタル化するとはどういうことなのか。またデジタル化することによって映画はどう変わるのか。制作、配給、興行などさまざまな要素が絡む従来の映画産業のスタイルはどのように変化するのか。デジタル技術の進化と映画との関わりを見てみよう。
19世紀後半にエジソンらによって発明された映画は、機械(カメラ、現像機、編集機、映写機)を使うことを前提とした娯楽であり、これが人類が古代から楽しんできた絵画や音楽との基本的な違いだ。技術の成果はただちに作品に反映され、無声映画から、音の入ったトーキーへと進み、カラー、大画面化などアナログの時代の進化を経て、今やデジタルの時代と、映画の発展にも寄与している。
映画のデジタル化でまず思い浮かぶのは、CG(Computer graphics=コンピュータ・グラフィックス)を駆使した映像表現の多様化であり、現在のほとんどの映画作品は何らかの形でCGを使用している。その進化が映画に与えた影響は測り知れない。CGは商業映画が80年間かけて培ってきた特殊撮影技術を根底から覆す技術として成長し、現在もなお進化を遂げている。その意味でCGは、トーキー以上に映画にとって画期的な役割を果たしたと言える。
CGはもともと、冷戦時代の米軍がソ連の大陸間弾道ミサイルを迎え撃つためのシミュレーション技術としてスタートしたもので、1970年代に入ってこの技術が映像メディアにも応用されるようになり、1977年にジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』で本格的に採用して話題となった。しかし当時のコンピュータでは、3ヶ月かけて90秒のシーンを作成するのがやっとで、かつそのコストは膨大なものだった。
1982年にはディズニーが、実写とアニメとCG画像を融合したファンタジーSF映画『トロン』で、15分に及ぶCG画像を組み込んで注目を集めた。『トロン』は当時最速のスーパーコンピュータを使用して各プロダクションが6ヶ月かけて作ったCG画像をディズニーのスタジオに集め、実写部分と手描きのアニメーションを加えてフィルムにしたもので、CG画像作成以外はすべて手作業によって制作された。
「『トロン』は作品としては面白かったのですが、CGを駆使してコンピュータのCPU内を人間が駆け巡るという大胆な発想が時代に先行し過ぎたせいか、興行的には中ヒットという結果に終わりました。しかし映画関係者の間では、新たな制作技術として大変な話題となり、その後のCG普及のきっかけとなりました」。日本最大の映画情報サイト「シネマトゥデイ」を主催する株式会社ウエルバ、木尾保男社長はこう語る。
『スター・ウォーズ』第一作の1977年から『トロン』の1982年までの5年間でコンピュータを使って映画用のCG画像を作るコストは劇的に下がり続け、約8分の1に下がったとされている。その後のCPUパワーの能力向上・コスト低下は言うまでもなく、1995年にはフルCG画像による長編アニメーション『トイ・ストーリー』が誕生。更に2002年の『スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃』では、ソニーのデジタルHDカメラ「HDW-F900」を使用して全編デジタル撮影を行い、フィルムを全く使わないデジタルシネマが登場する。
|