| 矢野 |
オンライン・メディアの歴史にとって、1998年に発覚した「ルインスキー・スキャンダル」(日本ではふつう「米大統領セックス・スキャンダル」と呼ばれる)は、エポックメイキングな出来事でした。「ルインスキー・スキャンダル」はマット・ドラッジ(Matt Drudge)という人が第一報をインターネット上に開設した個人ホームページで流したことからはじまりました。
この事件に関しては、『マス・メディアの時代はどのように終わるか』(洋泉社、1998)で考察したことがありますが、特徴的な点がいくつかあります。
第1は、大事件の第一報が既存メディアではなく、オンライン・メディアで発せられたこと。第2は、いったんオンライン上で情報が流れた途端、既存メディアも自分の新聞や雑誌、テレビなどで報道するほかに、あるいはそれに先駆け、自社のオンラインサイトで報道、その結果、インターネットを巻き込んだメディア競争がはじまったことです。第3は、現職大統領のセックス・スキャンダルをめぐるスター独立検察官の捜査報告書がインターネットで即座に公開された点。報告書は450ページもの膨大なものであるにもかかわらず、国民がインターネットを通じて逐一見ることができた。そして第4が、事件関係者も続々と自分のホームページを立ち上げて、自分たちの主張を展開しはじめた。以前なら、情報発信のツールを持っていなかった一般の人たちが、こういった活動をするのは至難でした。
これらが、「ルインスキー・スキャンダル」がオンライン・メディアにおいて果たした重要な意義だったと思います。まず、「ドラッジ・レポート」の果たした功罪についてのご意見をお聞かせください。
|
| プロッツ |
 最初に指摘しなければいけないのは、この情報はドラッジが真っ先に入手したわけではないという点です。彼がこのスキャンダルをスッパ抜いたとはいえないのです。ドラッジ以前に、『Newsweek』と『Washington Post』がクリントン大統領の不倫疑惑に関しての取材をずっと続けていたのですから、必ずしもインターネットがこのスキャンダルをつくり出したというわけではないのですね。いずれ、両紙によってきちんとした報道がなされたと思います。 最初に指摘しなければいけないのは、この情報はドラッジが真っ先に入手したわけではないという点です。彼がこのスキャンダルをスッパ抜いたとはいえないのです。ドラッジ以前に、『Newsweek』と『Washington Post』がクリントン大統領の不倫疑惑に関しての取材をずっと続けていたのですから、必ずしもインターネットがこのスキャンダルをつくり出したというわけではないのですね。いずれ、両紙によってきちんとした報道がなされたと思います。
私はドラッジがやったこと自体は結構なことだと思います。彼は独自の調査ジャーナリズムの手法で、既存のジャーナリズムに対して挑むという役割を果たしたともいえるでしょう。ただ、私は彼の手法は好きではないですね。彼は真実ではない記事を掲載することもたびたびあります。しかし、「ルインスキー・スキャンダル」に関しては、ほとんどすべてが事実であったと明らかになっています。ただし、これがインターネット以外の媒体で報道された場合よりも、より興味本位な、キワモノ的な扱いをされたのも事実ですね。
この事件に関してもっとも重要なのは、インターネットが事件報道のサイクルを急速に早めたという点です。既存のニュース機関も、情報を入手してから一晩待って翌朝に報道するのではなく、もうその夜のうちに流してしまえというように、報道をせかされるようになったのです。私はこの点が非常に残念です。『The New York Times』も『Washington Post』も、もっとしっかりと考え、腰を据えて報道したほうがよかったでしょう。この一件以来、他のメディアと競い、できるだけ速く報道しなければならないというプレッシャーを記者が感じるようになったのです。
|
| 矢野 |
あの事件がインターネットの威力を世間に印象づけた面はありますが、一方で、ご指摘があったようなスピード競争のなかで、ジャーナリズム本来のあり方とは何か、メディア自身が揺れ動いたのも事実です。我々ジャーナリストとしては、そうした問題について考えざるを得なかったし、今後も議論していかなくてはならないですね。
|
| プロッツ |
そうですね。
|
 |
| 矢野 |
スター独立検察官の調査報告書がインターネット上に公開されたことは、メディアとしてのインターネットの可能性を大きくクローズアップさせたと思います。新聞にしろ、雑誌にしろ、既存メディアが即座に450ぺージもの膨大な内容を報じることは難しかった。分量的にも、時間的にも、制限のないインターネットだからこそできたことですね。
なにしろアメリカ全土の、いや全世界の読者が同時に、しかも、その全文を自分の目で直接見ることができた。これまでこうした資料は新聞などで要約を読むことはできたけれど、それは編集者の手を経た結果であって、全文を見るという経験はほとんどなかったはずです。ところが、インターネットはそのままのデータを全文読むことを可能にした。だからこそ1日に何百万人もがアクセスしたのでしょう。この一件によって、新しいメディアの時代がはじまったとの意見についてはどう思われますか。
|
| プロッツ |
あの調査報告が公開されたのは本当に驚くべき事態でした。当時、私もオンラインで全文を読もうとしたのを覚えています。ただ、この件についても、評価を躊躇せざるを得ない。それは、「ルインスキー・スキャンダル」が本当に特殊な異例の状況だからです。
もちろん、ある事件に関して、一般の人々が生の情報を知りたいという欲求はあるでしょう。しかし、ラジオやテレビ、さらに多様な新聞や雑誌から情報がどんどん垂れ流しにされると、まるで情報の洪水に飲み込まれているように感じるのではないですか。生の情報を知りたいと思った人も、いずれ「こんなに欲しくはない」、「もっと減らしてくれ」と感じるでしょうし、最終的には「自分たちが欲しい情報を、もっと秩序立った形で整理して提供してもらいたい」と言いたくなると思います。
メディアが本来果たすべき役割は、生のデータを提供するのではなく、それをきちんと整理し、より簡潔に凝縮された情報として提供することです。人々が年がら年中メディアから垂れ流される情報を読まなくちゃいけない、見なくちゃいけないというのは健全とはいえません。大切な情報を得つつ、自分の生活をエンジョイする時間も持てるように支援するのがメディアの仕事でもあります。
我々『Slate』の存在価値もまさにそこにあるのです。
|
| 矢野 |
 たしかにそのとおりです。僕があえて、スター報告書の例でインターネットの威力を強調したのは、膨大なデータも提供できるというデジタル技術の器の広さ、深さに対するプラス面をお話ししたわけです。一方で、プロッツさんがおっしゃったように、メディアの役割における編集作業の重要性にもまったく異論はありません。じつは、そのことに関して最近『情報編集の技術』(プロフィルサイトへリンク)という本を書きました。 たしかにそのとおりです。僕があえて、スター報告書の例でインターネットの威力を強調したのは、膨大なデータも提供できるというデジタル技術の器の広さ、深さに対するプラス面をお話ししたわけです。一方で、プロッツさんがおっしゃったように、メディアの役割における編集作業の重要性にもまったく異論はありません。じつは、そのことに関して最近『情報編集の技術』(プロフィルサイトへリンク)という本を書きました。
これからはじまるデジタル情報社会、サイバースペースを通じて情報が交流する社会を迎えて、それを賢く利用するためには、基礎的な知識、能力を身につけなくてはならないでしょう。そういった「サイバーリテラシー」について、哲学や法律、経済、芸術、文学といったさまざまな分野の人たちのお話をお聞きしながら、この対談を続けているのですが、きょうはメディアの現場で働いているプロッツさんにインターネット・ジャーナリズムについての興味深いお話をお聞きできて、大変うれしく思っております。
|
| プロッツ |
「サイバーリテラシー」については、ヘンリー・ジェンキンスという人の書いたものをご存知ですか。彼は哲学者のような人で、Webページを持っていますが、非常に聡明な方です。MITのWebサイトにいってヘンリー・ジェンキンズを探していただくと、矢野さんによく似た関心を持っているのがわかります。こんど彼にインタービューされたら、おもしろいと思いますよ。
|
| 矢野 |
彼は本を出していますか?
|
| プロッツ |
何冊か本を書いています。サブカルチャーなんですけど、矢野さんの提唱とたいへん通じることを書いています。
|
| 矢野 |
それはどうもありがとうございます。さっそく見てみます。
|
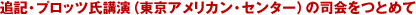 |
このインタビューは、米日財団メディアフェローの一員として来 日していたデビッド・プロッツ氏が東京アメリカン・センターで講演をする司会役を矢野が引き受けたのがきっかけで実現した。東京アメリカ ン・センター、アメリカ大使館のみなさまのご協力にお礼申し上げます。
5月20日に東京アメリカン・センターで50人余りの聴衆を集めて行われた講演で、プロッツ氏は、「日本ではiモードなどが普及して、インターネットで各種の実用情報を入手することが盛んだが、アメリカではケータイはそれほど普及しておらず、インターネットはむしろパソコンでさまざまな情報を入手し、それをさらに加工、編集することに使われている」と、日米の電子メディアの使い方の違いに言及し、また、勃興しつつあるオンライン・マガジンは、とかく上から読者を見下ろしがちな新聞とは違う、読者と同じ視点でものを見、なるべくくだけた、カジュアルな文体をもちいるという新しい記事のスタイルを打ち立てつつある、私には1日100通のe−mailが来るなど、読者との距離がぐっと縮まったといった話もした。
私がとくに興味深く思ったのは、オンライン・メディアの硬派誌を毅然 として(?)追求しているらしい『Slate』の編集方針だった。これについての私の見解は、対談で述べている通りである。
マイクロソフトという一大企業の傘下にあることと、中立・公正な報道とは両立するのかということに関して、聴衆のメディア関係者からいくつか質問が出されたが、それに対して、プロッツ氏は「いまのところ何の問題もない。将来的にもまったく干渉してこないとは、私はそう望むけれども、保証できない。喧嘩になれば我々のほうが負ける。自らお金さえ稼げれば、自分たちの思うように運営できるわけだから、早くそうなりたいと思っている。マイクロソフトは、このメディアはもうかると考えて年間数百万ドルの支援をしているのではないか。またインターネットというメディアを調査する手段、あるいはマイクロソフトのPRと考えているのだと思う」などと、かなり率直な意見を述べた。やや楽観的だとも思われたが、それは、紙のメディアで活躍していた多くのライターたちがオンライン・メディアに大挙して進出し、新しいメディア立ち上げに邁進しているアメリカならではの「自信」かもしれない。
日本でも、オンライン・ジャーナリズムを追求しているサイトはいくつかあるが、既存マスメディアのオンライン版を別にすると、きちんとした編集方針の元に運営されている新手のオンライン・メディアは非常に少ない。
プロッツ氏もふれているBlogというのは、Weblogの略で、最近、記事の更新が簡単にできるソフトの登場で急に増えてきた個人のジャーナリズム活動(日記掲載)のことである。そのソフトを使って、ウエブ上の情報を自ら編集して、それらにリンクを張るサービスをはじめるホームページも登場し、人気を集めている。『ハッカーズ』(工学社、1987、原書は1984)という本で有名な米ジャーナリスト、スティーブン・レビーは『Newsweek』に「ブロッグはオールドメディアを殺すか」という記事を書き、「2007年には多くの人びとがニューヨークタイムズではなく、ブロッグからニュースを得るようになるだろう」との関係者の予言(賭け)を紹介している。
既存マスメディアとは独立した個人のジャーナリズム活動が増えてくると、ジャーナリストのあり方も変わらざるを得ないし、紙のメディアと 電子メディアの差別化と棲み分けは、メディアに関わる人間にとって、これからの大きなテーマでもある。大事なのは、既存メディアが曲りなりにも果たしてきたジャーナリズムという機能を、社会全体としてどう維持し、発展していけるかであろう。
私自身、NTTコムウェアという企業のホームページ、「コムジン」でこの対談を続けており、これは私なりのオンライン・ジャーナリズムの実験でもある。こういう機会をいただけたことをありがたいと思っている。この場を借りて、NTTコムウェアおよび関係者にお礼申し上げる。
対談でもふれているように、プロッツ氏の「いいメディアをつくれば生き残れる」という発言は、その点で心強くもあるが、ことはそう簡単でないようにも思われる。問題は、広告収入も含めて、ビジネスとして採算がとれるようなうまい方法が見つかるかどうか、あるいは誰がそのために金を出すか、ということであろう。
|