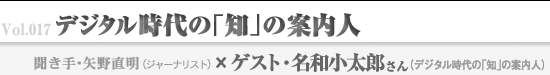 |
 |
|||||
|
||||||
|
矢野 |
『デジタル・ミレニアムの到来』の中で、現代人はあるときは消費者であり、あるときは企業人であり、あるときは専門家として、タイム・シェアリングで活動しているのだから、どの理念や倫理に高いプライオリティを与えるかどうかは場面場面において当事者が「自己決定」しなければならないとお書きになっていますが、やはり情報倫理の土台は自己決定ということですか。 |
|
|
名和 |
格好よく書きましたが、本当にそう言い切れるかどうか、正直、よく分からないですね(笑)。 |
|
|
矢野 |
末尾に「消費者のなすべきことは、愛想のよいネチケットなどに同調することでは足りない。疑問があれば、臆せず、それを専門家に質す。これしかない」とお書きになっています。 |
|
|
名和 |
この5〜6年、「科学技術への市民参加を考える会(AJCOST)」というNPOの活動を手伝っているんですが、この会の目的は一般市民の視点で科学技術政策に影響を与えたいということです。1980年代なかばにデンマークで生まれた「コンセンサス会議」という市民参加によるテクノロジー・アセスメント(事前評価)の一方式です。これは公募によって選ばれた市民たちが専門家と討議を重ね、コンセンサス(合意)を得て結果をまとめ、公表するのです。デンマークでは実際に社会に影響を及ぼすようになっており、スウェーデンやオランダでも制度化されています。 |
|
NPOが市民の代弁者に |
|
矢野 |
アメリカでは政策に影響を及ぼすほどの強いボランティア団体がありますが、日本でもボランティア活動が少しずつさかんになっているんですね。 |
||
|
名和 |
僕もこの活動をはじめて、似たようなことをやっている人たちが多いのに驚きました。ボランティアの人たちは熱心のあまり、会員同士でぶつかってやめてしまうなど、人の出入りは激しいのですが、全体として増えていることは間違いないですね。 |
||
|
矢野 |
インターネットの世界を専門家がコントロールできなくなり、一方で非専門家がNPOを作って動き出している。つまり、世の中の構造が変わりつつあるなかで、古い組織が崩壊して、新しい秩序が生まれようとしているのだが、まだ力を持っていないという段階でしょうね。 |
||
|
名和 |
杉本さんは技術士です。技術士は専門家としての社会的認知もあり、自立してもいます。だが、そうした資格も持たず、組織も持たない市民がどうやって社会的に自立できるのか。1人では持てる力は小さい。その1人を支援するところにNPOの役割があるんだと思います。 |
||
|
矢野 |
いまのお話は、「消費者のなすべきことは、愛想のよいネチケットなどに同調することでは足りない。疑問があれば、臆せず、それを専門家に質す。これしかない」とお書きになったことに続くものとして理解していいですね。 |
||
|
名和 |
そうです。その通りです。したがって逆にいえば、市民の疑問に応えるのが専門家の倫理、また、市民の疑問をしかるべき専門家を探してそこに繋ぐのも専門家の役割、こう考えています。 |
||
|
矢野 |
僕は長らく編集者をやってきて、編集者の仕事というのは、「現代」という土俵の上に多くの著作者、あるいは時代のテーマを引き出すことだと考えています。これからは誰もが編集者になる時代でもありますが、それはとりもなおさず、いたるところに交流の場を作っていくということでもありますね。 |
||
|
| 撮影/岡田明彦 |