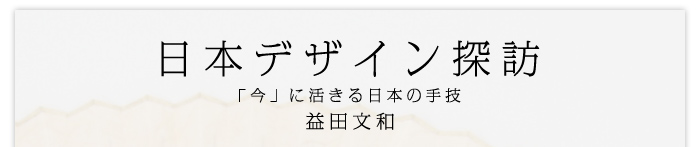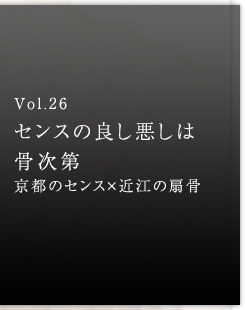梅雨から夏へかけて蒸し暑い日がやってくる。夏になると電気で冷やすのが常態だから、節電しなければなどと思うのであって、今年もいつも通り暑い夏がやってくると心得れば、むしろありがたい。とは言え、暑いことには変わりないのだから、それなりの備えをするのが身だしなみ、ということで、京都へ行ったついでに扇子を新調しようと考えた。
確かに、扇子と言えば京扇子が有名だが、日本で作る扇子の骨の部分、つまり扇骨の9割はお隣の滋賀県産だと聞いたことがある。調べてみると、近江の安曇川流域に自生する竹を使った扇子作りの起源は古く、300年前とも言われているが、今の高島市で扇骨づくりの工芸が栄えた歴史も幕末までさかのぼるらしい。それなら、ということで琵琶湖まで足を伸ばすことにした。
京都から安曇川駅まで湖西線で小一時間、新快速なら40分ちょっとである。右側の車窓からは琵琶湖と、湖畔の箱庭のような風景が眺められ、飽きることがない。安曇川駅から琵琶湖に向けて東に進む。途中、大きな扇型の立て看板に扇骨工房の所在を知らせる案内板など珍しく眺めながら、何軒かの扇子製造直売店をのぞいて歩く。そのうちの一軒、「すいた扇子」で求めたのがこの夏扇である。
わざわざ夏扇というのは、扇子には舞い扇や飾り扇などさまざまな用途があるためで、これは扇(あお)いで涼むための実用品である。扇骨の産地らしく、竹を薄くはいで作った骨が占める部分が広く、本数も40本と一般の扇子より多いのが特徴だ。薄く、しなやかならば扇骨で扇いで何ら不都合はない訳だ。申し訳程度に張られた無地の雲竜紙は、ご愛嬌。ここに京都の紙を張れば京扇子となる。京のセンスも骨次第なのである。
- 1949年
- 東京生まれ。
- 1973年
- 東京造形大学デザイン学科卒業
- 1982年〜88年
- INDUSTRAL DESIGN 誌編集長を歴任
- 1989年
- 世界デザイン会議ICSID'89 NAGOYA実行委員
- 1991年
- (株)オープンハウスを設立
- 1994年
- 国際デザインフェア'94 NAGOYAプロデューサー
- 1995年
- Tennen Design '95 Kyotoを主催
- 現在
- (株)オープンハウス代表取締役。近年は特にエコロジカルなデザインの研究と実践をテーマに活動している。