| 矢野 |
「LIFE」の後に、いくつか面白いサイトを立ち上げておられますね。
|
| 粟飯原 |
プライベートで立ち上げたサイトが2つあります。1つは「よせがきコム」という、インターネット上で無料で寄せ書きを作成できるサイトです。そのサービスを思いついて、ドメイン(yosegaki.com)が空いているとわかったときは、すごく興奮してわくわくしました(笑)。
結婚や出産、退職とかのタイミングで、例えば、矢野さんのお誕生日に、友人皆でメッセージを送ろうというときに、私が発起人だとすると「よせがきコム」に行って、「矢野さんへの寄せ書き」というのを作成するんですね。寄せ書きをしてほしい人のメールアドレスを入力して、OKというボタンを押すと、皆にメールが行って、「矢野さんにお誕生日の寄せ書きを書いてあげましょう。ついてはこのURLにアクセスしてメッセージを書いてください」と。すると世界中、日本中のメンバーが一気にアクセスしてメッセージを書く。結婚式の寄せ書きで200人も集まる方もいらっしゃって、すごくすてきですよ。
|
| 矢野 |
これはいつ立ち上げたんですか。
|
| 粟飯原 |
 2000年5月です。親友の結婚式のときに180人ぐらいから寄せ書きが集まって、それを徹夜でレイアウトして印刷、当日結婚式に持っていって、全員に配りました。 2000年5月です。親友の結婚式のときに180人ぐらいから寄せ書きが集まって、それを徹夜でレイアウトして印刷、当日結婚式に持っていって、全員に配りました。
3月の時点で総ユニーク登録者数(ホームページを何人の人が見たか、重複しない利用者数)が延べ18万人。これはプロモーション費用をまったくかけてないんです。寄せ書きってすごく面白くて、発起人と受取人が1人いれば、その友だちが1回で全員会員になってしまう。ある寄せ書きを企画すると、その参加者たちが1人でも多くの人に書いてもらおうとするので、必死でメンバーを集めてくれるというロジックのもとに成り立っているサービスで、どんどん人が増えていく。これは株式会社にしています。
|
| 矢野 |
何を収入にしているわけですか。
|
| 粟飯原 |
寄せ書きを書くタイミングって、ものを贈るタイミングなんですよね。お花だったり、お祝いだったり。ここに広告を出したいというオファーがすごく多いんです。
|
| 矢野 |
なるほど、広告収入でペイしているわけですか。
|
| 粟飯原 |
はい、普通に黒字。赤字ではないです。いままでインターネットはバーチャルの世界だと言われていたんだけれど、どちらかと言うと、リアルなコミュニティに対するツールとしてこれから利用できるんじゃないかと感じて、よせがきコムを立ち上げたわけです。
その1年前に作ったのが、「OL美食特捜隊」というグルメサイトです。99年に同僚5人で、自分たちの脚で探し、自分たちのお金で食べたおいしい料理とお店を紹介するサイトとメールマガジンを立ち上げました。そのうち、読者からお店紹介のレスポンスがくるようになって。私たちは「クチコミ隊員さん」と呼んでいるのですが、いま、2万5000人に達しています。
|
| 矢野 |
店にはアポなしで行って、載せちゃうわけですよね。「困る」と言われたことはありませんか。
|
| 粟飯原 |
メールマガジンに掲載したお店で、「困る」と言われたところはまだありません。
|
| 矢野 |
ラーメンサイトが百いくつかはあるでしょう。そうなると、全国のラーメン屋はどこかのサイトに評判を書かれる恐れがある。お店としてはだれがどんなことを書くかわからないと思って緊張する。だから全体として味が少し良くなったという話もあるけど、どうでしょうかね。皆が発信して何でも書けるということで、どんどん書かれて、悪い評判が立ったりすると困るじゃないですか。そういう世の中の仕組み自体が、全体として少しずつ変わって来ていると、僕はそういう話を聞くと思いますね。
こういうことが、ビジネスやサービスの質を変化させていっているのではないか、と。これはインターネット社会のいい面と言えるでしょうね。
|
| 粟飯原 |
おっしゃる通りかもしれないですね。そういう意味でサービスのグレードが引っ張られて上がっていくというようなことが実現するのかもしれないですね。
|
| 矢野 |
店で、あなたは「OL美食特捜隊の1人じゃないでしょうね」って言われたりして。
|
| 粟飯原 |
聞かれたことはただの1回もないですね(笑)。
|
| 粟飯原 |
みんなが発信者になることで、サービスのグレードが引き上げられていくとしたら、楽しいことだと思います。
|
| 矢野 |
そうですね。僕が提唱している「サイバーリテラシー」では、インターネットのプラス面とマイナス面の両方をきちんと見ていきたいと思っていますが、いい面もたくさんありますね。
「OL美食特捜隊」の活動を集大成したのが『TOKYO 美食パラダイス』(実業之日本社、01年)という本ですね。サブタイトルに「全部自腹で食べました」とあるのがいいですね(笑)。
|
| 粟飯原 |
本当に覆面で行って、自腹で食べて、みんなボーナス1回分ぐらいは使ってしまいました。
|
| 矢野 |
この本は、いろいろ紹介されて評判になりましたね。
|
| 粟飯原 |
おかげさまでかなり好評のようです。新聞やテレビの30分番組で紹介されたり、オンライン書店のAmazonでは7日間連続総合ベストセラーの第1位になって、私たちもびっくりしています。
|
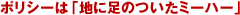 |
| 矢野 |
粟飯原さんは、次から次へと面白いアイデアがわいてきて、それをどんどん具体化して楽しんでおられるように思います。いまはウエブでも若い女性たちの元気が目立つ時代ですね。
|
| 粟飯原 |
 気軽に発信できる時代に生まれたのは、すごく幸福なことだと思います。いま、私の周囲でもウエブ日記を書くのがはやっていて、「どうしているかな」と思ったらウエブをのぞけば近況が分かる。そういうのも発信の1つですよね。 気軽に発信できる時代に生まれたのは、すごく幸福なことだと思います。いま、私の周囲でもウエブ日記を書くのがはやっていて、「どうしているかな」と思ったらウエブをのぞけば近況が分かる。そういうのも発信の1つですよね。
私がこれからやりたいのは、情報編集の仕組みを提供するようなことです。雑誌の場合は編集者が仕組みも中身も作っていきますが、ネットでは編集の仕組みを用意して、中身は投稿者に委ねるようなことが自由自在にできる。データベースにランキングなり、新着なり、仕組みを用意して、あとは情報を入れていってくださいと。それがすごくおもしろいと思っているんです。
|
| 矢野 |
次々と企画が湧いてきますね。あなたは仲間にどんなふうに言われていますか。
|
| 粟飯原 |
どうでしょうね。
|
| 矢野 |
「インターネットわくわくレディ」とか?(笑)
|
| 粟飯原 |
すてき(笑)。これからも、自分の中のわくわくと一致するものを作っていけたらいいな、と思っています。
|
| 矢野 |
アイデアは湧く湧く、気持ちはわくわく、ということね。
|
| 粟飯原 |
私は、はじめてお目にかかる方から、「意外と普通ですね」と言われることが多いんです。私自身も、本当に何か強烈な個性を持っているわけではないんですね。だからなのかもしれませんが、普通のOL、普通のミーハーの気持ちを忘れたくないな、という思いがあって、ふだんの生活の中で思いついたことを地に足をつけてやっていきたい。「地に足のついたミーハー」という言葉が気にいっていて、私のポリシーでもあるんです。
|
| 矢野 |
コンピュータにはいつごろから親しんでいましたか。
|
| 粟飯原 |
社会人1年目、96年の8月にはじめて触りました。
|
| 矢野 |
それまでは、ITと縁がなかった? 大学では何を専攻されたのですか。
|
| 粟飯原 |
マスコミュニケーションと社会学です。学生時代にケーブルテレビのアルバイトをして、番組を作ったりしゃべったりしていました。その当時、NTTコミュニケーションズが「マルチメディア元年」と言っていて、それにひかれて入社しました。
|
| 矢野 |
この時代が若い女性にチャンスを与えてくれたという、モデルのような方ですね。素直にインターネットを楽しんで、それが世間の反響を呼んでいく。
メディアに興味を持って、この世界に入られたと言われましたが、5年たってやっているのが「All About Japan」という、まさに新しいメディアですし、仕組みを作りたいという希望どおり、まさに仕組みそのものを提供しておられる。これからの抱負は?
|
| 粟飯原 |
ひとつ温めているアイデアがあって、それを具体化するタイミングを探しているんです。
|
| 矢野 |
この次を考えていらっしゃるわけですね。今日は、若い女性がインターネットを縦横に駆使して、人生を楽しんでいるモデルケースとして、粟飯原さんのお話をお聞きしたわけだけれど、文字通りの「わくわくインターネットライフ」でしたね。どうもありがとうございました。
|

私は今年7月29日で朝日新聞を定年退社し、あわせて「サイバーリテラシー研究所」のホームページを立ち上げたが、この対談を編集してくださっている吉原佐紀子さんが「よせがきコム」を使って、私に「サイバーリテラシー研究所」開設祝いの寄せ書きを集めてくださった。
対談のときの冗談でそんな話は出たが、すっかり忘れていたので、ある日突然、寄せ書きのお知らせが来たときはびっくりした。アクセスするホームページのURLが記されており、そこで自分のアドレスを打ち込むと、数十人の方からの寄せ書きを一覧できた。これはなかなかいいアイデアです。いままでの寄せ書きは、ある会場に集まった人たちがお祝いの場に存在した証として書いたわけだけれど、この寄せ書きは世界中のどこからでも書けるわけです。システムはよくできており、寄せ書きに対するお礼もすぐ送信できるようになっている。
女性らしく気配りのきいた企画でもあり、粟飯原さん本人が言うように、寄せ書きを贈られる人と世話人がいると、たちどころに数十人のメールアドレスが集まるという仕組みもなかなかのアイデアです。
矢野直明・記 |
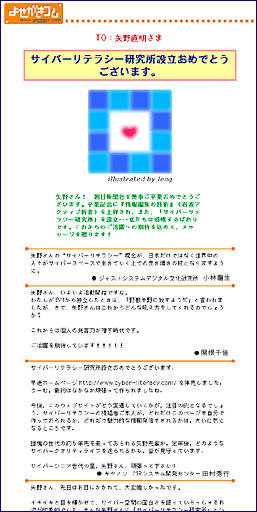 |
| なお、よせがきコムを運営する株式会社サイドビー・ネットワークは、 2002年8月30日付けで、楽天株式会社に全株式を売却されたそうです/編集部 |
|