| 矢野 |
インターネット・コミュニティは、IETF(Internet Engineering Task Force)に象徴されるように、それがもっぱら技術の問題だったときにはきわめてスムーズに運営されてきたが、その規模の拡大で社会的な問題を解決しなくてはならなくなって、転機を迎えているとも言えますね。サイバースペースの拡大が現実世界に大きな挑戦を突き付け、同時にインターネット・コミュニティをも揺るがしている。
|
| 会津 |
サイバースペースと現実世界という分け方、僕はあんまり好きじゃないんですけど……。現実世界の中にサイバースペースがあると思っています。あるいは、いまの世界の一部はもうサイバースペースなんですね。こっちは現実世界で、あっちはサイバースペースだという、そういう分け方が間違っていると僕は思っています。
|
| 矢野 |
僕がなぜ現実世界とサイバースペースを分けた方がいいと思っているかというと、第一にデジタル空間であるサイバースペースは現実世界とはまるで違う原理で動いており、しかも、会津さんが言うように、いまでは現実世界と密接な関係をもっている。だからこそ、サイバースペースのもつ特性をきちんと理解しないと、それを上手に使って、現実世界を豊かなものにすることも難しい。
たとえば盗聴でも何でもいいけれど、デジタル情報であることで、これまでのアナログ電話の盗聴とはまるで違うやっかいな問題が起こってくるわけで、デジタル技術が生み出すサイバースペースの基本構造を理解する能力をサイバーリテラシーと呼んでいるわけですね。サイバースペースはすでに現実そのものであるというのは、その通りでもあるが、サイバースペースと現実世界をいったん区別することで、その相互関係をより明確にできるし、これからのIT社会により有効に対処できると考えているわけです。
さらに技術と社会の関係で言えば、現実世界においては、社会と技術は相互に影響しあって社会を変えていくと言えるけれど、サイバースペースにおいては、技術はその基盤そのものです。技術によってサイバースペースはいかようにも変えられる。そうしてできたサイバースペースが、現実世界に大きな影響を与えるわけです。
|
| 会津 |
経済が社会の一要素であるのと同じように、技術も社会の中に入れなきゃいけない。
僕は、社会と技術を同じウエイトで2つに分けるのは違うと思っています。社会の1つのコンポーネントが技術です、というのなら正しい。ほかのコンポーネントとして、経済、文化、安全保障などなどいくつものものがあり、それらの間のインタラクションを考えなくてはいけない。それを、技術者は技術者、あとは社会系の人というふうに、文科系と理科系みたいに分けても、実際には、技術の社会的影響力は大きい。逆もしかりで、社会が技術をディクテートすることもあるわけですね。
|
| 矢野 |
その基本は、僕もまったく同じ意見なんだけど。インターネット社会が、いままで比較的ボランティアでセルフガバナンスであり得てきたのは技術の問題だったからじゃないかと思うんですね。いわゆる技術の標準を作るという部分で、うまくいってきた。社会の問題を考えるべきではあるが、考えなくても済んだか、あるいは外へ出してもとりあえず問題にならなかったと。それが、社会の問題を考えざるを得なくなっているいま、矛盾が噴出したのだと理解しています。
|
| 会津 |
 いままでも社会の問題とか、利用者の問題は考えてきたと思います。そのとき、利用者と提供者プロバイダーとは距離が非常に近かった。けれど、利用者が変わり、プロバイダーも変わっていったという認識がついていってないのだと思います。 いままでも社会の問題とか、利用者の問題は考えてきたと思います。そのとき、利用者と提供者プロバイダーとは距離が非常に近かった。けれど、利用者が変わり、プロバイダーも変わっていったという認識がついていってないのだと思います。
加藤さんなんかにもじつは近い考え方があって、彼はICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers、アイキャン)の理事会でビント・サーフたちと激論したらしいんですが、「彼らは本当に技術者だけでものを決めようとするんだよ」と。彼はロイヤーだから、ロイヤーもエコノミストもユーザーも、全然違う観点を持った人たちが一緒になって決めなきゃいけないわけ。
そういう点で、ICANNそのもののあり方にも疑問があるし、日本でもこれまでJPNICとか村井さんに代表される、インターネット・コミュニティと言われる人たちが、重要な問題を決める仕組みを必ずしもオープンにしないできたことは、同じように問題だと思います。それは彼らの業績を認めないというわけではないんです。ただ、方法論として、そのままでいいんだろうかという疑問がすごくあるわけです。
|
| 矢野 |
そういう社会の問題がいやおうなく大きくなって、技術者だけで考えてもらっては困る事態になっていくことは間違いないわけでしょう。
|
| 会津 |
そうです。僕は、技術者の人には、自分たちがつくっているものの影響がどこに出ているか、徹底的に自分でトレースしてほしいと思う。作りっ放しにするなよな、と。そうすれば、いろいろなことがわかる、逆に技術的にだってわかるでしょうから。
|
| 矢野 |
僕がそういうことを言ったときに、ある人が、「車をつくった人は、その車が普及したことによってフリーセックスが流行ったりなんてことは思いつかないだろう」と言っていた。
|
| 会津 |
最初はね。
|
| 矢野 |
だから、いずれそういう問題がどんどん出てくることについて、技術者だけで考えなくてもいいんですよ。
|
| 会津 |
じつは、かつて車のマーケティングの仕事にさんざんつき合ったことがあるのですが、いい車を出すときは、エンジニアはマーケットへ出ていって自分で調べるんですよ。すると、その車は思ってもみないような使われ方をしていた。そこで、ユーザーに聞いてみるとか、自分で使ってみるそうです。そして、もう一回技術の場に戻して、次の企画でフィードバックをやらないといけない。そうしないと、下手すると無意識のうちに、社会的な点に強い人たちでマーケティングを進めて、技術者を社会の現場から遠ざけることになりかねない。それも違っていると思う。
|
| 矢野 |
それはもちろん違いますよね。
|
| 会津 |
技術者もいっしょにつき合いなさい、最後まで責任をとりなさいと。自分たちは作った人であって、使う人じゃないから、あとはそっちで考えてくれというのも困るし、技術者だけで考えるのも困るんですよ。あくまで共同作業だ、と。
それをどうやってループ全体のシステムとして作っていくかということをやらないと、さっきの2分法がいつまでも続いて、専門家だけになってしまう。
|
| 矢野 |
僕は2分法じゃないんだよ。
|
| 会津 |
往々にして議論はそっちへ流れていくでしょう。だって、ISOC(アイソック=インターネット協会)でIETFの真似をしてISTF(Internet Societal Task Force)というのをつくり、技術者が中心になって社会的問題を扱おうとしたことがあって……。
|
| 矢野 |
そういうふうにしたけれど、結局うまくいかなかった。それを1つの歴史的教訓としていいんだと僕は思う。だから、僕はそれがどうなっているかということを聞きたかったわけ。うまくいかないんですよ、やっぱり。技術の問題で僕が常々考えているのは、技術でつくり上げていくサイバースペースの構造というのは、現実にはね返ってきていろいろな問題を起こす。そのときに、技術の人は、技術のことだけを考えていちゃまずいということです。
|
| 会津 |
ものすごくまずい。
|
| 矢野 |
社会というか、一般の人たちもそういうことに参加していかなくてはいけないし,人文系の人ももちろん議論に参加しなくちゃいけない。そういうグラウンドを作っていくことが非常に大事なんだけれど、これがけっこう難しい。と同時に、いまは技術の影響があまりにも大きいから、あっという間にそれが決定的なことになる可能性もある。昔は技術というものが間違っていても、危険はまだ少なかった。
|
| 会津 |
時間的にも、そんなにいっぺんに広がらないとか……。
|
| 矢野 |
そう、そう。それに、おのずと技術の制約があって。
|
| 会津 |
それでも、電気が出てきたときには、アメリカで、これで世界は民主化されると言った人がいたわけでしょう。貧しい人も安くエネルギーが手に入る、と。その歴史はすごいんですよね。
|
| 矢野 |
電気もそうだけれど、遠いところへいけば自然に暗くなるんですよね。ところが、インターネットになると、あっという間に全世界に放たれていく。どこまでもいくとか、そういう意味で、技術の影響はすごく大きいわけです。
|
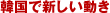 |
| 会津 |
僕はインターネットがいままでの技術に比べて、本質的に社会的影響力が違うかどうかというのは、そう明確にはわからないと思っています。19世紀初めころの電信技術が19世紀社会をどのぐらいのインパクトで変えたかということと同じには論じられない。 たとえば、同じ通信技術といっても、大西洋を無線が走ったことによって戦争のあり方がどう変わったかということと、インターネットのユーザーが何億人いるから地球社会にどんな影響があるかということを同じレベルでは計れないですよね。
もちろんいまのインターネットの影響、マグニチュードというのがあるかもしれませんけれども、それは衛星のテレビがあったり、ジャンボ機が飛んでいたり、インターネットと直接は全然関係ないグローバル金融システムがあったりと、それぞれものすごく大きなファクターが全部つながっているような気がしているんです。同じような意味で、電力や電信もそうなんですけどね。かつてのテクノロジーの社会的なインパクトの度合いというのは、いまの我々はもう知りようがないから。こっちのほうがすごく大きいだろうとは思いますが。
それから、矢野さんが言っていることも、否定はしません。たしかにインターネットのインパクトも非常に大きいと思うけれど、ただ、いままでの人間が持っていたほかの技術なりがシビライゼーションとしてもつインパクトに比べて圧倒的に違うといえるかどうか僕は疑問です。
|
| 矢野 |
それはわからないし、人によって意見が違うから、そこはいいんですが。
|
| 会津 |
どうでもいいのかもしれない。
|
| 矢野 |
個人個人の意見の相違はいいんだけれど、とりあえず、会津さんが言ったように、技術というものを考えるときに社会の問題を考えていかなくちゃいけないんだということは、まったくそのとおりだと思います。
|
| 会津 |
なぜそんなことを言うかというと、僕は日本がそうだと思うんですが、技術者になればなるほど社会の問題を考えなくていいという風潮、教育、体制が強すぎる。
|
| 矢野 |
とくに日本ですよ。
|
| 会津 |
アメリカでは、文科系と理科系の両方の博士号をもっている人もいるけれど、日本では考えられないとか。たとえば慶応の藤沢キャンパスの環境情報と総合政策の両学部の関係を聞いてみるとわかりますけど、ほとんど共通性がない。共同プログラムも少ないし。
|
| 矢野 |
僕が『ASAHIパソコン』を創刊する前に、会津さんにも手伝ってもらって『思いっきりネットワーキング』というムックをつくった時、「BBSのつくり方」という原稿を技術畑のライターに頼んだら、まったく分からない原稿が出てきた。「これじゃ全然わからない」と言ったら、彼が、「わからなくていいんですよ。技術はわかる人だけわかればいいんで、わからない人が読む必要はない」と言ったわけです。それを会津さんも懇意だった、いまは亡き三浦賢一君と2人で徹夜で説得して書きなおしてもらった。そうしたら、翌日のうちに見違えるような原稿が出てきたということがありました。そういうふうに彼らは原稿を書いてきたわけですよ。そこになんというか、日本の技術者の……。
|
| 会津 |
だけではないかもしれないな。
|
| 矢野 |
かなりひどい。
|
| 会津 |
中国も似たようなところがあるとか。アメリカも一部はあるかなと思うけれど、でも、少なくとも日本ほどひどくはないかな。別に相対比較しなくてもいいんだけど、日本では非常に問題だと思います。
|
|
 いま韓国でインターネットプロモーション・エージェンシー(「インターネット促進庁」)という構想が出ています。IPAと言ってるんだけど。これを通信省(MIC)が提案して、いま法律を書いている。万一これがそのまま実現すると、そしてそこにドメイン名を管理しているKRNICが統合されると、政府直営のドメインネーム管理機構と、その他インターネットの社会制度に関するあらゆることを規制したり促進したりする部門が政府内にできる。 いま韓国でインターネットプロモーション・エージェンシー(「インターネット促進庁」)という構想が出ています。IPAと言ってるんだけど。これを通信省(MIC)が提案して、いま法律を書いている。万一これがそのまま実現すると、そしてそこにドメイン名を管理しているKRNICが統合されると、政府直営のドメインネーム管理機構と、その他インターネットの社会制度に関するあらゆることを規制したり促進したりする部門が政府内にできる。
この動きにはそれなりの社会的な背景があって、インターネットが一部の人が使うものではなくなってきている現象が、いま世界で一番激しく起きているのが韓国なんです。単に普及率が高いだけでなく、市民生活、社会生活の中での利用度も非常に高い。ある種のポジティブ・スパイラルで、誰でもみんなが簡単にアクセスするから、クレジットカードと組み合わせて税金も払えるようにできる。逆に使えない人の方が少数派で、そのギャップの問題は非常に難しい。
これは富山県山田村の倉田勇雄さんがよく言うんですよね。ネットを村の9割の人が使うようになったときに、絶対に使わない1割の人が残る。この少数派の人の問題というのは、すごくつらいと。全員を対象にしたサービスができるかできないか。極端にいうと、「公共の利益と福祉のためには、皆さんインターネット使ってください。使えない人なんて知りません」というほうが効率がいいということになりかねない。これをどうするのかと。
ちょっと前まではまったく逆で、インターネットをしている人の方がおたくで少数派で、そんな人たち相手にしてもしようがないと。日本ではまだ僕らは少数派に近いマイノリティで、社会生活の中でインターネットがなければ困ると本当に思っている人の数はまだまだ少ないと思いますが、そうではなくなっている韓国では、単純にいうと交通量が増えたら交通事故が起きるのとまったく同じ意味で、サイバースペースでのトラブルが山のように起きていると思うんですよ。
それに対して、インターネット業界による「セルフガバナンス」や既存の警察などもたいしたことができていないとすると、役所がIPAをつくるという提案をする基盤は、相当社会的現実が先にいってるということでしょう。
ICANNが半分ままごとだったのは、まだそこまでの現実になっていなかったから、ままごとですんでいたのかもしれません。政府が出てきても相手にしないとか、ドメインネームの決め方をちょっとやっているぐらいで、まだ、それはどうぞご自由に、の世界ですよ。だけど、その向こう側にもっと違う問題が次々に連鎖的に起きてきたときに、どうするのかという問題があります。
じつはICANNというのは、そういうときの1つの先行実験のはずだったんです。ICANNを作る前に、アメリカ商務省のアイラ・マガジナーと話したとき、「ICANNでインターネットのガバナンス全体をやる考えなのか」と聞いたら、「いや、そんなことは考えていない。分野別にいろいろな組織をこれからつくっていかなきゃならない。その第一号実験だよ」と言っていました。たしかに、我々も含めて、よく「実験なんだ」と言ってきました。
そこで、まさに社会の重大要素として技術があるということを、技術者にもわかってもらいたい。それも生命倫理と同じレベルで。逆に言えば、そういう生命倫理の議論をしているところと、ICANNのような議論をしているところが一緒に議論しないといけない。インターネットおたくだけ集まって、社会の問題を解決できるわけがないということです。
たとえば、クローン情報みたいなものをインターネット経由で広げられたらどうするんだという点では、十分に相互に連関している問題だと思うんです。
|
| 矢野 |
結局、一般のユーザーの立場から考えると、自分たちが使っているインターネットがそういう大きな問題をはらんでいるということについて、その運営にも興味をもって、ある種の参加意識が大事だということですね。
|
| 会津 |
理念としては、確かに一般市民が参加すべきだというのは正しいんです。しかし実態を伴った参加が大切であって、うちの奥さんがいきなりICANN会員になって投票する、というようなことはないほうがいいと思います。どの分野でもいいんですが、やはりある程度問題意識をもち、勉強している人たちへの働きかけを考えていかなければいけないでしょう。それはNPOとかNGOの役割と似ていると思います。
衆愚性の危険というか、だれでもいいから全員に同じ票を与えればいい結果が出るなんてことはありえないし、逆に言えば、これだけ情報が自由に流通できるようになったということは、知恵を磨く仕組みをいっしょにもっていかないとマイナスになると思うんです。
|
| 矢野 |
僕は、こういった問題を考えざるを得ない現状を、「肩にのしかかった重い荷物」と思うことがあるんですが、とにかくいろいろなことを考えざるを得ない状況になっているということですね。
今日は、あまり知られていない興味深い話をたくさんお聞かせいただき、どうもありがとうございました。
|