| 矢野 |
現実世界とバーチャルな世界の交流に関して、実際にどんなことが起こっているかおうかがいします。少し前になりますが、ハチ公前広場やアクロポリスの丘など世界中のいろんな所に備えられたカメラの映像を、ホームページでライブで見られるサイトが話題になりました。インタラクティブで、アングルを決めたり、ズームしたりできるという…。いまはどうなっているんですか。
|
| 田村 |
現実世界から切り取ってサイバースペースに移すという意味では、これも一種のミクスト・リアリティですね。これはMR研を立ち上げる前にやっていた仕事ですが、ますます広まっているんじゃないですか。従来は静止画が多かったんですが、ブロードバンドになったおかげで、動画で発信するサイトも増えてきました。当初は、インターネットでケンブリッジ大学のコーヒーメーカーが見えるとか、「今日の富士山」なんていうのもありましたね。別によそのコーヒーの残量がわかっても仕方ないんですけどね(笑)。「世界の窓」 「覗き穴」など、個人でこういうカメラへのリンクだけを集めたサイトもたくさんあります。私は最近あまりのぞかないんですが、随分増えているんじゃないでしょうか。
|
| 矢野 |
おもしろいなと思うけれど、一方でプライバシーの侵害が問題になりますよね。
|
| 田村 |
難しい問題です。監視される問題はありますが、自分が設置したカメラで特定の場所を見るのであれば、セキュリティの向上に役立ちます。アメリカでは、ベビーシッターが子どもを虐待して殺すという事件があって以来、急速に広まりました。最近では、ニューヨークテロ事件が大きなきっかけとなって、セキュリティ問題がますますクローズアップされ、その種のカメラの売り上げが急増していると聞いています。幼稚園や託児所でわが子が元気にしているかどうか見たいと考えるお母さん方もいるでしょう。しかし、そうなると今度は「URLを教えたために誘拐が起きたらどうするんだ」という議論が出る。
|
| 矢野 |
必ず出ますね。
|
| 田村 |
最近は、電力会社が無人の変電所の監視に使うといったように、イントラネットでの利用が増えています。これは問題ないですね。寝たきり老人がいるご家庭や、ペットのことが気になる場合も役に立ちます。パソコンを持ち歩かず、ケータイでみることもすでに実現しています。パラパラッとした動画程度ですが、携帯電話の画面でも十分、自宅の様子を見ることができます。使い方を一歩間違うとストーカーになってしまう危険性もありますから、やはり矢野さんがおっしゃる「サイバーリテラシー」の問題が重要になってきますね。
|
| 矢野 |
そこが難しい。これからのコンピュータの目指す方向は「ユビキタス」(ubiquitous どこにでもある状態)です。日常のあらゆるところにコンピュータが埋め込まれて、それが私たちの意向も読み取って自由に働いてくれる。そうなったとき、規制することも含めて、それらのツールをうまく活用していく知恵をもたないと、息苦しい世の中になることは間違いない。ハチ公前広場のカメラの性能も、プライバシーを考慮して、見えすぎないようにあえて解像度を上げないようにしているという話を聞いたことがありますが…。
|
| 田村 |
私どもが設置したカメラではそうしていました。ハチ公前のカメラでも、待ち合わせに使いたい人は「もっと、ズーム倍率をあげてよく見えるようにしてくれ」と言ってこられましたし、「勝手に映されちゃプライバシーの侵害だ」と言う人も必ずいます。そうである以上、ズーム倍率は上げられません。また、キヤノンではこういった商品には必ず、「プライバシーの侵害にならないように運用にお気をつけください」と一文を入れています。
実は、インターネットで発信する場合の個人の肖像権やプライバシーの問題については、専門の弁護士の先生に相談したんです。公共の場所でならプライバシーはないんじゃないかとも言えますね。よくテレビのニュースで東京駅前の通勤姿や新宿の成田空港での帰国ラッシュ風景が映りますが、あれはいいのかと。あの場合は、短時間でありニュース性があると言えるけれど、常時設置されているカメラでいつでも見られるということになると、やはり公共の場所であっても一定のプライバシーはあると解釈できるそうです。
カメラをエンドユーザーが制御してズームを変えられる場合は、それは見る人の責任であって、設置者に責任はないのではという問題に対しても、そういう機能をもったページを開設し公開している以上、プライバシーの侵害の幇助になる恐れがあるという解釈をいただきました。もっとも、限られた場所で、ここにカメラが設置されていると断ってある場合はそうではないようです。書店やコンビニなどに監視カメラがあることは、もう誰でも知っていますからね。待ち合わせ場所がよく見えるインターネット・カメラを設置すべきかどうかは、社会的コンセンサスがいるし、まさにサイバーリテラシーの問題です。
現状では、公開するサイトの場合、人物が特定できない範囲が安全だということになりました。ここでいう「特定」とは、一般の人が見てという意味であって、奥さんが見たら旦那さんの不倫現場がわかるというレベルは含まれないそうです(笑)。
こうしたことを通して思うのは、一部の研究者、技術者が使っていたものが一般社会に普及するときは、必ず摩擦があるということです。先端技術というのは、普及の過程で数々の問題が出てきて、やがて世の中が正しい使い方とモラルを学ぶものですよね。自動車や電話が登場したとき、人間の叡智が正しい使い方を学びとってきたように、この問題もこれからよりよい解決法を探っていくということでしょう。
それにしても、パソコンやインターネットの普及はあまりにも速すぎて、同じ世代の中でもギャップがあります。15年、20年後に振り返ったときには、笑い話になっているんじゃないかと思うんですけどね。
|
| 矢野 |
田村さんは、ある原稿で「夢を感じることよりも他人に夢を感じさせる仕事はさらに楽しいに違いない。夢なくして世界の発展はない」と書いておられましたね。
|
| 田村 |
「夢なくして世界の発展はない」という最後の言葉は、ハノーバー万博の政府展示館のプロデューサーの言葉です。前半は最近の私の心境です。MRプロジェクトの中盤から、そういうことをより強く感じるようになりました。もともと技術者というのは、便利な技術をつくることに生きがいを感じるわけで、MR技術も当初は医療・防災・都市計画などでの利用を考えていました。ところが、実際に引き合いが来たのは、テーマパーク、博覧会、ゲームなど、ほとんどがエンターテインメント関係でした。一番高く買ってくださっているのがゲーム業界と展示業界で、とくに展示業界では「MRは展示の世界を一変させる」と言ってくださっています。2005年の愛知万博で使いたいという展示企画者が何人かおられます。
なぜ、そこまで注目されるかというと、ミクスト・リアリティは今までにない新しい表現力をもったメディアだからでしょう。アニメやゲームで日本が世界に存在感を示したためか、いま、こういった分野のクリエーターを志向する若者がすごく増えていますね。エンターテインメントが伸びる社会というのは、豊かで平和である証拠です。研究成果にすぐ社会的利用価値とか採算を求めるのは、セコイですよ。高度成長期、あるいはそれ以前の貧しい時代の発想です(笑)。最近は、国の支援でやった研究でも、その成果の最大の用途はエンターテインメントだと平気で言えるようになりました。
こういうことを言うと、インタビューでいつも決まって聞かれるのが、「田村さんの夢を語ってください」「MRで何を描きたいか、何をやりたいか」という質問です。ゲーム・クリエーターや、ペット・ロボットや歩行ロボットの開発者のような回答を引き出そうとしてるんですよ(笑)。そうじゃないんです。私は夢なんて見ていなくて、もっと現実的に新しい技術をつくり上げるのが役目だと考えているんです。もう一歩踏み込んで言うと、夢を描く人たちに便利な道具を与えたい。人が夢を感じるような作品を創りたい人たち、彼らに供給するツールを世の中に送り出したいんです。
|
| 矢野 |
夢のコンテンツではなく、夢のコンテンツをつくる道具をつくると。
|
| 田村 |
そういうクリエーターの中には、我々の技術を知らずに、MR的な表現を求めている人がたくさんいます。たとえば、昨年公開された映画の『ファイナルファンタジー』です。興行的には失敗しましたが、フルCGであそこまでのリアリティを出そうというのは、称賛すべき挑戦でした。あの映画の中に、MR的なシーンがいっぱい出てくるんです。地球を侵略してくるエイリアンたちは兵士がつけた片目のメガネを通すと見えるし、メガネをかけてないのに、テーブル状のディスプレイが浮き上がって見えたり、腕時計状の装置に情報が重なって見えたりする。どういう原理でそうなるのかは説明されていませんが、未来にはそういう機能があったらいいなということですね。同じようなシーンは他のSF映画でもよく出てきます。
ですから、それに一歩でも近づく技術が供給できれば、それだけ表現力、企画力が豊かになるということです。楽しいことを職業にしたい人たちが増えるのは喜ぶべきことで、単にインターネットで儲かるかどうかを言っているよりは、ずっと素晴らしいことだと感じているんです。
|
| 矢野 |
実用価値や採算だけでなく、楽しいかどうか、夢を感じられるかどうかがもっと重視されるべきだとの田村さんの原点を再確認させていただきました。これからも、未来に夢を感じる人、夢を描きたい人のためにご活躍ください。今日はどうもありがとうございました。
|
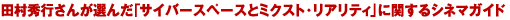 |
(1)
仮想世界と現実世界を行き来する作品
●『マトリックス』(1999)[監督:ウシャウスキー兄弟、主演:キアヌ・リーブス、キャリー=アン・モス]
まず1本を挙げるなら、何をおいてもこの作品だろう。W・ギブスンの原典でも、複雑な幻想空間が「マトリックス」と表現されている。アクションや視覚効果でも新境地を拓いた。DVDの特典映像では、『スター・ウォーズ エピソード1』を抑えてアカデミー賞をとった特殊視覚効果の舞台裏が詳しく解説されている。現在『マトリックス2
(The Matrix Reloaded)』『マトリックス3 (The Matrix Revolutions)』が同時製作中(2003年公開予定)。
●『13F』(1999)[監督:ジョセフ・ラスナック、主演:クレイグ・ビアーコ、グレッチェン・モル]
あるビルの13階から別人格になって1937年のロサンゼルスと行き来するという設定。無名俳優ばかりのB級作品だが、ストーリーは結構楽しめる。ただし、「この世の果て」とやらの描き方はあまりにも稚拙で滑稽。
●『イグジステンズ』(1999)[監督:デビッド・クロネンバーグ、主演:ジェニファー・ジェイソン・リー、ジュード・ロウ]
こちらもB級作品。背中に開けたバイオポートなる穴から中枢神経にアクセスして、仮想空間でRPGを楽しむという設定。一般受けする映画ではないが、この監督特有のグロテスクな造形物と特殊メイクは、固定ファンにはたまらなく嬉しいらしい。
(2)MR的描写が登場する作品
●『レッド・プラネット』(2000)[監督:アントニー・ホフマン、主演:ヴァル・キルマー]
●『シックス・デイ』(2000)[監督:ロジャー・スポティスウッド、主演:アーノルド・シュワルツェネッガー]
●『ファイナルファンタジー』(2001)[監督:坂口博信]
SF映画には、ロボット,クローン人間、タイムトラベルなどと並んで、仮想データが目の前に浮かぶMR的な描写がしばしば登場する。『レッド・プラネット』では火星上で宇宙飛行士が開く巻物状のフレキシブル・ディスプレイが、『シックス・デイ』ではアメフトのクォーターバックのへルメットが、透過型の複合現実型ディスプレイになっている。そして、フルCG映画の『FF』では多数のMR的シーンが登場する。これは、近未来に実現しそうな技術として、MRへの期待が大きい証拠だろうが、残念ながら3本とも映画としてはイマイチで、興行的にも惨敗に終わったのが気になるところだ。
(3)その他
●『ブレードランナー』(1982)[監督:リドリー・スコット、主演:ハリソン・フォード]
SF映画の古典的名作。「サイバースペース」は登場しないが、W・ギブスンの『ニューロマンサー』が描く退廃的な近未来社会に最も近く、影響を与えた作品として知られる。
●『ディスクロージャー』(1994)[監督:バリー・レヴィンソン、主演:マイケル・ダグラス、デミ・ムーア]
女性が男性を誘惑する逆セクハラで話題を呼んだ社会派サスペンス作品。後半、主人公がHMDとグローブをつけて仮想空間を体験するシーンが登場するが、ここでの設定はフルバーチャルの普通のVRである。仮想空間内で透明状の軽いメガネをつけているように見えるためか、このシーンを「複合現実」だと勘違いしている人が少なくない。皮肉にも、「MR研究プロジェクト」はこの誤解から誕生した。
注)CGを多用するSFX/VFXに関しては「こちらの映画評」も参考にしてください。
|
|