| 矢野 |
坂村さんが1987年に出された『TRONからの発想』(岩波書店)という本を当時、繰り返し読ませていただきました。
|
| 坂村 |
かなり力を入れて書いた本で、私の考え方はすべてそこに出ています。
|
| 矢野 |
日米貿易摩擦が問題になっていた1989年、アメリカは新通商法「スーパー301条(不公正貿易国・慣行の認定と制裁条項)」に基づいて、日本市場の閉鎖的分野として半導体、スーパーコンピュータ、自動車部品などをあげ、そのなかに教育用コンピュータソフト・トロンが加えられました。それがきっかけとなって日本は教育パソコン構想から撤退、一躍脚光を浴びたトロンがスーッとしぼんだ印象を世間に与えました。ところが、「ユビキタス・コンピュータ」時代になって、組込みOSとしてのトロンが着実に実績を上げていることが認知され、ふたたび社会の前面に出てきました。
トロンはパーッとデビューしたが、一時しぼみ、ふたたび脚光を浴びた、というふうに世間では受け取られているわけですが、それはまったく違う、と坂村さんは言っておられますね。
|
| 坂村 |
もともとトロンはパソコンをつくるプロジェクトではなかった。それが理解されていなかったのです。
トロンとは「The Real-time Operating system Nucleus」、つまり「実時間処理にすぐれたコンピュータの基本ソフトの核」という意味の略語です。パーソナル・コンピュータという言葉はプロジェクト名にも一切使われていませんし、もともとがユビキタスという「どこでもコンピュータ」の中核になるシステムをつくろうということを目標に、20年前にはじめたことなのです。
|
| 矢野 |
「ユビキタス(ubiquitous)・コンピュータ」は、1988年に米国ゼロックス社パロアルト研究所のマーク・ワイザーによって提唱されたのが最初ですね(ユビキタスとは、ラテン語で「遍在する=どこにでもある」という意味)。こういう考えは、それより前に坂村さんが『TRONからの発想』で十分に展開していることですね。もっとも「どこでもコンピュータ」という表現は使っていない。
|
| 坂村 |
概念的にはそういうことを言っているんだけれど。「どこでもコンピュータ」というのは、その後だんだん考えていったキャッチフレーズですから。
|
| 矢野 |
マーク・ワイザーが「ユビキタス・コンピュータ」と言ったのに対して、坂村さんは「トロン」と言い、「超機能分散システム」と言ってこられた。
|
| 坂村 |
いまでは「どこでもコンピュータ」と言ってもわかってもらえますが、最初にあたらしい考え方を提示するとき、和語にすると何かちょっと重みがないから(笑)。まだ「超機能分散」とか漢語のほうが重々しい。口では「どこでもコンピュータ」と言っていたけれども、書いてみると、なんだかドラえもんみたい、マンガみたいになっちゃう(笑)。
|
| 矢野 |
その辺の事情は、よくわかります(笑)。
|
| 坂村 |
 90年代の日本は、まずパーソナル・コンピュータがブレイクしました。PCにもリアルタイム性にすぐれたトロンが使えるのではないか。また、個人のためのコミュニケーターとしては、言語が重要になるので、アジアの言語を処理できるようなコンピュータをつくる必要があるんじゃないかと、僕は繰り返し言っていました。それに賛同してくださる方たちの中から、パーソナル・コンピュータにトロンを組み込んでもいいんじゃないかという話が出てきたんです。ITという言葉がブームになる10年以上も前ですが、標準的な教育用コンピュータが必要だという声が、一回は盛り上がったんですね。 90年代の日本は、まずパーソナル・コンピュータがブレイクしました。PCにもリアルタイム性にすぐれたトロンが使えるのではないか。また、個人のためのコミュニケーターとしては、言語が重要になるので、アジアの言語を処理できるようなコンピュータをつくる必要があるんじゃないかと、僕は繰り返し言っていました。それに賛同してくださる方たちの中から、パーソナル・コンピュータにトロンを組み込んでもいいんじゃないかという話が出てきたんです。ITという言葉がブームになる10年以上も前ですが、標準的な教育用コンピュータが必要だという声が、一回は盛り上がったんですね。
ただ、時代が悪かった。アメリカの言うことに追従する傾向があったのと、グローバリゼーション、世界標準といった熱が高まるなかで、独自技術が重要だと言っても、振り向いてもらえなかった。マスコミもですが。
|
| 矢野 |
せっかく日本独自の教育用コンピュータをつくろうとしたのに、それが止まってしまったのはどうしてなんでしょうか。
|
| 坂村 |
『21世紀日本の情報戦略』(岩波書店、2002年)でも書きましたが、日本は50年前のトラウマをずっとひきずり、アメリカから入ってくるコンセプトや戦略を無条件に受け入れてしまう傾向があった。
例えばマイクロソフトのWindowsなどは、会社や実務で使うのはいいと思いますが、教育に適したものではないですよね。なぜなら、中がどうなっているか、その原理を教え、どうして動くのかを教えるのが教育なのに、中を見ることができないブラックボックスになっていますから。
ちょうど同じころ、イギリスでも教育用コンピュータをつくる話が出るんです。それもアメリカのスーパー301条の対象にあがりますが、イギリス政府もマスコミもいちいち騒ぐほどではないと、これを無視した。
実際、独自OS、独自ハードウェアの教育用コンピュータを完成して、最近になるまで使っていたんです。8ビットマシンで100万台、8ビット以上でも50万台をつくっています。そのときにAcorn社が独自チップを開発し、それが発展してARM(アーム、Advanced RISC Machines)という名前の石(チップ)になった。インテルがライセンスを買っているイギリスのマイクロプロセッサで、世界中でPDAや携帯電話、ゲームなどに使われています。独自技術を貫いたから、インテルですらライセンスを買うくらいまで成長したわけです。無条件で受け入れた日本との違いを、まざまざと思い知らされます。
当時の日本ではパーソナル・コンピュータの意味をよく理解している人が少なかった。ITに対して、基盤技術になるという理解も、産業的にも重要だという理解もなかった。そういう情報戦略に対して理解していない人たちがたくさんいたということですね。マスコミも含めて。
|
| 矢野 |
当時、僕は『ASAHIパソコン』の編集長でした。ちょっと反論できないかも。
|
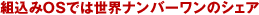 |
| 坂村 |
そういう時代だったんですよ。いまになって、ちょっと間違えたことをやったかなと、みんなも気づきはじめているんじゃないですか。
|
| 矢野 |
現実にはトロンを支援する人たちもまたいた、ということですね。
|
| 坂村 |
ええ、それでトロンの開発が続けられたんです。それには感謝しています。
ストレスがたまるのは、政治の話にされたらちょっと戦いようがないということですね。BTRONの性能が悪いからだめになった、もともとMS-DOSのほうがよかったんだ、などと言う人もいますがまったくトンチンカンな、技術を知らない人のマーケット論です。それは結果論。売れたから、よかったと言っているのにすぎない。政治介入がなくて、マーケットで何の妨害もなくやれて、それでだめになるんだったらしようがないですよね、実力がなかったということになりますから。
だけど、スーパー301条の経緯は、ある意味でアメリカ人が最も嫌うアンフェアなやり方じゃないですか。輸出もしていないものに対して、アメリカ政府から貿易障害だと言われて、日本が何の抵抗もせずに引いてしまい、それでさらに戦えというのはちょっと酷じゃないですか。
|
| 矢野 |
アンフェアだと思うけれど、アメリカらしくもある。「そちらこそアンフェアだ」と日本が言えば、アメリカは聞き入れたかもしれない。恐れ入っちゃうところに問題があるんですね。
|
| 坂村 |
そうそう、まったくその通りです。僕が言ったアンフェアも、アメリカ人に対してではありません。彼らははっきりした戦略をもっていて、自分の国が一番だと確信しており、とにかくアメリカのものを買えという交渉に出てくるわけです。こちらはアメリカ人と戦うなんて意識は皆無なんだけれど、文句あるなら言えばいい、言わないほうがおかしいんだ、となっちゃう。
|
| 矢野 |
いろんな人たちが、その辺で非常に歯がゆい思いもしていると思います。そういうなかでトロンはずっと研究開発を進めてきて、組込みOSとして携帯電話などさまざまな用途に利用されるようになったわけですね。
|
| 坂村 |
車のエンジンなどにも使われています。
|
| 矢野 |
世界でのシェアはどうなんですか。
|
| 坂村 |
組込みOSで日本のナンバーワンということは、世界でもナンバーワンです。コンシューマー・エレクトロニクスの供給基地はもうアジア以外になくなっていますから。アメリカに家電メーカーはないに等しい。もちろん売ってはいますが、ほとんどOEM(相手先ブランド生産)で、他国でつくっているわけです。そして、そういう製品の中にトロンが入っている。
トロンは、日本だけじゃなくて、米国と韓国にプロジェクトの支部があります。例えばLinux(リナックス)で世界ナンバーワンのRED HAT(レッドハット)という会社も、「eCOS(イーコス)」という商品名のトロンを出しています。
|
| 矢野 |
「eCOS」はトロンなんですね。
|
| 坂村 |
ええ、トロンは商品名じゃないですから。カナダのトロントに本社を置くATI Technologiesという会社も売っていますし、そういう例はたくさんあります。
|