| ��� |
���f�B�A�E�͂��̐��N�A�����̃}�X���f�B�A�ƐV�����p�[�\�i�����f�B�A�����������ς��Ă��܂��B����͂������낢���ʁA�����Ƃ�������ł��B
�@���z����̓��f�B�A�����҂Ƃ��āA�����w�@�̏��w�ł̎��Ƃ�j�[�N�Ȏ��H������ʂ��ă��f�B�A�̌���ɐg���Ă����܂����B�ŏ��ɈȑO������Ă�����u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�ɂ��Ă����������������B
|
| ���z |
�u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�Ƃ������t��l���ŏ��ɒ����̂́A1996�N�����ɏo�ł����w20���I�̃��f�B�A�@�G���N�g���b�N����f�B�A�̎���x�i�W���X�g�V�X�e���j�ł̊����_���ł����B�P���̖{��ӔC�������ĕ҂ނ̂͂͂��߂Ă̌o���ł������A�����ɑS�̂𑩂˂�_�����K�v���낤�ƍl���A���̂Ȃ��ň��̃L�[���[�h�Ƃ��Čf���܂����B
�@�����Ō����Ă���u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�Ƃ����̂́A���f�B�A��f�B�A�̎Љ�I�ȉe�����A�]���̂悤�ɋZ�p�̐i���Ɏ�����u���čl����̂ł͂Ȃ��A�_�C�i�~�b�N�ɂ����߂����퐶���̖Ԃ̖ڂ̒��Ō��Ă������Ƃ����l�����ł��B
�@���̖{�ł͋g���r�Ƃ���i������w�������j�́u�����Z�p�ƃC���[�W�������Љ�v�A��������i������w�������j�́u�b���Ƃ������Ƃ��߂����āv�A�h�C�c���w�̌�������i������w�����j�́u�G���N�g���b�N�E�o�i�i�v��v�Ȃǃ��j�[�N�Ș_�������ڂ��Ă��܂��B�����̕M�҂����L���Ă��铯���悤�Ȏ��_���u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�Ƃ��ĕ\�������킯�ł��B
|
| ��� |
�u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�͐��z����̑���ł����B�{���o���ߒ��Łu�\�V�I�E���f�B�A�_�Ƃ͂͂����������̂��v�����M�҂����̍��ӂ��`�����ꂽ�̂ł����B
|
| ���z |
 �����ł��ˁB�����A���퐶����Љ�Ƃ����D������ݓI�ɑ�����A���邢�͗��j�I�ɂ݂�Ƃ����l�����͖l�̃I���W�i���ł͂���܂���B���j�����╶�������A�Љ�w�ł͈ȑO���狤�L����Ă���l�����ł��B �����ł��ˁB�����A���퐶����Љ�Ƃ����D������ݓI�ɑ�����A���邢�͗��j�I�ɂ݂�Ƃ����l�����͖l�̃I���W�i���ł͂���܂���B���j�����╶�������A�Љ�w�ł͈ȑO���狤�L����Ă���l�����ł��B
�@�l�������āu�\�V�I�E���f�B�A�_�v�Ƃ����������������̂́A���ʂȈӐ}������������ł��B�傫��������Ɠ�����āA��ɂ͏]���A���f�B�A�����Ƃ����ƁA�Z�p�_����s���ĎЉ�Ƃ����Ԃ̖ڂ̂����߂��ɒ��ڂ��������͔��ɏ��Ȃ��������ƁB�Z�p�_���W�������߁A�l��̂悤�ȍl�����͂Q���Ƃ������䗦�ł��B����͓��{�Ɍ���܂��A�l�͂����ĒN�����Ȃ��������낤�A�t�T�C�h�ɑ����Ċ��𗧂ĂĂ����K�v������̂ł͂Ȃ����ƍl�����킯�ł��B
�@������̈Ӑ}�́A�l�炪�Љ�̂����߂��̒��ɂ���ȏ�A�l�玩�g�̍l�����╪�͂̎��_���A���̂����߂��̒��Ɉ��ݍ��܂�Ȃ�����ׂ����Ƃ������o��\���������������Ƃł��B�u���z������Ă���͕̂��n�̃��f�B�A�_�ł��ˁv�Ƃ悭�����܂��B�������ӂ��A���n�̌����Ƃ����͕̂����͂�����A�����ׂ���Ƃ�����Ƃ����S�ŁA���ʂ����Ƃɉ������f�U�C��������A�v���f���[�X�����肷�邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B����w����o�c�w���̒��ɂ͊w�Z�̐搶�Ƌ��͂��Ď��ƃJ���L���������������A�V�����^�C�v�̉�Ђ�m�o�n�𗧂��グ��A���邢�͒n��ݕ��̂��߂̋�̓I�ȕ�����l����Ƃ������������Ă�����͂��܂��B�������A�����_��Љ�w�A���j�w�Ƃ���������ł́A�قƂ�ǂ����������Ƃ͂����A�e���̃e�[�}�ɉ����Č��ۂ���j��ᔻ�I�ɓǂ݉����̂����������̒��S�ł��B
�@�l�̓��f�B�A�̗��j�̌���������Ă���Ƃ�����A���ꂾ���ł͕�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B���������������������낢�m�����̂Ȃ�A���݂̍��ׂƂ������f�B�A�̒��ɂ�����Ҍ����Ă��������B�l�̌����Ώۂ��ÓT���w�Ȃ�ʂɂ����͎v��Ȃ������ł��傤���A���܌������̃C���^�[�l�b�g���A�e���r���A�V�����A�l�̖ڂ̑O�ɂ���B�ڑO�ɂ���Ώۂ���������Ƃ������Ƃ́A�_�C�i�~�b�N�ȖԂ̖ڂ̓����ɖl���g������Ă���Ƃ�������킯�ł��B
�@�w20���I�̃��f�B�A�x�����s�����������A�ŋ߂͂����ƌ����ɓ��������A���f�B�A��g�ݒ�����Ƃ����f�B�A�_�̈�Ƃ��Ē������ƍl����悤�ɂȂ�܂����B���߂čl����ƁA�l�������o�����u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�́A�v�����ȏ�ɖ�\�����L���āA���̒��ł̓��f�B�A���H�_�A���f�B�A�\���_���厖�ȕ������߂Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B
|
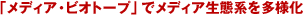 |
| ��� |
�u���f�B�A�E�r�I�g�[�v�v�̎��H���������̈�ł����B
|
| ���z |
���������Ƃ���ł��B����͐����w�Ō����u�r�I�g�[�v�v�Ƃ������t���A���^�t�@�[�i�Úg�j�Ƃ��Ďg�����T�O�ł��B�u�r�I�g�[�v�v�Ƃ������t���̂́A100�N�قǑO�Ƀh�C�c�Œ��ꂽ����ŁA��������̐����ɓK���������ȏꏊ��ł��ˁB
�@�Ⴆ�A�r�̂قƂ�₩��Ԃ������A�Ί_�̌��ԁA�R���̔p���A�s�s�Ɏc��_�Ђ̋����◢�R�ȂǁA�L��Ȏ��R�ی��ł��Ȃ����A�~�͂̂悤�Ȑl�H�I�ɍ��ꂽ���R�ł��Ȃ��A���̒��Ԃɂ����āA�G���Ȑ��������������鏬���Ȑ��Ԍn�̂��Ƃ��w���܂��B��ЂƂ̃r�I�g�[�v���ɂ���A�����ɓ��A�����s�������Ȃ��琶�������m�̃l�b�g���[�N�����܂��B���������ӂ��ɁA�_����ʂցA�����̑��l�����ێ���W�J���Ă������Ƃ����l���ł��B
�@�u���f�B�A��r�I�g�[�v�v���܂����������ł��B�e���r�̃L�[�ǂ��V���Ђɑ�\����鋐�僁�f�B�A��l�H�I�A�т��ꂽ�傫�Ȏ��A�P�[�^�C�Ȃǂ̃v���C�x�[�g�ȃ��f�B�A��~�͓I�Ȏ��R�Ƃ��đ�����A�l�������u���f�B�A��r�I�g�[�v�v�͂��̒��ԓI�ȑ��݂ł��B�l���������퐶���̒��ł�������K�͂̃��f�B�A���Ԍn�����܂܂ňȏ�ɑ��l�����悤�Ƃ������z����u���f�B�A��r�I�g�[�v�v����Ă��܂��B
|
| ��� |
�r�⏬��Ƃ��������Ԍn���Đ�������̂Ɠ������Ƃ��A���f�B�A�̐��E�ł�낤�Ƃ����킯�ł��ˁB
|
| ���z |
���{�ł͖����ȍ~�̑�O�V���A�m�g�j�A���̖��ԕ����Ȃǂ����Ƃ��Ă��т��Ă��āA���ؒ��S�̐��k�Ȑ��Ԍn�����A�����������Ȃ��悤�ȏ������B��������A�O���[�o�������i���܁A�����ԗl�����ς���Ă��܂����B�V�������f�B�A���Ԍn�����܂����B�}�X���f�B�A�Ƃ������̐X�ɂ͓|�ꂽ����������A���̓|�������āA�������炢�낢��ȐA�����萁�����Ƃ�����B���邢�́A�ʂ̎�ނ̖Ƌ�������Ƃ������������o�Ă��Ă��܂��B
�@�����w�Ō����u�r�I�g�[�v�v�̊T�O�́A�傫�Ȓn��̐��Ԍn�����P����̂ł͂Ȃ��A�g���{�r�����Ƃ��������x�̏��K�͂Șb�ł��B�����ď����ȃr�I�g�[�v���A���܂��l�b�g���[�N���Ă����B��ЂƂ͂����ۂ��ł��A����炪�N���̑���ɂȂ邱�ƂŁA������Ƃ₻���Ƃł͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�Ɏd�g��ł����킯�ł��B�����悤�ɁA���������̐g�̂܂��ŋN�����Ă��鎖�ۂ����т��Ȃ���A���������f�B�A�̐��Ԍn�����Ă������Ƃ����̂��l�̍l���ł��B
�@�u���f�B�A�E�r�I�g�[�v�v�ɂ��ẮA�߂������ɋI�ɚ������X����X�P�b�`�u�b�N�̂悤�Ȗ{���o���\��ł��B�l�̓X�P�b�`�u�b�N�ɊG��`���Ȃ�����̂��l���邱�Ƃ�������ł����A���̗Ⴆ�b���G�{�ɂ����ق����킩��₷����Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
|
| ��� |
�����Ȏ��H��ςݏd�˂Ă����ƁB
|
| ���z |
�u���f�B�A�E�r�I�g�[�v�v�͗Ⴆ�b�A�B�g�̑̌n�ł��B�����̖��ƌ��т��������œW�J���Ă���u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�A���邢�͂��̈ꕔ�ł��郁�f�B�A���H�_��f�B�A�\���_���킩��₷���\�����镨��Ƃ��āA�u���f�B�A�E�r�I�g�[�v�v�ƌ����Ă���B�u�\�V�I�E���f�B�A�_�v�Ƃ�����\����������ȏ�A���ɒ��g�����K�v���������B�����Ɉ��̕��ꐫ��^���悤�Ƃ����킯�ł��B
|