| ��� |
���ꂩ��̃W���[�i���Y���̂�����ɂ��Ă��������܂��B����܂ŃW���[�i���Y���́A��{�I�ɂ͊����̃}�X���f�B�A��Ƃɂ���ĒS���Ă��܂������A�}�X���f�B�A�����f�B�A�E�̒��S�Ƃ��ċ@�\���Ă�������͏I������܂��B�R���s���[�^��ʐM�C���t���A�G���^�[�e�C�������g�Ƃ������ًƎ��Ƃ����X�ƃ}�X���f�B�A�ɎQ�����A���̂��Ƃɂ���ă}�X���f�B�A���̂��̂��ώ����Ă����B���̉ߒ��ŃW���[�i���Y���Ƃ��Ă̋@�\�A���_�@�\�����ނ�����܂��B
�@����Ńz�[���y�[�W��d�q���[���A���[���}�K�W���A���[�����O���X�g�Ȃǂ̃p�[�\�i�����f�B�A���ʓI�Ɋg�債�Ă��Ă��܂��B�l�͂��̌�����u�����f�B�A�Љ�̓����v�i�w�C���^�[�l�b�g�p��W�U�x��g�V���j�Ƒ����A�}�X���f�B�A�ƃp�[�\�i�����f�B�A�����𗬂���Ȃ��ŁA���ꂼ��̃��f�B�A���W���[�i���Y�����ǂ̂悤�ɒS���Ă����邩��^���ɍl����ׂ����Ǝv���Ă��܂��B���z����̂��l���������������������B
|
| ���z |
 �����̃}�X���f�B�A�����f�B�A�E�̒��S�ł͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����w�E�͓������܂��B����܂ł��}�X���f�B�A�͒��S�I���݂ł͂Ȃ��ƌ����邱�Ƃ�����܂������A����͎Y�ƊE�̂Ȃ��ł̈ʒu�Â��Ƃ��Ďw�E������肾�����B�������A���݂ł͕̂�����Ƃ����{���I�Ȗ��Ƃ��Ă��̌X��������Ă���Ǝv���܂��B �����̃}�X���f�B�A�����f�B�A�E�̒��S�ł͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����w�E�͓������܂��B����܂ł��}�X���f�B�A�͒��S�I���݂ł͂Ȃ��ƌ����邱�Ƃ�����܂������A����͎Y�ƊE�̂Ȃ��ł̈ʒu�Â��Ƃ��Ďw�E������肾�����B�������A���݂ł͕̂�����Ƃ����{���I�Ȗ��Ƃ��Ă��̌X��������Ă���Ǝv���܂��B
�@�Ⴆ�Ό��݂̖k���N���Ɋւ��āA���{�̃}�X���f�B�A�͎Љ�̖ؑ��Ƃ��Ă̖������\���ʂ������ɁA��O�}���I�ȕp���ɌX���Ă���B�Ђɂ���ĈႢ�͂���܂����A�e���r���V�����A�k���N�ł́A���Ƀi�V���i���X�e�B�b�N�ł��ˁB��X�̃i�V���i���Y�������F�ʂ����߂Ă���B���������p���ɏ]���̃}�X���f�B�A�̗͂̐����������܂��B����ŁA�}�X���f�B�A�������ɔp�ꂽ�Ƃ͌����A��͂�傫�ȗ͂������Ă���͂��������ς��Ȃ��ł��傤�B
�@ �p�[�\�i�����f�B�A�͂ǂ����ƌ����ƁA����܂ł̃}�X���f�B�A�ɂƂ��đ����ăW���[�i���Y���̈ꗃ��S���قǂɂ͐��n���Ă��Ȃ��B�W���[�i���Y���Ɋւ��āA�p�[�\�i�����f�B�A�ƃ}�X���f�B�A�̊ԂŖ������S���\���ɂł��Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�厖�Ȃ̂́A�}�X���f�B�A�ł͂Ȃ����p�[�\�i���Ȑ��E�ɕ��Ă����Ȃ����ԕ������A�p�u���b�N�Ȍ��_�@�\�Ƃ��Č����ɉ������`�ň�ĂĂ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@ ����͏��������ꂾ���ł͕Еt���Ȃ��B���݂̃p�[�\�i�����f�B�A�͎���̐����ŔM�ы��������Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�����ɂ͂������O�ɑ��ĊJ����Ă��܂���B�C�̐��Ԍn�ɂ͂��悻�W�̂Ȃ����Ƃł���ˁB�Ⴆ�Όg�ѓd�b�̃R���e���c�r�W�l�X�ɏ���āA�p�[�\�i�����f�B�A���g���Ă��������ł́A���̃f�W�^���Z�p�̐��ݗ͂��\���ɐ������܂���B����ŁA���X��z�����V���⍏�X�����e���r���f����������Ƃ����������̃}�X���f�B�A�ɗ������X�^�C�������ł́A�W���[�i���Y���͍r��ł�������ł��傤�B
�@�l�������Ă���u���f�B�A�E�r�I�g�[�v�v�Ƃ����̂́A�}�X���f�B�A�ƃp�[�\�i�����f�B�A�̒��ԁB�K�͂͏���������ǁA�Љ�Ɍ����ĊJ���ꂽ���݂ł��B�l��͂����������f�B�A��Ԃ�ϋɓI�ɍ��ׂ����Ǝv���Ă��܂��B
�@�]�k�ł����A���S�~�̃��T�C�N���ŕ��t�y����銈�����͂���Ă��܂��B�l���������ł���Ă��܂����A����͂����Ȃ�ʍL���肪����܂��ˁB����̃x�����_�ł���Ă����Ƃ��A�ׂ̉Ƃ̒�Ƃ��ߏ��̋n�ɂȂ���\�����߂Ă���B�������������͒n��ݕ��̉^���Ƃ����j�o�[�T���f�U�C���Œn��̌����{�݂������Ă����Ƃ����b�Ɠ������Ă����ł��傤�B���f�B�A�̐��E�ł��A���������W�J���\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
|
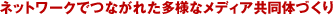 |
| ��� |
���z����́w�f�W�^�����f�B�A�Љ�x�i��g���X�j�ł��A���w�I�Ȍ�����������Ă��܂����A�ǂ������ӂ��ɂ��������Ă��������̂ł��傤
|
| ���z |
���������ɎU�݂��Ă���m�E�n�E���Љ�A���т��Ă��������I�ȍ���݂�Ȃōl���Ă����K�v������܂��B�d�v�Ȃ̂͑��l�ȃl�b�g���[�N��厖�ɂ������f�B�A�����̂���邱�Ƃł��B���������Ẵ~�j�R�~���̊�����Z�N�g�����Ă������s���^���Ƃ̈Ⴂ�ł��ˁB���������������������Ƃ�����Ă���Ƃ������I�Ȏp���ł́A�n��̂Ȃ��⑼�Ǝ�̐l�ƊW�����ׂ��A�����ꓑ�����ꎀ�ł��Ă��܂��ł��傤�B����͐�ɔ�����ׂ��ŁA���f�B�A�̐��Ԍn�ɕ҂ݍ��܂��`�Ŋ������p������悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����܂���B
|
| ��� |
�����܂ł����R�I�ŁA�������C�������Ȃ��H
|
| ���z |
�u���f�B�A���e���V�[�v�Ƃ������t�́A�P�Ƃōl����Ƃ悭�Ӗ����킩��Ȃ��ł��傤�B��ʓI�ɂ́A�e���r��V����ᔻ�I�ɓǂ݉������Ƃ��ƌ����Ă��āA�l��̊����Ƃ͊W�Ȃ��Ǝv���邩������܂���B�������A�u���f�B�A��ǂ݉����v�Ƃ����̂́A���̑����Ǝ肪�z���邱�ƂƗ���ł���Ǝv����ł��B�����Ǝ肪�����A�z���銈���ɂ���Č��S�ȃ��f�B�A���e���V�[���g�ɂ��A���f�B�A�̐��Ԍn��������v���Z�X�ɂ��Ȃ�B
�@�l�炪�����v���W�F�N�g�Ŏ��H�Ƃ��Ă���Ă���̂́A���̑����Ǝ�Ƃ��Θb�ł���悤�ȏ��݂�����A�f�l�������ɂȂ��ăv������ɂȂ����肷��悤�ȋ@��Â���ł��B
�@��̓I�ɂ͂Q�N�O���瑱���Ă���u�����A�v���W�F�N�g�v������܂��B�����A�Ƌ����ŁA�n���̃��[�J���ǂƒn���̎q�ǂ����������т��A���݂��Ɍ𗬂��Ȃ��������ԑg��������Ă��܂��B�l��͂��������v���W�F�N�g��ʂ��āA�n��̑��l�ȃZ�N�^�[�����т���B�����ŁA�����Ǝ肪���݂��Ɋw�э����A���ɂȂ����Ă����悤�ȏz����W��z���A������}�X���f�B�A�Ƃ����傫�ȕ���ɂ����т��Ǝv���Ă��܂��B
|
| ��� |
�W���[�i���Y���̂�������߂����ẮA�̎��R�̖����ւ���Ă��܂��B
|
| ���z |
������ƍl����ׂ��厖�Ȗ�肾�Ƃ͎v���܂����A��{�I�ɂ́u�傫�����f�B�A�̕���v�̖�肾�Ǝv���܂��B�������u����������v�Ƃ��Ȃ����Ă���̂ł����A�����A�l���g�͂��܂ƂĂ������܂ł͂ł��Ȃ��B
�@�����l�́A�}�X���f�B�A�ƃp�[�\�i�����f�B�A�̒��Ԃɂ�������I�ȃ��f�B�A�͎����ł��邵�A�����ɂȂ�炩�̉������܂��Ɗm�M���Ă��܂��B����͑����I�Ȏd�g�݂ł����āA��ɂ͓��ꂳ��Ȃ���������܂��B�����m�M�����̂͋��N�̉Ă��疯���A�v���W�F�N�g�̈�Ƃ��āA�����Ƒ�k�̎q�ǂ��������Ȃ��v���W�F�N�g��������̂����������ł��B���̃v���W�F�N�g�́A�o���̎q�ǂ������������ō�����r�f�I��i��ʂ��āA���݂��̒n��ɂ��ė������������Ƃ����˂炢�ł����B�Q�������͕̂����Ƒ�k�̎q�ǂ������̂ق��A��p�����d����ARKB���������B�������ł�NPO�Ƃ��Ċ������Ă���50�Α�̌��C�ȏ������T�|�[�g���Ă���܂����B
�@���̔ޏ��������u�e���r�͂���ς�n��ɂƂ��āA�ƂĂ��厖���Ƃ悭�킩�����v�ƌ����̂ł��B�e���r�̃v���Ƃ������Ȃ���q�ǂ��������G�R���e��`���A�r�f�I�J�������A�ҏW�܂ł�����o�����傫����������ł��傤�B�����������o�����Ă݂�ƕς���ł��B
�@�܂�l��̏���������́A�}�X���f�B�A���W���[�i���Y���Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃɑ傫�ȈӖ�������ƁA��ʂ̐l�ɑ̊����Ă��炤�v���O�����ł�����̂ł��B
|
| ��� |
�Ⴆ���ܘ_�c����Ă���l���ی�@�ł����A�@�̓K�p���O�ƂȂ�@�ւ̒�`������B���܂܂ŕ@�ւƌ����A�����ǂƂ��V���ЁA�ʐM�ЁA�o�ŎЂƂ��Ɩ��m�ɕ����邱�Ƃ��ł�������ǁA�p�[�\�i�����f�B�A�A���邢�͐��z����̂����u���f�B�A�E�r�I�g�[�v�v�I�Ȃ��̂��@�ւɊ܂܂��̂ǂ����A���@�ւŒ�`����͖̂����ł��ˁB�p�[�\�i�����f�B�A���܂߁A���ׂĂ��u�̗p�ɋ�������́v�Ƃ��ēK�p�����O����ƌ����������̂ł����A����ň�@�s�ׂ���f�s�ׂ������Ă���B���������̂Ȃ��Ōl���̕ی�ɂǂ��Ή����邩�A���ꂩ��̃��f�B�A�̂�������܂߂čl���Ă����K�v������Ǝv���܂��B
|
| ���z |
�l���ی��f�W�^�����f�B�A�̋K���Ɋւ���@�����ǂ����邩�́A���̐��N�ł�����ƌ��߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��ł��傤�B�������A��ʂ̐l���}�X���f�B�A�ɑ��ĕ����Ă���s�M���△�S�́A�uNO�e���r�E�f�[�v��l���ی�@�����������Ƃ����Ă��A�����ȒP�ɂ͕��@����Ȃ��B�ނ���A���̃v���O�����̂悤�ɏ�������������L����ق����厖���Ǝv���̂ł��B������������Ƃ��Ɍo�����Ȃ���A�}�X���f�B�A�Ǝs���̊Ԃɂ���a�߂Ă����A�����ꐧ�x���̃��`�x�[�V�����͎s���̑����琶�܂�Ă���Ǝv���Ă��܂��B
�@�����̃}�X���f�B�A�̒��Œ��N�ς���ς�������₱���𝆂݂ق����Ă����Ȃ���A�{���I�Ȗ����������邱�Ƃ͂ł��܂���B���̂��߂ɂ��l��͏����������ςݏd�˂�K�v�������ł����A���Ԃ��ǂ����Ȃ��ł��B�u�傫������v�Ɓu����������v���Ȃ�����A�݂��ɋ��͂��������肵�Ȃ���A���f�B�A�Љ�������Ɍ��킹��������ǁA�{���ɂł��邩�ǂ����ߊϓI�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�����A�l�͊y�V�I�Ȑl�ԂȂ̂ŁA���C�悭�{����������A���w�������Ɣ��W������悤�v�������肵�����Ǝv���Ă��܂��B�l�����܂���Ă��銈���͖��炩�ɈӖ�������ƐM���Ă��܂�����ˁB
|
| ��� |
�����͐��z����̃��f�B�A�_�Ƃ���ɗ��ł����ꂽ��̓I�Ȏ��H�������I�ɂ������ł��A�����ւ�Q�l�ɂȂ�܂����B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
|
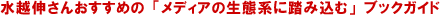 |
���w�S�����s�̗��j�F�\�㐢�I�ɂ������ԂƎ��Ԃ̍H�Ɖ��x
�i���H���t�K���O�E�V���F���u�V�����^������Y��A�@����w�o�ŋǁA1982�N �j
���f�B�A�̐��Ԍn���\�����Ă���̂́A�e���r��V���Ƃ�������f�B�A�����ł͂Ȃ��B����Љ���ł���{�I�ȂƂ���Ő��藧�����Ă��郁�f�B�A�̈�ł���S���ɏœ_�Ă��Љ�j�̌���B19���I�̐l�X�ɋ���ȓS�̉�Ə��C�@�ւ������炵���Ռ��𖾂炩�ɂ��A�G�l���M�[�A���́A�g�́A�]�ɁA�v���C�x�[�g�ƃp�u���b�N�Ƃ������A���ł͂�����܂��̂��̂̍l�����A���������A�S���Ƃ̊W�łǂ̂悤�ɐ��ݏo���ꂽ����`���o���Ă���B
��
�w�K���X�̗V���n�x�i�i�R���v���A�W�p�Е��ɁA1993�N�j
1960�N��A���x�o�ϐ����̌����ƍ��ׂ̒��A�����e���r�̖��ɖ��������n���̕���B�̌i�R���v�����`�I�ɕ`���o���A���{�e���r�̐��쌻��̕��͋C�ƁA�\���҂����̐S�ӋC�́A�j�V�r�Ń��[�����X�Ŏ�X�����B2003�N�A�e���r50�N���j������v���p�K���_���肪�������邯��ǁA�\���̌���̊y���݂͂ǂꂾ�������҂ɓ`����Ă��邾�낤���B�l�������e���r�̃I�[���^�i�e�B�u�Ȃ�������C���[�W���邽�߂ɖ��ɗ��A�M�d�ł������낢�ǂݕ��B
��
�w���E�|�p�_�x�i�ߌ��r�㒘�A�����܊w�|���ɁA1999�N�j
�����{�̎s���^�����O�������߂���v�z�̂����܂��f���Ă����ߌ��̖����̘_�l�B���Љ�����A�Љ�Ɛ藣�ꂽ�����|�p�A���Ɖ�����A���������ꂽ��O�|�p�ɑ��āA�l�X�̓��퐶���̒��ɕ҂ݍ��܂ꂽ���I���l�W���������E�|�p�ɒ��ڂ��A���X�̕�炵��V�сA�R�~���j�P�[�V�����̉��l�Ɖ\����������B���E�|�p�̌����҂Ƃ��Ă̖��c���j�A��]�ƂƂ��Ă̖��@�x�A���H�ƂƂ��Ă̋{���ɒ��ڂ��A�Ƃ��ɋ{��̈Ӌ`���Č������邱�ƂŁA�����̎���̒��ł̎s���̐헪���Î����Ă����B�����A�f�W�^���̏����ȃ��f�B�A�̕���𗧂��グ�鎞�ɁA�ߌ��̎v�z�͍Ăя�������邱�ƂɂȂ�B
��
�w�l��̍z���W�I�x�i���ь��A�}�����[�A1997�N�j
20���I�����Ɏp���������z���W�I�Ƃ����Âڂ������f�B�A�̖��͂��A�]���Ƃ���Ȃ��`���o���Ă���Ă���B���ꂽ��ɐ�������グ�A�d���g�̐_��������閳�����N�����B���܂��܂ȃN���X�^������т��g�����A����i�̂悤�ȋ@��̐��X�B�����R�~���j�P�[�V�����̎d�g�݂��w�Ԃ��Ƃ̊y�����B����Șb��Ŗ��ڂ̂��̖{�́A���f�B�A�̖��͂��Z�p�̐V���������ɂ͂Ȃ����Ƃ������Ă���B�u����Ȗ{������Ă݂�����ˁv�ƁA���r�Y���l�ɋ����Ă��ꂽ�B
��
�w���r�Y�̎d���Ǝ��Ӂx�i���r�Y���A�Z�s�ЁA2000�N�j
���f�B�A�A�[�e�B�X�g�A���r�Y�̎d���ƍ�i�̑S�̑����ł��郔�B�W���A���{�B���̍�i�́A�f��ȑO�̃��f�B�A�̖L���ȉ\�������ݏグ�A���퐶���̒��Ŏq�ǂ�������s�������i�����Ȃ��Ă���R�~���j�P�[�V�����̒��ɗV�т�y���݂����������Ă������Ƃ����p���Ɋт���Ă���B�����郁�f�B�A��g�ݑւ��A�����I�ȃR�~���j�P�[�V������W�J���邽�߂ɁA���f�B�A�Ɛl�Ԃ̊W�������炽�߂Ė₢�����Ă�������������^���Ă����B
|
|