| 矢野 |
3年前の東大情報学環立ち上げにはずいぶん尽力されましたね。現に教壇にも立っておられますが、「メディア・ビオトープ」の活動とはどう関連していますか。
|
| 水越 |
情報学環という智慧の環のような組織ができたから「ソシオ・メディア論」や「メディア・ビオトープ」の研究を進められるようになったとも言えます。情報学環の立ち上げに携わった経験が、組織という網の目のうごめきに乗ってメディア実践をしていこうとはっきり自覚する大事な契機になりました。
情報学環の設立理念は学内外に開かれた大学院ということでしたから、「メディア・ビオトープ」を考えるプロセスとまったく同じでした。こうした場を与えられたことで、これまでの文系、理系とか表現系といった縦割りの研究領域ではなく、リング状で情報の問題を考えられるコミュニティが生まれた。
|
| 矢野 |
情報学環にはいろいろな経歴の人が集まってくるようですね。
|
| 水越 |
僕のところの院生は平均年齢34歳〜35歳。ふつう、学部卒で大学院に入ると21歳〜22歳ですから、10年近い社会人経験があったり、留学経験があったりする強者揃いです。
出版社や放送局、新聞社、広告代理店などの一線で働いていて、自分たちの日々の仕事に広い意味での思想をもちたいと思っている人たちが多い。いずれにしても誰が先生だか生徒だかわからない感じですね(笑い)。
こうした傾向は情報学環のあり方うんぬんということよりも、もっと広い意味での社会の変化と関係しているでしょう。SFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)や一橋大学、関西大学の大学院でも同じような傾向にあります。情報学環の特色は現場で役立つ資格を取ろうとして来ている人が少ないことです。
東大でも法学部でロースクールをつくろうとしています。このような専門大学院では、学んだことが即、現場で役立つ。もちろん僕らも現場で役に立つ研究をやっているつもりだけれど、場合によっては現場を批判したり、現状を変えようとしたりするねらいもある。メディアとかジャーナリズムの研究というのは、ほかの分野とは多少違い、それほどストレートに、あるいはシステマティックに現場に役立つわけではないんです。
僕はよく、情報学環はスタッフも大学院生も、みんなキメラだと言うんです。「キメラ」というのは、ギリシア神話に登場する想像上の動物で、頭はライオンでしっぽがヘビというふうに、何種類もの動物が合体してできている。要するに多様でハイブリッドだと言いたいんです。僕は以前から市民として何らかの表現活動をしている人を「新しいメディア表現者」と呼んできたのですが、彼らには共通してキメラ的な要素があります。実際、情報学環にはそんな人が来るようになりました。「学環には変わったやつが行くね」とよく言われます(笑い)。
組織の中で「あいつはちょっと変わったやつだ」とか、「ときどき、社の方針に従わない」と言われがちな連中です。彼らは保守本流たるマスメディアや企業の権威をそのまま信じていない。大組織の中の辺境、あるいは周縁的なポジションにいながら、じっくりと物事を考えてみたい、いまの職場とは違うやり方で自由に手足を動かしたいという人が多いようです。
|
| 矢野 |
現役の会社員は社員の身分のまま来るわけですか?
|
| 水越 |
所定の単位を取って修士論文を書くのが院生の条件です。社会人の中には、休職をして来る人もいますが、仕事をしながら来る場合も多い。大手町から15分でやってきて授業にでてまた戻っていく、二日徹夜をしてCMを作り翌朝の授業に来るなんていう、大変な苦労をしています。
|
| 矢野 |
コロンビア大学のジャーナリズム・スクールに来ているのは、いままでの仕事をやめて新たなスキルを得るのが目的だという人が多いでしょう。自分を磨いてもっといいキャリアを獲得するためですね
|
| 水越 |
コロンビア大学のジャーナリズム・スクールは、いわゆる職業人養成の専門大学院で、情報学環とは基本的に違います。情報学環は、社会人が多いけれど、職業人養成を目指していない。ちなみにあのジャーナリズム・スクールは1学年230人ぐらい、SFCの大学院も修士課程で150人ぐらいいると聞いていますが、情報学環の学生数は修士課程で1学年50人、博士課程で20人。それに対し教官数は39人。僕のような基幹教官が指導できる学生数も数名程度で、マスプロ教育ではないんです。教授陣は西垣通さん、坂村健さん、原島博さん、河口洋一郎さん、佐倉統さんといった有名な方から僕のようなものまで非常にバラエティに富んでいますが、体系化されていないとも言えるんですね。
コロンビア大学のジャーナリズム・スクールの学生たちは次の職場へのステップアップを第一に考えている。だから実務に興味はあっても、メディア論とか、デジタル技術などよけいな勉強はしないです。一方で学環の院生は、現場での悩みをじっくり考えてみたり、自分の立ち位置自体を疑うようなことを積極的にするために、多様で学際的な勉強を進んでやります。僕たちは情報学環が一種の交差点になればいいと思っています。
|
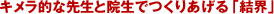 |
| 矢野 |
授業はどのように進めていますか。
|
| 水越 |
僕は大学院で複数の授業をもっています。一方で伝統的な文献講読、院生の研究発表などを行うゼミナール。片一方では「メディア表現論」という実践的な演習をしています。ここでは、前半でメディア論の概要を話し、その後院生たちがチームを組んで、子どもたちや市民のメディア表現を支援するようなプログラムを企画したり、実践するということをやっています。今年度は、子どもたちが公共的な場で自己主張をするためのメディア作りをしたチーム、コミュニティFMの活性化プランを考えるチーム、粘土を使ってアニメを作るチームなどがありました。僕自身は、仲間とともに情報学環で「メルプロジェクト」という共同研究プロジェクトを進めており、この授業の成果と深く結びついています。
|
| 矢野 |
メルプロジェクトというのは、「メディア表現、学び、リテラシーなどをめぐって関心や志を分かち合う多様な人々のゆるやかなネットワーク型組織」で、情報学環の共同研究プロジェクトとして、2001年から始まったものですね。
|
| 水越 |
そうです。今年も3月上旬に本郷でシンポジウムを開催しました。僕は「メディア」という言葉をかなり幅広い概念として捉えています。そしてメディアの読み書き能力などと呼ばれる「メディアリテラシー」もまた、それ単体で捉えるのではなく、メディアと人間のかかわり方の基本を組み替えたり、ずらしたりするようなメディアアートや「メディア遊び」、地域社会などでの現実の「メディア実践」などと結びつけて考えていく必要があると思います。これらはいずれもメディア論という大きな器の中に位置する概念です。
|
| 矢野 |
情報学環は、思っていた以上に時流に合った研究活動をしているんですね。
|
| 水越 |
学環では、メルプロジェクト以外にもいくつものプロジェクトが同時に走っています。メルプロジェクトはまだ3年目なので、僕らの試みが今後成功するかどうか、なんとも評価できないし、結論も出せません。ラジカルに始まり、時流に乗りはしたが、その反動もあるだろうし、どうなるかわからないですね。
いま国立大学では独立行政法人化という制度改革が進んでいますが、情報学環はこの独法化を先取りしている。僕らは大学を社会に開いていく作業を先駆的にやっていると自負しています。
旧帝国大学たる東京大学は、例えて言えば、幕藩体制だったわけです。そこには法学部、医学部といった雄藩があるが、独法化によって幕藩体制は崩れざるを得ないでしょう。そのときに雄藩が時代にあったかたちで内部を改革することができるか。一方で情報学環のような新しい動きをよしとして、それらを窓口に異領域や社会と結びついていくことができるかどうかということが、課題になってくると思います。
|
| 矢野 |
 一般社会でも、いたるところで古い秩序が崩壊しつつあります。旧秩序が崩壊していく過程では、それを守ろうとする意識もまたピークに達する。内部はシロアリに食われてボロボロになっているけれど、外観はなお立派なマホガニーのドアのようなもので、だれかがそれに一撃を加えると、どっと崩れるんでしょうね。マスメディアの世界も同じで、なお古い秩序の束縛が続いていて、身動きがとれない。情報学環の去就とマスメディアの現状を重ね合わせて考えると興味深いですね。 一般社会でも、いたるところで古い秩序が崩壊しつつあります。旧秩序が崩壊していく過程では、それを守ろうとする意識もまたピークに達する。内部はシロアリに食われてボロボロになっているけれど、外観はなお立派なマホガニーのドアのようなもので、だれかがそれに一撃を加えると、どっと崩れるんでしょうね。マスメディアの世界も同じで、なお古い秩序の束縛が続いていて、身動きがとれない。情報学環の去就とマスメディアの現状を重ね合わせて考えると興味深いですね。
ぼくはサイバーリテラシーという考えを提唱していますが、いまの関心は、日本社会の基本構造がIT化によってどう変わるのか、変わらないのかということです。
|
| 水越 |
旧秩序ではあるが、現実に東京大学には全体で何千人というスタッフがいて、いまのままでも存在意義は大きいことはたしかです。ただ、情報学環のような柔軟な組織がきちんと機能していけるかどうかは、東大が現代においても健全に運営されているかどうかを測るバロメーターにはなりますね。
僕自身は情報学環が東京大学の一部局であるかどうかということよりも、おもしろい人材が集まり、コミュニティを形成していることそのものに関心があります。教授陣も既存の学問領域をはみだしているキメラ的な、ユニークな方が多いですね。そのキメラ先生と院生が結界をつくるという面妖な状況(笑い)。明らかに異色な伝統が生まれつつありますが、それだけに実りがある。この結界は強力だから、おいそれとは破れないですよ。50年、60年続くかどうかはわかりませんが、現実的なコミュニケーションの場は、そう簡単に崩れないでしょう。5年10年はしっかりやっていけると思っています。
|