| 矢野 |
関根さんはUDIT(ユーディット、Universal
Design Institute for Information Technology)という会社を起こし、情報技術(IT)の進展が、高齢者や障害者も含めて、すべての人にとって有益なものとなるよう「情報のユニバーサルデザイン」の普及につとめておられます。「ユニバーサルデザイン」とは何か、それは「バリアフリー」とどう違うのか、というあたりからお聞きかせください。
|
| 関根 |
社会生活を営むうえで、女性や子ども、高齢者や障害者にとって、さまざまなバリア=障壁があるから、それをはずしましょうというのがバリアフリーです。それに対して、街づくりにしても、物づくりにしても、設計段階からバリアがないようにしようという考え方がユニバーサルデザインですね。「バリアフリー」から「ユニバーサルデザイン」へ。私たちの社会が、ようやく発想転換を始めたということでしょうか。
そもそもバリアフリーというのは、生産性が最優先された20世紀の高度工業化社会の置き土産のようなものです。道路も交通機関も物も、そのすべてが、健康な成人男性を中心とした労働力を効率よく活かすために発達してきたんです。だから当然、高齢者や障害者にとってはバリアだらけで、「せめて道路にはスロープを、駅には車椅子昇降機をつけましょう」と、後から工夫を施す、そのことをバリアフリーと言ってきたわけです。
しかし、後付けの配慮ではコストがかさむし、そのための専用機器を調達しなくてはなりません。それでいて、例えば駅の車椅子昇降機は付き添いの方がいっしょに使えるわけではなく、ベビーカーや足の弱った高齢者も使えない。特定のニーズだけを選別し、その周辺の人を遮断していますよね。それがバリアフリーの欠点であり、問題点でした。
ユニバーサルデザインは、そういった後付けのアプローチでは高齢社会には間に合わない、はじめから高齢者や障害者、乳幼児連れのお母さん、妊産婦が使えるように、その意見を取り入れながら街や物をつくっていこう、という発想なんです。
ユニバーサルデザインという考えは、アメリカのノースカロライナ州立大学教授だったロン・メイス氏によって提唱されました。ロンの方が有名ですが、同じく車椅子ユーザーであった奥様の影響も強かったと聞いています。1980年ごろのことです。
|
| 矢野 |
現在、ノースカロライナ州立大学に置かれている「センター・オブ・ユニバーサルデザイン」は、ロン・メイス氏が創設したものですか。
|
| 関根 |
そうです。いまでも彼らの遺志を引き継いで、ノースカロライナ州立大学がユニバーサルデザイン運動の中心になっています。
|
| 矢野 |
UDITのホームページを拝見しましたが、そこにユニバーサルデザインの7原則がわかりやすく、写真を添えて掲載されていますね。
原則1:誰にでも公平に利用できること
原則2:使う上で自由度が高いこと
原則3:使い方が簡単ですぐわかること
原則4:必要な情報がすぐに理解できること
原則5:うっかりミスや危険につながらないデザインであること
原則6:無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること
原則7:アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること
というものですが、僕は、非常に素晴らしいと感じました。
|
| 関根 |
この7原則は、センター・オブ・ユニバーサルデザインで、建築家や工業デザイナー、技術者、環境デザイン研究者などが討議したものを、日本用にWeb上にまとめたものです。物をつくる人、街をつくる人、政策を決定する人にはぜひとも頭の中に入れておいてほしいことだと思います。
原則1では、「誰にでも」がポイントです。2は、さまざまな好みや能力に合うように。3に関しては、いま一つ使い方がわからないIT機器を思い出してください。4は、使う人の条件に関係なく、必要な情報が理解できる設計、5は、パソコンのソフトなどで、一度やったことを、すぐ元に戻せる、やり直せるように設計されていることが例に挙げられます。
7原則のどこにも、障害者とか高齢者とか妊産婦とか書いてありません。原則1に「誰にでも」という表現があるだけです。ごくごく当たり前の物づくりの原点が語られているだけです。
|
| 矢野 |
UDITのホームページでは、この7原則とその定義、それを守るためのガイドラインがていねいに書いてあって、非常にわかりやすいですね。
話がちょっと飛びますが、僕は今、編集という仕事がどういうものかを少し整理しています。読者にいかにわかりやすく情報を提供するかが編集者のつとめです。それは、ユニバーサルデザインが追求していることとまったく同じですね。
|
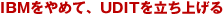 |
| 矢野 |
関根さんがUDITを設立したのは1998年秋ですね。その前はIBMのSNS(スペシャル・ニーズ・システム)センターに勤務していらっしゃったとか。
|
| 関根 |
 IBMで「情報のバリアフリー」にたずさわりました。パソコンやホームページを障害者の方が使えるように構築することが当時の私の仕事でした。 IBMで「情報のバリアフリー」にたずさわりました。パソコンやホームページを障害者の方が使えるように構築することが当時の私の仕事でした。
全盲の方がウェブサイトを見るためのホームページ・リーダー、点訳ワープロのソフトである点字編集システム、また、画面上の文字を点字ピンディスプレイという周辺機器に表示するソフトなどを手がけました。当時、NHKと協力して制作した手話学習のCD−ROMは、世界初の試みだったんですよ。
そんなふうに、世の中に必要だと思うものを企画して、予算を獲得し、製品化する。お客さまのフィードバックをいただいて、さらに次のバージョンをつくる、という繰り返しでした。すごくやりがいがあって、面白かったんですけれど。
|
| 矢野 |
行き詰まりを感じたということですか。
|
| 関根 |
障害者に使っていただく専用機器をつくっていたわけですから、ターゲットは限られているし、市場は小さく、コストはかかる、商品を普及させるための支援技術者がいない……、といったビジネス上における限界にいつも直面していました。6年間ぐらい悶々としていたでしょうか。
そして、「バリアフリーというアプローチが間違っているのではないか。今後のIT産業は、ユニバーサルデザインという考え方に立って、健常者が使うものが、そのまま高齢者や障害者も使えるといった製品群をつくることが必要だ」と気づきました。一般消費者向け製品の設計段階から関わっていくべきだと思ったんですね。
|
| 矢野 |
IBMという企業の中で、それを追求するお気持ちはなかったんですか。
|
| 関根 |
IBMでは、バリアフリー関連の仕事は企業の社会貢献としてきちんと位置づけられ、尊重されていましたが、当時はまだ、メインラインの製品から障害者も使えるようにしようという考え方はありませんでした。どこの企業もそうでした。
IBMのSNSセンターにいたおかげで、年間1万人近くの障害者の方々と、ネットやオフライン、展示会などで出会ってきました。多くの日本企業は、社員に障害をもつ人がほとんどいないので、障害者のニーズがわからない。それでいろいろな方から、「こういうときどうしたらいいと思う?」と、聞かれることが増えてきていたんです。私のようなノウハウをもっている人は日本にまだ少ない、もしかしたらコンサルタントとして独立してやっていけるかもしれない、と無謀にも思っちゃったんですね(笑)。
ちょうど自宅一帯で、ケーブルテレビ局がインターネット・サービスを開始していたのも、独立のきっかけになりました。ネットで仕事ができる!通勤時間も節約できる!やろう!というわけで、つい会社をつくってしまいました。
|
| 矢野 |
それはすばらしい。ご主人もごいっしょですか。
|
| 関根 |
夫は、まだIBM社員です。ここだけの話ですが、保険です(笑)
|
| 矢野 |
UDITという社名の由来は?
|
| 関根 |
UDとIT(アイティ)、つまりITのUD化を進める会社という意味ですが、ダブルミーニングになっているんです。UDITは外国の人にはアディットと読まれてしまうので、ユーディットと読んでもらうために、社名ロゴの下に「You
Do It」と入れて、かけ言葉にしました。とくにアメリカでは、障害のある学生を支援する「DOIT」というプロジェクトが広く知られていますので、「Oh,
You do it!」と、この業界ではとても通りがいいんです。
|
| 矢野 |
君がやるんだよ、と暗に強調してるんですね(笑)。
|