| 矢野 |
河口さんにも、当然のことながら、苦節時代があったわけですね。
|
| 河口 |
78年に工業技術院も筑波に移転することになりましたが、出原先生はどこかの大学に移ろうと考えていらして、僕も当然ついて行くと思われていたんですね。先生が「北海道に行く」とおっしゃったときには、「えーっ!」と。北海道といったら、種子島生まれの僕の居住の北限を越している(笑)。せいぜい関東地方までが北限だと思っていましたから、「気持ちはすごく行きたいんですが、本能的に寒いところに行くことは考えられないんです」と丁重にお断りしました。
すると先生は、「東京の電子系の専門学校で、CGアートを取り入れようとしているところがある。のぞいてみないか」と言ってくれました。それが新宿の日本電子専門学校です。工学系専門学校は情報処理が主流だった時代に、この学校はコンピュータを使ってやりたいことがあるという。話を聞きに行ったら、週に1回1コマ授業を持ってくれればいいと言われ、引き受けました。
日本電子専門学校のコンピュータは、キャラクターや文字しか出ませんでした。グラフィックディスプレイではないので、せっかくつくった3次元グラフィックスの巻貝なんかが出てこない。とりあえず教材用のツールとして、線や点で般若の面などをつくっていました。講師になって2、3カ月たったころ、芸術学部長が「アメリカでCGの国際大会があるからいっしょに見に行こう」と誘ってくださった。それがSIGGRAPH(Special Interest Group on Computer Graphics、シーグラフ)のシカゴ大会で、ものすごくラッキーでした。日本でもまだ数人しか知らないようなCGアートのトップが集まるSIGGRAPHを、いきなり見て来たんですから。
|
| 矢野 |
そのとき、作品を持って行かれたんですか。
|
| 河口 |
いいえ、持って行きません。生まれて始めての海外旅行で(笑)、映画『トイ・ストーリー』をつくったピクサー社の社長をはじめ、当時のCG界のパイオニアといわれるほぼすべての人に会いました。驚いたのは、すでに陰影をつけた自動車や宇宙船、ビルのCG作品が出品されていたことです。日本は10年から20年遅れていると思った。
帰国後、学部長が校長と相談して、シリコンバレーから色の出るコンピュータを取り寄せてくれたんですね。それで、これまでの巻貝や渦巻の作品を、カラーグラフィックディスプレイ用に全部つくり換えました。色の出るコンピュータが、まだ話題にもならない時代です。
|
| 矢野 |
その少し後に、僕が取材にうかがいました。1982年4月30日号のまだ大判だった『アサヒグラフ』の巻頭25ページを使って「コンピュータ・イメージ」特集をしたとき、河口さんの作品を8ページほど紹介したわけです。岡田明彦カメラマンがディスプレイから苦労して写し取った巻貝などのカラー作品が掲載されています(旺文社文庫『コンピューターの衝撃』1983に再録、絶版)。
|
| 河口 |
まだ256色しか出なかったのですが、色のトーンを統一して陰影をつける方法を考えました。フルカラーを使うとかえって硬い感じになってしまうので、たった256色で、なるべく滑らかな色にする。ものすごく苦労した覚えがあります。
|
| 矢野 |
河口さんの作品を世に伝えること自体がニュースだったころです。「グロースモデル」という考えはどこで発表されたんですか。
|
| 河口 |
81年か82年のSIGGRAPHから帰国後、「僕もこういうのをつくっています」と、自己紹介を兼ねてスライドやお礼の手紙を各方面に送りました。作品に名前が必要だったので、「グロースモデル」と。「アンモナイト」でも「ナマコ」でもない(笑)、何か統一的な方法論を示す名前をつけたほうがいいと思ったんですね。
はじめてテレビに出たのが79年、NHKの『サイエンスレーダー』という番組でしたが、その後、雑誌の表紙やポスターの制作依頼、取材の申し込みが飛び込んでくるようになりました。国際的には81年のSIGGRAPHにエントリーして、それが通って82年に発表したのが最初でした。アート賞に静止画を出しましたが、まさか通ると思わなかった。
当時の研究室はJR大久保駅近くの焼鳥屋の2階で、夜、仕事をしていると、焼き鳥の匂いがプンプン入ってくる(笑)。コンピュータも今みたいに速くないから、計算に何時間もかかる。毎晩2、3種類、画像をつくる仕掛けをつくって、夜9時すぎにいっせいにそれを走らせて、新宿界隈に飲みに行く。翌朝、出勤してくるころには計算が出来上がっている、という具合で、やればやるほどおもしろかった、燃えていましたね。あんなに時間との格闘でやったことは、ないくらいです。
|
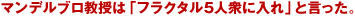 |
| 矢野 |
僕が取材したときも、「いまは時間との競争。食事をする時間も惜しくて」と言ってましたね。「時代の波にうまくはまった」面もありますが、流行と離れたところで好きなことをやってきたから、かえって花開いたとも言えますね。
|
| 河口 |
 さっきも言ったけど、大学卒業から日本電子専門学校に入るまでは、かなりきつかった。大学院では四面楚歌だったし……。79年のSIGGRAPHでようやく光が見えたんです。アメリカではすごいテクノロジーを使っているが、「無から有を生み出す」というアート的なコンセプトをもっている人はいない、とわかったことがよかった。テクノロジーだけではアートは生まれない。映像はきれいだけれど、発想のコンセプトが見当たらないのでは、テクノロジーの有効利用ではない。 さっきも言ったけど、大学卒業から日本電子専門学校に入るまでは、かなりきつかった。大学院では四面楚歌だったし……。79年のSIGGRAPHでようやく光が見えたんです。アメリカではすごいテクノロジーを使っているが、「無から有を生み出す」というアート的なコンセプトをもっている人はいない、とわかったことがよかった。テクノロジーだけではアートは生まれない。映像はきれいだけれど、発想のコンセプトが見当たらないのでは、テクノロジーの有効利用ではない。
それと、僕自身、目標を高くもつことができるようになったのもよかった。「一刻も早く、アメリカ並みに色の陰影を表現できるコンピュータを」と、学部長たちを焚きつけましたし、それでやっと僕の「グロースモデル」に色がついた。色がないうちは、マスコミは注目しなかったけれど、82年にボストン大学で発表したら超満員でした。ちょうどそのころ、マンデルブロ教授のフラクタル理論が注目されていて、発表後の質疑応答で「グロースモデルはフラクタルと、どんな関係があるのか」と聞かれました。僕は「わかりません。何ですかそれは」(笑)。まだ日本に「フラクタル」という言葉は入っていなかったですから。
|
| 矢野 |
河口さんは「フラクタル」を知っていて、その理論をCGに応用したのかと思っていたけれど、違ったのですね。その話は実におもしろい。というか、感動的ですらあります。
フラクタル(Fractal)というのは自己相似性のことで、ある図形の部分が全図形の縮小された像になっているようなものをいい、世の中にある複雑なものの中には、こういう特徴をもったものが数多く存在するんですね。じつは、僕も河口さんの作品を取材したとき、はじめてフラクタルという言葉を知りました。作品を解説した記事なんかにそんなことが書いてあったわけで、たしかに河口さんから直接、フラクタルと聞いたわけではなかった。
|
| 河口 |
マンデルブロ教授は数学者で、関数としての振れを使ってディテールを構成していくんです。最初にバシッとハリボテをつくり、それを中間で割って、また中間で割ってという具合に繰り返し、細かい海岸曲線をつくり出す。「グロースモデル」の場合は、1個の細胞体がなんらかの刺激でザーっと伸びたりグルグル回ったり、どんどん増えていきますが、全体の構図があらかじめわかっているわけではない。
最初におおまかなハリボテをつくるという理論を聞いて思い浮かんだのは大聖堂です。西洋では建築物の全体像を、まず構築的にこしらえたうえで、ディテールを削りとっていくのだろうと。一方、僕は東洋人だから、雨に濡れ、風に吹かれながら、部分部分からつくっていく。だから、構図は風まかせ、雨まかせなんだと。それはマンデルブロ教授にはない考え方です。西洋の文化では、キリスト教的な決まりに従って世界が構築され、そこからディテールが生まれ、つくり込まれていく。僕には東洋のアニミズム(自然崇拝)的な発想が強くあって、彼らの流れとは逆なんだと気づきました。
|
| 矢野 |
マンデルブロ集合というのは大変有名で、科学ジャーナリストの書いた『カオス』(ジェイムズ・グリック著、新潮文庫)という本にたくさんの例が収録されていますね。おたまじゃくしのような図形にタツノオトシゴの尻尾そっくりのでっぱりや島の微粒子のようなものがついており、その部分が全体とうりふたつの構造をもっていて、河口さんの作品の巻貝なんかにもよく似ています。しかし、河口さんがつくる巻貝は、どういうふうに成長していくかがわからないわけですね。
取材した当時は、その辺がよくわからないままに、「(河口さんの作品は)巻貝や樹木など成長する生物を描いたものが多いが、それは彼が生きとし生ける物に共通に潜む形態の美しさにひかれ、その数学的法則を見つけようとしているためらしい。数学から美へ迫ろうというなんとも壮大な試みで、彼はコンピューター・グラフィックスを『画像表現の全過程を論理的に構築されたアルゴリズム(算法)に基づいて行う新しい芸術行為』と位置づけている」(『コンピューターの衝撃』)と書いています。最後に「そういえば数学者岡潔は、かつて『数学とは自己を表現するものだ』といったことがある」と付記しているところに、薄々ながらも、河口作品の独創性を感じていたらしい片鱗がうかがわれます(笑)。
|
| 河口 |
マンデルブロ教授は僕の作品を認めてくれて、ニューヨークの自宅に招いてくれました。銀河星雲の作品をさして、「これはフラクタル関数だろう」と言うんですが、僕はまったくフラクタルを知らないところでやってたんですからね。「おまえも我々フラクタル5人衆に入ったらどうだ」と勧誘されたのには困った(笑)。僕が5人衆に入ったとしても、どうしようもないでしょう。
フラクタルの発想には、おおまかな未来への視野や展望がある。しかし、僕の考え方は非決定論的なんです。未来は決めないほうがおもしろいという発想だから、非常に東洋的。どう伸びていくか、やってみなければわからないところを大事にする。画家が絵を描くのに完成予想図はないし、描いているうちにどんどん変わるという発想と同じです。
|
| 矢野 |
プログラムが自己増殖することによって形ができる。制作者がどうしようと決めているわけじゃないんですね。
|
| 河口 |
刺激値が6通りから10通りあって、微妙に変えていくと形が変わるんです。しかし実際にはやってみないとわからないから、試行錯誤の連続だし、時間がかかる。当時は1枚の映像をつくるのに30分から1時間かかっていました。フラクタルはあらかじめ建築図みたいなものをつくって再分割していくわけだから、僕のやり方とはまったく方法論が違うんです。
|
| 矢野 |
それこそが、「ザ・種子島」なんですね(笑)。
|