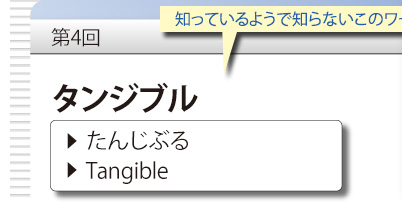英語の「Tangible(タンジブル)」の本来の意味は、「実体がある様」「(物体などが)触れられる、触知できる」。「tangible assets」は有形資産(現金・商品など)と訳される。語源はラテン語の「tangere(タンジェール)=触れる」で、三角関数の「tangent(タンジェント)」が「正接」と呼ばれるよう、「接する」という意味が本来の意であることを知ると、この数年、ICT業界で使用される「タンジブル・ビット」「タンジブル・インターフェース」というワードへの理解は早い。
「タンジブル」という言葉がICT業界で使用され始めたのは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の石井裕教授が1997年に発表した「タンジブル・ビッツ」という論文が、世界的な評価を得たことが契機となった。そのネーミングの妙もあり、言葉自体がヒューマンインターフェースの世界で引用され始めた。同氏の提唱するユーザインターフェースの形態が既存のコンピュータの概念を一新。キーボード、マウス、ディスプレーなど従来のインターフェースの枠組みを超えて、ユーザがデジタル情報と直に接する研究が、「タンジブル・ユーザインターフェース」として世に広まった。
「タンジブル・ユーザインターフェース」の技術を使用した具体的なプロジェクトとしては、NTTコムウェアによる、紙地図にマークするように複数のユーザが同時に情報を共有する防災ソリューションシステムや、内田洋行による、企業・博物館向けにキーボードやマウスを使わずにプレゼンテーションできる「プロジェクションテーブル」などが挙げられる。ガラス瓶にデジタル情報として音楽を詰めて、ふたを開けると音楽が流れる「ミュージックボトル」など、エモーショナルなアプローチの研究も進められている。

Tangerine Dream
『Electronic Meditation』
「Tangerine Dream」
ジャーマン・プログレのバンド。クラフトワークと並ぶテクノの源流の一筋であるタンジェリン・ドリームの70年に発売されたデビューアルバム。バンド名の「タンジェリンドリーム」は北アフリカ原産のオレンジの名前として知られているが、ラテン語のタンジェールなら「触れられる夢」。