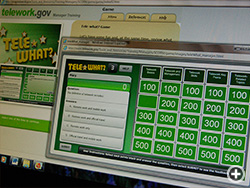
アメリカの連邦政府のためのテレワーク・ガイドラインのウェブサイト。トレーニングには職員用と上司用がある。最後には、内容を十分把握したかゲーム方式で確認するようになっている。遊び心を忘れないアメリカらしさがうかがえる。
www.telework.gov
共働きが当たり前のアメリカ。ところが、幼稚園や小学校では、保護者のボランティアを依頼されることが多く、働いているはずの母親たちも、頻繁に学校に顔を出している。スクールバスのお迎えも、3時や4時でも、きちんとバス停で待つ親は多い。「専業主婦か、パートタイマーかな?」と思って聞いてみると、「フルタイムで働いているわよ。でも、テレワークで仕事の一部は家でしているの」という答えが返ってくることが、D.C.では珍しくない。勤務先も、銀行、法律事務所、コンサルタントと、聞くたびにそのすそ野が広がっていくから驚きだ。
テレワークとは、電話やインターネットなどのネットワークを使って職場以外で仕事をする勤務形態で、在宅勤務の場合が多い。「子供の面倒を見ながら仕事ができるなら、女性にぴったり!」と思いきや、意外に厳しい制限もあるようだ。ある女性によれば、「子供が学校から帰ると、宿題を見たり、おやつを出したりしないといけないから、そういう時間は、仕事の時間から外さないといけないの」とのこと。それでも、テレワークが特に女性に人気があるのは、通勤時間が省けて、家庭と仕事とのバランスが取りやすくなるからというのは言うまでもない。そして、すべてが片付いて、夜の静かなひとときは、「結構集中して仕事ができる」という声もある。
こうした「働き手」のメリットを重視して、アメリカでは以前からテレワークが浸透し始めていた。ところが最近は、国の政策として、大々的に促進されている。知り合いに勧められてホワイトハウスのウェブサイトで検索してみると、確かに2010年12月には、「テレワーク推進法」がオバマ大統領の署名によって成立している。その効果として「自然災害や緊急事態にも、政府機関が機能できること」がうたわれている。その年の2月には、百年に一度という大雪に見舞われ、ワシントンD.C.の政府機関はまひ状態に陥り、23万人もの政府職員が一週間近く休みをとる羽目になった。ある試算では、1日1億ドル(約90億円)もの生産性損失になったそうだから、財政の苦しい政府としては新たな対策を迫られた結果、テレワークを推進することになったとも言える。
そうは言っても「家での仕事を認めたら、みんなズルするんじゃない?」と思う人は多いだろう。私も、どんな情報を聞いても、職場と同じように家でまじめに仕事するとは思えなかった。だが、ひょんなことから、私自身が実際にテレワークで仕事をすることになり、いざやってみると「サボってなんかいられない!」ことに気がついた。結果を出さないといけない上に、もしサボって他の人に仕事を取られたら…と思うと、むしろ効率を上げる努力が必要になってくるのだ。上司が信頼してくれている反面、その期待に応えないと申し訳ない気もしてくる。さらに、テレワークの時間が長くなると職場のメンバーとのコミュニケーションが恋しくなり、「ずっと家で働きたい」とは思わないものなのだ。どれもこれも、意外な発見だった。
役所に勤務し、テレワークの職員を監督する立場だった女性によれば、「職場で効率良く働いている人は家でもきちんと結果を出すし、職場で態度が良くない人は家でも同じだから、誰がテレワークに適しているか、すぐにわかる」らしい。彼女の勤め先では、賃貸で借りる物件をどんどん減らしてワークスペースを縮小しているらしく、多くの職員が当たり前のようにテレワークしているという。その代わり家に持ち帰るラップトップは支給され、スカイプを使ってオンライン会議をしたり、報告書を作成するのにも複数のメンバーでパソコン画面上のデータを共有し、編集し合うことも可能だという。
「アメリカでも、テレワークは10年前くらいにパイロット版がテストされていたぐらいだから、日本も10年後にはこれが当たり前の生活になるかもしれないわね」彼女の言葉と彼女のバーチャルオフィスを目の前にして、私はそれが確実に今後、日本にも広がるような予感がした。
笹栗実根(ささぐり・みね)
1999年、テレビ局のワシントン特派員としてアメリカへ。以後、結婚退職してフリーライターに。『asahi.com』(webサイト)、『教室の 窓』(東京書籍)、『エコマム』(日経BP)などにアメリカに関する原稿を執筆する他、FM802でラジオレポート。現在、ワシントンDCで、翻訳の仕事も担当。


