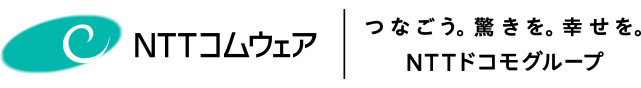「ゼロトラスト」という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的に何なのか、自社に必要なのか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に少人数でセキュリティを担っている中小企業では、対応に大きな負担を感じることもあります。また、様々なクラウドサービスの利用が当たり前になった今、「うちの会社のセキュリティは大丈夫なのか」と漠然とした不安を抱えている担当者も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、「ゼロトラストとは何か」という基本から、導入のメリットや方法まで、できるだけ易しくお伝えします。セキュリティに詳しくなくても大丈夫です。一緒にゼロトラストを理解していきましょう。
01 そもそも”ゼロトラスト”とはどんな考え方?

ゼロトラストは「全てのアクセスを常に信頼せず検証する」という原則に基づいた、現代の働き方に適したセキュリティモデルです。以前は「社内ネットワーク=安全」とされていたため、ファイアウォールやVPNで外部からの脅威を防げば十分とされてきました。
しかし、現在ではテレワークやクラウドサービスの利用拡大に伴い、社内·社外の境界があいまいになりました。その結果、企業の情報資産が社外にも広がっています。社員が自宅や外出先から様々な端末で社内の情報にアクセスできるようになり、“外部からの脅威を防ぐだけ”の対策では対応しきれないケースが増えています。
ゼロトラストでは、「社内·社外」といった場所の違いに関係なく、全てのアクセスについて「ユーザーの正当性」や「端末の安全性」をチェックします。
ユーザーID·デバイスの状態·アクセス先などを確認して、必要最小限の範囲にのみアクセスを許可するのが、ゼロトラストの基本的な仕組みです。
02 “社内=安全”はもう通用しない?ゼロトラストが必要なワケ

この章ではゼロトラストが必要とされる3つの理由を解説していきます。
テレワークやクラウド化で「守るべき範囲」が広がった
現在では、テレワークやクラウドサービスの利用が当たり前になりました。社員は自宅や外出先から様々な端末で社内システムにアクセスしています。その結果として「社内は安全、社外は危険」といった従来の前提は通用しにくくなり、誰がどこからアクセスしているのか把握するのも難しくなっています。
実際には、私物のスマートフォンからクラウドにアクセスする社員や、個人のクラウドストレージに業務データをアップロードするなど、管理しきれない状況が増えているのが現状です。
こうした複雑な環境には、アクセスごとに検証を行うゼロトラストの考え方が欠かせません。
サイバー攻撃は気づかないうちに入り込んでくる
ランサムウェアや標的型攻撃など、最近のサイバー攻撃は手口がますます巧妙になっています。
例えば、社内の誰かになりすましたメールに添付されたファイルを開封してしまう、普段使っているクラウドサービスに似たログイン画面にうっかり情報を入力してしまうなど “見破るのが難しい”ケースも少なくありません。
こうして盗まれた情報を使って不正なアクセスが行われ、それが原因で社内に被害が拡大することもあります。ゼロトラストでは、アクセスのたびにユーザーや端末の状態をチェックするため、こうした攻撃の侵入や拡大を防ぐことが可能です。
「社内だから安心」は、もう通用しない
情報漏洩や不正アクセスの原因は、外部からだけではありません。
例えば、退職した社員アカウントが削除されずに残っている、特定のメンバーに必要以上のアクセス権限が付与されている場合です。こうした小さな管理ミスが、思わぬセキュリティ事故に繋がる恐れがあります。
ゼロトラストでは、社内外に関係なく全てのアクセスを検証し、必要最低限の権限だけを与えることで、こうした“内部リスク”にも対応できます。
03 ゼロトラストで何が変わる?導入する3つのメリット

ここからは、ゼロトラストを導入することで得られる主なメリットを3つご紹介します。
セキュリティを強化し、リスクを最小限に抑えられる
これまで多くの企業が利用してきたVPNは、一度接続すると、社内ネットワークに広くアクセスできる仕組みが一般的でした。このような構成では、仮に不正アクセスやマルウェア感染が起きた場合に、被害が一気に広がるリスクがあります。
一方ゼロトラストでは、アクセス範囲を最小限に制限できるため、ランサムウェアのような攻撃に対しても影響を抑えやすくなります。また、アクセス権限を必要最低限にしておくことで、万が一の情報漏洩や、紛失·盗難による端末リスクにも備えることも可能です。
このように、ゼロトラストは“侵入を防ぐ”だけではなく、“侵入された後に被害を広げない”という防御にも効果を発揮します。
クラウドサービスを安全に使い続けられる
ファイル共有やスケジュール管理のようなクラウドサービスは、今や多くの業務で欠かせません。便利な反面 「社員がどこからアクセスしているのか、本当に把握できているだろうか…」と不安を感じる場面もあるのではないでしょうか?
ゼロトラストの考え方をベースに、データ損失防止(DLP)やクラウドアクセスセキュリティブローカー(CASB)などの技術を組み合わせることで、不正な情報共有や、外部流出を自動で検知・ブロックすることが可能です。
さらに、シングルサインオン(SSO)や多要素認証(MFA)を組み合わせれば、利便性を損なわずにセキュリティ強化もできます。
これにより、社外からのアクセスが増えても、安心してクラウドを業務に活用できます。
少人数でもセキュリティ運用がしやすくなる
限られた人員でセキュリティを管理しながら、日々の業務に追われる中で、全ての管理を手動で行うのは現実的ではありません。ゼロトラストを実現する仕組みを導入すれば、社員の入退社時の権限設定を自動化したり、不要なアカウントを検知したりといった方法で、管理の負担を減らせます。
セキュリティは日々変化し、新たな脅威が次々に登場します。そのため、いつでも相談できるパートナーを持つことも大切です。必要に応じてセキュリティを専門とする外部パートナーに任せることで、最新の知見を活かしながら運用し続けることも一つの手段です。
04 ゼロトラスト導入、まずはここから

ゼロトラストは、たったの3ステップで導入できます。ステップこそシンプルですが、一つひとつの準備や進め方がとても大切なので、それぞれの段階を丁寧に行いましょう。
- 現状のセキュリティ状況の可視化、把握をする
- セキュリティに関するルールの見直しと整備を行う
- 優先順位に応じて必要なソリューションを導入する
まずは、自社のIT環境やリスクの把握が重要です。オンプレミス·クラウドの利用状況や脅威を評価し、客観的なデータを収集しましょう。
05 まとめ

ゼロトラストは、社内外を問わず全てのアクセスを検証し、必要最小限の権限だけを付与することで、現代の働き方に合ったセキュリティを実現します。
導入することで、セキュリティ強化はもちろん、クラウド活用や少人数での運用効率化も可能になります。
ただし、自社だけで進めるのは難しい場合もあります。そんなときは、セキュリティ専門のパートナーに相談するのが安心です。
NTTドコモソリューションズでは、ゼロトラスト導入に向けた現状分析から、必要なソリューションの選定·導入、運用まで一貫してサポートしています。まずは小さな疑問や不安からでも、お気軽にご相談ください。
また、中小企業向けに現実的で柔軟な導入プランを提供しています。豊富な実績と専門的なサポート体制により、コストを抑えながら安心のゼロトラスト環境を実現できます。ゼロトラストの導入を検討中の方は、ぜひご利用ください。