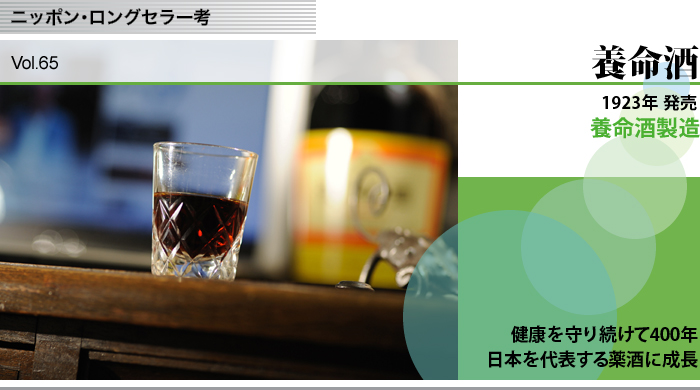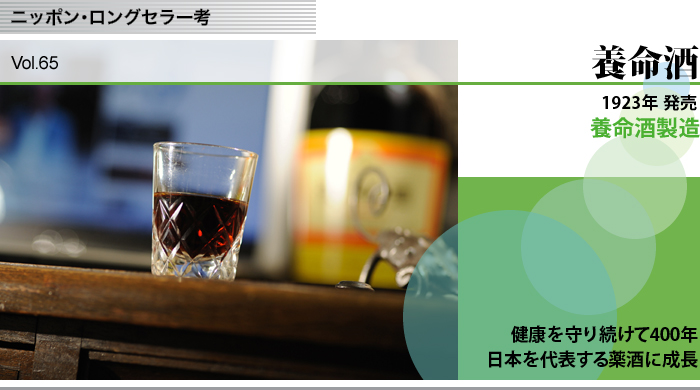|
| 連続ラジオ放送劇「少年探偵団」の録音風景。 |
|
|
|
宣伝カーによる街頭宣伝。1960(昭和35)年頃。
|
戦後の1949(昭和24)年、養命酒は再び薬局・薬店ルートで販売できることになった。加えてその翌年には戦時中に敷かれていた価格統制が撤廃され、養命酒の自由販売が実現。これを機に、経営陣は今まで以上の積極販売に乗り出すことになる。51(昭和26)年には社名も現在の「養命酒製造株式会社」に改称した。
ちょうどこの頃、日本のマスメディアに大きな変革が訪れていた。51年にはラジオの民間放送がスタート。その2年後にはテレビ放送が開始されている。広告効果を熟知していた養命酒製造が新しいマスメディアを見逃すはずはなかった。同社は52(昭和27)年には早くもラジオ東京(現:TBSラジオ)でスポット広告を打っている。昭和30年代に入るとメディア露出はさらに加速し、55(昭和30)年にはCMソング「養命酒音頭」「幸福の酒」を制作。翌56(昭和31)年にはシンギングCM「養命酒一杯の歌」を制作したほか、ニッポン放送の連続ラジオ放送劇「少年探偵団」のスポンサーにもなっている。
興味深いのは、この頃の広告が多分に子供を意識している点だろう。子供向けラジオ番組の提供がそうだし『少年サンデー』『少年マガジン』といった当時の少年漫画誌には、漫画スタイルの広告が掲載されている。漫画がブームになっていたこともあるが、その背景には養命酒ならではの巧みな広告戦略があった。
元々養命酒は滋養強壮剤を目的とした薬酒である。昭和30年代、最も滋養強壮を必要としていたのは大人ではなく子供だった。食糧事情の悪かった状況が完全に払拭されたわけではなく、巷にはまだ虚弱児童が少なくなかったのである。果たして養命酒製造の子供向け広告戦略は大いに成功し、「子供が飲んで元気になったから親も養命酒を飲むようになった」というケースが増えたという。今は時代が変わり、14度数のアルコール分を含む事もあって、養命酒は子供向けには宣伝・販売していない。
養命酒製造の広告戦略はまだまだ続く。1964(昭和39)年からは本格的にテレビCMに参入。ワイドショーや家族向けのバラエティ番組、ゴールデンタイムのドラマ等、あらゆるジャンルで番組提供を行い、養命酒の知名度を大きくアップさせた。CMタレントも俳優の坪井研二に始まり、山本學、加藤芳郎、藤田まこと等、親しみやすい顔ぶれを多数起用してきた。現在オンエアされているのは、女優・原田美枝子を起用した落ち着いたテレビCM。淡々と養命酒の効能を語る語り口が印象深い。
こうしたマスメディア広告以外にも、養命酒製造は宣伝カーによる街頭での拡販活動、東京国際ホームショー等の展示会への出展、店頭ポスターやチラシの配布など、地道な宣伝活動を継続して行った。
企業規模から考えると、同社が広告にかけた予算はかなり大きい。リスクも相当あったはずだが、ここまで思い切った戦略を取ったからこそ、養命酒は市場で独占的な地位を築くことができたともいえる。市場には養命酒に競合する商品が何度も登場したが、結局はどの商品も養命酒の牙城を切り崩すことができなかった。
1965(昭和40)年、養命酒の年間販売量は4000キロリットルを越えた。その後も高度経済成長期と足並みを揃えるように、養命酒はその販売量を年々増加させていく。ピークは1996(平成8)年に記録した約14000キロリットル。近年は漸減気味だが、平成以降も平均約12000キロリットルを販売している。薬酒業界のシェアは、なんと90%以上になるという。
|
|
|
|
 |
|
1958(昭和33)年制作のポスター。
|
1970(昭和45)年頃の雑誌広告。漫画形式になっている。
|
昭和40年代のポスター。
|
珍しいホーロー看板広告。 |
|