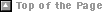エスビー食品の創業者・山崎峯次郎。戦後の日本にカレーを根付かせた重要人物だ。
農水省の統計から計算すると、日本人は1年に約84回、つまり毎週1回以上はカレーを食べているのだという。また、各種の調査から類推すると、月に2.5回前後は家庭でカレーを作って食べていることになるらしい。日本人は本当にカレーが大好きだ。
カレーがインドからヨーロッパを経て日本に入ってきたのは、文明開化のころだと言われている。明治から大正にかけて、カレーは町の洋食屋で提供されるハイカラな料理として人気を集めるようになっていた。そこで使われていたのは、イギリスの会社が販売する「C&Bカレーパウダー」という商品。洋食屋では圧倒的なシェアを占めていた。
この洋食屋のカレーと出会い、その後の人生を決定づけられた一人の男がいる。名前は山崎峯次郎。後のエスビー食品の創業者だ。1920(大正9)年、17歳で埼玉から東京に出てソース店で働いていた峯次郎は、ある日の仕事帰り、ふと洋食屋に立ち寄った。そこで噂に聞くカレーを食べ、一口食べた瞬間、こう叫んだという。「辛い! しかし、なんと旨いんだろう」。感動はそこで留まらなかった。峯次郎は自らの手でカレー粉を作ることを決意する。当時も日本製と称するカレー粉は売られていたが、それらは「C&Bカレーパウダー」に他の香辛料を加えて増量した代物だったからだ。
決意はしたものの、峯次郎は最初から行き詰まってしまった。カレーに関する書物や資料はどこにもない。輸入されたカレー粉の説明書きを翻訳してもらっても、そこには「東洋の神秘的な方法によって製造された」と書いてあるだけ。途方に暮れていたある日、峯次郎はインド在住30年の老人と偶然知り合う機会を得る。老人は峯次郎に興味を示し、わざわざインドから数種類のスパイスを取り寄せてくれた。峯次郎は歓喜するが、スパイスの袋には原料名が書かれていなかった。インドでは各家庭のレシピに沿ってこれらを調合するのだが、基礎知識すらない峯次郎にはどうしようもない。そこで、まずは使われているスパイスを特定するために、日本の生薬を買い込んでは比較し、一つひとつ原料を解明していった。
スパイスの特定に次ぐ課題は、それらをどういう割合でブレンドするかという"調合"。峯次郎が特定したスパイスを組み合わせるだけでも、その作業は膨大な量になる。あのカレー独特の香ばしい香りは、どのような黄金比率から生まれるのか。峯次郎は自分の舌と鼻だけを頼りに、調合作業に没頭した。鼻が効かなくなると、銭湯へ行って鼻と身体を洗う。家に戻ってもすぐには中へ入らず、カレーの香りがしないかと玄関先をウロウロする始末。近所からは変人扱いされ、警察沙汰になったこともあった。
ある年の暮れ、峯次郎は石油缶に入れて保存していた大量の調合袋を処分するため、一つひとつの香りを再びチェックしていた。するとある袋から、あの懐かしいカレーの香りが立ち上ってくるではないか。峯次郎はハタと気が付いた。「そうか。カレー粉も酒と同じように、一定期間寝かせておく必要があるんだ」
峯次郎の研究は更にここから大きく前進した。スパイスは煎ることで香りを引き立て、全体の香りを整えることができる。そのため、自ら「八角ドラム」と呼ばれる焙煎機を開発した。スパイスの製粉工程にもこだわった。高速製粉機を使えば効率は上がるが、香りは飛んでしまう。峯次郎は臼と杵を使った「スタンプミル」という製粉機を開発。時間はかかるが香りを失うことなく作業できるこの機械は、今も工場内で稼働しているという。
スパイスの選定、調合、焙煎、熟成という、カレー粉作りに欠かせない4つのポイントを相次いで発見した峯次郎は、念願の"純国産カレー粉"を完成させた。「C&Bカレーパウダー」をベースにした既存のカレー粉とは違う、オリジナルなカレー粉の誕生だった。

「ヒドリ印カレー粉」。内容量は38gで、瓶に入れて発売された。

「赤缶カレー粉」の前に発売されていた「白缶カレー粉」。これも業務用だった。

発売当時の「赤缶カレー粉」。缶のデザインは60年後の今も全く変わっていない。
1923(大正12)年、純国産カレー粉を発売するため、峯次郎は浅草にエスビー食品の前身となる「日賀志屋」を創業。渾身の作であるカレー粉を1ポンド(約450g)缶に詰め、業務用として洋食屋に販売した。当時の「C&Bカレーパウダー」の値段は1円15銭。峯次郎のカレー粉はそれより5銭安かったが、当初はなかなか売れなかった。洋食屋は「C&Bカレーパウダー」を長く使っている。コックは安易に料理の味を変えたくなかったのだ。
だが、峯次郎は諦めなかった。料理の大家に試食を依頼して推薦状を書いてもらい、それを商品のラベルに貼った。有力な問屋のオーナーを説得し、商品を扱ってもらったこともあった。1931(昭和6)年には、思わぬ追い風が吹いた。輸入品の洋酒や缶詰などに偽造品が見つかり、全国で販売が一時中止されたのだ。カレー粉もこの中に入っていたため、峯次郎のカレー粉に注文が殺到。洋食屋などプロの世界で認められ、評価は一気に高まった。
このころ峯次郎は新たな展開に乗り出している。1930(昭和5)年には、初の家庭用カレー粉となる「ヒドリ印カレー粉」を発売。ヒドリ印は太陽と鳥をあしらった商標図案で、そこには日が昇るような勢いで会社を成長させたい、鳥が大空を駆け巡るように製品を全国津々浦々まで浸透させたいという願いが込められていた。翌年には、ヒドリ印に「太陽(SUN)」と「鳥 (BIRD)」の頭文字である「S&B」を併記して商標登録。ちなみにこの「S&B」ロゴは社名のS&Bの由来であり、現在はエスビー食品のコーポレートシンボル「SPICE & HERB」を意味している。
33(昭和8)年には、「赤缶カレー粉」の前身にあたる本格的な業務用カレー粉(通称「白缶カレー粉」)を発売。今まで以上に洋食屋に浸透していった。
順調に見える峯次郎の事業だが、戦前から戦中にかけては大きな試練に見舞われている。カレーの原料であるターメリック、クミン、カルダモンといったスパイスは、そのほとんどがインドやアジアなどからの輸入品だったが、戦時中は物資統制によって限られた数量しか入手できなくなったのだ。業界団体の代表になっていた峯次郎は、社長業の傍ら業界全体が原料を入手できるよう関係筋と交渉を行うなど、時間を惜しまず東奔西走した。戦後もしばらくは原料不足が続いたが、1950(昭和25)年、ついにスパイスの輸入が再開されることになる。
同年、満を持してエスビー食品が発売したのが、家庭用の「赤缶カレー粉」だった。おとなしい白に変わって、なぜ鮮烈な赤が選ばれたのか? もちろん赤はカレーの刺激的な香りや風味を象徴しているが、そこには峯次郎やエスビー食品の、もっと大きな意志がこめられている。戦争が終わって5年。戦禍はまだあちこちに残っているが、世の中には新しい風が吹き始めていた。誰もが新たな時代の胎動を感じ、もう一度この国をつくり直そうとしている。そう、赤は復興のエネルギーの象徴でもあったのだ。
赤い缶に描かれたレトロなデザインの白文字はよく知られているが、その背景に国会議事堂が描かれているのを御存知だろうか? 国会議事堂の竣工は1936(昭和11)年。日本を代表する建築物であることから、峯次郎は議事堂に憧れを抱いていたのだろう。戦前から自社の製品のデザインに採り入れていたようだ。戦後間もなく、峯次郎は板橋工場の敷地内に議事堂を模した建物を建設。同じ頃、国会議事堂にカレー粉のネーミングを配した商標登録を出願している。「赤缶カレー粉」に国会議事堂が描かれているのもまた、日本の復興に向けた峯次郎の願望だったのだろう。

現行の「赤缶カレー粉」。缶のサイズは20g、37g、84g、400g、2kg、10kgの6種類ある。
ラジオ放送で盛んにCMを打ったこともあり、「赤缶カレー粉」は発売当初から消費者の人気を集めた。市場には競合する製品も少なくなかったが、業務用分野で確立した「S&B」ブランドには、信頼に基づく大きな優位性があったのだ。
「赤缶カレー粉」発売後、ほどなくして市場には手軽に作れる固形の即席カレーが登場するが、意外にも「赤缶カレー粉」が売れ行きを落とすことはなかった。理由はいくつもある。「赤缶カレー粉」は業務用のカレー粉として、既にレストランなどから「白缶カレー粉」以上の支持を得ていた。小麦粉とバターを加えてルウから作る必要はあるが、一缶で多人数分のカレーを作れるので、多人数家庭や工場・学校などで使われた。それは当時から既にカレー粉としての完成度が高かったということだろう。
「赤缶カレー粉」の味覚や風味が確立したのは、発売から10年後のこと。峯次郎が開発したオリジナルの味を守りながら、当時の日本人の味覚に合うように細かな改良が続けられた。数十種類に及ぶスパイスは、一つひとつがその特徴を活かしながらも、どれか一つが突出することはない。微妙なバランスの上に作り上げた、日本人の嗜好にぴったり合うカレー。それが「赤缶カレー粉」の本質と言えるだろう。
特徴的な缶のデザインと同じように、以降の「赤缶カレー粉」の味は、現在に至るまで全くと言っていいほど変わっていない。と書くのは簡単だが、実際にはこれはなかなか難しいことだ。そのほとんどを輸入に頼るスパイスは、収穫される地域、時期、天候などによって影響を受ける。風味や辛さに微妙な違いがあるので、同じ製法で作っても同じ味になるとは限らない。
「赤缶カレー粉」だけに限らないが、スパイスの選定はエスビー食品にとって最も大きな仕事の一つになっている。まず、スパイスのニュークロップ(新摘みしたもの)をいち早く世界中から入手し、最新の分析装置に加え、味覚のプロフェッショナルが、その年使用するものを決定する。機械だけでは完璧ではなく、最後は人間の味覚や嗅覚に頼るところがカレーやスパイスの奥深さ。エスビー食品には、こうした味覚のプロが大勢そろっているという。

「赤缶カレー粉」を使ったメニュー例。「カレー粉で作る! 野菜たっぷりのカレー鍋」。

「ブリのカレームニエル」。魚料理への応用は主婦の間で人気が高い。

「カレーツナマヨ巻き」。「赤缶カレー粉」はツナマヨにミックスする。
日本のカレー市場は、「赤缶カレー粉」や固形カレーが登場した1950年前後から順調に拡大し続けてきた。60年代の終わり頃にはレトルトカレーが登場。市場は更に拡大し、今では粉・固形・レトルトという3種類のカレーが日本中の家庭に浸透している。80年代以降の推移は落ち着いているが、それでも現在の家庭用カレーの市場は小売りベースで約900億円と言われている。
ちなみにカレー粉の市場規模は22億円(2009年)。大きくはないが、この数字には別の意味で注目すべき理由がある。この5年間で14.6%も伸びているのだ。そのうちの約8割を占めているのがエスビー食品の「赤缶カレー粉」。実際、「赤缶カレー粉」は2009年に過去最高の売上げを記録している。
カレー市場の中でも、カレー粉はほぼ成熟したと思われていた。業務用途が多いので、昨今の経済状況を考えれば減っていてもおかしくはない。これほど伸びている理由はどこにあるのだろう?
背景に、ここ数年の内食回帰があるのは間違いない。しかも近年は消費者の嗜好が、利便性を重視した簡単な料理から、手がかかっても美味しいものを食べたいという方向に変わってきた。カレー粉なら、カレー以外のメニューにも簡単に応用が利く。
レシピサイト「クックパッド」で「カレー粉」を検索すると、1万6000を越えるレシピが上がってくる。炒飯などの炒め物、タンドリーチキンやかき揚げなどの揚げ物、更にはスープカレーなど、ありとあらゆる料理でカレー粉が使われていることがよく分かる。調味料としての使い道は昔からあったが、近年は特にその傾向が目立っているようだ。
一般家庭の食卓モニタリングデータをみると、面白いことが分かる。ここ1年ほどのデータではカレー粉の使われ方が大きく変化しており、カレー粉が味噌・醤油と並ぶ調味料の一つとして使用されるケースが大幅に増えている事が明らかになった。最近は魚料理にもよく使われている。中でも「かじ きまぐろ」の使用率が高く、かじきまぐろをソテーやムニエルにし、「赤缶カレー粉」でカレー風味に調理したメニューが人気だ。フライパンひとつで簡単にでき、ボリュームも充分。骨がないので子供のお弁当にも最適だ。
エスビー食品も、現在展開しているスパイス&ハーブプロモーションの重点訴求商品に「赤缶カレー粉」をアピールしている。頒布用のレシピブックでは、「野菜たっぷりのカレー鍋」「ブリのカレームニエル」「カレーツナマヨ巻き」など、食欲をそそるメニューを細かく紹介。もちろん、同社のホームページ上でもレシピ検索できるようになっている。
今やどの家庭にも欠かせない基本調味料となった「赤缶カレー粉」。創業者・山崎峯次郎が創り出したオリジナルの味と確かな品質を60年にわたって守り抜き、再び注目を集めつつある。カレー作りから調味料へと主な用途は変わったが、復興・成長への期待が込められた赤い缶の存在感は、豊かになった21世紀の食卓においても全く変わっていない。
圧倒的なブランド力を持つ「赤缶カレー粉」だが、エスビー食品には他にもカレー粉関連の商品がある。1999年に発売した「ナチュラルピュアカレーパウダー」と「ナチュラルハーブカレーパウダー」は、同社が誇るカレー粉のノウハウを注ぎ込んだ逸品。世界各地から厳選した原料を丁寧に調合・焙煎・熟成し、神秘的な味わいに仕上げている。カレー関連調味料としては、「カレーパウダー」「ガラムマサラ」「料理用カレー」の3種類をラインアップ。顆粒タイプなので、様々なメニューに幅広く使える。2003年登場の「赤缶カレーミックス」は、新製法で作り上げた新感覚の即席カレールウ。エスビー食品80周年の年に発売されたこの商品は、「赤缶カレー粉」のイメージをデザインに取り入れている。フレークタイプのルウをパウダーでコーティングしており、固まりにくいのが特徴だ。

「ナチュラルピュアカレーパウダー」(左)と「ナチュラルハーブカレーパウダー」。各415円。