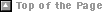三島食品の創業者・三島哲男。「ゆかり」の生みの親でもある。

梅干しなどの色づけに使われている赤しそ。ふりかけにするアイデアは三島食品のオリジナルだ。

漬け込み工程。アクを抜いた後の赤しそを梅酢に漬けて熟成させる。
炊き立ての白い御飯の上に、赤紫色のふりかけをパラパラ。湯気の中から立ち上がる甘酸っぱい香りが、たまらなく食欲をそそる。ふりかけるだけでなく、御飯に混ぜ込んでも美味しい。子供の頃、お弁当の中によく小さな赤紫色のおむすびが入っていた。そう言えば、学校給食のメニューにもあのふりかけがあったなあ……。
ふりかけの種類は数多いが、赤しそのふりかけといえば、誰もがまず「ゆかり」の名を挙げるだろう。広島の三島食品株式会社が「ゆかり」を発売したのは、今から40年前の1970(昭和45)年。ブレンドタイプのふりかけとしては丸美屋の「のりたま」が有名だが、単一原料のふりかけのベストセラーは、間違いなくこの「ゆかり」。赤しそふりかけのカテゴリーシェアは、なんと9割近くにもなるという。
三島食品の創業者・三島哲男が広島市に三島商店を興したのは、1949(昭和24)年のこと。当初はトウガラシ粉や桜でんぶを製造していたが、当時人気を集めていたふりかけに注目。魚粉末原料のふりかけ「弁当の友」を製造し、一斗缶に入れて業者向けに販売した。これが売れて、個人商店だった三島食品は会社組織に改組。後に発売した鰹節ベースのブレンドふりかけ「瀬戸風味」と「かつおみりん」もヒットし、50年代から60年代にかけて三島食品は大きな成長を遂げる。
当時のふりかけ原料の大半は、魚粉末や海苔などの海産物。赤しそ原料の「ゆかり」は珍しい存在だったに違いない。いったいどんな発想から誕生したのだろう?
「こちらでは赤しそを細かく刻んだ漬物がよく売れています。うちでも作れませんか?」──60年代後半、名古屋の営業所から三島食品の本社に宛てて、毎日のようにこんな営業日報が上がってきた。
日報を書いていたのは、販売に熱心な一人の営業マン。三島食品はふりかけ一筋にやってきた会社だから、漬物の商売を始める可能性は低い。それでも彼はあきらめず、赤しその漬物を要望する声を本社に送り続けた。はじめの頃は「うちは漬物屋じゃない」と聞く耳をもたなかった三島も、あまりのしつこさに根負けし「漬物は駄目だが乾かして売るのならいいだろう」と、新商品の開発にゴーサインを出す。ここから、赤しそふりかけの研究が始まった。
だが、赤しそをふりかけの原料にするのは簡単ではなかった。作り方の基本は今も変わらない。まず、収穫した赤しそを塩もみし、余分な水分とアクを抜く。それに梅酢と食塩を加え、貯蔵タンクで1〜2ヶ月熟成させる。ここまでが産地の工場で行われる一次加工。次は本社の工場で味付けした原料を乾燥させるのだが、ここが難関だった。温度設定が低すぎると充分に乾燥せず、高すぎると焦げ付いてしまう。程良い香りを残しながら鮮やかな赤紫色になる適温を見つけるまでに、数ヶ月間かかった。
三島食品は完成した新商品を「ゆかり」と名付け、大袋に入れた業務用ふりかけとして販売した。一般消費者向けにも透明の袋に詰めた簡易包装で販売したが、思ったほどには売れなかった。長く店頭に置いておくと、白っぽく変色してますます売れなくなる。営業マンは毎日のように商品を入れ替えたが、返品が止むことはなかった。
赤しその漬物に負けない意気込みで作った「ゆかり」だったが、当初はなかなか商機を見出せなかったのだ。

最初のパッケージ。外部の著名なデザイナーが手掛けたもので、基本デザインは今も変わっていない。

現行商品のパッケージ。初期パッケージで「しそめし用」となっていた表記は「しそごはん用」に変わった。


現行パッケージの上と横に付いている点字表記。「ゆかり」と記されている。
ここで、商品名の「ゆかり」について触れておこう。古今和歌集の中に、「紫の ひともとゆゑに 武蔵野の 草はみながら あはれとぞ見る」(読み人知らず)という歌がある。意味は「むらさき草が1本咲いているという縁(=ゆかり)だけで、武蔵野の草花全てが愛おしく身近に感じられる」というもの。むらさき草が、縁あるものの象徴として語られているのだ。平安時代の昔から紫は高貴な色とされ、貴族の間では、紫色を染め出すためにむらさき草が珍重されていたという。
三島食品が作った赤しそのふりかけは、鮮やかな赤紫色をしている。「ゆかり」はこれ以外に考えられないほど的を射た商品名だった。
ところが、ここで困ったことが発覚した。「ゆかり」という商品名が、1960(昭和35)年に商標登録されていたのだ。登録していたのは愛知県の株式会社中埜酢店(現在のミツカングループ)。
幸いにも三島食品は同社とお酢の取引があったため、先方の厚意によって「ゆかり」の名を使うことができた。商標としての「ゆかり」は1999(平成11)年にミツカングループから三島食品へ譲渡され、名実共に三島食品のものとなる。
「ゆかり」のアイデンティティーとなっている紫色は、パッケージにも効果的に使われている。正規のデザイン包装が誕生したのは、発売から5年後の1975(昭和50)年。紫色の全体イメージとストライプパターンが採用されている点は今と同じだが、色調がやや薄く、商品名のロゴタイプと会社のシンボルマークが今とは違っている。
85(昭和60)年には最初のデザイン変更を実施。白抜き文字になったロゴタイプは現行商品に近くなり、パッケージの紫色も深みのあるものに変わった。96(平成8)年に行った2度目のリニューアルでは、ストライプのパターンを変更すると共に、新しくなった会社のシンボルマークを採用。同時にチャック式のパッケージを採り入れ、開封後も安心して使えるようにした。現行商品はこのパッケージデザインを踏襲している。
「ゆかり」のパッケージで特徴的なのは、目の不自由な人のために点字を採用していることだろう。2002(平成14)年に袋の上部へ点字(読みは「ゆかり」)を表示したところ、利用者から多くの支持を集めた。一方で、一度開封してしまうと点字の部分は捨てられてしまうため、商品が何であるかが分からなくなってしまうという欠点もあった。三島食品はこの3年後、袋の横の部分にも点字を表示して更なる利便性の向上を図った。
ビール缶のプルトップ部分や調味料のキャップに点字を表示するケースはあるが、食品の袋包装に表示しているのは珍しい。「ゆかり」が三島食品にとって重要な商品であると共に、多くの消費者に愛されている証と言えるだろう。
さて、販売当時は売れ行きが芳しくなかった「ゆかり」だが、その後は意外なところから大きく販売量を伸ばしていくことになる。道を開いたのは、学校給食への採用だった。
小学生の頃、給食のメニューに一食タイプの袋入り「ゆかり」が付いていたり、「ゆかり」を混ぜ込んだ御飯が出た記憶を持つ読者も多いのではないだろうか。子供にとっては、白飯よりも味や香りがついた御飯の方が食べやすい。ゆかり御飯は今も各地の給食メニューとして好評を得ているという。
「ゆかり」は事業所や病院など、学校以外の施設にも販路を拡大していった。

赤しその収穫風景。香りと色を重視し、若い新葉しか使用しない。

赤しそ畑の風景。

広島県北広島町に開設した自社農園。豊香はここで栽培されている。
食品の中でも、ふりかけは極めてシンプルな商品だ。単一原料の「ゆかり」はその代表と言っていい。それだけに、原料の善し悪しが商品の品質を大きく左右することになる。三島食品は、販売時から赤しその品質と収穫方法にこだわってきた。
収穫にあたっては、赤しその葉で香りと色が良いのは株上部の若い新葉だけなので、成長が進んで固くなった下部の葉は使用しない。太くて固い茎が原料に混入すると食感が悪くなるので、刈り取り時はできるだけ刈り取り機の刃を浅くいれ、葉だけをうまくカットする。
品質へのこだわりも見逃せない。販売量が増えるにつれ、「ゆかり」には予期せぬ課題が持ち上がってきた。良質な赤しその確保が難しくなってきたのだ。中部や四国の農家と一緒に高品質な赤しその栽培に取り組んだが、爽やかな香りを持つ赤しそはなかなか育たない。赤しその香りのもとはペリラアルデヒドという成分だが、長年にわたって自然交配が進んだ結果、どうしても刺激臭や不快臭のある赤しそが混じってしまうのだ。
「こうなったら自分たちで新しい品種を作るしかない!」。この考えを実行に移したのは、現社長の三島豊だった。食品メーカーが原料そのものを開発するという大胆な挑戦は、1988(昭和63)年にスタート。目標は、爽やかな香りを生み出すペリラアルデヒドと、鮮やかな赤紫色の色素であるシソニンを豊富に含んだ品種を作り出し、その成分を固定化すること。同時に、従来品種並みの収穫量も確保しなければならない。品質は良くても収穫量が少ないと、農家に負担をかけてしまうからだ。開発担当者は品質の良い株を見つけては種を採取し、翌年その種を蒔くという、地道な研究に没頭した。
残された株の品質が上がってくると、担当者の心配事も増えてくる。赤しその花が咲く10月には望まない交配がなされないよう、細心の注意が求められた。台風シーズンには種が吹き飛ばされないよう、担当者はビニールハウスを押さえる綱を引き続けた。露地栽培していた畑では、せっかく残した良質な種を失ったこともあるという。
こうした努力が実を結び、1999(平成11)年、香りと色を固定化した新品種がついに完成した。翌年、農水省に「豊香」の名で品種登録を申請。2004(平成16)年には無事に新品種の認可が下りた。
現在、三島食品は「ゆかり」の生産に年間約2400トンの赤しそを使っている。この数字は国内生産量の約半分に相当する。産地は国内(九州や南紀地方)と海外(主に中国)がほぼ半分ずつ。ちなみに中国生産の赤しそは、農薬の使用量が少ないこともあり、品質は国産に負けないほど高いという。
同社は2001(平成13)年から、中国の遼寧省で豊香の種の大量栽培を開始。また、2008年からは更なる安心安全を求めて、自社農園での直接栽培をスタートさせた。国内の自社農園から出荷される量は年間約80トンとまだ少ないが、三島食品は種だけでなく、新品種の開発に伴って蓄えられた栽培技術や加工法を契約農家に指導し、産地と協同して良質な赤しその生産に取り組んでいる。豊香はその後も改良が進み、今は第3世代の品種開発が進んでいるところだ。

「ゆかり 梅入り」。22g、130円。

「ゆかりシリーズ・ミニ」。2g×20袋、255円

「ソフトふりかけ ゆかり 昆布入り」。30g、200円。

「おウチでごはん」の提案メニュー「なすと赤しそのスパゲッティー」。
現在の「ゆかり」シリーズは、定番の「ゆかり」を中心に、「ゆかり 梅入り」「ゆかり 胡麻入り」「ゆかり かつお入り」「ゆかり しょうが入り」からなる5種類のスタンダードタイプをラインアップ。これらに加え、薄塩味に仕上げた「ソフトふりかけ ゆかり」「ソフトふりかけ ゆかり梅入り」「ソフトふりかけ ゆかり昆布入り」の3種類で構成されている。パッケージは容量の異なる袋タイプが主流だが、1回使い切りタイプを詰め合わせた「ゆかりシリーズ・ミニ」や、片手で簡単に開閉できる瓶入りタイプもある。
赤しそベースのふりかけでこんなに多くの商品をバリエーション展開しているのは、もちろん三島食品だけだ。
ここ数年の御飯食回帰と内食増加が大きく寄与し、ふりかけ市場は2009(平成21)年まで、4年連続で市場規模を拡大してきた。三島食品はリーマンショックがあった08(平成20)年、他社に先駆けて「ゆかり」の値上げを実施したため売上げを落としたが、近年は大きく持ち直しているという。
その大きな要因は、消費者に対する新たな食シーンの提供だ。「ゆかり」を御飯の上にかけたり、混ぜ御飯にするのは、昔からある最もオーソドックスな食べ方。ふりかけに固定観念を持っていない若い主婦たちは、もっと自由な発想で「ゆかり」を使ったレシピを考案している。試しに日本最大のレシピサイト「クックパッド」で「ゆかり」を検索してみたところ、約2000ものレシピがピックアップされた(2011年1月時点)。パスタやサラダへの応用はもちろん、ケーキやパンの調理にも使われていることに驚く。今の消費者は周りに言われるまでもなく、「ゆかり」を調味料的に使っているのだろう。
三島食品も、自社が運営するサイト「おウチでごはん」で、ふりかけのレシピを多数紹介している。その数、定番の「ゆかり」だけでも約70種類(2011年1月時点)。ふりかけを販売しているメーカーの中でも群を抜いて多い。広報担当者によると、同社は業務用商品を手掛けていることから、専任のプランナーが常時レシピを開発して顧客に提案しているとのこと。社内に、プロが作った人気レシピが豊富にストックされているのだ。
時代のニーズを反映しながら度々内容の見直しが行われている「ゆかり」だが、その味は約40年にわたってほとんど変わっていない。紫とストライプのパッケージも、基本的なデザインは初期のイメージを今も踏襲している。誕生したときからほとんど変わっていない商品と、自分たちのアイデアで使い方に工夫を凝らす賢い消費者。二つの要素がそろったとき、商品は単なる消費財の枠を越え、文化的な意味を帯びてくる。これこそ、ロングセラー商品の王道ではないだろうか。
2月1日、「ゆかり」シリーズに新しい仲間が加わる。2年ぶりに登場する新商品は「ゆかり 青菜入り」。菜の花のシーズンに合わせて発売する、清々しい味わいのふりかけだ。「ゆかり」が持つ赤しその香りはそのままに、青菜の風味と色合いをプラス。目に鮮やかなピンクと緑の彩りが、春先のイメージにぴったり合う。近年のお弁当ブームにあって、ふりかけを使ったデコレーションはちょっとしたブームになっている。若い女性やお母さんたちが、御飯を好きな色合いにアレンジして楽しんでいるのだ。「ゆかり 青菜入り」は、この点でも注目を集めるかもしれない。

「ゆかり 青菜入り」。20g、110円。