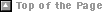1955年 発売
カンロ
世代を超えて伝わる懐かしさ
日本独自のしょうゆ味キャンディ

創業者の宮本政一。実家は製菓業を営んでいたが、19歳で独立した。

カンロ飴以前の商品群。シンボルマークは象を星で囲んだ「星象」だった。
昭和20〜30年代に生まれた子供にとって、飴(あめ)やキャンディはおやつの筆頭候補だった。チョコレートやキャラメルもあったけれど、それらはちょっとぜいたくな存在。飴はもっと身近で、親子ともども気軽に楽しめるおやつだった。
飴のロングセラーと言えば、黄金色の丸い飴玉、「カンロ飴」を外すわけにはいかない。製造するのは山口県光市にて創業した「カンロ株式会社」。発売は1955(昭和30)年だから、今年58年目を迎える。
創業者の宮本政一が現在の光市で「宮本製菓所」を開業したのは1912(大正元)年、若干19歳の時だった。手掛けたのは飴玉と焼き菓子の製造販売。「宮本の生玉(いくたま)」と呼ばれた和風飴が人気を博し、太平洋戦争後は「かりん糖」と「梅鉢(おこしを使った飴)」「ドロップス」などで、県内有数の菓子会社へと成長した。50(昭和25)年には株式会社へと組織変更している。
だが戦後しばらくすると、砂糖価格の上昇と過当競争が業界を直撃した。カンロは法人化4年目に、最高の売上高と最低の利益を計上。会社は苦境に陥った。
この苦境から脱するにはどうしたらいいのか? 飴で成功した政一の頭にあったのは、「日本には日本人だけが好む味のふるさとがある」という発想だった。日本人であれば、誰もが飛び付くような風味を持った飴。それが実現できれば、無理な競争から脱して市場を独占できると考えたのだ。
日本人が好む味わいで、誰もが思い浮かべるのはしょうゆ味。それと、適度な塩分。当時習慣的に使われていた化学調味料も検討材料とされた。これらを飴と混合すれば、従来にない画期的な新商品ができるはず。開発目標が明確になった。 実は、この発想自体は以前から菓子業界にあったという。だが、どのメーカーも具体化するまでには至らなかった。飴は製造過程で酸や塩分を添加すると、べとつきが増して保存性が著しく悪化する。酸については加工法が見つかっていたが、塩分によるべとつきは未解決のまま。しょうゆについては手つかずのままだった。この課題を克服することが、新商品開発の大きなポイントだった。

「カンロ玉」と「カンロ飴」の包装紙。“宮本の”というコピーが付いている。

初期のツイスト包装機。手作業とは比較にならないスピードを実現した。
飴は基本的に砂糖、水飴、添加物から作るシンプルなもの。だからこそ原料の種類や配合によって、味が大きく変わってくる。カンロには膨大な製造ノウハウがあったが、新商品の開発は想像以上に困難だった。しょうゆ味をメインにした新しい飴なので、従来の製造法はほとんど役に立たない。開発陣は目標をはっきり見据えていたが、そこに至る道筋は完全に手探り状態だった。
最初の試作品は、タバコのヤニを溶かしたような色の濃さ。なめると焦げているような味がした。しかも一晩置くと煮詰まってしまい、缶の中から取り出すこともままならない始末。塩分としょうゆの量や配合を変えてみたものの、煮詰めと焦げ臭さの問題はなかなか解決できなかった。ここで諦めたら、他の会社と同じ結果だったろう。だがカンロは数年にわたり、根気強く試作を繰り返した。
水飴と砂糖の比率を変える。水飴に含まれる各成分の組み合わせを見直す。さらには真空煮詰釜の火力と時間の関係を調べ上げる。細かな実験を繰り返した結果、ついに煮詰めの問題を解決することができた。
だがもう一つの問題である焦げ臭さに関しては、解決の糸口さえつかめない。当時の常識では、どんなしょうゆでも高温の釜の中に入れれば、即座に焦げ付くのが当たり前だったのだ。悩んだカンロが出した結論は、醸造メーカーに焦げ付かないしょうゆを一から開発してもらうこと。地元醸造メーカーとの共同研究の結果、晴れて念願の焦げ付かないしょうゆを開発することができた。
苦心の末に生み出した飴は「カンロ玉」と名付けられ、1954(昭和29)年の春、山口県内で発売された。カンロ=甘露とは「天から降る甘い露」の意味。カタカナで表現したのは、幅広い消費者に認知してもらうためだった。
当時のお菓子は量り売り。「カンロ玉」の大きさは1粒8gと標準的な大きさだったが、1個2円で販売された。ほとんどの飴が1個1円の時代だったから、問屋から「売れるはずがない」と冷遇されることもあったという。だが、「カンロ玉」は最初から爆発的に売れた。しょうゆが醸し出すコクのある味わいが、子供だけでなく大人をもひき付けたのだ。
発売当時は無包装だったが、まもなく印刷したセロハン紙によるひねり個装を導入。1955(昭和30)年には手作業だった包装を機械化し、生産効率を劇的に向上させた。同時に商品名を「カンロ飴」に変更。販路も山口県から中国・四国・九州地方へと拡大し、57(昭和32)年には首都圏の卸売店との取引も始まった。
発売から3年も経たずに全国的なヒット商品となった「カンロ飴」。関係者は口をそろえてこう言った。「カンロ飴は業界の奇跡だ」と。

1958年頃。店頭用の大袋に使われていたデザイン。

1963年頃のパッケージ。現行パッケージに近い印象。

1973年頃のパッケージ。「カンロ飴」が最も売れていた頃。

40周年(1995年)を期に採用されたデザイン。

現行商品のパッケージ。50周年(2005年)時から採用。
味以外にも、「カンロ飴」にはひときわ目立つ大きな特徴がある。50年以上にわたって使用されている欧文の“Kanro”ロゴと、独特の赤オレンジ色に印刷されたパッケージだ。販売された1955(昭和30)年頃はまだ使われていなかったが、その3年後と思われる800g入りの大袋には、既にこのロゴが印刷されていた。
デザインしたのは、当時活躍していた有名デザイナー。和風味をセールスポイントにした飴であるにも関わらず、それを逆手にとるように欧文のロゴタイプを使った点が、なんとも大胆で注目に値する。
この“Kanro”ロゴは1963(昭和38)年頃に新しいデザインに変更され、05(平成17)年、「カンロ飴」が発売50周年を迎える時まで継続使用された。おなじみの赤オレンジパッケージがいつ頃登場したのか定かではないが、おそらくロゴが新デザインに変わったこの頃だと思われる。
やや赤みがかったオレンジ色は、「カンロ飴」以外のお菓子ではあまり使われていない。商品の黄金色を連想させる、優れた色使いと言えるだろう。
新デザインの欧文ロゴと赤オレンジ色のパッケージは、その後数度、デザイン変更されている。1973(昭和48)年頃には区切りのラインが直線から曲線に変更され、90(平成2)年頃にはロゴと区切りラインにゴールドが加色された。当時はバブル時代が終わりを迎えるころ。パッケージが時代の空気を反映している点も興味深い。
発売40周年を期に、95(平成7)年頃には“白抜きロゴ”と“ゴールド&ホワイト”の帯を使用。この2点は現行商品のアイコンにもなっている。
そして2005(平成17)年、パッケージは現行のデザインへとチェンジされた。赤オレンジ色のパッケージに変わりはないが、長らく使ってきた欧文の“Kanro”ロゴをついに変更。ややレトロチックだったデザインは、モダンなイメージに刷新された。
このタイミングに合わせ、柔らかく温かみのあるパッケージデザインを採用した50周年記念の限定商品も登場している。

1965年頃に販売されていたキャンディ。ロゴは「カンロ飴」と同じだが、成分が異なる別種の商品。

50周年記念で発売された限定商品。パッケージデザインはセキユリヲ。
飴菓子(キャンディ類、キャラメル、ドロップ、グミ、ゼリー、マシュマロ等)の市場規模は、ここ数年2500億円ほどで推移している。若年層の嗜好(しこう)を見るとグミやゼリーなどのソフトキャンディが売れているような気がするが、販売の主流は依然としてハードキャンディ。バリエーション商品を持たない単一商品の「カンロ飴」は、その中でも独特のポジションにある。
のど飴以外のスタンダードなハードキャンディで、「カンロ飴」ほどの知名度を持つ商品は思いのほか少ない。もともと飴は各地方特有の生産物(地アメと呼ばれる)だったこともあり、全国的な商品に育てるのが難しい商品なのだ。戦後の早い時期にヒット商品を開発し、販路を全国に拡大できたカンロは、業界でも珍しい例と言えるだろう。
「カンロ飴」が生産量のピークを迎えたのは、1970年代初頭から半ばにかけて。最盛期には年中無休で工場をフル稼働させていたという。今はさすがにその頃の勢いはないが、8年前に迎えた50周年をきっかけに、徐々に市場を回復しつつある。
功を奏したのは、新聞広告や消費者プレゼントなどのキャンペーン。それまでは社内でも消費者が固定化したと思われていたので、「カンロ飴」は積極的な販促がなされていなかった。ところが改めて告知してみると、昔は買っていたものの、長らく「カンロ飴」から離れていた人々が反応した。
子供の頃や若かった頃になめていた「カンロ飴」が、今も変わらず売られている。再び口にしてみると、昔と全く変わらない味がする。こみ上げる懐かしさ。うれしくなって、子供や孫にも勧めることに…。
消費者に“気付き”を与えることで、「カンロ飴」は眠っていた需要を掘り起こすことに成功した。世代を受け継いで愛されることは、ロングセラー商品にとって欠かせない要件の一つ。それができるのは、「カンロ飴」が日本人の“味のふるさと”をしっかり伝えているからにほかならない。