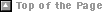1945年 発売
オリエンタル
憧れの味を庶民の味に!
国内最長寿の即席カレー

オリエンタル創業者の星野益一郎。傑出したアイデアマンだった。

1951年の「即席カレー」。発売当時はキャラメル包装されていた。

1960年の「即席カレー」。現行商品とほぼ同じ形とデザインになった。

工場で「即席カレー」を製造しているところ。写真は昭和30年代。まだ手作業でカレー粉を炒めていた。
家庭で食べるカレーというと、誰もが固形ルウの商品かレトルトカレーを連想するだろう。固形ルウのカレーでも、作り方は至って簡単。野菜を炒めて鍋に入れ、水を加えて沸騰したらルウを入れて煮込むだけ。
でも、そうなったのは今から70年ほど前の話。とある商品が世に出るまで、カレーは庶民が家庭で手軽に作れる料理ではなかった。
そのとある商品とは、日本初の本格的なインスタントカレーとして発売されたオリエンタル「即席カレー」。作ったのは、戦前から輸入食品を扱っていた名古屋の商売人・星野益一郎だった。まだ甘い食べ物が少なかったこの時代に、益一郎はおからのような材料に砂糖と食紅を加えて作った「代用あんこ」を考案。これが大いに売れ、その資金を元手に大量の香辛料を購入し、日本初のインスタントカレーの開発に乗り出した。
カレーは明治の初めにイギリスから日本に伝わった。明治大正時代は高級レストランだけで供されるハイカラ料理。昭和に入ると普通の食堂で出されることも多くなったが、値段は高く、庶民には憧れのメニューだったという。
カレー粉は販売されていたから家庭で作ることはできたが、小麦粉と脂を炒めてルウを作るところから始めなければならない。肉と野菜のスープも必要。主婦にとっては、手間暇がかかる面倒な料理だった。
益一郎はこの手間を省くため、カレー粉に牛脂やバターで炒めた小麦粉を加え、調味料も入った粉末状のカレールウを考案。1945(昭和20)年11月、個人商店のオリエンタルを創業し、日本初となる本格的な「即席カレー」を世に送り出した。
興味深いのは、その販売手法。当時の人々にはカレーに対する憧れはあっても、それが家庭で食べられるという発想はほとんどない。その思い込みを払拭してカレーを認知させるには、何よりもインパクトが必要だ。益一郎はちんどん屋に先導させたリヤカーに商品を積み込み、自らも頭にターバンを巻いてインド人に扮装。アッと驚くようなやり方で自ら商品を売り歩いた。
「即席カレー」の価格は5皿分で35円。あんパン1個が5円だったから、今なら800円くらいの感覚だろうか。決して安くはなかったが、愛知県内では飛ぶように売れた。人々が食べ物に飢えていたのは確かだが、それ以上に「自分の家でカレーを簡単に作れる」ことが、大きな衝撃だったに違いない。

トラックの後部を改造した宣伝カーと芸人たち。数台が全国を同時に走り回っていた。

販促に使われたスプーンと風船。スプーンは3,000万本ほど配布されたという。

ラジオ番組の公開録音で「オリエンタルカレーの唄」を歌うトミ藤山。

南利明のテレビCM。名古屋弁の名セリフが一世を風靡した。
県内の売れ行きに力を得た益一郎は、「即席カレー」の販路拡大を決意。問屋に卸せば販売ルートを確保することはできるが、益一郎はそれを良しとしなかった。リヤカーで売っていた時と同じように、自社の力で商品を顧客に届けることを選んだのだ。
宣伝カーを使った全国行脚の販促活動を1953(昭和28)年から開始。駅前や団地など人の集まるところに車を停め、前代未聞のユニークな街頭宣伝を行った。
大型トラックを改造した宣伝カーの後部には、ステージが設えてある。そこで、歌手やマジシャン、腹話術師などの芸人がショーを行うのだ。娯楽の少ない時代だから、人はすぐに集まる。ショーが終わったところで「即席カレー」の作り方を教え、その場で販売するという段取りだった。注目すべきは、オリエンタルがショーに出ていた芸人を正社員として雇っていたこと。芸人は最盛期で約40人、宣伝カーは10台ほどが稼働していたという。
宣伝にあたり、オリエンタルは販促グッズとして風船やスプーンを配った。オリジナルキャラクターの「オリエンタル坊や」をアレンジしたスプーンは、特に人気があったという。「即席カレー」販売時はまだ洋食に馴染みがなく、スプーンがある家庭が少なかったのだ。
芸人によるショーで人を集め、グッズで購入意欲を高めるこの手法は大当たりした。多い時は1ヵ所で1,000個ほども商品が売れたという。こうして、「即席カレー」の名は全国に広がっていった。
一方で、益一郎はマスメディアを使った販促活動にも力を注いだ。1954(昭和29)年には、ラジオ宣伝用にCMソング「オリエンタルカレーの唄」を制作してレコード化。地元出身の若手女性歌手・トミ藤山(当時の芸名は山路智子)が歌う「なつかし〜い、なつかし〜い、あのリズム♪」というメロディーは宣伝カーからも流され、あっという間に大ヒット曲になった。
数年後にはテレビCMも制作。「オリエンタルカレーの唄」は日本初の本格的CMソングとして、当時の人々の記憶に残っている。
テレビCMでは、名古屋出身の俳優・南利明を起用した「スナックカレー」の宣伝も話題になった。南がまくし立てるアクの強い名古屋弁。「ハヤシもあるでよ」という締めのセリフは流行語にもなった。
また、オリエンタルはテレビの買い物ゲーム番組「がっちり買いまショウ」の初期冠スポンサーにもなっていた。漫才コンビの夢路いとし・喜味こいしの軽妙な司会ぶりを覚えている人も多いことだろう。

発売当時の「マースカレー」。当時の価格は70円。パッケージはほとんど変わっていない。

1999(平成11)年発売の「マースカレーゴールド 中辛」。粉末にチャツネを練り込んでいる。

2000(平成12)年には「マースカレー レトルト版」を発売。まろやかなコクが魅力。

悲運のヒット商品「スナックカレー」。辛口と甘口、姉妹商品の「クッキングハヤシ」があった。
1950年代に「即席カレー」で世の中を席巻したオリエンタルだったが、60年代に入ると競合他社の参入と食の多様化が進み、競争力のある新製品の開発が急務となった。それまでのカレー業界は辛いカレーと甘いハヤシの2つに棲み分けられていたが、この頃登場した甘口カレーが、ハヤシの市場を脅かすようになったのだ。
オリエンタルには「即席カレー」とほぼ同じ時期に発売した「即席ハヤシドビー」があったが、1962(昭和37)年、甘口カレーに対抗する「マースカレー」を発売した。果実に香辛料と砂糖、酢などを加えて煮詰めた調味料(マースチャツネ)を別添にし、好みに合わせてマイルドな味わいに変えられる画期的な新商品。独特の旨味と甘みが消費者に受け、これもまたヒット商品となった。その後「マースカレー」は品揃えも増え、現在も同社の主力商品であり続けている。
順風満帆のオリエンタルだったが、60年代後半以降は徐々にその勢いを失ってゆく。主な要因は、インスタントカレーに対する消費者ニーズの変化にあった。この頃から市場の中心は、より簡単に調理できる固形ルウの商品へとシフトしていく。競合他社はみな固形ルウへと移行したが、オリエンタルだけは頑なに粉末ルウにこだわり、固形ルウ商品を作らなかった。
固形ルウは製造上、高融点の油脂を使わざるを得ない。その油脂が健康上問題になったことがあったため、同社は敢えてそこに踏み込まなかったのだ。自然な食品づくりをポリシーにしていたからだが、この判断はその後のオリエンタルを予想外の苦境へと導くことになる。
販売が落ち込んでいた60年代後半、復活のヒントになる新商品が市場に現れた。大塚食品が発売した世界初のレトルト食品、「ボンカレー」が1968(昭和43)年に発売されたのだ。市場が変わることを確信したオリエンタルは、その翌年に自社初のレトルト商品「スナックカレー」を発売。先述した南利明のCM効果もあり、瞬く間にヒット商品となった。
だが、大塚食品との間で特許紛争が発生。レトルトの製造法は特許に当たらないという司法判断が下ったが、同時に各社が争ってレトルトカレーを販売したため、市場は一挙に加熱した。しかし当時のレトルト技術は未熟で、味は明らかに粉末や固形ルウの商品に劣っていた。それなのに種類ばかりが増えたため、消費者が離れてしまったのだ。
オリエンタルは、人気商品だった「スナックカレー」の販売を5年で停止。以降は軸足をレトルトに置きつつ、新たな方向性を模索することになる。

発売当時の「濃縮生乃カレー」。

「濃縮生乃カレー」。レトルトとインスタントカレールウの中間的な商品。

「男乃カレー」は、小麦粉を一切使っていない本格派インドカレー。
粉末ルウは味が良くても、利便性の点で固形ルウに劣る。レトルトは簡便だが、満足のいく味にすることが難しい。「スナックカレー」で苦汁をなめたオリエンタルが次に目指したのは、簡便性と美味しさを両立した新しいタイプのカレーだった。それが、1972年(昭和47)年に発売した「濃縮生乃カレー」。見た目はレトルトだが、中身は5皿分のカレーを濃縮してパッキングしたもの。水を加えて煮込むことで、深みのある味わいを醸し出している。
味にこだわったカレーづくりのノウハウは、その後のレトルトカレーにも生かされている。代表例が、1983(昭和58)年に発売した「男乃カレー」。カレー開発者の大きな目標である本格派インドカレーを目指した商品で、一流インド人シェフによる味と作り方を忠実に再現しているのが特徴。高圧殺菌釜で香辛料が変化するという課題があったが、香辛料の香味を油に移すことで解決した。発売当時は「辛過ぎる」という声もあったが、その後に激辛ブームが到来。未来を予見した商品となった。
現在のオリエンタルは、地産地消を念頭に置いた個性的なカレーづくりに力を入れている。例えば、工場のある稲沢市の特産、銀杏を使った「いなッピー銀杏カレー」や新潟県上越市・妙高市の米粉や酒を使った「レルヒさんカレー」、各地の銘柄牛肉を使った高級カレー等々。オリエンタルは、各地の商工会議所などが手掛けるご当地カレーの開発・製造を、年間10種類以上も請け負っているという。
こうした依頼が寄せられるのは、オリエンタルの開発力を見込んでのこと。商品の開発力はもちろん、会社の規模が大き過ぎないので小回りが利き、小ロットの生産にも対応できるのだ。
残念なことにオリエンタルは名古屋地区以外に大きな販路を持たないので、東京や大阪のスーパーで同社の商品を見つけるのは難しい。かつて全国区だった頃に「即席カレー」や「マースカレー」の味を覚えた中年層にとっては寂しい話だが、安易に大量生産の道を選ばなかったからこそ現在の個性豊かなオリエンタルになった、という見方もできる。
インスタントカレーのパイオニアとして、いくつもの道を切り開いてきたオリエンタル。商売上手ではないけれど、カレーに対する情熱はどのメーカーにも負けない。先進性があり、開発力も群を抜いている。ポリシーを守り続ける志の高さも、現代のメーカーとしては特筆すべき美点だろう。
販売数ではなく、商品の独自性と品質こそがロングセラー商品の大切な要件。全国区で売れる商品ではなくなった今も、昔からの熱心なファンがオリエンタルカレーをしっかり支えている。
愛知県発祥のオリエンタルは、“名古屋の味”にこだわったユニークな商品をいくつも販売している。カレーでは知る人ぞ知る名古屋名物、カレーうどん関連の商品が2種類。「名古屋カレーうどんの素(フレークタイプ)」は、独自の直火焼製法によって生み出した香ばしさが大きな特徴だ。「名古屋カレーうどん レトルト版」は、名古屋カレーうどんの特色であるとろみのあるスープと、辛口風味を手軽に楽しめる。三河赤鶏の挽肉をたっぷり使った「肉味噌カレー」と、愛知県産牛すじ肉の旨味を生かした「あいちの牛すじどてカレー」も要注目。カレー以外では「名古屋どてめし」と「あんかけスパゲッティーソース」を販売中だ。ちょっと不思議な名古屋の食文化。これを機会に試してみてはいかが?

「名古屋カレーうどん レトルト版」。三河赤鶏と油揚げ入り。