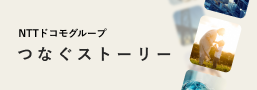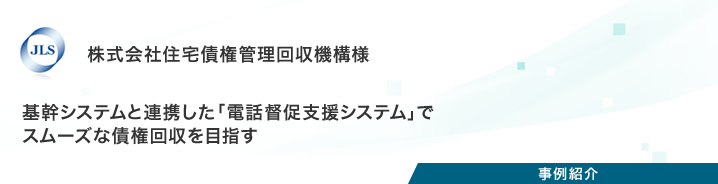
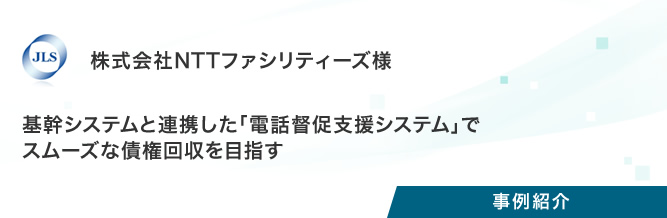
基幹システムと連携した「電話督促支援システム」でスムーズな債権回収を目指す
多くの人が利用している住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローン。利用者への貸出は銀行・信用金庫などが窓口になって行っているが、こうした金融機関から委託を受けて債権管理回収業務を行うのが、株式会社住宅債権管理回収機構様(以下、JLS)の主な業務の一つだ。このほどJLSでは、NTTコムウェアの「債権管理ソリューション」の一部である「電話督促支援システム」を導入した。導入の背景や効果についてJLSの水落氏、木下氏、阿佐美氏にお話を伺った。
NTTコムウェアの実績と経験、「やり切る力」に期待
JLSの業務内容について教えてください。

水落 一氏
株式会社住宅債権管理回収機構
常務取締役
当社は一般的に「サービサー」と呼ばれる債権回収会社です。事業面での特徴は、住宅ローンを中心に金融機関からの委託を受けて管理回収する業務が多いことです。
ローンの返済が滞った場合、延滞期間が比較的短い状態(初期延滞)から始まり、だんだん長期化していく段階(中長期延滞)を経て、最悪、返済できなくなる状態(期限の利益喪失)に至ります。初期延滞の大半は、うっかりしていて銀行口座が残高不足だったというようなことが原因で、件数も多くあります。長期延滞の場合は何らかの事情で返済できないもので、件数的には少ないです。
債務者(借り手)とのやり取りは、初期延滞債権については比較的マニュアル化しやすいのですが、中長期延滞となると債務者それぞれに事情が異なり、個別の対応が必要となります。このため、なるべく初期の段階で働きかけ、正常返済へと戻っていただくことが債権管理のカギになります。このため電話での督促を確実に効率よく行うことが、当社の業務においては大変重要なのです。

木下 隆治氏
株式会社住宅債権管理回収機構
業務推進部 コールセンター長

株式会社住宅債権管理回収機構
情報システム室 課長代理
業務システムの利用状況や課題についてはいかがでしょうか。
業務を行うために、システム利用は欠かせません。以前は、任意売却業務、競売業務といった回収措置ごとに分かれたいくつかのシステムを持ち、おのおののシステムで債務者の氏名や物件の所在地情報を保持していました。それぞれの業務には最適化していても、回収措置は債務者の状況変化に応じて変わることから、全体としては非効率でした。そこで、債務者の状況変化に応じた「シームレスな管理回収」を実現するため、データベースのマスタを共通化するなど、業務系システムを統合し、2011年5月に基幹業務システムを稼動させました。
ただその際、初期延滞の督促を行う「コールシステム」だけは、システムがそれなりに大規模になることもあって、同時に構築はせず、従来使用していたパッケージのシステムを継続利用することにしました。システムそのものに大きな問題はなかったのですが、やはり基幹業務システムと二重のシステムになってしまう点で不便がありました。
例えば、サービサーには、債務者との交渉記録などの帳簿を具備することが法律で義務付けられています。それを作成して出力する機能は従来のパッケージにもあったのですが、基幹業務システムとデータが連携していないため、データを二重に投入する必要がありました。また、法改正などで必要な帳票の内容が変わったりすると、基幹業務システムとパッケージシステムの両方をメンテナンスしなければなりませんでした。
そうした二重システムのデメリットを解消するために、2011年の秋ごろからコールシステム更改の検討に入りました。使い慣れたパッケージをカスタマイズすることも選択肢としてはありましたが、全体最適の実現を最優先し、基幹業務システムにコールシステムを追加する形で、スクラッチによる開発を選びました。
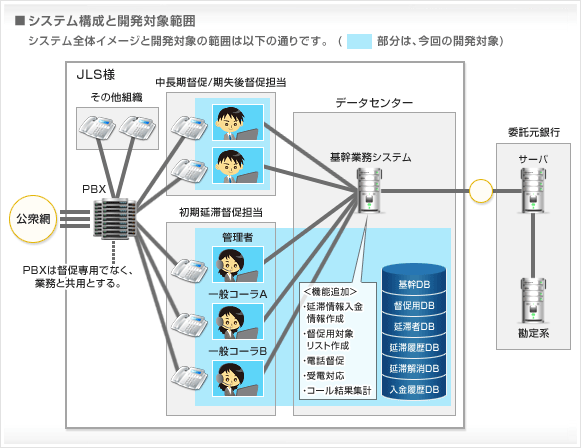
新しいコールシステムの検討ポイントは何だったのでしょうか。
初期延滞債権を対象とするコールシステムとして、NTTコムウェアの「電話督促支援システム」の提案を採用しました。決定に際して最も重視したのはプロジェクト体制です。NTTコムウェアは複数のサービサー向けにシステムを開発した実績がありましたし、NTTグループということでコールセンターのシステム開発実績も豊富。そうした経験やノウハウを持つ人材がいるという強みがありました。
一般的にシステム開発会社には優秀なSEはいても、金融用語・サービサー用語や、この業界のビジネスの流れをご存じない。ところがNTTコムウェアの担当者は基本的な知識があり、われわれが業務のことを説明しても飲み込みが早かったですね。
また、システム開発が大規模プロジェクトになると、ともすれば当初予算をオーバーしたり、予定のカットオーバー時期に間に合わないといった事態を招きがちです。しかし、NTTグループの大規模システムを支えてきたNTTコムウェアなら、「やり切る力」があるだろうという信頼感もありました。