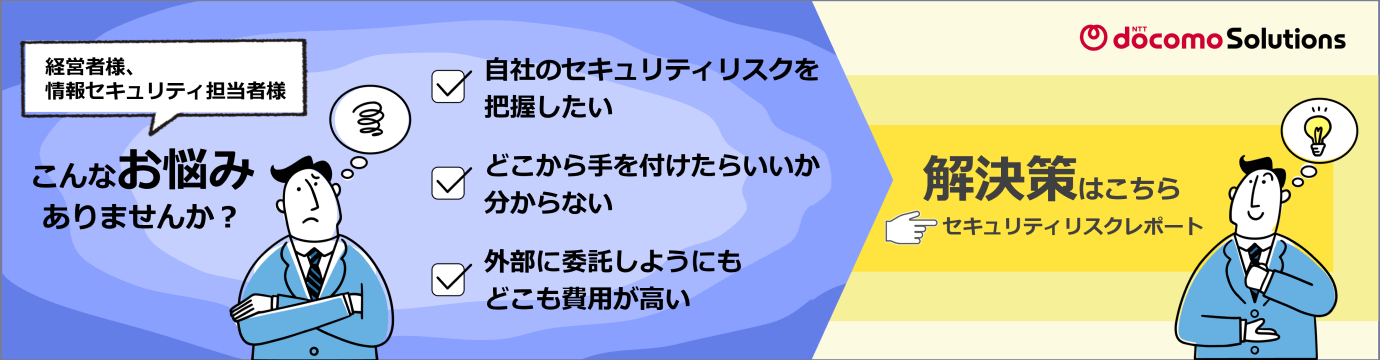昨今、サイバー攻撃の脅威はますます高まっています。
「標的になるのは大企業だけ」と考え、セキュリティ対策を後回しにしている中小企業も少なくありません。
しかし、警察庁の調査によると、2024年に発生したランサムウェア被害の約6割が中小企業を対象としており、大企業を上回る結果となりました。
今や企業規模に関係なく、あらゆる企業が攻撃の対象となる時代です。
自社を守るためには、今すぐセキュリティ対策を始めることが重要です。
(出典:「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(2024年発表))
本記事では、見えない脅威への備えと、すぐに実践できる対策をご紹介します。
01 大企業だけじゃない―中小企業がサイバー攻撃の主なターゲットに
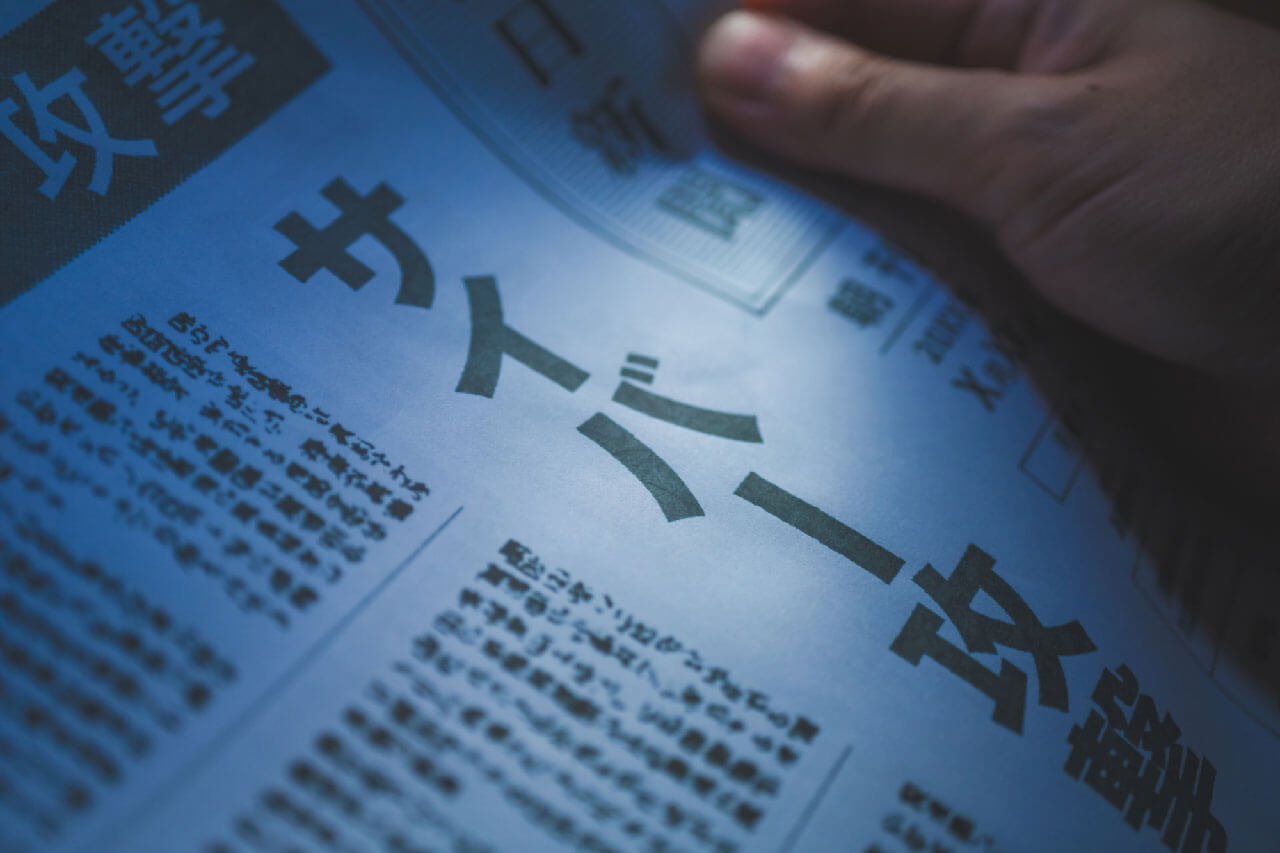
では、なぜ中小企業が狙われるのでしょうか?
その理由の一つは、セキュリティ対策の甘さです。大企業に比べてIT予算や専門人材が限られている中小企業は、攻撃者にとって「侵入しやすい標的」とみなされることが多いのです。
情報処理推進機構(IPA)が2024年に実施した調査によると、約7割の中小企業で組織的なセキュリティ体制を整備していないことが明らかになりました。
出典:「2024年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」の報告書
また、攻撃者は大企業に侵入するために、中小企業とのネットワークを利用するケースも増えています。中小企業が大企業と取引することは一般的であり、セキュリティ対策が不十分な中小企業を足がかりに、大企業への攻撃を仕掛けるため、中小企業も大企業と同様の水準でセキュリティ対策を講じることが必要です。
02 サイバー攻撃で企業が直面するリスクとは

サイバー攻撃は企業の存続や信用を揺るがす重大なリスクとなり得ます。実際、対策を講じていない企業が直面する主な被害には、次のようなものがあります。
1. 金銭的損失
ランサムウェアによる身代金要求、詐欺による送金被害、不正アクセスによる売上や利益の喪失など、直接的な金銭被害を受けるリスク
2. 業務停止・遅延
システムがダウンしたり、業務データが暗号化されたりすることで、通常の業務が停止・遅延し、復旧までに多大な時間とコストがかかるリスク
3. 顧客情報や機密情報の漏えい
顧客データや取引先情報、社内の機密データなどが外部に流出し、信用失墜や損害賠償請求につながるリスク
4. 社会的信用の失墜
情報漏えいやサービス停止が報道されることで、取引先や顧客との信頼関係が損なわれ、企業イメージが大きく傷つくリスク
5. 法的責任・制裁
個人情報保護法などの法令違反と認定された場合、企業として法的責任や行政指導、損害賠償などの発生リスク
6. 取引先との関係悪化
自社からの情報漏えいにより取引先に損害を与えた場合、取引停止や契約解除などの事態に発展するリスク
7. 二次被害の拡大
被害が他の取引先や顧客まで波及し、自社だけでなく関係する他企業にも損失やトラブルを与えるリスク
情報処理推進機構(IPA)の2024年の調査によると、過去3期に発生したサイバー攻撃などによる被害額は平均約73万円、最大で1億円に達するケースも報告されています。さらに、事業の復旧に平均5.8日、最大で360日を要した事例もあり、業務停止による影響は非常に深刻です。
出典:「2024年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」の報告書
このように、サイバー攻撃による被害は単なる一時的な損失にとどまらず、長期間にわたって企業活動に大きなダメージを与える可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、早急なセキュリティ対策が不可欠です。
03 企業に迫る主なサイバー脅威とは

サイバー攻撃と言っても、その手口や種類は様々です。
企業が十分な対策を行うためには、どのような脅威が存在するのかを知っておくことが重要です。ここでは企業が特に注意すべき主なサイバー攻撃の種類をご紹介します。
1.ランサムウェア攻撃
データやシステムを暗号化し、復旧と引き換えに身代金を要求。
2.フィッシング攻撃
偽メールや偽サイトを使った情報詐取。
3.マルウェア感染
悪意あるプログラムによる情報盗難やデータ破壊。
4.不正アクセス
パスワードの突破やシステムの脆弱性を突いた侵入。
5.標的型攻撃
特定企業を狙い、周到に準備された巧妙な侵入。
6.DDoS攻撃
大量のアクセスによるサービス妨害。
7.内部不正
従業員など関係者による情報漏えい・不正操作。
8.サプライチェーン攻撃
取引先や業務委託先を経由した間接的な侵入。
多様化するサイバー攻撃に対応するためには、日常的なリスク管理と対策が重要です。
04 企業が取り組むべき3つの対策

サイバー攻撃から企業を守るためには、入口・内部・出口で対策を講じることが重要です。
まずは入口対策です。多要素認証や細かなアクセス制限だけでなく、最新のセキュリティパッチの適用や不正ログイン検知など、技術的な防御を組み合わせることで、外部からの侵入リスクを大幅に減らせます。
次に内部対策です。ネットワークやシステムの監視を徹底し、異常な動きや不審なアクセスは即座に検知・対応できる体制を整えることで、被害の拡大を防ぐことができます。
最後に出口対策です。重要なデータは必ず暗号化し、ファイアウォールや情報漏えい防止ツールを活用することで、外部への流出リスクを低減し、検知・遮断の可能性を高められます。
企業の安全を守るためには、入口から出口まで継続的に対策することが大切です。
05 見えない脅威への備え方

サイバー攻撃は、もはや“目に見える外部からの侵入”だけではありません。正規のアカウントを使ったなりすましや、社内に潜む不正、気づかぬうちに感染した端末からの情報流出など、脅威はあらゆる場所に潜み、日々進化しています。
こうした“見えない脅威”に対抗するには、アクセスのたびにユーザーや端末の信頼性を確認し、必要最小限の権限だけを与える仕組みが必要です。
この考え方に基づくのがゼロトラスト型セキュリティです。すべてのアクセスを「信頼」ではなく「検証」によって管理することで、入口・内部・出口すべてのリスクに対して一貫したポリシーで対処しやすくなります。
今の対策に少しでも不安があるなら、それはすでに脅威にさらされている可能性があります。ゼロトラスト型セキュリティの導入はそうした不安を“仕組“で解消するための選択肢です。
とはいえ、見えない脅威に備えるには、まず自社のセキュリティ状況を正しく把握することが欠かせません。その第一歩として有効なのが、セキュリティ診断です。
システムやネットワークに潜むリスクを洗い出すことで、どこに対策が必要かを明確にできます。現状を“見える化”することで、的確な対策につながり、継続的な防御体制の構築にも役立ちます。
06 まとめ

サイバー攻撃のリスクは日々変化しており、企業の資産を狙った“見えない脅威”への対策が急務となっています。関心を持った今この瞬間が対策を始めるチャンスです。
私たちNTTドコモソリューションズでは、ドコモグループで培った豊富な知見をもとに、セキュリティ診断から対策の設計・導入、そして運用までを一気通貫で支援しています。自社のセキュリティに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。現状の課題を明確にし、最適な対策をご提案いたします。