|
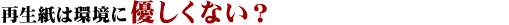 |
| |
−− |
まず、先生のご著書などを拝読すると、私達一般の人々の持つ知識がいかにあやふやなものかということが見えてきます。例えば再生紙を使った名刺についてのお話がありました。 |
 |
 |
 |
|
安井 |
紙の再生自体が悪いということではありません。まずもって、どんな紙だろうと紙を使うということが植物資源を枯渇させます。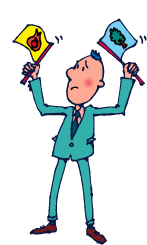 加えて再生紙は、トラックで回収し、再生工程では紙を溶かして印刷インクを取り除かなくてはいけません。その過程では石油などの化石燃料が、ばんばん使われているわけです。一方、木材からバージンパルプを作る際にはリグリンという成分を取り除く必要があり、このリグリンは上質紙を作る際に燃料として利用することができます。 加えて再生紙は、トラックで回収し、再生工程では紙を溶かして印刷インクを取り除かなくてはいけません。その過程では石油などの化石燃料が、ばんばん使われているわけです。一方、木材からバージンパルプを作る際にはリグリンという成分を取り除く必要があり、このリグリンは上質紙を作る際に燃料として利用することができます。
ですから、地球温暖化という側面から環境を考えた時には、再生紙を利用することが環境に良いとは一概に言えなくなります。
これらがすなわち、環境問題はトレードオフだと言っている点です。トレードオフとは「あちらを立てればこちらが立たず」というような状態のことです。紙について言うとトータルなエネルギーは多少、古紙の方が低いと思いますが、だからと言ってそれぞれに対してどちらが良いという明確な解答があるわけではありません。バージンパルプを作る方が化石燃料の使用量は少ないですよ、再生パルプなら木材を消費せずに済みます、それらを踏まえてどちらが良いかを判断しましょう、ということなのです
。 |
| |
|
|
|
|
|
−− |
同様に、天然なら良い、人工のものは良くないという思い込みもありますが、これも大いなる誤解だとおっしゃっておられます。 |
|
|
|
|
安井 |
これも全くの誤解ですね。知られている人工の化学物質は5万くらいですが、これに対して天然に存在する物質は100万くらいあります。それらの天然化合物について、私達はまだほとんど何も知らないという状態です。
例えば、植物は動けませんから、虫が来た時に人間のように叩くわけにもいきませんよね。そのため外敵に対抗する手段として、多くが天然毒を持っています。持っていない方が少ないくらいです。私達はその中で、あまり毒のないものを選んで食用としているにすぎません。山菜だって詳しくない人が採ってきて食あたりになったり、最悪の場合には死に至ることもあります。となると、天然成分由来だから良いという考え方は危険だということになります。
表記の仕方の問題もあります。食品の保存料としてアスコルビン酸と書かれていたら化学物質だと思って避けるでしょう。でもこれはビタミンCのこと。皆さんがサプリメントとしてわざわざ摂取しているものですね
。 |
 |
|
|
|
|
|
−− |
なるほど。人々の誤解ということでもう一つ。何より環境は自分の子供の頃より悪くなっていると考えている人がほとんどだと思うのですが、これも誤った認識とおっしゃっていますね。 |
|
|
|
|
安井 |
そうですね。例えば1970年に大気汚染が原因の損失余命(※)は日本の場合2.5年程度。現在もまだ0.5年ぐらいありますが、70年代は現在の5倍は空気が悪かったということです。
水道水も昔はおいしかったという声がありますが、70年代は鉛管を使っていましたから、水道水中の鉛の含有量ときたら、大変なものです。
そんなこんなを考え合わせると、70年頃に環境によって失われる生命は、雑駁に言って今の20倍程度はあったでしょう。ちなみに環境要因の発ガンは、おそらくディーゼルエンジン車の排気が最大でしょうが、それでも十数日という単位です。
※「損失余命」:あるリスクがなくなったと想定した際、各人が期待できる寿命の増加量。ちなみにたばこがなくなると、日本人の寿命は6年延びる。 |
| |
|
|
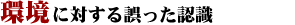 |
| |
−− |
となると、これらを含め私達は環境について随分誤った認識を持っているようですが、それはどうしてなんでしょう? |
|
|
|
|
安井 |
報道に問題があるのでしょうね。基本的にメディアは「News」しか扱わないので、環境ホルモンが怖い、ダイオキシンが怖いという話題だけが人々の目に触れることになり、1970年あたりから見ると、空気中の有害物質の濃度が下がってきましたという話は、誌面に載らないんです。
そして「ある食品添加物から発ガン物質が見つかりました」という報道があったとします。そうすると皆さんはびっくりして、やはり化合物はだめだという反応になってしまいます。ですが、その報道自体が事実だとしても、例えば発ガン物質の中で一番重要なものはB型・C型肝炎、子宮ガン、白血球ウィルスといったウイルスや胃ガンの原因と言われるピロリ菌ですね。ガンの研究者いわく、発ガンの35%は食品添加物など一切関係なく、普通の食物ですし、飲酒と喫煙で30%ずつ、その他で5%です。
もしもそれを知っていたら、もちろん発ガン性があることは問題ですが、少し冷静に対処できます。
私は、今の環境は過去最高、空前絶後だから、今のうちにちゃんと子供を作りなさいって言っています。
地球から得られる鉱物資源、化石燃料、それから食料資源等の限界が、そろそろ見えてきているわけですから、全体として地球環境が「悪くなる」という言い方はできるでしょう。これは人類出現以来、悪くなり続けているんです。それは4億年かかってできた石炭や、数千万年かかってできた石油を500年で使い切ろうというわけですから、当然ですね。 |
 |
|
|
|
|
|
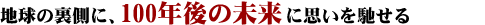 |
|
−− |
そこで、私達が環境について何ができるかという話になりますね。 |
|
|
|
|
安井 |
 そうですね。環境は一人ひとりの行動と密接に結び付いていますから、まずは「環境に優しい」という宣伝文句をうのみにせず、本当にそうだろうかという視点を持つことでしょう。 そうですね。環境は一人ひとりの行動と密接に結び付いていますから、まずは「環境に優しい」という宣伝文句をうのみにせず、本当にそうだろうかという視点を持つことでしょう。
最初の紙の話に戻りますが、再生紙を作るにしてもバージンパルプを使うにしても、どうしても環境に負荷がかかります。負荷をゼロにするには何もしなければ良いわけですが、そういうわけにはいきません。そこで、私は環境に優しいとされているモノについて、全体として考えた時にどうなのかというトレードオフ的検討を提示しているわけです。例えば合成洗剤と石鹸、無洗米と普通米ではそれぞれ環境にどんな負荷がかかるのかをトータルに見てみようというものです。
環境問題というのは、一人の人間が把握できる範囲を越えていて、非常に難しい問題ですから、個々人の環境に対するアプローチが重要だと考えています
。
|
| |
|
|
|
|
|
−− |
確かに、環境を考えてベストな選択肢を取ろうとしても、一般の人にはその判断は非常に難しいと思います。実際、私も環境についていろいろと調べていくうちに、結局どうしていいのか分からなくなってしまったという経験があります。 |
|
|
|
|
安井 |
環境学をやっていくと「そもそも人間は何で生きているのか」などというところにまで話が及んでいきます。
例えば鮭は雌が産卵し雄が精子を振りまいて死んでしまう。「親子の対話が少ない」なんて考えることはもちろんありませんよね。でも次の世代も当然のこととして綿々と続いていく営みがあります。人間だけが自分の周囲の環境を都合の良いように作り替えているんですね。しかし、そうやって自分の周辺だけを考えていくと長続きしないだろう、少し大きいところで考えましょうというのが環境学的な「かしこい生き方」だと思います。
ゴミを出したら「その先は知らない」のではなく、どうやって処理されているのか、今の焼却炉の状況はどうなのか、そういう情報を収集しようという姿勢を持ちながら、想像力を巡らせていくのが大切です。
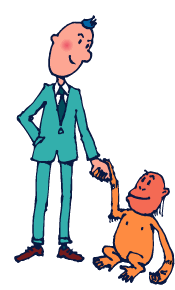 自分の生活を日本の中だけ、東京の中だけで見ているという姿勢はやはり「かしこい」とは言い難いでしょう。自分の行為が地球の裏側の人々の暮らしにどんな影響を及ぼすのかという空間的広がりのあるイマジネーションをつけなくてはいけないと思います。 自分の生活を日本の中だけ、東京の中だけで見ているという姿勢はやはり「かしこい」とは言い難いでしょう。自分の行為が地球の裏側の人々の暮らしにどんな影響を及ぼすのかという空間的広がりのあるイマジネーションをつけなくてはいけないと思います。
もう一つ、時間的な広がりも重要です。クロマニヨン人が出てきたのが14、5万年前くらい。46億年という地球の歴史から考えると、1万分の1以下です。そうして考えると、石油だって、数千万年かけてでき上がったものを、人類のたかだか500年くらいの活動で使い尽くしてしまう。それでいいんだろうか?
という考え方も大切です。
十何万年という単位でモノを考えると言ってもあまりピンとこないかもしれませんから、せめて100年くらいのスパンでモノを見てはどうでしょう。
人間というのは極めて社会的な存在です。他の人間に対して、次の社会に対して自分が何を残せるかというのが人間が生きている意味だと思いますから、自分の周りだけではないところに思いを巡らしていくという姿勢が重要でしょう
。 |
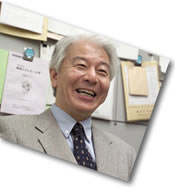
|
|
インタビュア 飯塚りえ
|
|
| 安井 至(やすい・いたる)東京大学生産技術研究所教授 |
1945年東京都生まれ。68年東京大学工学部卒業。73年同大学大学院博士課程修了。90年東京大学生産技術研究所教授。96年東京大学国際・産学共同研究センター、センター長併任、97年全国産学連携センター協議会会長、99年より現職へ復帰。
現在、中央環境審議会総合政策部会臨時委員、科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会臨時委員、厚生労働省独立行政法人評価委員などを務める。
主著に『高機能性ガラス』『光材料―アモルファスと単結晶』『リサイクルのすすめ』『市民のための環境学ガイド』『21世紀の環境予測と対策』などがある
。 |
|
|
|
|