「魚や海の調査を通して、人間のより良い生き方に貢献できればいいですね。」
魚を中心とした日本の食生活は、健康に良いとされ
世界的にも評価されているが、年によって漁獲量が変化するのが悩み。
今回登場いただく益田玲爾さんは、海の変化や
魚の行動パターンを解明することで、海の資源のメカニズムを
解こうとしている。
日本各地の海に潜って定点観測を続けたり、魚の心理を探ったり、と
ユニークな研究を続ける益田さんにお話を伺った。
―― |
先生のご専門は「魚の心理学」と伺ったのですが、まずは魚に「心理」があるのでしょうか? |
益田 |
結論から申し上げると、あるのです。まず「心理」とは大きく「情動」と「認知」とに分けられます。「情動」とは、怒り、不安、安心といった喜怒哀楽。それより上位のものとして「認知」、つまり学習と推理があります。学習と推理では、推理の方がより高度です。高い所にバナナがぶら下がっていて、近くに棒があるという状況で、その棒を使ってバナナを落とせるかどうか。経験が無いことでも「こうしたらできるかも」と考える、これが推理です。人間以外はほとんどできません。チンパンジーは少しできると言われていますが、犬には無理です。魚にも、ちょっと無理だろうと思います(笑)。しかし魚にも学習能力はあります。魚は繰り返し学習することで、それまでに経験の無いこともできるようになります。輪くぐりなどがそうですね。 |
―― |
人の姿が見えると餌をもらえると思って、池のコイが寄ってくるのも学習ですね。 |
益田 |
そうです。それに魚には情動もあります。人は不安な時、どきどきしたり、目をきょろきょろしたりしますね。魚は目にはあまり表れませんが(笑)、エラの動きが早くなってくると「どきどきしてるな」と分かります。そうやって、魚の気持ちになって考えるということが、魚類心理学の一つの視点です。 |
―― |
魚に情動があるというのは、驚きです。 |
益田 |
|
―― |
人間にも、そういうピークがありそうです(苦笑)。魚の学習能力に興味を持たれたのは、ハワイ大学で魚の行動の研究者を募集していたのがきっかけだったとか。 |
益田 |
はい。ハワイでは、稚魚を放流して成長したら漁獲するという栽培漁業が進んでいますが、当時、放流した稚魚が漁獲する以前に捕食されてしまうので、漁師さんも困っていました。そこで魚の行動学から解決を試みようとしたわけです。 |
―― |
どんな魚で実験されたのですか? |
益田 |
ハワイでよく食べられるモイという魚です。日本ではナンヨウアゴナシという名前が付いています。 |
―― |
実験はどのように? |
益田 |
毎日の給餌の前に、空気を入れる「エアー」―あの水槽などでブクブクやっている器具です―を止めるという条件付けを行いました。するとエアーが止まると、給餌の場所にモイが集まるようになるのです。サイズの違うモイごとに、それを学習するのに何日掛かるか測ることで、学習能力を調べました。調べていくと、5~9cmのモイが最も学習が早いことが分かりました。一方で、別の実験では体長がより大きな方が食べられにくいという結果が得らました。 |
―― |
漁業に直接役立つ研究結果ですね。日本でも同じような例がありますか。 |
益田 |
若狭湾の漁師さんから「最近、魚の漁獲量が減る一方、クラゲが増えている」という話を耳にして10年ほど前から調査を始めました。 |
―― |
クラゲが増えた理由は何だったのでしょう? |
益田 |
理由については、諸説言われていますが、私はクラゲの天敵となる、カワハギやマダイといった魚が減っているのが、最も大きな原因だと考えています。 |
―― |
魚が学習能力を持ち、かつ年齢による違いがあるということが分かってきたわけですが、その能力には差が出るのですか? |
益田 |
そうなんです。同じ年齢でも個体差があることが分かってきました。 |
―― |
なるほど。 |
益田 |
そこで、人間のサプリメントとしてもよく知られているDHA(ドコサヘキサエン酸)が、魚にとっても重要な栄養素で、実はこの要素が足りないと群れを作れないということを見つけたのです。 |
―― |
DHAの量によって魚のかしこさに違いが出るのですか!? |
益田 |
以前からDHAが魚の成長に影響を与えているとされてきたのですが、こんなに顕著に表れるとは思っていませんでした。しかも、自然界の動物プランクトンに含まれるDHAの量は意外に変動が大きく、例えば紫外線が当たるだけで減ってしまいます。 |
―― |
もう一つ、先生は日本各地の海に潜って定点観測をされていますが、東日本大震災の後、宮城県気仙沼の舞根(もうね)湾でも調査を始められたそうですね。 |
益田 |
震災から2カ月後に、京都大学の調査研究チームに同行して潜り、それから2カ月に一回、定点観測のために潜水調査を行っています。 |
―― |
以前、このコーナーにも登場いただいた牡蠣の養殖を営む畠山重篤さんの養殖場も津波によって大きな被害を受けられました。畠山さんはその時のことを「海が空っぽになってしまった」と表現されていました。 |
益田 |
はい。最初に潜った時には、海底全体が泥で覆われ、小さな魚が点々といるという程度で、基本的に海藻も魚もほとんどいない、それこそ海の砂漠状態でした。 |
―― |
小さな魚が? |
益田 |
津波というのは、波というより泥の流れです。時速数十キロの泥が押し寄せて、引いていく際に、本来そこにいた魚が陸に打ち上げられたり、沖に流されたりして空洞状態になるのです。そこに、沖から来た小さな魚がいたのでしょう。そして、その数が増えていくのです。ただ、増えるのはなぜかキヌバリというハゼの仲間だけでした。 |
―― |
海の中の「復興」が現実的になってきたということですね。 |
益田 |
生物学の分野に「遷移」という用語があります。ある環境ができる時に、溶岩が流れて、しばらく何もない状態が、放置しておくと、やがて草が生え、ススキが生え、低木、高木が生えて、最終的には、その地域の状態に適した森林、極相林ができ上がることで、陸上では、この極相林ができるのに、最低で50年かかると言われています。しかし海の中は、陸に比べてはるかに遷移が早いのだ、と今回、肌で感じました。海の中の主な植生は海藻ですが、海藻は、早いものでは半年で茂り、1、2年で海藻林ができました。 |
―― |
震災以前に舞根湾で潜ったことはありましたか。 |
益田 |
ありません。ですので、一緒に調査をしている畠山さんの息子さんから、「この辺りには、こんな魚が居た」という震災以前の情報をもらっています。彼は、小さいころから、そこでずっと育っていますからね。 |
―― |
畠山さんは、「海は森の恋人」をスローガンに上流の山に植林を続けてこられましたね。 |
益田 |
畠山さんは、自然の岩場の上に生えている松の木にロープを結わえて、それに筏(いかだ)をつないで養殖をされていました。彼にとっては、何気なく行ったことかもしれませんが、とても上手に自然の地形を利用しているんですね。それによって多様性が保たれていると感じました。実際、もし養殖場を護岸していたら、回復にはもっと時間がかかっていたと思います。垂直な護岸は、確かに牡蠣の養殖はしやすいかもしれませんが、元の地形にほとんど手を加えず、天然の岩場をちゃんと残していたからこそ、今回も速やかに生き物が戻って来られたし、海藻も生えやすかったのだと思うのです。多様性は、強さを与えます。いろいろな災害があった時に、回復力を与えるということもあるでしょう。海の中と陸とを眺めた時にそう実感しました。 |
―― |
今後も観測を続けることで、何が見えてきそうですか? |
益田 |
年を経るごとに、魚の種類が増え、数が増え、今はそれらが大きくなってきたというように、少しずつ変化がありますが、やがて季節に従って、毎年同じようなことが観測できるようになったら、それが一つの完成系です。 |
―― |
全体のシステムというのは、夏になったら去年と同じ魚が来た、といったことですか? |
益田 |
|
益田玲爾(ますだ・れいじ)
1990年静岡大学理学部生物学科卒。東京大学海洋研究所にて学位を取得。 96年英国Dunstaffnage Marine Laboratoryに留学。98年米国ハワイのThe Oceanic Instituteでの研究を経て現在に至る。著書に『魚の心をさぐる―魚の心理と行動 』(ベルソーブックス)、共著に『魚類生態学の基礎』、『魚類の行動研究と水産資源管理』(共に恒星社厚生閣)。
●取材後記
魚のかしこさの違いが見えてきたら、次に取り組みたいのは個性だと言う益田さん。「学習実験では、やたらとかしこい魚と、そうでもないのがいるんです。それが遺伝的な違いなのか、環境はどの程度影響するのか調べたいと思っています」とのこと。ただ、例えばかしこく大胆な性格がいいかと言えば、そうでもない。餌を見つけてすぐかぶりつけば捕食されてしまうこともあるから、結局慎重で最後まで尻込みしていた個体が生き残る。人間の目で見ると、つい優劣をつけたくなるけれど、多様性の真価はここにあるというわけだ。
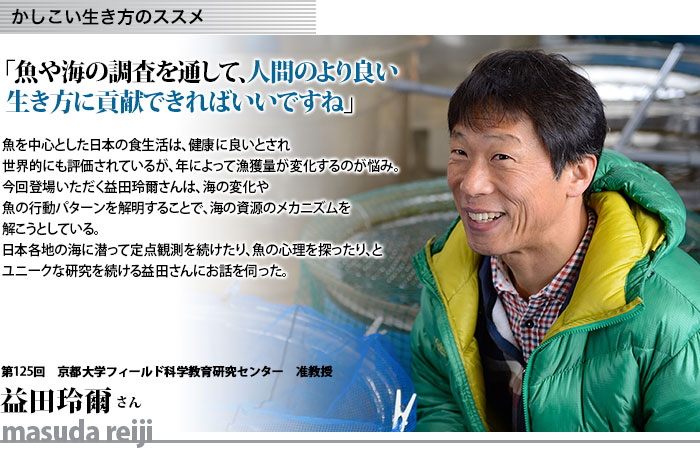

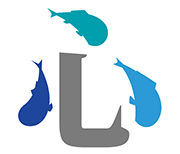 心理の定義の仕方を広く捉えれば、心理学で扱う事項の4分の3は、魚にも当てはまります。それならば、それらを科学的な方法で測ることもできるはずだと考えて実験してみました。例えばY迷路は、その名の通りY字型に分岐した迷路の水槽ですが、それを使って分岐の一方に行けば餌をもらえるように学習させてから、今度はそれを逆に、例えば右に行けば餌がもらえていた条件を左にしてみるのです。この実験によって学習の書き換えができるかどうかが調べられます。
心理の定義の仕方を広く捉えれば、心理学で扱う事項の4分の3は、魚にも当てはまります。それならば、それらを科学的な方法で測ることもできるはずだと考えて実験してみました。例えばY迷路は、その名の通りY字型に分岐した迷路の水槽ですが、それを使って分岐の一方に行けば餌をもらえるように学習させてから、今度はそれを逆に、例えば右に行けば餌がもらえていた条件を左にしてみるのです。この実験によって学習の書き換えができるかどうかが調べられます。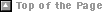
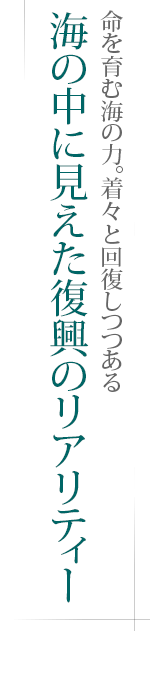
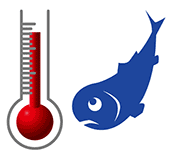 「同じ」ではなくて、「同じような」魚です。入れ替わることは多少あります。しかし、システムとして似たようなことが安定して繰り返されるということが、特に日本のような温帯で、季節の変化がある国にとっては、重要なのです。
「同じ」ではなくて、「同じような」魚です。入れ替わることは多少あります。しかし、システムとして似たようなことが安定して繰り返されるということが、特に日本のような温帯で、季節の変化がある国にとっては、重要なのです。