「科学とは、知ること、発見すること、考えることなのです。」
「科学技術」という日本語がある。
科学の先にあるのは、私たちの暮らしが便利になったり、
豊かになったりする世界だと思いがちだ。
しかし、科学上の新しい発見がすぐに実用に結び付くのは、
むしろまれだ。
科学は“ムダ”な学問だろうか。そんなことはないだろう。
そこで、物理学を専門とし、科学番組などの監修を広く行う
高千穂大学学長の並木雅俊先生に、
科学の成り立ち、役割について伺った。
―― |
生命科学にしても、物理科学にしても、国の機関では莫大(ばくだい)な予算が付くようなこともあって、それが人々の暮らしにどんなふうに役立つのかなどと言われることもありますね。 |
並木 |
科学と技術は、本来別々のものです。しかし、日本人は「サイエンス&テクノロジー」を一つにして考えることに違和感がありません。世界で最も早く工学を学部としたのは日本の大学(帝国大学)であることからも分かります。また、ご存じのように、日本は1853年のペリー来航の翌年から開国へと向かいました。ペリーは日本に「黒船」「大砲」「蒸気機関車」といった技術をもたらしたと同時に、開国によって「科学」の知識も入ってきました。ここに、日本人が科学と技術をひとまとめに捉えるようになったきっかけがあるのではないかと思います。 |
―― |
本来、分けて考えるべきなのに、ということですか。 |
並木 |
サイエンスの語源「scientia」が知識全般を意味することからも理解できる通り、科学とは、知ること、発見すること、考えることなのです。放射線の研究で知られる物理学者であり化学者のマリー・キュリー(1867~1934)は、アンリ・ベクレル(1852~1908)の部屋で放射線を初めて見て、X線のように装置もなく、石ころが一つあるだけで放射線が出るということがとても不思議に思えたのです。そして、その本質を解明しようと取り組みました。そこに「これを解明したら何かに使えそうだ」という考えはなく、純粋に「なぜだろう」という興味から、決して諦めることなく研究を続けたのです。何があるかは分かりませんし、解明するためには、高く厚い壁がある。それでも、彼女は立ち向かったわけです。しかも彼女は、大学や研究所に属していたわけでもありません。 |
―― |
大学と科学の関係というのは、どうなっていたのでしょう? |
並木 |
ヨーロッパの大学制度においては、医学、法学、神学などが柱で、それを支える一般教養として論理、修辞、言語の3学と、算術、幾何、天文と音楽――ここでいう音楽は「調和」を意味し、数学的な学問なのですが――などを学ぶのが基本でした。今でいう「理科」「科学」の要素はほとんどなかったのです。 |
―― |
それ以前では、体系的に科学を学ぶ場はなかった、ということなのですね。 |
並木 |
そういえます。大学という機構は、11~12世紀に始まるとされていますが、大学で科学が学べるようになったのは、ずっと後になってからです。では、科学はどのように発展してきたかというと、みんな自宅で実験をしていました。例えば、ヘンリー・キャヴェンディッシュ(1731~1810)―地球の密度測定や水素の発見などで知られるイギリスの実験物理学者―は、人嫌いで人と会うのが苦手でした(笑)。けれども貴族の家に生まれ育った彼は、豊富な資金を元に、自宅に備えた実験室でさまざまな発見をしました。エネルギーの単位の名前で知られるジェームズ・ジュール(1818~89)の本業は醸造業です。醸造業を営む傍らでエネルギーの概念を発見しましたし、質量保存の法則を発見したアントワーヌ・ラヴォアジェ(1743~94)は徴税官でした。「科学者」として生計を立てていた人は少ないのです。 |
―― |
趣味で科学の研究をしていたということですか? |
並木 |
本人たちにとって、どちらが本業なのかは分かりませんが(笑)、自分の生活費を稼ぐために研究していたわけではなく、また、研究して発表するのが目的ではなく、その発見自体が楽しかったのだと思われます。科学が好きだったのでしょう。 |
―― |
今、私たちがその恩恵を受けている科学の発見をした人たちは「知りたかった」から研究をし、その答えを導き出しただけで、その先に何か実用的なことを期待したわけではないのですね。 |
並木 |
|
―― |
無線の例は、科学と技術の幸福な出合いだったけれど、科学的発見がすべて何かに役立つというのは、昨今、陥りやすい誤解ですね。 |
並木 |
特に日本では科学と技術とが同時に押し寄せたことに理由があるのかもしれません。明治時代、技術を学ぶ機関としては政府の工部省が管轄した工部大学校がありますが、これは現在の東京大学(当時の帝国大学)工学部の前身です。冒頭でお話したように、大学に工学部を設置したのは、帝国大学が最初でした。 |
―― |
意外ですが、日本に科学と技術の概念が同時に入ってきたことを象徴するような話ですね。 |
並木 |
例えば、名門といわれるMIT(Massachusetts Institute of Technology/マサチューセッツ工科大学)もカリフォルニア工科大学(California Institute of Technology)も、「Institute(単科大学)」であって「University(総合大学)」の中にはありませんでした。昔は、すべての学問の基礎は哲学であるとされ、工学的なものは敬遠されていたのです。 |
―― |
例えばノーベル賞なども、結果的に私たちの暮らしに役立ったという業績が多くありますが、ご本人はその研究を何か実用に生かそう、という意図は必ずしもないようにも思います。 |
並木 |
古代ギリシャの数学者・物理学者であるアルキメデス(BC287~BC212)は「流体中の物体は、その物体が押しのけた流体の重さと同じ大きさの浮力を受ける」という原理を発見した時に「エウレカ!(分かった!)」と叫んだといわれていますが、キュリーにしても、マクスウェルにしても、みんなこの「分かった!」が喜びなのだと思います。その点はみなさん共感できるのではありませんか? 実際に誰かが既に発見したものであったとしても、自分が今まで知らなかったことを「分かった」と得心すること、それは大きな喜びになります。 |
―― |
「分かった」という達成感は大きいと思います。 |
並木 |
|
―― |
科学は「知ろうという力」ということですか。 |
並木 |
そうです。それは生きる力にもつながります。キュリー夫人は、そのパーソナリティーも非常にユニークで芯の強い女性です。地道にコツコツと研究を続け、決して諦めなかったのは「知りたかった」からだと思うのです。結局、彼女は、ノーベル賞で得た賞金でレントゲン車を手に入れ、娘イレーヌと共に戦場に赴き、敵味方関係なく負傷者の診断に駆け回りました。その点では放射線はすぐに実用に結び付いたわけです。キュリーは晩年、働きながら実験を続け、ラジウムとポロニウムを発見した時が、一番幸せだったと語っています。彼女にとっての宝物が見つかったわけです。 |
―― |
私たちは科学に成果を求めがちですが、それは少し的が外れているようですね。 |
並木 |
例えば、空に輝く満月を鏡に映したら、きれいに光りますよね。その鏡を横から見たことはありますか? 真っ黒です。光は横に反射しませんから。では、半月はなぜ光るのか。それは月の表面がざらざらで、太陽からの光が乱反射しているためです。月の表面が鏡のように平滑であれば、こちらに光は届きません。それは、誰もが知っていることかもしれません。けれども、それを自分で納得して理解することほど、うれしいことはないと思うのです。科学というのは、そうやって考えていく力と、諦めない力の源です。そうした力は何も科学でもなくても、あらゆる場面で輝く力になると思います。 |
並木雅俊(なみき・まさとし)
1953年生まれ。高千穂大学学長・教授。1980年東京都立大学大学院理学研究科博士課程物理学専攻単位取得退学。世界物理年日本委員会運営委員会副委員長、一般社団法人日本物理学会理事、公益社団法人日本工学会理事、特定非営利活動法人物理オリンピック日本委員会副理事長(2012年8月まで、現在は理事)を歴任。共著に『知っておきたい物理の疑問55』(講談社)、『文明開化の数学と物理』(岩波書店)、『ノーベル賞100年のあゆみ②ノーベル物理学賞』(ポプラ社)、著書に『教科書にでてくる物理学者小伝』(シュプリンガー・ジャパン)、『星と宇宙の物理学読本』(丸善)、『大学生のための物理入門』(講談社)、翻訳に『アインシュタイン奇跡の年1905』(シュプリンガー)、『宇宙の発見』(丸善)、『明解ガロア理論』(講談社)など。
●取材後記
今年の夏休みにも、物理の全国大会である「物理チャレンジ」が行われる。物理オリンピック日本委員会理事でもある並木さんは、こうした場で物理好きの中高生と会う機会をとても楽しみにしている。彼ら・彼女らのユニークな発想に接するたびに元気が出るそうだ。高校生の時には敬遠していた科学や物理だが、大人になってその面白さがようやく分かった。今年は、純粋に科学の面白さに触れてみる体験を夏の計画に入れてみよう。
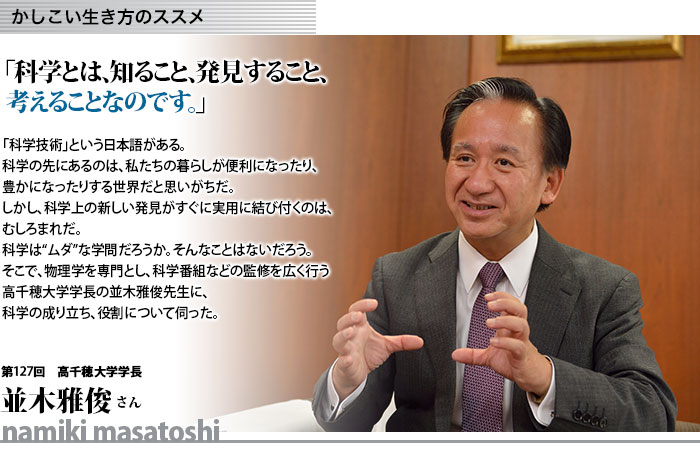
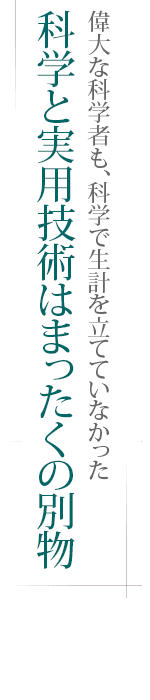
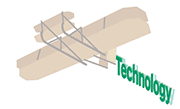 そうなのです。科学好きの小・中学生は、科学を学んで何をしたいのかと聞かれると「周りの人が幸せになる物を作りたい」「高速ロケットを作りたい」と、技術的なことを挙げます。それ自体、とても素晴らしいことです。ただ「科学を勉強すると技術が発展する」というのは、ちょっと違うのです。
そうなのです。科学好きの小・中学生は、科学を学んで何をしたいのかと聞かれると「周りの人が幸せになる物を作りたい」「高速ロケットを作りたい」と、技術的なことを挙げます。それ自体、とても素晴らしいことです。ただ「科学を勉強すると技術が発展する」というのは、ちょっと違うのです。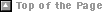
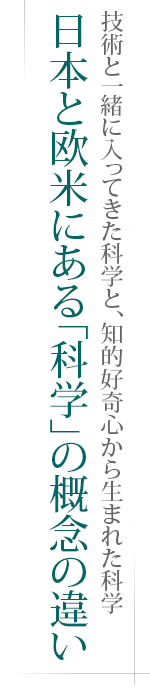
 数学の証明でも同じかもしれません。「知りたい」のです。
数学の証明でも同じかもしれません。「知りたい」のです。