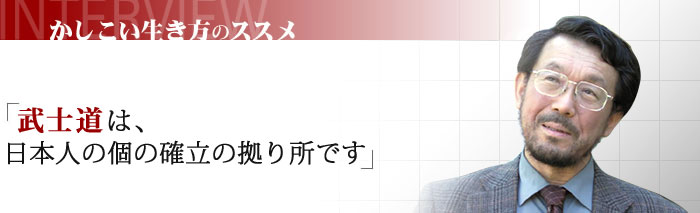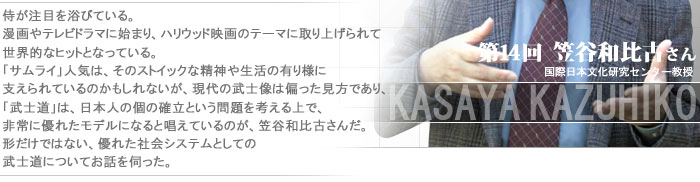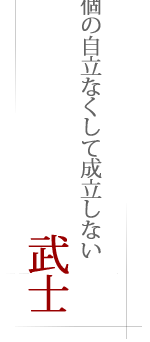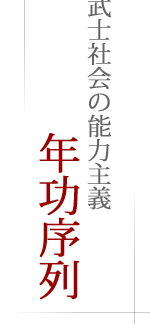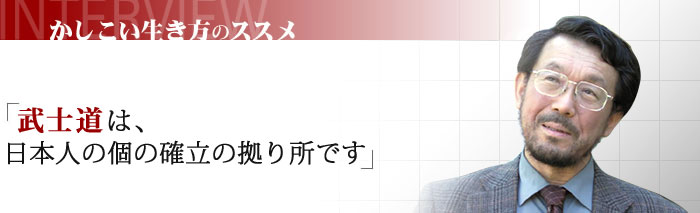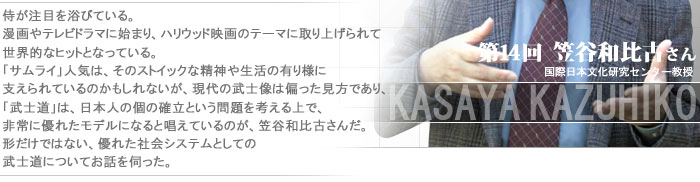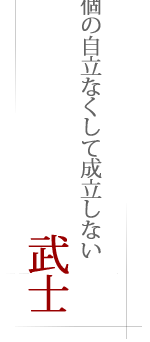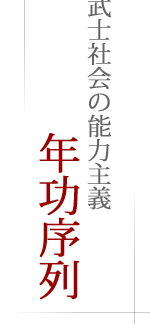−− |
最近、漫画や映画などでもそうですが「武士道」が大変に注目を浴びています。 |
 |
 |
笠谷 |
私が提唱していることのひとつに「武士道モデル」という考え方があり、これは日本社会、日本人における「個の自立」という問題が関係しているかと思います。
90年代頃からでしょうか、日本社会というのは集団としては強力なのですが、個人となると弱いという指摘がありました。確かに、私も諸外国で教鞭を執っていますが、欧米の学生は、良くも悪くもタフ、非常に強固な個を持っています。
ドイツで教鞭を執っていた時、面白いことがありました。大学院の学生は学位を取るために専門論文を書かなくてはなりません。そこで私は、講義の時間外にも要望があれば相談にも乗り、資料の解読にもつき合いました。一方、市民相手に日本文化について講演するというような機会もあります。そんなときは通訳が必要なので、日頃教えている学生に依頼すると、この返答が「忙しいので」などと、はかばかしくありません。どうも違和感を感じて、同僚の教授に話したところ、それは私が自分の義務を越えて厚意で論文制作を手伝っていることを学生に伝えるべきだった、そうでないと彼らの心の内のバランスシートには私に対しての負債が刻まれない、というのです。なるほどこれが契約社会というものか、と分かりました。
そもそも欧米型のシステムは、個人は常に神に対してのみ責任を負うというキリスト教の論理構造から出てきました。だから世間にどう関与するかには、極論すれば関心がなく、周囲との関係は基本的に利用し利用される関係です。そういう関係性だからこそ「契約」というシステムが発達します。欧米の契約書って、すごく厚いでしょう?
全てのケースについて、利益とリスクの関係を事細かく記して、それで初めて社会の関係が成り立つような社会なんですよ。
ですが日本社会は根本的にバックボーンが違います。日本は、やはり良くも悪くも、人間社会の中におけるそれぞれの人間の立場、あるいは成すべき事、成しては成らないことを相互に決め合い、信頼によって関係を成り立たせるような社会です。「武士道」はそうした社会、組織の中で「個の自立の在り方」のひとつの有効なモデルケースになるのではないかと考えています。
|
|
| 主君、御家、そして民衆への忠義 |
|
−− |
私達には「武士道」は「滅私奉公」や「二君に仕えず」と言った頑ななイメージがありますが、そうではないということでしょうか? |
|
笠谷 |
 武士道には「忠義」という軸となる概念があります。一般的に「忠義」と聞くと、主君に対して絶対服従というイメージがありますが、それは多分に意味を履き違えています。武士道の一番最盛期、徳川時代の武士道というものを見た場合、「個の自立」という契機を抜きにして忠義はあり得ないんです。 武士道には「忠義」という軸となる概念があります。一般的に「忠義」と聞くと、主君に対して絶対服従というイメージがありますが、それは多分に意味を履き違えています。武士道の一番最盛期、徳川時代の武士道というものを見た場合、「個の自立」という契機を抜きにして忠義はあり得ないんです。
赤穂浪士の事件は「忠義」という問題を考える上で非常に興味深い例です。「松の廊下」の事件後、浅野家の家臣は、主君、浅野内匠頭のために復讐を果たそうと考える堀部安兵衛のような人物と、大石内蔵助に代表される家の再興を優先する派とで意見が対立しました。ここに忠義の構造に変化が生まれたことが見て取れます。
もうひとつ注目すべきは、堀部らが「自己の名誉と存在を守る」ために仇を討とうとしていた点です。「忠義」とは決して自分を捨ててしまうことを意味していないのです。
そこには武士たる者は、我が強く、自分の信念に対して非常に忠実であること、あるいは周囲に付和雷同せず、主君の命令であってもおかしいと思うものに対しては、堂々と「おかしい」と多くの人の前で申し立てることが出来るような気概を持つことが肝要であり、御家、つまり組織の強さはそうした人間をどれだけたくさん抱えているかにかかっていると考えられていたのです。
|
| |
| −− |
個人の強さがなくては、組織も確固たるものにならない、と考えたわけですね。 |
| |
笠谷 |
そうです。そして18世紀になると忠義の対象が変化していきます。
藩主の悪行、暴政が重なったときには、家臣が主君に意見をするという「諫言」の制度が生まれ、さらにこれをしても、主君に聞き入れられない場合、家臣の手で藩主を辞任させるという「押込(おしこめ)」という制度もありました。これは17世紀であれば完全に反逆行為と見なされたわけですが、御家に対する忠義のために、個別の主君に対する忠義を停止する、これも忠義の一つだという考え方に変化していきます。
18世紀後半には、忠義の対象が、御家から一般人民まで含めた公共世界になります。武士はもともと戦士だったわけですが、戦争のなくなった徳川時代に、どうして領民から年貢を取り立てて支配する存在でいられるのか、という自己反省が武士の間に生まれ、武士は領国を治めるための「治者」であり、領国の平和と繁栄に対して責任を負うべき政治家であり、行政マンだと考えるようになります。フランス革命の4年も前に、米沢藩の上杉鷹山(うえすぎ・ようざん)が「藩主というのは、国家と人民のための藩主であって、藩主のための国家人民ではない」という、フランス革命やアメリカの独立宣言に近い内容の政治綱領が、日本の侍社会ですでに独自に作られていました。類似の表現は徳川吉宗や他の藩主の文章にも多く見られます。つまり「御家」を越えた、大きな公共性のために藩、あるいは藩主が存在するという考え方が18世紀に確立したんです。 |
| |
| −− |
こうしてお話を伺うと、今のシステムよりもはるかに優れているのではないかなと思いますが(笑)。 |
| |
|