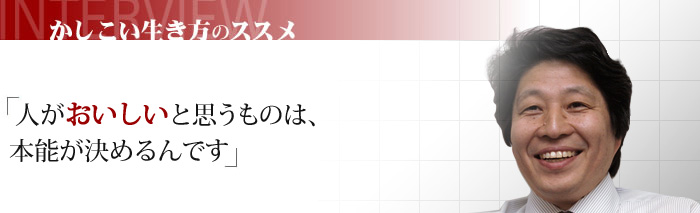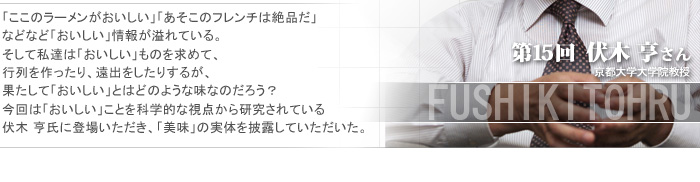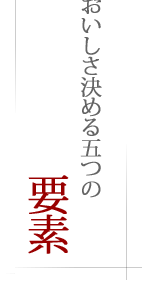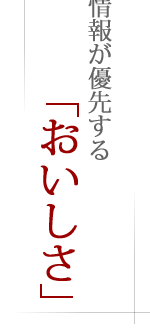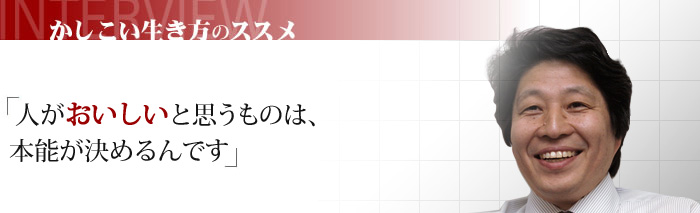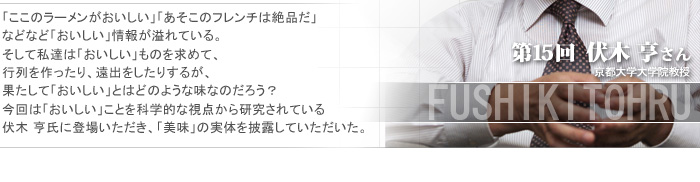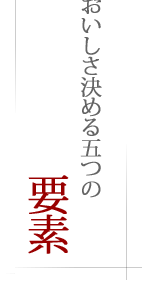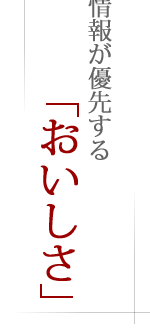|
 |
−− |
「おいしさ」の基準の中に、「情報」がありましたが、これは社会学や心理学、さらにはマーケティングにも関わってくるものです。
|
| |
伏木 |
人間とネズミとでは、脳の構造で大きく違う点があるんですが、それが「情報」に関わる点です。動物は、栄養素を取る事にすごく忠実ですし、自分の舌だけが頼りの動物は、誤って毒物を食べてしまったらそれで終わりですから食べ物の安全性に対してものすごく敏感で、食物を取るときには非常に恐れながら、かつ的確な栄養素を取ろうと必死になります。ところが人間は、味から得た情報の価値が判断される直前に「情報」が入ります。賞味期限が過ぎると、例えそれが腐っていなくても危ないんじゃないかと思う。これは文字情報の方が味より優先しているからです。 |
|
−− |
しかし情報が優先している状態というのは、見方を変えると危険な事ではないでしょうか?
|
|
伏木 |
そうですね。我々は、情報に寄りかかり過ぎて、味から得た情報を感知する能力が退化しちゃったんじゃないかと思うんですよ。自分の舌で感じる自信があれば、うまいかまずいかも分かるし、安全かどうかもある程度判断が付くと思うんですが、自分の舌で判断する能力が無いと分かっているから、情報に左右されてしまうんです。今、塩の量や栄養素、カロリーなど表示がどんどん詳しくなっていますね。つまり情報で食べているんです。 |
|
−− |
今「おいしいもの」が流行っていますが、それと「食」に対する興味が高まっていることとは異なるということでしょうか?
|
伏木 |
パンのブーム、ラーメンのブーム、辛いものブーム。おいしさを競うテレビ番組もたくさんありますが、ちょっと異常な感じがあります。必ずしも食に対する興味が高まっているのではなく「その先に何があるか」という刺激や快感を求めているんではないでしょうか。ということは、コンピュータゲームに夢中になるのと変わらない。より強い快感を与えてくれるものを探しているわけです。
いわゆる「グルメブーム」が、本来の食べ物の食べ方を壊している一面があるかと。それがなければ、我々は普通のもの、つまり本来の食文化に合致した「おいしいもの」を食べていると思います。 |
−− |
「おいしい」という感覚は、本来自分の中に培われた食文化であるはずなのに、それを放棄している部分があるかもしれません。 |
| 正しい食を伝えるためにすべきこと--離乳食 |
−− |
心臓疾患や糖尿病など、いわゆる生活習慣病が問題になっていますが「おいしい」要素の砂糖とだしと油の内、「だし」だけはこの問題をクリアしていますね。 |
伏木 |
ですから、日本は、元々生活習慣病が少なかったんですよ。
1977年にアメリカで理想的な食事を探求すべく巨大なプロジェクトが組まれました。国内で急増する肥満に対して、世界中の科学者たちに調べさせ理想的な食事の在り方を探った訳です。現在、理想的な食事というと、その報告書がベースになっているんですが、その中で理想的な食事をしている国として日本が紹介されています。しかし、日本の食文化はその当時から比べて崩れてきている。何を食べるかというのは個人の好みだし、別に何を食べても構わないと思いますが、栄養学的な観点からすると、やはり伝統的な「だしの文化」を大事にしなければいけないのではないかと思います。「だし」が、油と砂糖に対抗して、本能的な執着を起こさせる「おいしさ」を持つものだということも実験の結果が出ています。ですから、その大切さをもっともっと、広げていこうと考えています。 |
−− |
未来食開発プロジェクトでは、どのような研究をなさっているのでしょうか。 |
伏木 |
今、離乳食に非常に興味があります。日本人の健康のためにも、もっと、だしの味を子供にも広めていく。それが、日本の将来のために大事だと考えています。これもマウスで実験したのですが、生まれてからいろいろな時期にだしの味を与える。そうすると離乳期前後にだしを与えたマウスは、ものすごくだしの味を好きになるんです。離乳期というのは、母乳を飲みながら母親が食べている餌を覚えていく時期。その時期に子供は「これからこういう餌を食べていくんだ」という情報収集をしているんです。その時に味わったモノは、大人になってからも好きな味です。人間で言えば、離乳食で日本的な、だしの味わいのものを食べさせるべきだと考えています。 |
−− |
離乳食も市販されているものが数多くありますよね。 |
伏木 |
離乳食は買うものではないと思います。僕らの子供の頃は、母親が食べるものをちょっと薄味にして軟らかくして食べていました。それは親の味を子供に伝えるという意味でとても良いことです。 でも今の若いお母さんたちは、いかに子供を効率よく大きく育てるかってことを考えるでしょう? 平均より下だったら、ショックを受けたりする。日本の伝統的な味付けの食べ物というのは、必ずしも子供が最も早く大きくなる食事ではありません。欧米から輸入された高脂肪、高たんぱくの離乳食の方が、早く大きくなります。しかしそれと引き換えに子供は日本の味を全く知らずに、幼稚園まで育ってしまう。そうすると、だしを与えてもそれをおいしいと思わなくなります。 でも今の若いお母さんたちは、いかに子供を効率よく大きく育てるかってことを考えるでしょう? 平均より下だったら、ショックを受けたりする。日本の伝統的な味付けの食べ物というのは、必ずしも子供が最も早く大きくなる食事ではありません。欧米から輸入された高脂肪、高たんぱくの離乳食の方が、早く大きくなります。しかしそれと引き換えに子供は日本の味を全く知らずに、幼稚園まで育ってしまう。そうすると、だしを与えてもそれをおいしいと思わなくなります。
向こうが知らない間に、刷り込んでしまえということです(笑)。 |
−− |
親の味を受け継ぎ、なおかつ個々の食文化がある。つまり「おいしいものはこれだ」というものはないということですね。 |
伏木 |
すべての人にとっておいしいのは、だしと脂肪と砂糖。それ以外は、文化で食べるか、情報で食べるか、生理的欲求で食べるか……その違いです。それらは、如何様にも出来るもの。出身地が違うだけで、卵焼きのおいしさは違うわけだから、普遍的においしいものなんてないわけですよ。だからこそ、正しい食事を小さい頃に伝えることが大切です。そこでの経験が「おいしさ」を決めていくのですから。 |
| |
| インタビュア 飯塚りえ |
|
| 伏木 亨(ふしき・とおる) |
| 京都生まれ。京都大学農学部卒業。現在京都大学農学研究科教授。専門は食品、栄養学。主な著書に『子供を救う給食革命』(新潮社)、『食品と味』(光琳)、『ニッポン全国マヨネーズ中毒』(講談社)、『グルメの話おいしさの科学』(恒星出版)、『魔法の舌』(祥伝社)『うまさ究める』(かもがわ出版)など。 |
|
|