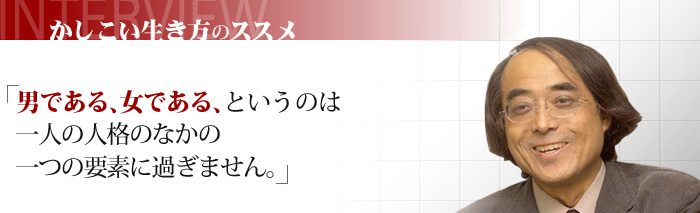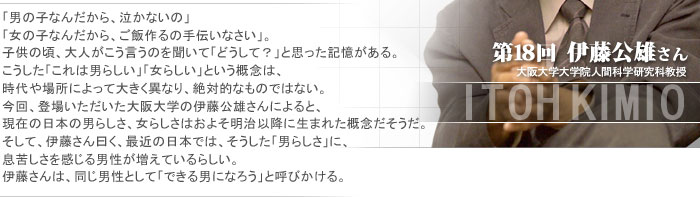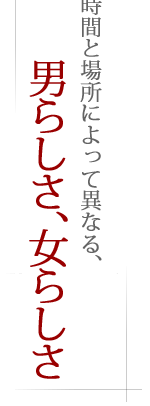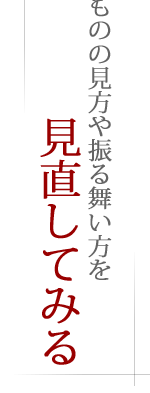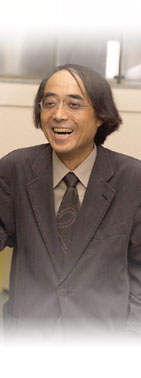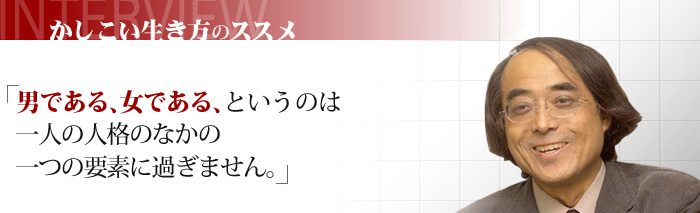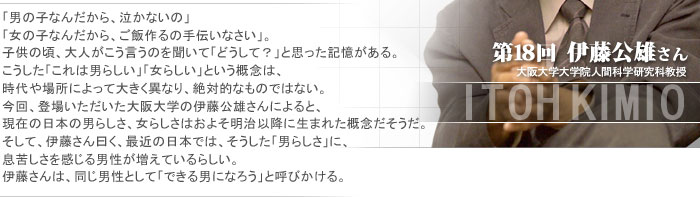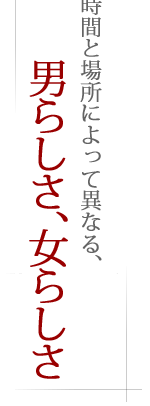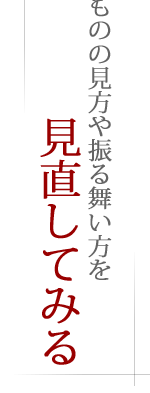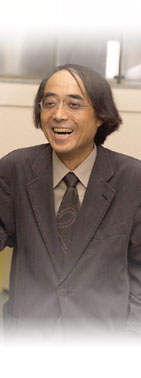|
 |
−− |
私達は、文化的な「刷り込み」によって無意識のうちに、男性と女性を区別している、ということは確かにありますね。 |
| |
伊藤 |
毎年、新入生に次のような質問をしています。
「お父さんと息子が交通事故に遭い、お父さんは即死、息子は救急病院に運ばれました。運ばれた病院で男の子の手術をしようとした外科医が、子供の顔を見て驚いて言いました。『私には、この子の手術はできません。なぜならこの男の子は、私の実の息子だからです』。さて、この外科医と男の子の関係は?」
これに対して「男の子は、この医師が精子を提供して体外受精で生まれた子だ」「医師は離婚していて、一緒に事故に遭った人は義理の父だ」などなどひねった答えが出てきますが、一番簡単な答えが、なかなか出てこないんです。つまり「外科医は息子の母親だった」。10代の学生でも「外科医=男性」という固定的な意識がある、ということです。こうしたジェンダーを巡る無意識な概念が、私達には染みついているのですね。
|
|
−− |
私もこの質問をされた時、最初に「どういう関係だろう」と一瞬考え込んでしまったことに、自分でも驚きました。 |
|
伊藤 |
日本でも、80年代の後半からジェンダーという概念を含め、男女平等の動きが盛んになり始めましたが、僕は男なので、男性の立場から、そうした男と女の関わりの再編成を考える必要があるだろうと考えました。
いざ男性に光りを当てて男女の問題を考えると、男女の性に対する固定的な社会認識の中で、男性自身が幸せに生きているか、というと、自信を持ってそうだと言える状況にもない。実際に90年代に入ると男性が抱えている問題が、日本でもクローズアップされてきました。例えば年間数万件もある過労死の問題。80年代末から90年代後半になると40、50代の男性の自殺が急増しました。もちろんリストラなど経済的な要因がありますが、その背後には、弱みを見せるな、感情を表に出すな、自分の問題は自分一人で解決せよ、といった「男らしさ」があるのではないか、それに縛られ、一人で背負い込んで、背負いきれなくなって、自殺という最後の一線を越えるようなことがあるのではないでしょうか。
|
|
−− |
最近は少なくなったかもしれませんが、炊飯器も洗濯機も使えないという男性がいますね。 |
|
伊藤 |
これまで男性は仕事社会に生きてきたために、生活力がなくなってしまったのではないかと思います。中高年男性は特に、自分の身の回りのことができないという人も多いのではないでしょうか。
こうした戦後の日本の男女の働き方や生活の仕方というのは、女性を苦しめている一方で、男性も豊かとは言えない人生を生む結果になってしまった部分があると思います。男性自身が、今までの生き方を点検しながら、夫婦関係、地域関係、子供との関係、また仕事以外の自分の生き方を見つける、あるいは選択できるようになっていった方が、女性にとっても、男性にとっても、さらには子供たちにとっても、ハッピーな生活になるんじゃないかと思います。
ただ、最近は、定年後の生き方を巡る本が盛んに出版されるなど、男性の意識も変化しつつあります。30代の男性は、妻がフェミニズムの洗礼を受けているので、家庭生活を送り始めた時に「家事は協力してやりましょう」と言われているし、定年を前にした50代の男性、つまりがむしゃらに仕事をしてきた世代ですが、定年を前にこれまでの人生を見つめ直し、定年後をどう生きようか、と考え始めています。男性=仕事をするということだけではない、新しい価値が模索され始めているのではないでしょうか。長い目で見た時には、国際的な流れの中で、より大きな地殻変動を求められるでしょうし、仕事も生活もバランス良くできる社会を、また制度を整えなければならないと思います。
実際、私は家事や子育てをしましたが、小さい頃の子供との触れあいは何ものにも代えられないし、保育園の送り迎えで自然と近所との繋がりもできて、道を歩けば声をかけてくれる子供もけっこういます。買い物だってやってみればとても楽しく、ストレス解消にもってこいです。日本の男性は、こうした家族や地域社会との繋がり、さらには環境をも犠牲にしながら、70年代以降の高度成長を達成したと言えるでしょう。その一方で、多くのところでその歪みも出始めている。バブルも崩壊した今、性別分業のままに経済の回復を達成しようというのは、難しいのではないでしょうか。
|
|
−− |
それは女性の生き方と男性の生き方を均質なものにしよう、という意味ではありませんね。
|
伊藤 |
ジェンダーフリーというと、男女の性差をなくしてしまうことだという議論がありますが、これは違います。性差の解消ではなくて、性差別をなくしましょうと言っているのです。女性が妊娠出産する性だということに対する配慮は忘れてはいけません。男女の性を機械的に同じにすると考えるのは論点をはき違えていると思います。
生物学的に男である、女である、というのは多様な要素で成り立っている人格のなかの一つの要素でしかありません。問題は、その一つの要素を取り上げて「あなたは男だから、女だから」と決めつけて考えることです。一人一人の多様性をもっと認識する。それがこれからの生き方だと思います。
今までは、男と女で社会を分けていた、いわゆる二色刷りの世界です。ジェンダーフリーを誤って解釈する人は、それを一色刷りにすることだと勘違いしています。そうではなくて多色刷りにするんです。一人一人が、色を持っている。更に自分らしさも固定的なものではないし、今日の自分と、明日の自分は違うはずです。いつも変化しながら、自分らしさをもっと軽やかに考えながら、一方で自分を見つめる生き方が問われているのだと思う。私達が自覚すべきは、男である、女であるというのは、自分の多様な要素の中の一つに過ぎないということです。
|
| |
| インタビュア 飯塚りえ |
|
| 伊藤公雄(いとう・きみお) |
1951(昭和26)年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科教授。京都大学卒業、京都大学大学院文学科修了。
主な著書に『男らしさのゆくえ』(新潮社)、『男性学入門』(作品社)、『女性学・男性学』(共著・有斐閣)などがある。内閣府男女共同参画会議基本問題調査専門委員会委員、大阪府男女協働社会作り審議会快調代理など男女参画の政策にも携わる。 |
|
|