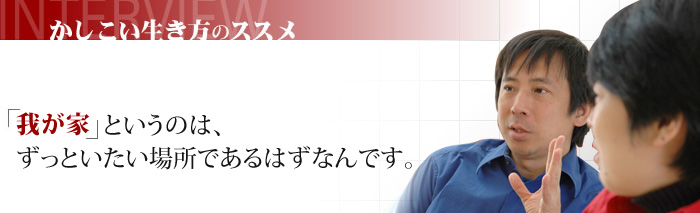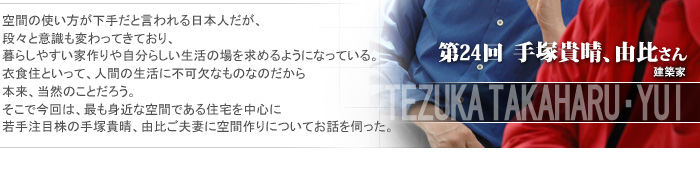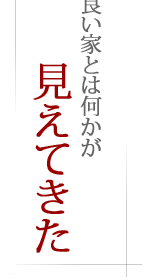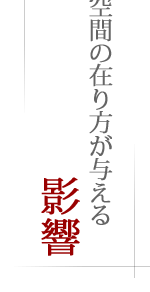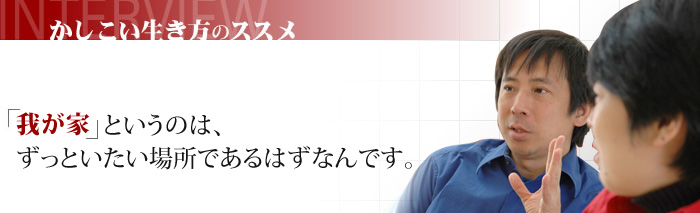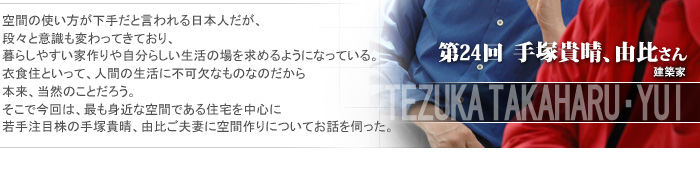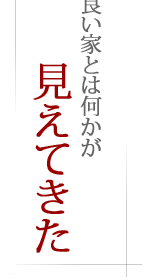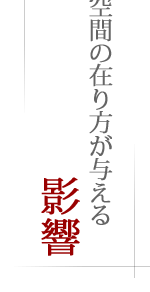|
 |
−− |
手塚さんが手掛けれられた住宅を拝見すると、いわゆる「LDK」と言われる空間とは違う空間の作り方をされているように感じます。手塚さん自身、どのような空間を作り、そこでどのような暮らしを提案したいと考えておられるのでしょうか?
|
|
貴晴 |
そこに「長いこと居たい」と思えるような、家族が一体となるような家を作りたいですね。子供が自分の部屋にこもって出てこない家というのは、感心しません。子供を仲間はずれにするような作りではなくて、仲間に入れてあげる。皆が当たり前に話をして、いつもコミュニケーションをとっていれば、気持ちのズレも生じないと思う。そういう家を作りたいですね。
昔の日本の家というのは、大家族に対応できる柔軟な空間でした。それがいつの間にか、中途半端に西洋の形を入れたことで崩れてしまった。 |
|
−− |
西洋の形と言うと? |
|
貴晴 |
ベッドルームがいくつあって、リビングがあってという形です。それを導入するにあたって、部屋の「大きさ、広さ」が伴ってこなかったのです。本来「リビングルーム」というのは、その中に全員が集まれる広さを持っていて、皆が集まっても、お互いのことを気にしなくて良い広さがあった。日本は、そこを考えずに空間を切っていったから「リビングルーム」が本来の役割を果たせないのです。 |
|
由比 |
 家というのは、家族が暮らす場ですから、お互いに迷惑をかけあわずには暮らせない。「屋根の家」の場合、一つの大きなワンルームになっているのですが、おねえちゃんがそこで宿題を始めると、妹は気を遣ってテレビの音をイヤホンで聞いたりする。そんな風に家族がお互いに相手のことを気にしながら暮らしていくことで、社会性が身に付いていくのだと思います。個室にとじこもって「誰にも迷惑をかけないから何をしても良いよ」という環境より、何かしたら、皆に迷惑がかかるという環境で、お互い気を遣いながら暮らしていく方が良いのかなと(笑)。 家というのは、家族が暮らす場ですから、お互いに迷惑をかけあわずには暮らせない。「屋根の家」の場合、一つの大きなワンルームになっているのですが、おねえちゃんがそこで宿題を始めると、妹は気を遣ってテレビの音をイヤホンで聞いたりする。そんな風に家族がお互いに相手のことを気にしながら暮らしていくことで、社会性が身に付いていくのだと思います。個室にとじこもって「誰にも迷惑をかけないから何をしても良いよ」という環境より、何かしたら、皆に迷惑がかかるという環境で、お互い気を遣いながら暮らしていく方が良いのかなと(笑)。
|
|
貴晴 |
ただし、空間が狭いと、それは無理ですね。 |
|
由比 |
一定の広さが大事ですね。本当に狭い空間の中で、お互いに違うことをしようとすると辛い。広ければ、多少相手を気にしながらも、自分のことに集中できますから。 |
|
−− |
家が人を変え得るということでしょうか。これまで設計をされてきて、それを感じたことはありますか? |
|
貴晴 |
「屋根の家」の奥さんは中学校でカウンセラーをしていたのですが、グレれている学生をご自宅に連れて来るんだそうです。屋根の上に上ってごろんと横になりながら話をすると、皆、憑き物が落ちたように人が変わっていくと言うんです。いじめられる側と、いじめる側が「屋根の家」では、同じ景色を見て互いに言葉に交わしたりする。
どういう状況に置かれるかよりも、どういう環境にいるかで人の心が変わっていくということがあると思います。写真には映りませんが、空間って、すごい力をもっているんです。 |
|
由比 |
本当に気持ちの良い家に住むと、休日に、皆家から出なくなってしまうんですよね(笑) |
|
貴晴 |
日本人は、休日になると出かける人が多いですが、要するに、家の中にいられないから出かけることになる。「ホーム」、「我が家」というのは、本来ずっといたい場所であるはず。以前、設計を手掛けたある家で、「この家ができたら、あとは何もいらないわね」と言われたことがありました。住むところ─つまり家があって食べるものがあれば何の不自由もない。それが本来の家の在り方だと思いますし、最高の生活だと思います。
|
|
−− |
なるほど。現在のブームには、ともすると、格好良いデザインという面に目が行きがちです。そうではなく、そこからさらに一歩進んで、そこに住んで初めて分かるものが空間にはあると。
|
|
貴晴 |
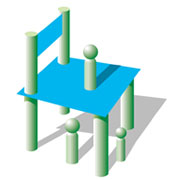 家は椅子に似ています。面白い椅子なら、いくらでも作ることが出来ますが、座りにくい椅子は、すぐに売れなくなってしまうし、飽きてしまう。椅子なら買い換えれば良いけれど、家はそう簡単に捨てられるものではありません。住みやすくて、気持ち良いと思ってもらえるものを作れば、長く使ってもらえるはず。 家は椅子に似ています。面白い椅子なら、いくらでも作ることが出来ますが、座りにくい椅子は、すぐに売れなくなってしまうし、飽きてしまう。椅子なら買い換えれば良いけれど、家はそう簡単に捨てられるものではありません。住みやすくて、気持ち良いと思ってもらえるものを作れば、長く使ってもらえるはず。
|
|
−− |
椅子だったら実際に座ってみて判断することもできますし、買い替えることもできます。しかし住宅の場合は、そうした「良さ」を、どう判断すれば良いのでしょうか。
|
|
由比 |
「こういうのが気持ち良い空間だ」というのは、おいしい料理を食べたことがない人がおいしいものが分からないように、やはりある程度、経験がないと分からないところではあります。
しかし、おいしいものって人それぞれ全く違うというわけでもなくて、やはり本当に美味しい手打ちのお蕎麦は8割位の人がおいしいと言う。建物も同じで、皆が共通認識として「良い」と思えるものがあると思うんです。
|
|