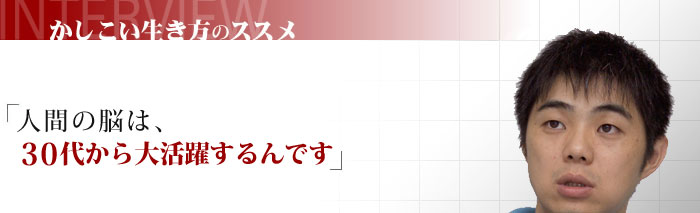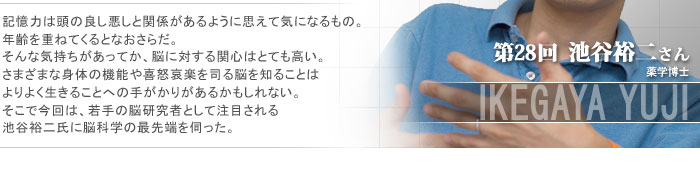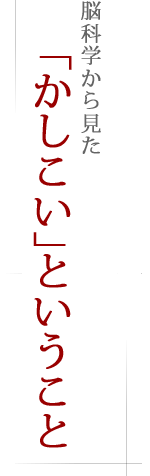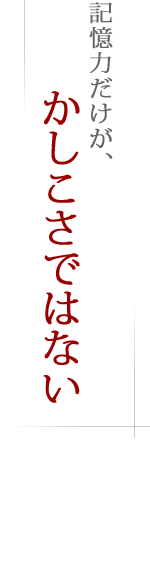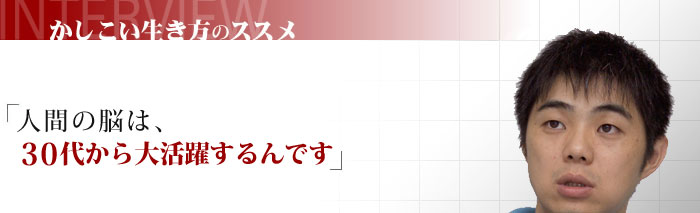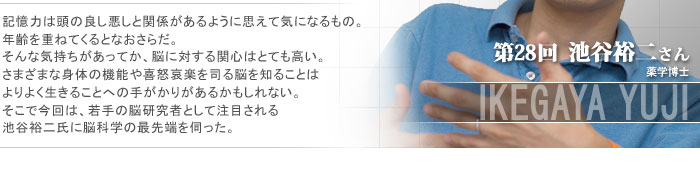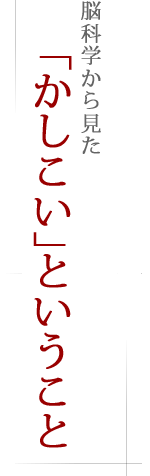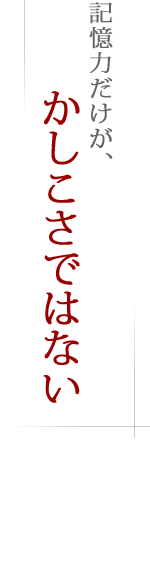−− |
そのθ波とγ波は、脳にどのような作用をするのでしょう。 |
|
池谷 |
脳の神経細胞は、一度結合してネットワークを作ると、かなり固く結びつくのですが、この二つの波を組み合わせた電気刺激を与えた時だけ、神経細胞の組み合わせパターンが緩やかになり、ダイナミックに変化するようになるんです。僕は「神経細胞が柔らかくなる」という表現を使っています。つまり、アセチルコリンが働いていて、θ波とγ波が脳波として出ている状態というのは「脳が柔らかい状態」と言え、神経細胞の結びつきが密になったり、つなぎ直したりするのです。
また、アセチルコリンは、この量が高まると記憶力も高まり、これが低くなると集中力や記憶力が低下することが分かっています。人によってリズムは異なりますが、普段の生活では、集中力が高い状態と低い状態というのがあるはずです。このかなりの部分をアセチルコリンが左右しているというか、アセチルコリンで説明できるのではないかと思います。
|
|
−− |
体によって脳の働きが変わるという実験をテレビで観たことがあります。左右が逆に見えるような装置を付けて1週間過ごすというものです。最初は、あちこちにぶつかり食事をしてもぼろぼろとこぼしていたのが、そのうちすんなりと動けるようになる。それと同時に脳の活動分野も変化していました。これは身体の形態によって脳の仕組みが決まることがあるということに非常に驚きました。 |
|
| 池谷 |
そうです。そこまで劇的な脳の変化は、残念ながら、日常生活の中ではありませんが、それでもちょっとした変化は、起きます。普段から利き手ではないほうの手で歯を磨いたり、箸を持つことで、脳の活動の部分が広がったりします。 |
| |
|
−− |
それは活発な脳にとって良いことですか。 |
| |
|
| 池谷 |
 何とも言えないですが、そうやって、できるだけたくさんの分野を使うことは、良いことなのじゃないかと僕は思っています。とりわけ、脳がたくさんの領域の面積を割いている、指や舌を刺激する方が良いのではないかと考えています。 何とも言えないですが、そうやって、できるだけたくさんの分野を使うことは、良いことなのじゃないかと僕は思っています。とりわけ、脳がたくさんの領域の面積を割いている、指や舌を刺激する方が良いのではないかと考えています。
僕自身「脳がこうなっているから、こうしたら良いだろう」と考えて、過ごしてはいます(笑)。例えば、毎日、同じルーチンワークをしなければいけない時も、時間単位で区切ってみたり、栄養というより、脳に気を遣って食事に変化を持たせたり……。それはもちろん、それが脳に良いと信じているからなんですが、実際の効果はよく分かりません(笑)。
|
−− |
物質としての脳のお話を伺ってきましたが、気になるのが脳とコンピュータの関係です。 |
| 池谷 |
脳とコンピュータの大きな違いは体だと思います。しかし、多くの人がそれを忘れているのではないかと思うのです。例えば、主人公が自分の体を捨ててネットの世界で生きるというアニメがあったり、「電脳」という言葉が流行ったりしていますが、そうした発想が出てくること自体、体の重要性を忘れていると思うのです。コンピュータ至上主義とでも言いますか、一度聞いたことを忘れない、写真のように物事を記憶する・・そうしたコンピュータのような正確性や確実性を脳に要求する傾向がありますが、それは間違っていると思います。
だって人間の脳が忘れやすいからこそ、紙と鉛筆という道具が生まれて、忘れないように紙に書き留めるようになったわけですよね? そうした道具が進化したところにコンピュータの登場があるのではないでしょうか? 苦手分野を補うべくコンピュータを作ったのだから、それはコンピュータに任せておけば良くて、漢字を1,000個、2,000個暗記した……暗記できるのが「かしこい」……そういう考え方自体が、コンピュータ的だと思います。 |
−− |
その考え方からすれば、記憶力の良い悪いには意味がないということですよね。 |
| 池谷 |
僕は記憶力がないので「記憶力は重要じゃない」というのは、個人的な意味があるのですが(笑)。それを高める重要性というのは、今の世の中ではないと思いますね。
全般に、記憶力が高いと言われる人は、イマジネーションが弱いと言われています。というのも人間のイマジネーションは、記憶力の曖昧なところをつじつまを合わせることから出てきているからだと思います。記憶力とイマジネーション、どちらを取っても、本人の勝手だとは思いますが、今、現在のコンピュータではイマジネーションがないから、人間はイマジネーションを取ったほうがベターではと言っているのですが。 |
−− |
脳の性質として、勝手にこじつけたものを明確な記憶として意識してしまうところがあるんですよね? |
| 池谷 |
そうすることによって、記憶の容量が減るんです。写真を見た時に、コンピュータは記憶するドットの数だけデータ量が必要になりますが、脳は、入力された情報を過去の経験に則って分類して「ここはあれに似てる」と、言ってみれば勝手に補っていくんです。そうすると覚えなければいけないバイト数が減りますから、思い出すのも楽なのでしょう。 |
−− |
その、脳が勝手に記憶を作ってしまうということを示すものとして、ご著書に掲載されていた実験は、非常に衝撃的でした。(『海馬』参照) |
| 池谷 |
そうして脳が勝手に記憶を作っていくのは、記憶には限界があるからで、それを経験で補うということを脳が行っているんです。実は脳の活躍は30代からが本番だと、僕は思っています。
先ほど、脳は「これに似ている」と過去の経験に即してデータを記録していくとお話しましたが、年を経れば減るほど参照できる事例がたくさん蓄積されていますから。もちろん、それまでの蓄積が重要ではあるのですが、それらの蓄積を生かすことが出来るのは、かろうじて30歳からだと思うのです。20代だと、脳の再編成がまだまだ起きている頃なのです。再編成が起きているということは、神経細胞が減る時期でもあり、記憶が定着しない。それが30代になると、神経細胞があまり減らなくなり、記憶が定着するんです。神経細胞が固まってしまっているとも言えますが、その残った細胞を、いかに上手く使えるかで、その後の脳の働き具合も変わってくるのだと思います。
と言うと、「どうやれば、脳を上手く使えるのか」と問われることもあるのですが、それは人それぞれ価値観が違うので、僕には答えられません。結局は、その人が目指す通りに生きることがかしこく生きることに繋がるのではないかと思います。 |