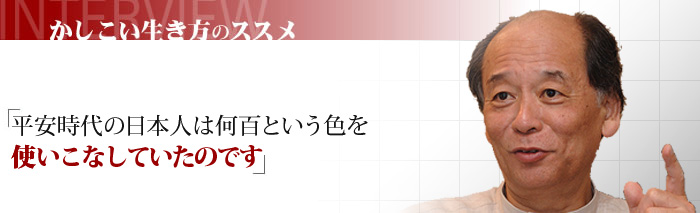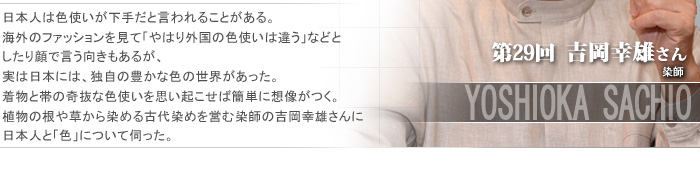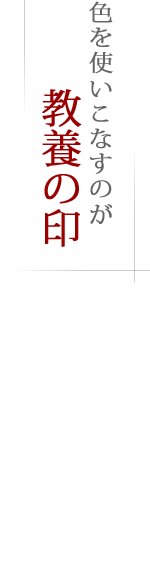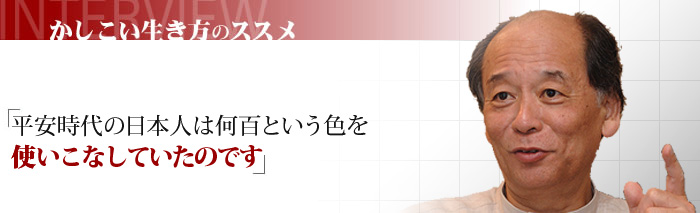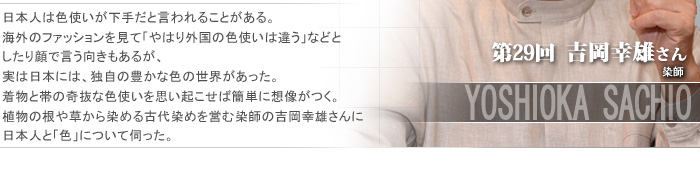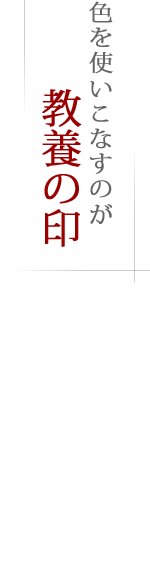吉岡 |
平安時代になると、更に色が発展しました。一つの日本らしい形が出来てきたといってもいいでしょう。
それ以前、奈良時代までは、建物などを見ても、中国や韓国に追いつけ、追い越せという意識が強い印象を受けます。ところが平安時代になると、ひらがなの発明があり、それを用いて歌を詠むようになります。その時、 主題となったのが季節感でした。日本の四季の移り変わりを楽しみ、尊び、歌に表現していったのです。そして、そこに色も加わりました。自然と色と人間の生活はイコールですから、例えば、桜の季節には桜の色の着物をまとい、山吹の花が咲く季節には山吹色の服をまとう。そうして季節感を出す事が教養と見なされていたのです。 主題となったのが季節感でした。日本の四季の移り変わりを楽しみ、尊び、歌に表現していったのです。そして、そこに色も加わりました。自然と色と人間の生活はイコールですから、例えば、桜の季節には桜の色の着物をまとい、山吹の花が咲く季節には山吹色の服をまとう。そうして季節感を出す事が教養と見なされていたのです。
でも「桜の季節には、皆、桜色の着物をまとっていたのか」というと、そんな事はありません。宮中の人は皆、工夫した桜襲を着てくるんです。中には、季節を先取りして、やまぶきを着てくる人もいるだろうし、桜と柳を合わせたりする人もいたでしょうね。そうやってセンスを磨いて競うんですね。
|
|
−− |
現代の生活では「桜の季節だから、桜色を着よう」と考える人は少ないでしょうね。
|
|
吉岡 |
清少納言は「なんて恐ろしい事なんでしょう。4月なのに、紅梅色の着物を着ているなんて」と書いています。季節音痴な人は、そんな風に扱われてしまうんです。
平安時代とは、いわば季節を感じる事が教養であり、それにまつわる儀式においての色選びが、ひとつの仕事でもあった時代です。そうした背景があって、日本の色というのは発展したのではないでしょうか。
他にも『源氏物語』は、色についての描写が非常に細かい。私は『源氏物語』を色の物語だと思っているくらいです。作者の紫式部は、平安朝の人がどういうシーンで、どういう色の着物を着ているのかを詳細に書いていて、秋口に、萩や女郎花の色の着物を召している事が「時に合いたる」、つまり「時節に合って素晴らしい」などと言っていますし、紫の上や藤壺など、主要な登場人物は、紫を連想させる名前が必ずついているんです。
|
|
| −− |
光源氏を軸とした登場人物の関係が、色で表現されているなんて興味深いですね。 |
| |
|
吉岡 |
平安朝の人は、本当によく色を使いこなしています。色の名前も300から400色くらいあります。『源氏物語』の他に、『栄華物語』、『枕草子』にも色がたくさん出てきます。それだけ、色にこだわっていたという事です。 |
| |
|
| −− |
現代の人の色の感覚をどうお感じですか。 |
| 吉岡 |
皆、色を使うのを怖がっているように感じます。まず黒が多過ぎますね。一つは化学染料の影響もあるのかもしれませんが、色の使い方を知らないのでしょうね。私は染めを色彩学を教える機会がありますが、その時に良く「自然の色を見なさい」と言います。自然は色の宝庫ですからね。 |
| −− |
吉岡さんがなさっている古代染めとはどのようなものなのでしょう。 |
| 吉岡 |
古代染めのルーツは、 弥生時代まで遡る事が出来ます。権力者が、目立つ色を求めた事から染色が始まったとされています。工房では、染めの原料となる木を削ったり、染料となる植物を畑で育ててるところから行っています。これも昔の人がやってきた事。稲作など食料の栽培からはじまり、染色の発展とともに染料や繊維の材料となる植物も栽培するようになっていました。更に大陸から染色や織りの技術が入ってきた事で、日本での「衣」は、だいたい1500年前にはほぼ完成していたと言えます。だから私の仕事は、その時代と変わらないという事ですね(笑)。 弥生時代まで遡る事が出来ます。権力者が、目立つ色を求めた事から染色が始まったとされています。工房では、染めの原料となる木を削ったり、染料となる植物を畑で育ててるところから行っています。これも昔の人がやってきた事。稲作など食料の栽培からはじまり、染色の発展とともに染料や繊維の材料となる植物も栽培するようになっていました。更に大陸から染色や織りの技術が入ってきた事で、日本での「衣」は、だいたい1500年前にはほぼ完成していたと言えます。だから私の仕事は、その時代と変わらないという事ですね(笑)。
最近は、染料と体の関係も研究され始めているんですよ。皆さんあまり気付いていませんが、毎日着ている衣服を通して、皮膚から入っていくものが体に影響を与えているんです。食べ物を口にするのと同じです。例えば昔は、紅染めの肌着を付けていましたが、紅は血行をよくする作用があるため、長時間身につける事で循環機能を高める効果があったんです。
|
−− |
当時、人々はその効果を知っていて、紅を用いていたのでしょうか。 |
| 吉岡 |
そうです。現代のように化学的根拠はなくとも、経験からそれを選んでいたのです。実は、植物染料というのは、漢方薬と共通する材料が多いんです。紫色の原料となる紫恨(しこん)も、古くは紫雲膏という火傷の塗り薬として使われていたもので、新陳代謝が高まるという理由から、今でも化粧品にも使われていますし、藍の匂いは虫や蛇が嫌う作用があるので、野良仕事の時には持ってこいですね。 |
−− |
精神的な豊かさと、物理的な豊かさと、色には深い意味があるのですね。今日は有り難うございました。 |