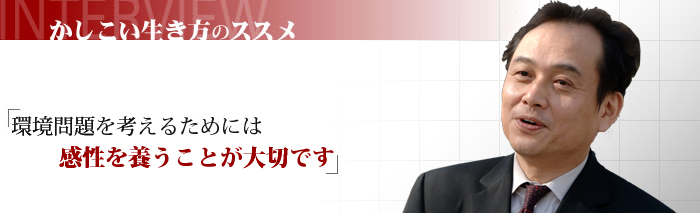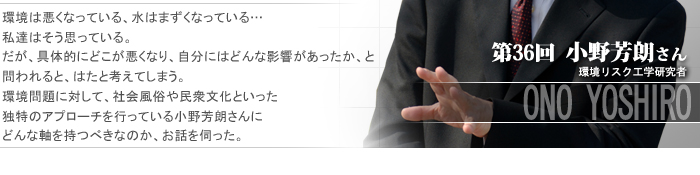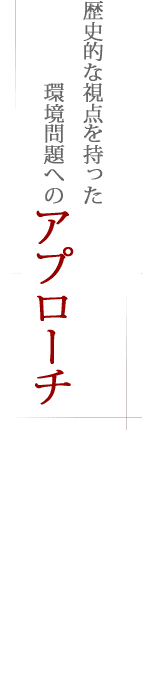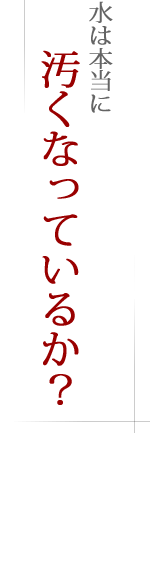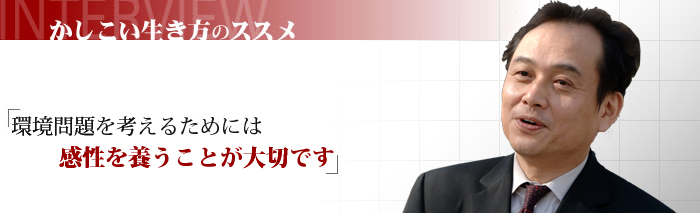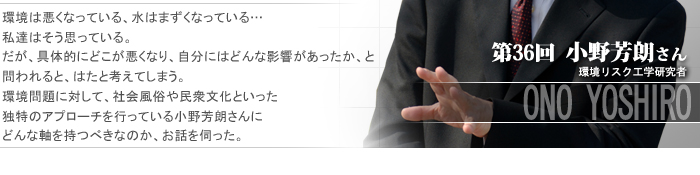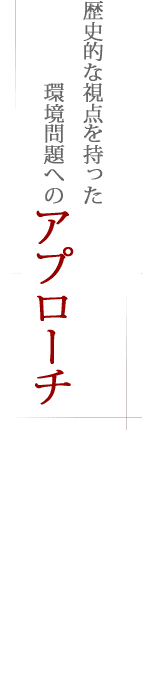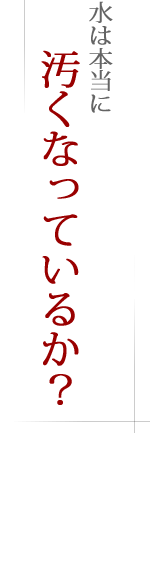−− |
小野さんは、資源循環理論や環境リスク工学を専門とされながら、歴史的な視点を入れる事で環境問題を解く「環境史」という独特のアプローチをとっていらっしゃいます。なぜ、そのような方法を選ばれたのでしょうか? |
小野 |
今、環境の研究というのは、一言で言えば「モノ」を対象にしています。水ならば水そのものの中に含まれているものを調べ、それが何かを研究する。例えば、ちょっと前に、川の水の中に含まれる環境ホルモンが話題になりましたが、これは先端の研究によって、人間の女性が出している女性ホルモン(エストロゲン)が、いわゆる環境ホルモンとして作用する主な原因だと分かってきました。 |
 |
|
| −− |
女性ホルモンですか?! |

|
|
小野 |
 そうです。特に魚に対しては、女性の尿に含まれているホルモンが処理されず川に流れ出て、それによって川の魚がメス化するという仕組みです。他にも人間が服用してやはり尿から排泄される医薬品も、環境ホルモンと関連があります。しかし良く考えてみてください。こうした現象は、おそらく昔から起こっていたはずです。ということは、果たしてそれだけを問題にすれば良いのでしょうか。 そうです。特に魚に対しては、女性の尿に含まれているホルモンが処理されず川に流れ出て、それによって川の魚がメス化するという仕組みです。他にも人間が服用してやはり尿から排泄される医薬品も、環境ホルモンと関連があります。しかし良く考えてみてください。こうした現象は、おそらく昔から起こっていたはずです。ということは、果たしてそれだけを問題にすれば良いのでしょうか。
環境の研究が常に「モノ」に向かってきたのは、一つには分析技術が高度に発達したためです。モノが測れるというのは「これだけあります」と言えるようになったということですが、裏を返せば、昔は分からなかっただけ、とも言えます。環境ホルモンは見えないものだから「実はこうですよ」と数値が出れば、一般の方は「おお!」と反応してしまうでしょう。このように「モノ」の研究に、重点が置かれていることが、環境問題の「問題」なのであって、その情報に対して怯えたり驚いたりしているのが、現状だと私は思うのです。
更には、環境が悪いのなら、どんな状態が良いのかという議論も抜けています。実際、環境問題というのは、今だけの話ではない。そこで歴史上起こった様々な環境問題を、人々がどのように受け入れようとしたのか、そして受け入れる人々の「感性」の話をできないか、そんなことから、歴史をひもとくことで環境問題を調べ直そう、考え直そうと思ったのです。
|
−− |
それが、例えば日本で行われた博覧会の様子を調べることに結びついたのですね。 |
 |
|
小野 |
「博覧会」というのは、都市に新しい装置を持ち込む時の実験場の役割も果たしています。そのため、それらを調べていくことで、当時、どんなことが流行ったか、新しい価値観がどうやって持ち込まれたかなどを見る一つのきっかけになります。 |
−− |
博覧会では、水の設備についても実験がなされたようですね。環境を見る上で、一つの軸になるのが、水だと思いますが、日本は、水がおいしくまた豊かだと言われていました。ところが最近では水道水は飲めないと思っている人も多いと思います。 |
小野 |
日本は水が非常に豊富です。何と言っても地球上の全降雨量のほぼ6割が、日本と中国の南と東南アジアを含めたエリアに降るんですから。それが、日本の、水との文化を生み出したと言えます。
降ってくる水ばかりではありません。地下水も非常に豊富です。京都は、山紫水明の地といわれるように、昔から水が豊かな地域です。中でも鴨川周辺は良い水が湧き出ます。最近では、京都盆地の下に、琵琶湖に匹敵する膨大な量の地下水があることが明らかになりました。これは琵琶湖の地下に、自然のダムがあるようなものです。一方、関東地方に目をやれば、関東ローム層という火山灰の上に位置する江戸も、木や植物を閉じ込めた関東ローム層が、自然の濾過装置として働いて、非常においしい水を作る役目を果たします。そうした良い水がある場所には、昔から幕府が置かれたり、御所が置かれたり、貴族が住んだりしていますが、これは決して偶然ではないと私は思います。
それでは、なぜ水が汚くなったのかを考えてみましょう。一つは、下水道の整備の遅れが理由だと思います。欧米の下水道普及率は、ほぼ100%ですが、日本はまだ60%強なんです。
水道、つまり上水道というシステムができたのは、東京では1897(明治30)年、大阪では95(明治28)年、京都では1912(明治45)年。これを境に、全国30くらいの都市に上水道システムが広まりました。この時、水道が整備されたのは、伝染病が大きな理由です。当時、コレラの流行によってパニックが起こったんですね。それで水道を作るべきだという気運が高まったのです。
ですが、上水道というのは水が少ないヨーロッパで作られたシステム。私は日本に水道が必要だったのかと、半分疑問に思う部分もあります。日本では、地下水からの井戸水を使っていたのですが、先に言ったように、日本の地下水は非常に質が良い。それが伝染病で汚されたと言うならば、伝染病は環境ホルモンと同じく人間の体から出てくるのですから、衛生学的には上水道よりも、むしろ下水道をきちんと整備した方が良いはずなんです。ところが、下水道に先駆けて上水道が作られたのです。確かに、都市化が進み、家が建て込んできたために、井戸とトイレが近くになって屎尿が井戸水に混入する恐れが生じたという理由もあったでしょう。しかし、理由はそれだけではないはずです。上水道ならば、水道料金としてお金が取れる…そういう判断もあったと思うのです。 |
−− |
日本は、豊かな水資源を持っているとのことでしたが、かつてのようなきれいな水を取り戻すことはできないのでしょうか。 |
小野 |
地下水をもう一度利用するのが、一つの方法でしょう。本来は清潔できれいだった水の環境が、伝染病が入ってきたことで水道水に切り替わったわけですが、水道水というのは川や湖、つまり地面の上に溜まっている水です。誰でも触れることができる、汚れやすい水なわけです。ならば、誰の手にも触れない地下水をどう使うかを考えた方が良いはずなのです。
ただ残念ながら、現在、地下水は産業用水として使われ、枯渇し始めています。それが日本の水資源の問題です。雨は多いのに、地下に水はない。ナンセンスな話です。例えばベルリンでは現在、地下の水をまた地下に戻す取り組みがなされています。水道の水は、すべて地下水。そうして一度使った水を下水処理した上で、郊外の畑地へ運びスプリンクラーでまく。それが地下に浸透し、それをまた汲み上げて水道水として使っているのです。しかし日本では法律で禁止されているので同じことはできません。下水のような汚い水は、処理したといっても、地下に戻してはいけないという法律があり、すべて川に流しているのです。東京であれば、関東ローム層という素晴らしい濾過装置を使って、おいしい飲料水が得られるはずなのです。研究はいろいろ進んでいますが、実現にはハードルがいくつかありますね。 |