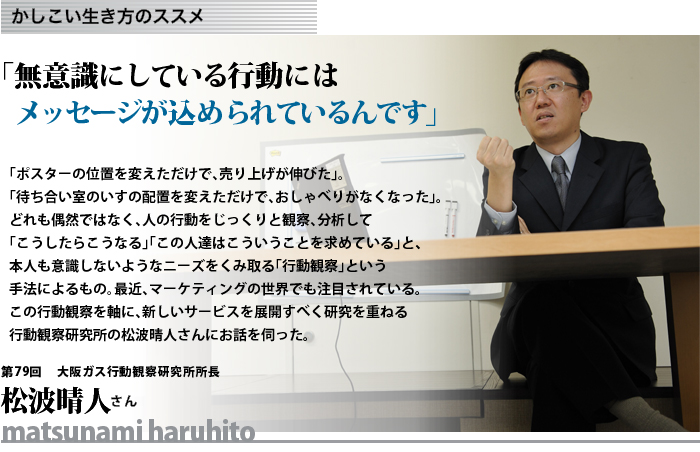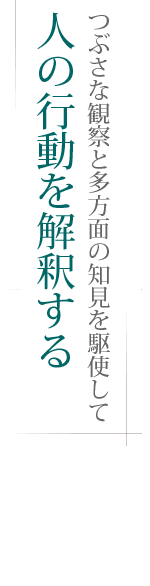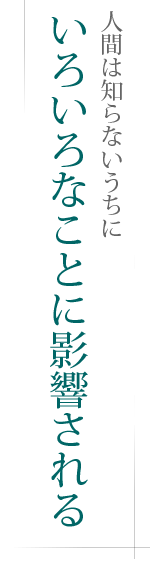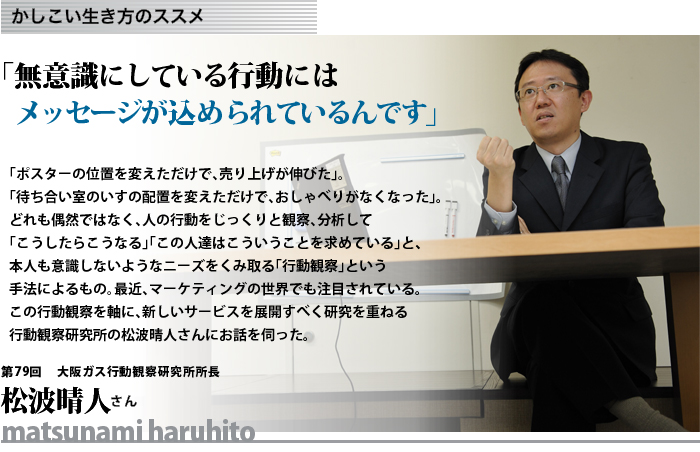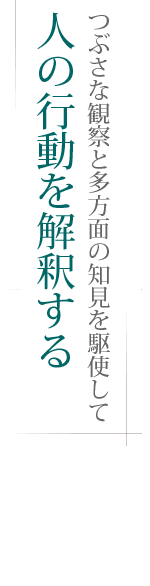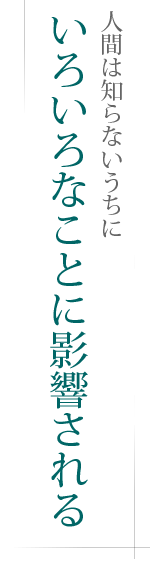−− |
現地に行って見る…言葉は悪いですが、ただ見ているだけで、なぜ分かるのか、不思議な気もします。 |
松波 |
最初にお話したように、エスノグラフィや人間工学、心理学などの知見をベースに行動を解釈するからです。例えば、人間の制約ということで言えば、たくさん数字を並べられても7個程度しか覚えられないとか、視野が決まっていて死角が存在したりするといったことです。 |
−− |
自分で意識していない、自分の行動の理由を知るというのは面白いですね。 |
松波 |
そういう知見は、行動観察を行う上で、非常に重要なんです。例えば、目をつぶってまっすぐ歩こうとすると、多くの人は左にそれていく。それは利き足が右足の人が多いからで、それを知っているか否かで観察から引き出される分析は違ってきます。
またエスノグラフィというのは、本来は異なる文化の人たちと長期間一緒に過ごして、かの地の文化や行動様式を知ることを目的とした学問ですが、それを私たちは短期間ながら行動を共にして、その企業やあるいは家庭、働く主婦の文化や価値観を調べています。 |
−− |
外部からの影響というのもありますね。 |
松波 |
ええ。環境心理学は、物理環境が人間の行動にどのような影響を与えるかを知るための学問です。人間は、自分で意識している以上に環境に大きな影響を受けている。例えば暑い日は、暴力的になります。殺人事件も圧倒的に気温が高い日に多い。あるいは、うるさい部屋と静かな部屋、双方に人を待たせておき、そこに本をたくさん持った人を行かせて、わざと転んで本をぶちまける。すると、うるさい部屋にいた人はほとんど、拾うのを手伝ってくれません。逆に静かな部屋にいた人の多くは手伝ってくれる。 |
−− |
周囲がうるさいかどうかで、自分の行動にそんな風に違いが出るとは、想像したこともありませんでした。 |
松波 |
では、クイズを出しましょう。文法が正しいかどうか答えてくださいという問題です。その問題の中に、高齢者に関係する文章を混ぜておきます。すると解答が終わって帰る時、皆さんの歩くスピードは遅くなっているんです。 |
−− |
え!遅くなる? 具体的に足が遅くなるなどと書いてあるんですか。 |
松波 |
いいえ。「高齢者が座った」「高齢者のスポーツ大会があった」といった文章を読んだ、ただそれだけで影響を受けてしまったということです。
似たようなものに、心理学で言うラベリングというのがあります。子供に「算数が良く出来るな」とラベリングするか「お前はあほやな。頑張らなあかんわ」とラベリングするかで、その後が違ってくる。前者のように良い言い方をしたほうが、圧倒的に成績が伸びるんです。皆さんがよくご存じなのは、血液型です。A型はまじめなどと言われますが、心理学的には、血液型と性格とは全く関係ないものです。でもこれも「A型だからまじめですね」と言われて、まじめになっていくんです。 |
−− |
何だか、単純な…。 |
松波 |
先程オフィスの生産性の話をしましたが、作業効率という点では、オフィスの机の配置といった少々の物理環境の変化よりも、新しいオフィスに移る方が、影響があります。 |
−− |
新オフィス? |
松波 |
 そうです。新しいオフィスに移ると、少々使いにくくても「新しいオフィスは良い」という評価が上がってくるんです。ホーソン効果と言います。ある工場で照明を暗くしたら、生産性がどうなるかという実験をしたことに由来します。暗くしたら作業がしづらくなるので、生産性は落ちるものですよね。でもどんどん向上したんです。なぜかと調べたら「調査員まで派遣して、労働環境を見てくれる」というのが嬉しくて、従業員は頑張っちゃったんです(笑)。ですから、少々の物理環境よりも、大切にしているというメッセージを出すことの方が重要なんですね。新しいオフィスに移るのも同じことです。自分は優遇されているという思いから、少々ひどいレイアウトであれ、最初は皆、喜ぶんです。 そうです。新しいオフィスに移ると、少々使いにくくても「新しいオフィスは良い」という評価が上がってくるんです。ホーソン効果と言います。ある工場で照明を暗くしたら、生産性がどうなるかという実験をしたことに由来します。暗くしたら作業がしづらくなるので、生産性は落ちるものですよね。でもどんどん向上したんです。なぜかと調べたら「調査員まで派遣して、労働環境を見てくれる」というのが嬉しくて、従業員は頑張っちゃったんです(笑)。ですから、少々の物理環境よりも、大切にしているというメッセージを出すことの方が重要なんですね。新しいオフィスに移るのも同じことです。自分は優遇されているという思いから、少々ひどいレイアウトであれ、最初は皆、喜ぶんです。
|
−− |
「最初は」なんですね(笑)。 |
松波 |
だから「良くなりました!」というアンケートの結果は、信用したらだめですよ(笑)。物理的に良いからではなく、「やってくれた」というのが嬉しいから良い評価が出ているだけかもしれない。 |
−− |
自分は理性的に行動していると思っても、実際はずいぶん違うようです…。 |
松波 |
だからこそ、問題を客観的に把握してからでないと、有効な対策が立てられないんです。ダイエットと同じで、自分が何を食べてどれだけ運動しているかときちんと認識してからでないと、有効な対策が立てられず結局やせられない。それが、行動観察が重要な意味を持つ点なんです。 |
−− |
行動観察からサービスを向上させるというプロジェクトが進行しているとか。 |
松波 |
はい。近畿経済産業局と大阪商工会議所が、地域をあげてサービス産業の生産性向上を図るため「関西サービス・イノベーション創造会議」という組織を立ち上げました。今、私達はその調査にあたっています。リーガロイヤルホテルに、車のナンバー、車種、会社、名前、顔、性格を5,000人も覚えているという有名なドアマンがいて、その能力をノウハウ化しようといった取り組みを行っているところです。 |
−− |
5,000人!? 松波さんからご覧になって、そこには一般化できるノウハウがあったのですか。 |
松波 |
あります。観察と、インタビューもさせてもらいました。どうやって覚えているのか、記憶に関する知見をもとに「どんな風に覚えているのですか?」「こんなことをやっていませんか?」と、質問をぶつけていくことで見えてきました。 |
−− |
ご本人は、それを意識されていなかったのですか。 |
松波 |
そうなんです。心理学の知見をもとに、というやり方ではなく、そのご自身の経験で培ったものだったんです。しかしインタビューをしていくと、そのやり方は、やはり認知心理学と合致していました。まだ研究中なので、詳細はお話できないのですが、将来的には調査結果が公開されます。 |
−− |
5,000人もの顔や性格、名前、車種、車のナンバーなんて、とても無理です。 |
松波 |
すごいですよ。その方はオリンピックの選手みたいなもの。天才でした。 |
−− |
それも行動観察という手法によって、そうしたビジネスのノウハウが解明されるというのもとても楽しみです。更に行動観察の考え方は、生き方そのものに生かすことができそうですね。 |
松波 |
はい。僕自身は、観察のために、非常に優秀な人に会いに行く機会が多々ありますが、ものすごく勉強になります。共通項がいっぱい出てきて、僕もそうしないといけないなと思うことがしばしばあります。多くの方が前向きで、かつ冷静に事実を受け止めている、正に行動観察の概念です。ただ理論を分かっているのと、それを実践出来るかというのは別の話でして(笑)。僕もなるべく実践したいとは思っています。取り入れていくのは面白いですよ。 |
−− |
今、何か取り入れていることはあるのですか? |
松波 |
書かないでくださいね。働く主婦の方の行動観察をした時、ある方が自分の娘に「○○ちゃんはクリスマスプレゼントがもらえていいよね」と話されるのを見ていて、確かに主婦はクリスマスプレゼントをもらう機会は少ないだろう。そういえば自分も嫁さんにずっとあげていないなと気付いて、それ以来、毎年あげるようになりました。 |
−− |
とても良い話です! 実際に行動に移すのが、また大変だとおっしゃってますが、松波さんご自身に、奥様を気遣うお気持ちがあればこそじゃないでしょうか。 |
松波 |
そうですか(笑)。それと家事に対してもコメントをするようになりました。体力も使うし、何も見返りもなければ辛いばかり。だから皆さん「自分へのご褒美」という言葉を使うじゃないですか。誰も褒めてくれないから、そう言うわけです。 |
−− |
よく分かります(笑)。戻って考えればお店でも「いつものですね」と覚えていてくれるだけで、大切にされているようで何だか嬉しいものです。 |
松波 |
そうです。人間って基本的に自分のことを過信しているんですよ。客観的に見た自分よりも、もっとすごいと思っている――それが進化の上では正常なんですが、でも、だから周囲から褒められる機会は自分が思っているよりも少ない。だから認めてもらうとすごく嬉しい。ということは「お前、そんな大したことないぜ」と言いたくなっても、言っちゃだめ。人間って、皆自分は論理的に考えて、冷静な判断を下していると思っているけれど、はたから見たらそんなことないんですよ。それを客観的に提示して、解決策を見出そうというのが行動観察の醍醐味ですね。 |