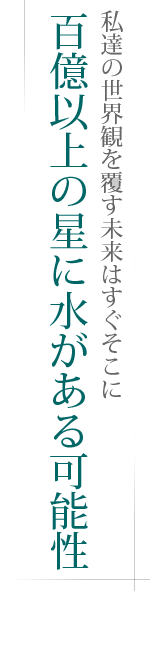−− |
宇宙分野での発見が相次いでいますが、まずはずばり、宇宙には生命体がいるのでしょうか。 |
井田 |
僕は、惑星系の現象それ自体が面白くて研究を続けているんですが、その副産物として「生命がいるかもしれない環境を持った惑星」がありそうだということが分かってきたんです。それで、そちらにも首を突っ込んでいる状態でして、決して地球外生命体の発見を目指して研究しているわけではないんです(笑)。 |
−− |
何が見つかったら生命があると言えるか、ということですね。 |
井田 |
そうです。ですがその議論は話が広がりすぎるので、最初は地球の生命のアナロジーで考えていくしかないわけです。 |
−− |
海は生命の源というのは、そういう意味だったんですね。では、水があれば生命が誕生する可能性があると考えられますか。 |
井田 |
|
−− |
ひと昔前は太陽系以外に惑星はなかったという印象があるのですが...。 |
井田 |
そうなんです。太陽系の惑星は知られていましたが、その他の星の周りを回っている惑星は、長い間見つかりませんでした。それが1995年に最初の一つが見つかったのを皮切りに、現在では450個以上発見され、発表されていないものも含めると1000個近くは見つかっています。それでも技術的な限界があって、観測出来るのは銀河系の中でも太陽系から近い星だけです。それでこれ程の数が見つかっているわけですから、確率的にも夜空を見上げた時に見える星の、少なくとも2個に1個は惑星が回っているだろうと考えられています。 |
−− |
それだけの数の惑星があるということは、地球と同じような環境があるのでは? そこには生命が…と考えたくなりますね。 |
井田 |
惑星の数は一般に思われているよりずっと多く、実際、ほとんどの星が惑星を持っていると言っていいと思います。木星や土星という巨大なガス惑星というのは、大きいが故に見つけやすいのですが、観測技術が向上して、岩石で出来たような比較的小型の惑星も見つかってきています。その観測結果から、先に説明したような、太陽からの適度な距離と空気を保持できる重さを持つ、つまり水のある可能性のある惑星も、そこら中にあるに違いないと分かってきて、地球外生命体が居るのではないか、いるならそれはどんな風に、という議論が急激に活発になってきました。 |
−− |
厳しい環境に適応するため進化せざるを得なかったということなんでしょうか。 |
井田 |
そうかもしれません。遺伝子解析からも、遺伝子はストレスを与えられると進化するということが分かってきています。そう考えるとやはり、紫外線が降り注ぐといった過酷な環境では、遺伝子がものすごく進化しているかもしれないと考えられるわけで、もしかしたら地球なんかより、はるかに高度な生物が居るかもしれません。これまでは、地球での生物や進化といったものが議論されてきましたが、地球外生命体の可能性に近づいたことで、あらためて地球の生命の進化や人類をどう見るのか、急激に世界観が変わりつつあるような状況です。 |
−− |
宇宙における生命の可能性がリアリティを帯びてきて、これまでの価値観が変わるということですね。 |
井田 |
日本が鎖国していた時代には「陸の向こうに人が住んで居るらしいけれど、きっとその人たちもまげを結って、刀を持っているだろう」と想像していた人も多かったでしょう。でも開国してみたら、全く違った文化を持つ違った肌の色、目の色のさまざまな人たちがいることが分かったわけです。現在の宇宙研究は、それに近い状況と言えます。つまり地球以外にも水があり、生物が居るかもしれないような惑星があると分かってきて、それまで生物がいるなら地球と似たような惑星と想像していたのが、さまざまな環境でさまざまに進化した生物というようなところに思いを馳せることができるようになってきたのです。ですが、我々は科学者ですから、空想で終わってはいられません。仮説を立てて実証する。そしてそれをベースに次を考えて進んでいくものです。今、宇宙の研究者は、生物が居るかもしれないと仮説を立てて、どうやって実証するかを議論しています。例えば大気の成分。自然界には「エントロピー増大の法則」というものがあって、生物が居るとエントロピーは局所的に減少し、平衡状態を崩す方向に向かうんです。 |
−− |
生物というのは、植物も含まれているわけですか。 |
井田 |
|
−− |
地球外生命体の研究は、そこまで進んでいるんですね。では現在発見されただけで、何百個もの惑星があるというお話がありましたが、その内、地球に似たような物というのは、どれ位あるのでしょうか。 |
井田 |
ここでもまた「何をもって地球と似ているというのか」を、よく吟味しなくてはいけません。今、正に我々はそこを問われているんです。太陽と同じような星があって、地球と同じくらいの距離のところで、地球と同じような重さの惑星が回っていることが「地球と似た」と言うのか。あるいは、表面に水があって生物が居そうなものを「地球と似た」と言うのか。後者なら、必ずしも地球と同じような距離や重さでなくともいいわけですから、もっと数は増えます。10個の恒星を見た時に、その内に1個位は、そういう物が回っていることもあり得るという話になります。 |
−− |
それは10%ということですか? 単純な言い方をすれば、生命が居る条件を備えている惑星が、宇宙全体の10%位はあると...。 |
井田 |
惑星の数ではありません。銀河には、太陽のような恒星がたくさんあります。そうした恒星が、それらの条件を満たした惑星を持っている確率が10%程度なんです。銀河には太陽に似た恒星が、数千億個あると言われていますから、その内の10%、つまり100億個位の恒星に、水があってもいいような条件を備えた惑星が回っているということです。 |
−− |
100億!しかも惑星は一つとは限らないわけですから、それは「生命体が居る」と考えるほうが自然な感じがします。 |
井田 |
少なくとも、単純な生物は居るだろうというのが、大方の天文学者や生物学者たちの間では常識になっています。十年というような単位の未来に、非常に高い確率で見つかるだろうと皆思っていますし、そういう時代にきているんです。見つかった時には、我々の世界観を大きくひっくり返す出来事となるでしょうね。 |
−− |
こうしてお話を伺うと、当然のことながら生命を育む地球自体がどのように生まれたかという興味も出てきますね。 |
井田 |
星は、まず銀河に浮いているガスが、自分の重力によってぎゅーっと集まってくるところから生まれます。霧みたいなものでも、互いに引き合って固まろうとするのですが、そうしたフワフワとしたものが集まってくると、回転が速くなるんです。フィギュアスケートの選手がスピンする時、広げていた両手を閉じるにつれて回転が速くなりますよね? そんなイメージで、集まると回転の勢いが増す。そうなると回転軸に対して垂直方向に遠心力が働くので、どうしても平べったくなります。つまり円盤状になる。でも摩擦力など、その円盤の回転の勢いを止める力が働いて、段々と勢いが弱まり、遠心力が弱くなり、また円盤が縮んで...と繰り返すうちに、太陽のような星が出来るんです。観測によると、円盤が出来てから星になるまでには、数百万年あるいは一千万年かかるとされています。そしてその円盤の中で固体成分が凝縮して取り残された塊が惑星になるんです。 |
−− |
だから太陽系などは丸い軌道を描くのですね。 |
井田 |
ええ。ただ、すべてが丸い軌道を描いていると思っていたら、ゆがんでいるものも発見されて、大議論になっているのですが(笑)、最新の理論では、出来た時は、やはり丸い軌道で、それが何かの影響で乱れる事があるのじゃないかとされています。 |
−− |
それは何の影響でしょう? |
井田 |
例えば惑星の配置から考えてみましょう。太陽系で重いのは木星と土星で、重いがゆえに重力も強く働いています。その次に重いのが天王星と海王星です。コンピュータシミュレーションで、仮に天王星と海王星を、今より重くしてみると、それらの重力によって木星、土星、天王星、海王星の軌道をゆがめてしまうことが分かります。今の状態でも、木星と土星は非常に重いので、お互いの重力でお互いの軌道を変化させています。ただ互いにエネルギーを相手に渡しては戻す...ちょうどキャッチボールをしているような状態なんです。地球の軌道だって、木星や金星の影響を受けて常に変化しているのですが、ちょっとゆがんでは、また戻り...と、その変動は規則的です。しかし変化も度を超すと、ゆがみが戻らなくなってしまいます。キャッチボールをする相手が増えて、4人で全員がボールを持ってキャッチボールをしたら、ある時、突然ボールが3つ飛んできたりする可能性もある。そうした時に、変化した軌道が戻れなくなるのじゃないかと、最近分かってきました。つまり非常に重い惑星が太陽系のように2つではなく、3つも4つも作られると、その惑星系では惑星の軌道が大きくゆがんでしまう可能性が高いのです。これも、太陽系以外の惑星系が発見されて解明されたことですね。 |
−− |
すべてが太陽系みたいになると思っていたら、全く違うものがある、と。 |
井田 |
そうです。重い恒星や軽い恒星ではもちろん惑星系の姿は異なるし、太陽と同じような恒星でも恒星の進化段階によって惑星系の姿は変化していきます。太陽はやがて膨張して赤色巨星へと進化し、周囲のガスがはがれて、ぶよぶよになっていくんですが、その時、周囲の惑星はどうなっているのかといった研究をしている人もいます。 |
−− |
太陽もそういう運命を辿りそうだというのも分かるわけですね。 |
井田 |
そうですが、太陽が赤色巨星に進化するのは60億年後のことなので、僕らは生きていませんし、人類もいないかもしれませんが(笑)。 |
−− |
元も子もない話ですが、それらを知ることで、何に役立つのでしょうか。 |
井田 |
僕は、新しい世界観を与えることが出来ると思います。この宇宙には、実にさまざまな惑星系があった。しかも太陽ほど明るくない恒星でも、その周りを惑星が回っていて、そこに水があり、生命が居るかもしれない。あるいは私達の認識を超えた「生命」がいるかもしれない。それらを知った上で、我々の太陽系や地球とは一体何なのかを考える――つまり日本人だけでなく、ヨーロッパ人やアフリカ人も居るという中で、日本人とは何なのかが見えてくるのと同じ感覚ですね。そういったことを知るだけで、世界の見え方は大きく違うと思うんです。 |
−− |
確かに「バクテリアのレベルなら、宇宙にいないはずがない」と言われれば、ワクワクもしますが、動揺もしますね。 |
井田 |
そうやって科学によって、生きていくビジョンやよりどころを提示したいと思っています。 |
井田茂(いだ・しげる)
1960年東京生まれ。東京工業大学地球惑星科学科教授。1984年京都大学理学部卒業、89年東京大学大学院地球物理学専攻修了。東京大学教養学部助手を経て、93年東京工業大学地球惑星科学科助教授。2006年より現職。著書に『宇宙は「地球」であふれている―見えてきた系外惑星の素顔- (知りたい!サイエンス)』(技術評論社)、『太陽系と惑星 (シリーズ現代の天文学)』(日本評論社)、『系外惑星』(東京大学出版会)、『異形の惑星―系外惑星形成理論から (NHKブックス)、『惑星学が解いた宇宙の謎 (新書y)』(洋泉社)など。
●取材後記
「人間なんて宇宙の広大さに比べれば、なんてちっぽけ」という台詞があるが「一つのシステムが動くのにどの位時間がかかり、それを何回繰り返したかと考える力学の視点からすれば、何度も代替わりをしているヒトは、ずいぶん成熟している」と井田さん。誕生から100億年以上経っている銀河系は、太陽が銀河を一周するのに2億年もかかり、まだ50回程しか回っていない。だから力学的には「生まれたばかり」。一方、地球は太陽の周りをもう46億回も回っている「大人の」システムというわけだ。星空にロマンチックな思いを馳せるのも悪くないが、科学の視点で宇宙を見ると、また違った興奮が沸いてくる。今夏の星空は、いつもと違って見えそうだ。
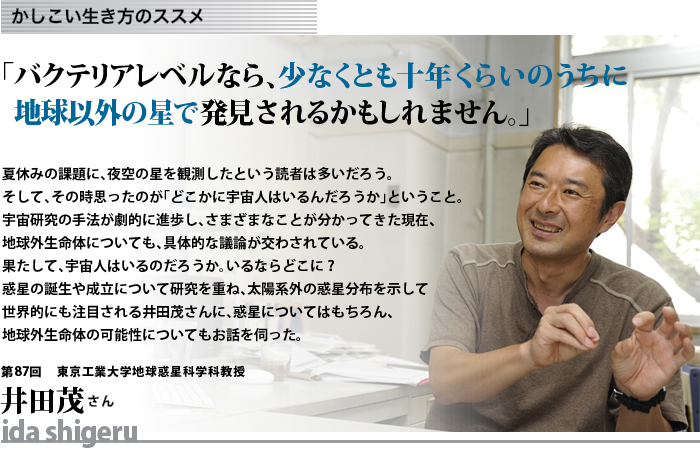
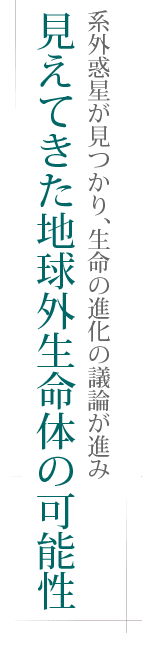
 地球では海ができて何億年もたたないうちに生命が誕生したらしいので、水があれば生命が簡単に誕生するという考えもありますが、一例だけの話なので、まだよく分かっていません。ですので、その前に、水が存在するための条件を考えましょう。水が存在するには、一定の温度と圧力が必要です。温度が高ければ蒸発して水蒸気になってしまうし、低ければ氷になってしまう。また圧力が低いと昇華してしまいます。温度は中心の恒星、つまり太陽系ならば太陽からの距離で決まります。そして圧力は、空気がどれ位あるかで決まり、それはその星の大きさに左右されます。例えば月は小さいので重力が弱く、空気を保持できない。ですから一般的には、大きな惑星程、たくさんの空気があります。
地球では海ができて何億年もたたないうちに生命が誕生したらしいので、水があれば生命が簡単に誕生するという考えもありますが、一例だけの話なので、まだよく分かっていません。ですので、その前に、水が存在するための条件を考えましょう。水が存在するには、一定の温度と圧力が必要です。温度が高ければ蒸発して水蒸気になってしまうし、低ければ氷になってしまう。また圧力が低いと昇華してしまいます。温度は中心の恒星、つまり太陽系ならば太陽からの距離で決まります。そして圧力は、空気がどれ位あるかで決まり、それはその星の大きさに左右されます。例えば月は小さいので重力が弱く、空気を保持できない。ですから一般的には、大きな惑星程、たくさんの空気があります。 もちろんです。陸に上がった生物の二大潮流は動物と植物です。動物は適応力は弱いのですが、自分自身が動く事で環境変動に耐えます。対して、植物はその場を動かないことを選びました。動かないけれども、何十年も昔の種を植えても芽を出す程、非常に高い適応力を持つ、高度に発達した生物と言えます。その植物も、地球の大気の平衡状態を大きく崩しています。本来、酸素というのは、非常に壊れやすい分子で、そのままだとすぐに他の物質と反応してしまって存在し得ないのですが、今これだけ地球の大気に酸素が含まれているのは、木や海の藻などが、せっせとCO2を吸って酸素を吐き出しているからです。そうした「平衡状態を崩す」という生物の特徴を使って、大気の成分を分析することで、生物の有無を調べようというわけです。
もちろんです。陸に上がった生物の二大潮流は動物と植物です。動物は適応力は弱いのですが、自分自身が動く事で環境変動に耐えます。対して、植物はその場を動かないことを選びました。動かないけれども、何十年も昔の種を植えても芽を出す程、非常に高い適応力を持つ、高度に発達した生物と言えます。その植物も、地球の大気の平衡状態を大きく崩しています。本来、酸素というのは、非常に壊れやすい分子で、そのままだとすぐに他の物質と反応してしまって存在し得ないのですが、今これだけ地球の大気に酸素が含まれているのは、木や海の藻などが、せっせとCO2を吸って酸素を吐き出しているからです。そうした「平衡状態を崩す」という生物の特徴を使って、大気の成分を分析することで、生物の有無を調べようというわけです。