−− |
五感という言い方がありますが、中でも嗅覚は意識されにくい感覚ではないかと思います。 |
中村 |
そうですね。ですが、年齢を経ると目がかすんできたり味覚が衰えてきたり、耳が遠くなったりするのと同じで、嗅覚も衰えます。それによって、免疫力が落ちたり、危険を把握出来なくなるんです。 |
−− |
危険を? |
中村 |
分かりやすいのはガス洩れなどですが、食べ物が腐ってしまってもそのにおいが分からなければ大変なことになります。においというのは私たちが考えている以上に、人の毎日の生活や健康に深く関わっているものなのです。 |
−− |
脳と直結しているのですか! |
中村 |
そうです。つまり一種の脳細胞とも言えるわけですね。ですから鼻の嗅細胞を観察すると、老化が分かると言われています。においを感じる嗅細胞は、ちょうどメガネの鼻アテの下、わさびがつん!ときたという時に鼻をつまむ辺りにあるんですが、この嗅細胞というのは、死滅と再生を繰り返すことが知られていて、香りに敏感な人ほど、嗅細胞の再生力は早いと言われています。そして人間は、地球上の大体40万種類のにおいを感じることが出来ます。 |
−− |
そんな数になるのですか。 |
中村 |
ええ、犬の話ではありませんよ(笑)。嗅覚というのは非常に敏感で、ごく微量のものを見つけることが出来ます。例えばブルガリアローズの香料をかいで「ちょっとおかしいな」と思う。聞くと、今年は天候のせいで薔薇の生育が悪かったと言うのです。それが香りにも出てしまっているんですね。 |
−− |
それは、先生のように訓練した方だからこそ分かるのでは…。 |
中村 |
確かにそういう面もあるかもしれませんが、人間が生きる上でにおい、香りの力というのは、計り知れないんです。こんな話があります。以前、いつもお会いしている取引先の女性が、その日に限って妙に美人に見えまして(笑)。香水が違うなとは思ったのですが、実はその香りの中に人の免疫を高める力があったんです。 |
−− |
香りの力を紹介するには、ぴったりのエピソードですね。 |
中村 |
ええ。体の不調の7割は免疫力の低下から起きると言われていますが、ある香りをかぐと、免疫力を高める分泌型のホルモンが非常に高くなるという研究結果が出ていますし、薔薇の香りは、よく鎮静効果があるとか、人の気持ちをなぐさめると言われます。ただ、一口に薔薇といっても2万種類もあって、ブルガリアローズの系統には、どちらかというと高揚効果があり、中国系統の薔薇が持つ成分には、非常に強い鎮静効果があるので、使い分ける必要がありますね。 |
−− |
というと? |
中村 |
|
−− |
免疫と男女の相性と体臭とにそんな関係があるとは、意外でした。 |
中村 |
遺伝子の支配する体臭というのは、個人個人で異なる、その人固有のもの、アイデンティティーなんです。 |
−− |
体臭を消す方向に向かっている現代において、体臭をなくすのはアイデンティティーをなくすことというのは、何か深い意味を感じます。 |
中村 |
体臭が固有というのは、動物にとって生命を左右するものなのです。野生のヌーは、子供を産み落としてすぐににおいをかぎます。子供も、生まれてすぐに親のにおいをかぐ。ヌーは大集団で移動しますが、自分の子供以外にはお乳を与えません。においで自分の子を覚えているんですね。子供も母親をにおいで覚える。そうした事が、自然の中で行われているんです。 |
−− |
体臭というのはそれほどに固有のものなのですね。 |
中村 |
ただ、体臭を構成するものには多くの複雑な要素があって、まず生まれながらのにおいがあります。それは人種や性別によって左右されますし、食べ物や職業、更に病気の影響も受けます。糖尿病を患っていると、甘酸っぱいにおいを発すると言われていますし、肺ガンでも体臭が変わってくるという研究があります。飲んでいる薬にも影響を受けます。 |
−− |
動物は、そういうにおいによって相手が攻撃してくるかもしれないと察知するわけですね。身を守る上では、重要なことです。 |
中村 |
においによって相手をひるませようとするし、反対ににおいを受ける側は身を守る備えをすることができるのですね。人間でも、分かりますよ。柔道の選手に伺ったことがありますが、「相手が『今日は絶対に勝つ』と意気込んでいる時はそれが分かる」というのです。私も自分が緊張していると、においで分かります。 |
−− |
先程、人間も40万種のにおいをかぎ分けられるとありましたが、気づかないうちににおいによって感じ取っているものがあるのですね。 |
中村 |
ええ、そうです。更に植物の研究では、においを発することによって、自分を防御していることも分かっています。最近、同種の植物間でのにおいによるコミュニケーションや、植物と昆虫のにおいによるコミュニケーションの研究が活発になっているのですが、例えばキャベツは、コナガの幼虫に葉を食べられると特定のにおいを出すということが分かっています。 |
−− |
食べられた植物のほうが、ですか。 |
中村 |
そうです。そのにおいが、幼虫の天敵である小さな蜂を呼ぶんです。においの信号をたどってきた蜂は、葉にいる幼虫に卵を産み付け、やがて幼虫の体内で卵がかえるので幼虫は生きられない。そうした、いわゆる植物と虫とのコミュニケーションについても研究が進んでいるところです。 |
中村 |
歴史的には古くから、良いにおい、つまり香りは、人々の願いを神に届ける力を持つと思われていました。神との交信ですね。原始社会では、香りを焚くと神が天から降りてくるとか、香煙によって自分たちの願いが天上の神に届くとかいったことが信じられていました。香りには、宗教的なエクスタシーを起こす力もあると思います。 |
−− |
なるほど。宗教的な場に行くと、何となく香りがするということは多いですね。 |
中村 |
日本人には身近な線香は、祖先の霊を慰める際にも使われます。香りが天上へと上がっていく、それによって先祖の霊が慰められると考えられてきたのです。 |
−− |
香を焚いて衣服にうつすのは、清めの意味もあるそうですが、そうした儀式的な行動は、具体的な効果があってそれを儀式に昇華したものなのでしょうか。 |
中村 |
現在ではアロマテラピーなど香りの生理的、心理的効果が注目されていますが、実際、香りの癒し効果は大昔から利用されてきました。原始時代から、人間は怪我や病気に悩まされてきました。現在のような合成医薬品が登場したのは1850年頃からですから、それまで人間は、身の回りに生えている草や花、木の幹や根、あるいは動物の角といったものに薬効がないかどうか試して、実際に使ってみるということを繰り返してきたのです。 |
−− |
香りに病を癒す力があるということなんですね。 |
中村 |
最近は漢方の研究が盛んですが、厚生労働省では、その効果を実証するために、丸薬にして二重盲検試験を行っています。これは効果があるとされる成分が入った実薬と、外見はまったく同じですが有効成分の入らない偽薬とを飲み比べて「薬を飲んだ!」という気分の問題ではなく、本当にその成分に効果があったのかどうかを調べる実験です。ところが漢方を丸薬にすると、実は効果が落ちてしまうんです。お腹に入るのだから、効果は一緒だろうと思うかもしれませんが、丸薬にすると飲み込んでしまうため、服用する時ににおいがしない。つまり嗅覚刺激がないから効果が落ちてしまうんです。 |
−− |
その事実自体は香りに効果があるということの証明になりそうです(笑)。 |
中村 |
そうですね。病に対する香りの効果を知る例は、他にもたくさんあります。古代ギリシャやローマでは、寝ている人の枕元にナイトメア、つまり「夢魔」が現れ人を苦しめるとされてきました。そこで夢魔を防ぐため、窓や戸口に、においの強い薬草を吊すということが行われていました。これは現代の解釈では、この薬草の香りが、眠る人の精神を安定させ、眠りを深くするから夢魔が出なくなるように感じたのだろうとされています。寝付きの悪い人や、不眠症の人を治療するというのは古代ギリシャから行われていて、そのための処方が今もいくつか残っていますが、それを見ると、やはり香りの植物がたくさん入っています。中にヒエログリフで書かれた処方で非常に効果の高いものがあり、やはりいくつもの香料植物が入っています。私も処方してみましたが、確かに不眠症には効果がありましたね。 |
−− |
香りもあるけれど飲んで効果があるというものもありますか。 |
中村 |
例えば、強心剤として使われるムスク(ジャコウ)は、強心作用の非常に高い薬です。天然のムスクはクルミ程の大きさで、その中に顆粒状の赤黒い砂みたいなものが入っているのですが、それを舐めると心臓の鼓動が、ドクドクと波打ち、寒い冬場でも、体がばっと温かくなる。そういう非常に強い効果を持っていますね。 |
−− |
一方で、日本人は、香りの使い方がうまくないと言われることがありますが、その点は、いかがでしょう。 |
中村 |
日本にも香道という伝統がありますが、確かに香水を上手に使っている人は今、少ないかもしれません。でも、その楽しみ方もぜひ知っていただきたいことの一つです。 |
−− |
香りによってそんな演出ができるんですか。 |
中村 |
アメリカのレブロンが発売した「チャーリー」も女性解放の香り。男性社会で抑圧されていた女性をぱっと開放する香りですね。フランスのブランド、サンローランが発表した「リヴゴーシュ」という香水がありますが、あれは反体制の香りです。 |
−− |
どんな点で、女性解放と位置付けられるのでしょう? |
中村 |
|
−− |
その時の時代の気分が色濃く反映され、また人気を得るというわけですね。 |
中村 |
一方で、自分の香りはこれ、と決めて、後ろを通ると「あ、あの人だ」と分かるような使い方をする方もいますね。と思えば、今日は初対面の人と会うから相手を緊張させないような香り、今日はラフな服装に合わせてカジュアルにいこうとか、おめでたい会だから思い切り華やかな香りをつけていこうとか、TPOに合わせて香りを使い分ける方もいます。 |
−− |
香りには、相手に心理的効果をもたらすこともできるわけですから、上手に使えば、初対面の方を香りで圧倒したり、逆に柔らかな印象を与えたり…。 |
中村 |
その通りです。例えばアメリカの競争の激しい社会では、仕事の上でも「香りも武器の一つだ」と言われます。そういう場では、パワフルな香りを好む女性も少なくありませんね。 |
−− |
日本はどうでしょうか。消臭グッズはたくさんありますが…。 |
中村 |
人が生活すると、体臭だけではなくいろいろなにおいが出ます。その際、強いにおいを出ないようにしたり、消したりするのもいいのですが、あまり神経質になる必要はないと思います。 |
−− |
日本では香水というと、一部の人には「くさい!」とまで言われてしまうことがあります。 |
中村 |
日本の生活環境が狭いということや湿度が高いということもあり、確かに満員電車でオリエンタルノートの官能的な香りは迷惑ですが、季節に応じて香りを選べば、幅が広がると感じています。僕は、夏よりも秋の終わりから春先までなんて、香りを楽しんでつけるのには適した季節だと思います。 |
−− |
好きだな、心地よいなと思うものから始めてみようということですね。 |
中村 |
優れた音楽を聴くと音楽が分かってくる。良い絵を観れば審美眼が出てくるのと同じように、香りの感性を育てて欲しいなと思っています。昨年に続いて、今年も小学校で香りの授業をしました。 |
−− |
学校の授業ですか。 |
中村 |
小学3年生の授業です。香る植物を持っていったり、香料を見せたり、今年は、薔薇から香料を採るところを記録したDVDを観てもらいました。そして最後に、女の子には香水、男の子にもメンズフレグランスをつけてあげました(笑)。そうすると、すごく喜ぶんですね。 |
−− |
私の母は、いつも香水をつけていて、「お母さんは良い香りだな」というのが小さい頃の記憶です。 |
中村 |
そういう経験は、とても重要です。香水に限らず、いろいろな香りをもっと自由に使えるようになると良いなと思いますね。 |
中村祥二(なかむら・しょうじ)
1935年東京生まれ。58年東京大学農学部農芸化学科卒業後、株式会社資生堂に入社。資生堂リサーチセンター香料研究部部長、チーフパフューマーを経て、95〜99年まで常勤顧問。40年にわたり、香水、化粧品の香料創作及び花香に関する研究、香りの生理的、心理的効果の研究を行う。現在は、国際香りと文化の会会長として香り文化の普及に尽力。フランス調香師協会会員。著書に『調香師の手帖』(朝日文庫)、『香りを楽しむ本』(講談社)、『香りの世界をのぞいてみよう』(ポプラ社)など。
●取材後記
「薬」として証明するのが難しいようだが、香りの力は確かにありそうだ。おしゃれの一つとして香りを楽しむのはもちろんのこと、より快適で健康的な暮らしを送るためにも、賢く利用したい香りの力。加えて、限られた誌面ではなかなか紹介しきれなかった香りにまつわるさまざまなエピソードも楽しいの一言。授業でこんな世界に触れることの出来た東京都文京区の小学生は幸せだ。
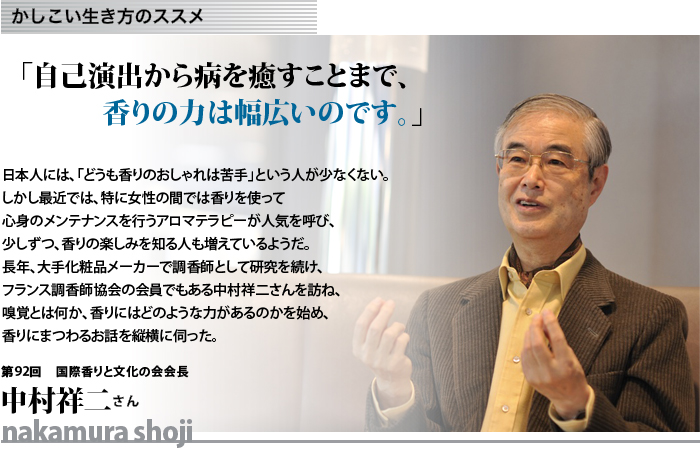
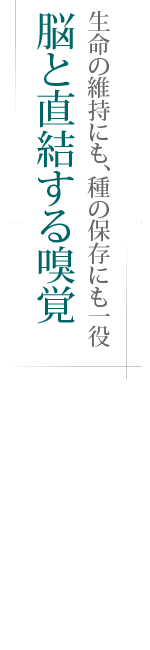
 実は免疫機能を司るMHCという遺伝子は、体臭も支配しているんです。ということは、体臭が似ていると免疫機能も近いものになると言えます。
実は免疫機能を司るMHCという遺伝子は、体臭も支配しているんです。ということは、体臭が似ていると免疫機能も近いものになると言えます。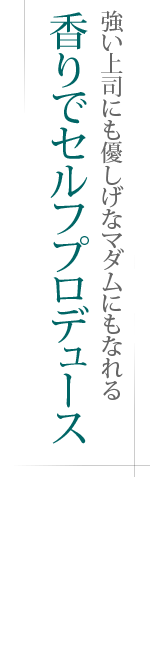
 1970年代の始めから、アメリカを中心にウーマンリブの運動が盛んになりました。「チャーリー」は、香水のメーカーがそうした社会的な変化、ムーブメントになる女性の気分を読んで、それまであった花のような甘い、女っぽい香りを極力抑え、柑橘やグリーンノート、木の香りといった活動的な要素を加え、あえて「チャールス」という男性の愛称「チャーリー」を香水の名前にしたものなんです。発売当初、フランスでは「あんなもの、香水ではない」と不評でしたが、ウーマンリブを旗印にしている女性が皆使い始め、アメリカで大ヒットしました。
1970年代の始めから、アメリカを中心にウーマンリブの運動が盛んになりました。「チャーリー」は、香水のメーカーがそうした社会的な変化、ムーブメントになる女性の気分を読んで、それまであった花のような甘い、女っぽい香りを極力抑え、柑橘やグリーンノート、木の香りといった活動的な要素を加え、あえて「チャールス」という男性の愛称「チャーリー」を香水の名前にしたものなんです。発売当初、フランスでは「あんなもの、香水ではない」と不評でしたが、ウーマンリブを旗印にしている女性が皆使い始め、アメリカで大ヒットしました。